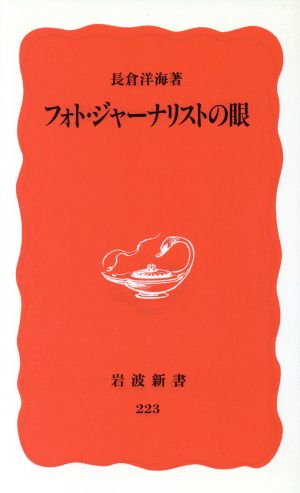
- 中古
- 店舗受取可
- 書籍
- 新書
- 1226-35-02
フォト・ジャーナリストの眼 岩波新書223
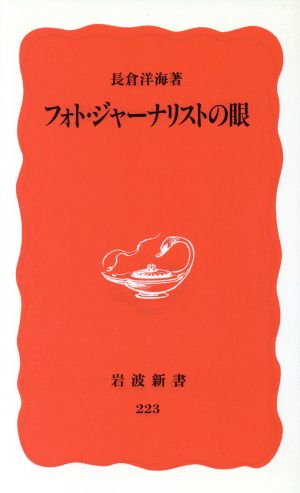
定価 ¥858
110円 定価より748円(87%)おトク
獲得ポイント1P
在庫わずか ご注文はお早めに
発送時期 1~5日以内に発送

店舗受取サービス対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 岩波書店/ |
| 発売年月日 | 1992/04/20 |
| JAN | 9784004302230 |


店舗受取サービス
対応商品
店舗受取なら1点でも送料無料!
さらにお買い物で使えるポイントがたまる
店舗到着予定
2/21(金)~2/26(水)
- 書籍
- 新書
フォト・ジャーナリストの眼
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
フォト・ジャーナリストの眼
¥110
在庫わずか
ご注文はお早めに
商品レビュー
4.8
13件のお客様レビュー
エル・サドバレル、…
エル・サドバレル、アフガニスタン、フィリピンなどで著者が撮影した写真を多数掲載。フォト・ジャーナリストとしてのあり方を語る。人物の表情を見事にとらえた写真が多く、心がひきつけられる。
文庫OFF
肋骨の浮き出た少女とその様子を背後から伺うハゲワシを撮影した報道写真家ケビン・カーター。ジャーナリズムの最高の権威であるピューリッツァー賞を受賞したが、少女に救いの手を差し伸べるより、先にシャッターを押したという世論の猛烈な非難にさらされ、自ら命を絶った。 フォトジャーナリスト...
肋骨の浮き出た少女とその様子を背後から伺うハゲワシを撮影した報道写真家ケビン・カーター。ジャーナリズムの最高の権威であるピューリッツァー賞を受賞したが、少女に救いの手を差し伸べるより、先にシャッターを押したという世論の猛烈な非難にさらされ、自ら命を絶った。 フォトジャーナリストとは、一体どういう職業なのか。他者の価値観を汲み取り、好奇な視点の代理行為として時代のニーズに適した瞬間を切り取り、それを売り捌くアコギな稼業か。例えば女性が現場仕事をする絵面を写し、女性活躍を印象操作するような、無限の被写体を演出し編集する権利を行使する世論または利害の代表。エポックメイキングな写真こそ素晴らしいという価値観の奴隷。いや、そうではないはずだ。 ー 本当に歴史を動かすもの。一九八六年二月二十五日、マラカニアン宮殿の前に詰めかけた人々が門を乗り越え、宮殿内に突入した。門の前でその様子を撮影していた私は、「現代史の瞬間」をこの目で、このカメうでとらえたという興奮にかられていた。しかし、五年後のいま、別の思いにとらわれている。「世界のマスコミが注目し、テレピが映像を渡し続けたあの瞬間”は単に歴史の表層にすぎず、本当に歴史を動かす底流はもっと別のところにあるはず・・・・・」という思いだ。 フィリピンで、私は出会ったさまざまな人々とその生活にカメラを向けてきた。彼らにとって、マラカニアン宮殿の主が変わることより、自分の住むスラムが撤去されたり、仕事のなくなることの方が、大事件であった。世界のニュースという観点から見れば、とるに足りないそんな小きな出来事が実は歴史の底流を形作り、歴史そのものを動かしていく 視点は感受性に突き動かされ、興味関心の対象が目に映る。その時代にしか捉えられないシーンは、広範囲で悠久な歴史のほんの一幕だ。その静止画が、何やら人類や時代、地域を代表しているように見えるのは、一体どういう事なのだろう。他者の価値観を意識する時、大勢の視点は同質の被写体を生み出し、個体は違えど、記号化されたシーンは、根底では同じ無意識の象徴だからだろうか。 言葉と似たものとして、写真は面白い。本書に多数掲載される写真は言葉を発さないが、確かに何かを伝えてくる。そしてそれは、言葉を介さず、ダイレクトに響く。
Posted by 
私に何ができるか、私は瞑ったままの目を見開いて何を見て何に気付くべきか、そして何を訴えていかなければならないか。読み終わった後に頭を巡る数々の言葉、カメラによって切り取られた瞬間。その場にいなくても充分に訴えかけてくれる映像と文字。私にはとても真似できないことだが、私にも何かでき...
私に何ができるか、私は瞑ったままの目を見開いて何を見て何に気付くべきか、そして何を訴えていかなければならないか。読み終わった後に頭を巡る数々の言葉、カメラによって切り取られた瞬間。その場にいなくても充分に訴えかけてくれる映像と文字。私にはとても真似できないことだが、私にも何かできる事はきっと有る。頭の中で自分に考えろ!考えろ!と繰り返し自分が叫んでいるようだ。 本書は内戦や貧困に苦しむ世界中の人々を写真で追いかけ続けるフォトジャーナリストの魂の叫びだと感じる。魂から叫んでいるから読者の心にある普段立ち入らない様にしている自分の嫌な領域を簡単に踏み荒らしていく。 エル・サルバドルでは長引く内戦下に於いて、何年かぶりに訪れた筆者が昔を懐かしみながらも、未だ終わりの見えない危険な状況下で暮らす人々に迫る。貧しさから犯罪に手を染める若者、一方でただ安全に暮らしたいだけと、ささやかな希望を抱いて生きる人々。口々に多くを望まないから安心が欲しいと言う。これが地球の反対側の日常なのだ。私は今日も晩御飯で食べきれないおかずを残していた。 そして長らくソ連やアメリカなど大国の利害衝突に翻弄され続けたアフガニスタン。日本人であれば誰もが危険を感じるこの地に居た英雄アフマド・シャー・マスード。マスードを追い続け、他にも多数の書籍を出している筆者だけあって、中枢部の人間達のリアルな会話や、戦闘とは異なる優しい人間性に触れる。だだっ広い枯れた平原しか頭に思い浮かばない私。何も知らず漠然と危険な人々に扱ってしまう自分、そこには恋をし、家族を守る我々と同じ人間がいる。ニュース映像によって表層しか捉えていない自分が情けない。 スモーキーマウンテンでゴミ拾いをするマニラの少年少女達にも笑顔がある。大きな政変や外交問題だけが我々日本人に伝わってくる。正に首都マニラで道一本挟んで最底辺の暮らしがある。そこをニュースは伝えない。そこにもやはり優しい母の眼差しや子を亡くし悲しみに暮れる人間の姿がある。場所を変えて国内に目を向ければ、出稼ぎでやってくる海外の人々だけでなく、日本人であっても安定した職に就けず、日雇いで最低限の生を繋いでいる人々。 本書で描かれる世界は全て我々が簡単にニュース映像で見ているものとは訳が違う。社会には必ず表に見える姿の裏側の姿があり、それは遠く離れた異国の地だけで無く、我々がいつもいる場所の隣にある。筆者は言う。ミクロの目で見つめてマクロでその背景や原因を考えるのだと。ファインダーを覗く目と逆の目はファインダーに映らない別の映像もしっかり捉え続けなければならないと。 私は目に見えるもの耳で聞いたものにしか触れられないが、それは私が私の意識を「見たくないものから目を逸らす」から、そう思えているだけで本当は見えて聴こえている気がする。深く考えずにニュースや雑誌を聞き流しページをただめくってきただけの自分。パレスチナの人々の本当の声を捉えることが出来ず、何も言わずに何も考えなくて済まそうとする自分。虐げらるパレスチナの人々の血が大地を染める。その事実から目を逸らす自分。そして危険を顧みずに真剣にファインダー越しに向き合う筆者。この違いが迫力のある文章にそのまま現れる。 なぜ私を撮るのか?なぜ私の子供を写すのかと叫ぶ女性の問いかけに、なぜ真実と背景をその目で見ないのか?との声を聴いた。
Posted by 


