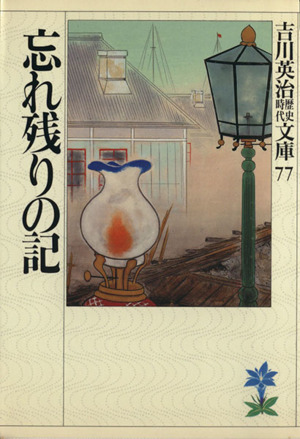
- 中古
- 書籍
- 文庫
- 1225-07-08
忘れ残りの記 吉川英治歴史時代文庫77
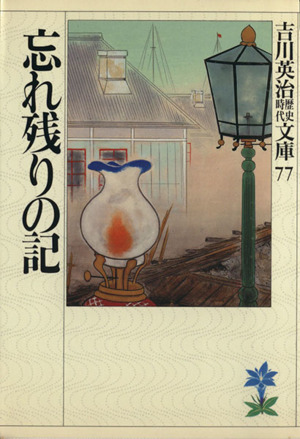
定価 ¥858
220円 定価より638円(74%)おトク
獲得ポイント2P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 講談社 |
| 発売年月日 | 1989/04/11 |
| JAN | 9784061965775 |
- 書籍
- 文庫
忘れ残りの記
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
忘れ残りの記
¥220
在庫なし
商品レビュー
5
2件のお客様レビュー
吉川英治記念館を訪れたとき、展示されているどの写真でも、心の底から笑っている様子に、友だちと「いかにも悠々自適の流行作家だね」と話していたが、とんでもなかった。食い扶持を稼ぐため中学へも上がれず働き通しだった苦労人、いじらしい孝行息子。しかし、その辛酸を「充分愉しかった」と括る。...
吉川英治記念館を訪れたとき、展示されているどの写真でも、心の底から笑っている様子に、友だちと「いかにも悠々自適の流行作家だね」と話していたが、とんでもなかった。食い扶持を稼ぐため中学へも上がれず働き通しだった苦労人、いじらしい孝行息子。しかし、その辛酸を「充分愉しかった」と括る。 とにかく耽読の人。古書店から一銭で本を買い、それを歩きながら読んでしまい、店に戻って、持っている本を買ってしまったということにして別の本に交換してもらう悪知恵も働いた。山師で封建的な父に堪え忍ぶ母を「冬柳」に喩えるなど、俳人を窺わせる語の選び。それでいてなんの衒いもなく綴る。 このような人の書いた歴史物語、そりゃあ人気がでるわ。吉川英治が用いる「貧苦」「思慕」「涙」などの言葉には万感の思いが込められているのだなぁ。『宮本武蔵』、只今2巻目後半。また読み方も変わってくることだろう。この随筆に巡り会えた幸運に手をあわせたい。
Posted by 
『三国志』や『宮本武蔵』などの国民的大衆小説でお馴染の吉川英治氏の自叙伝。 学生時代に『三国志』と『新平家物語』を半年がかりで読んだ。思えば自分が本好きになったのはこの頃からで、その後、『私本太平記』を読み、『平将門』『源頼朝』『上杉謙信』と読んだ。意識していなくても、おそら...
『三国志』や『宮本武蔵』などの国民的大衆小説でお馴染の吉川英治氏の自叙伝。 学生時代に『三国志』と『新平家物語』を半年がかりで読んだ。思えば自分が本好きになったのはこの頃からで、その後、『私本太平記』を読み、『平将門』『源頼朝』『上杉謙信』と読んだ。意識していなくても、おそらく自分は吉川英治氏の史観の影響を受けている。そんなこともあり、手にとってみた。 この本を読むまでは、とても厳格で、間違ったことが大嫌いな人格者、ちょっと堅物、というイメージが自分のなかにあったが、実際はそんなことはなく、間違いもすれば、悩み、落ち込みもする、いたって普通の人だった。 子供のころは父の事業が好調で、おぼっちゃまのように育ち、嫌味なこともするし、高飛車なところもあった。女中を蔑み手をあげたとき、「おぼっちゃまもいつかしっぺ返しをくらいますよ」と言われた。その言葉通り、父が事業に失敗してからは、一転貧乏のどん底に落ち、弱気になったり、卑屈になったり、で大変な苦労をしたようだ。丁稚奉公に出された妹が死んで深い悲しみも味わっている。作家になるような素養なんか微塵も感じない。 父親の独善に生涯母親は耐え忍んだようだ。今なら即離婚でも明治では無理な話で、かわいそうになってくる。でも父が悪いのかというと、この当時の男は、たぶんみんなこんななんだろうとも思う。日本全体が貧乏だった時代だから、過酷な競争社会で、人を蹴落としてでも勝ちにいった。プライドを失った男の悲哀が父親の人生には以後ずっとつきまとう。 母親は「お前たちがいなかったらと考えることが何度もあった」と言う。自殺を何度も考えるほど追い込まれたのに、それでも耐えて、子どもたちを育てた母の愛情は深い。 氏は青年時代、横浜のドックヤードで働いていたときに、高所から落ちて大けがを負う。それも同僚の不手際が原因なのに、生死の境から帰還したときも、その同僚は笑ってごまかし責任は感じていなかった。命の軽い時代だ。 明治に生きた家族の物語として十分に楽しめると思う。生きることが当たり前ではなく、必死にならないと生きることができなった時代だったのだと思う。 氏は『上杉謙信』の中で、「死中生あり、生中生なし」という言葉を謙信に語らせている。謙信の言葉ではあるけれども、氏が自らの人生の中で得た言葉のようにも思う。
Posted by 



