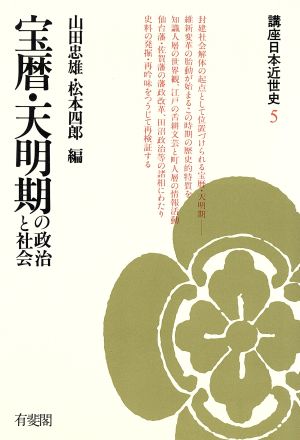
- 中古
- 書籍
- 書籍
- 1216-01-08
宝暦・天明期の政治と社会 講座 日本近世史5
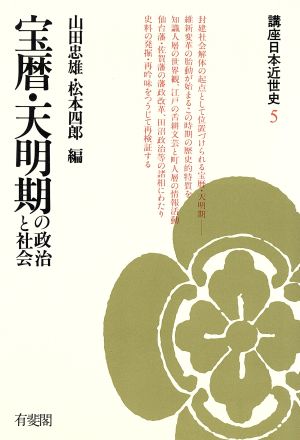
定価 ¥2,860
550円 定価より2,310円(80%)おトク
獲得ポイント5P
在庫なし
発送時期 1~5日以内に発送

商品詳細
| 内容紹介 | |
|---|---|
| 販売会社/発売会社 | 有斐閣 |
| 発売年月日 | 1988/11/30 |
| JAN | 9784641070950 |
- 書籍
- 書籍
宝暦・天明期の政治と社会
商品が入荷した店舗:0店
店頭で購入可能な商品の入荷情報となります
ご来店の際には売り切れの場合もございます
オンラインストア上の価格と店頭価格は異なります
お電話やお問い合わせフォームでの在庫確認、お客様宅への発送やお取り置き・お取り寄せは行っておりません
宝暦・天明期の政治と社会
¥550
在庫なし
商品レビュー
0
1件のお客様レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
1988年刊。 編者山田忠雄は慶応志木高校教諭・慶応義塾大学文学部講師。 同松本四郎は都留文科大学教授。 江戸時代の中で重商主義的側面が初めて見られる一方、後代に賄賂政治横行といった濡れ衣的悪評を残し、特異な位置を占める田沼時代に光を当てる5巻。 テーマは、 ① 幕府田沼政権の人事からその特徴を。 ② 郡上一揆を題材にした講談で一世を風靡した馬場文耕を素材に、都市民衆の興味関心とその方向性を。 ③ 当時の蘭学者を素材に、海外からの情報が日本の人々の世界観や世界認識をどのように拡大していったかを。 ④ 西国佐賀藩、東国仙台藩。 社会変化の帰結として生まれた藩財政の窮乏に対応を迫られた地方各藩の藩政改革を、先の2藩を例にしつつ、田沼時代に見られる社会構造の変化を解読する点。 というものである。 ①は、基本構造は政権担当者の変更が人事に大きく影響し、失脚すれば事実上連座というものだが、 ⑴ 田沼時代の登用人材の有能さから、一部は田沼失脚後も出世街道を、 ⑵ 勘定奉行・勘定方担当老中のポストは勿論、その勘定方の実務運営者、そして江戸を中心とする各町奉行を重視。 ⑶ 歴代より、抜擢のスピードは早い(出世の階段を一足飛びとはいかないが)。 ⑷ その抜擢者は田沼意次と縁戚関係・血縁関係を有する者が殆ど。 ③につき、 ⑴ 先駆者を、通説青木昆陽とは異なり、新井白石とする著者。 ⑵ 田沼時代には、前代に比して蘭学書の翻訳ペースが極大化。 ⑶ 医学や本草学の知識に加え、地理や地勢観の拡大と、世界の政治制度(特に選挙制度)への理解認識の拡大のみならず、形而上学的な視野も一部萌芽が。 ⑷ 重視するのは、解体新書メンバーと、司馬江漢・平賀源内、そして本多利明。最後に高野長英。 ④藩財政悪化の要因は何か。 ⑴ 新田開発の頭打ち=年貢増徴の上限。 ⑵ 新田開発を通じ、貨幣的余力があって開発新田を取得できた階層と、それ以外とに分化。→上昇農民の商人化と、没落農民の小作化と都市労働者化。後者は土地放棄民→全体的な年貢徴収減。隠し新田や上昇農民の年貢減交渉。 ⑶ 更に天明の飢饉。 対策としては、 ⑴ 運上益への課税(→商人層の反対でとん挫)、 ⑵ 藩借銀返済の事実上の棚上げ(次の借入が不可能という反作用)、 ⑶ 荒廃農村の再建(財政難で実現せず)、 ⑷ 藩札=銀の保有のない中、事実上の不換紙幣の発行。藩の信用度如何だが、大半は通貨安・物価高。→社会不安の温床。 ⑸ 藩産品の諸色を優先し、金銀の藩外流出を抑制する(安価な諸色の流入減による物価高)一方、藩外用特産品開発で藩保有金銀の増大(→簡単に特産品は出来ず、かつ農民年貢が基礎たる幕藩体制とは異質)。 特に⑸は、商品の全国的な自由流通と、貨幣取引の益々の亢進・規模拡大を招来。一方で物価高を招く貨幣価値下落政策と、不換藩札流通増=金銀の市井への流通抑制に伴う貨幣の価値下落。→一揆へ。 領国内製品の優遇と開発製造技術の先進地域からの移植は明治の殖産興業・技術導入政策と軌を一にする。そういう意味では、維新政府を構成する薩長の該時代の実態が知りたい。 事実よりも、ある種のイデオロギーに彩られて田沼を断じていく徳富蘇峰の田沼意次の書はもはや過去の遺物だが、事実の追求を重んじた辻善之助の著作は、今もまだ読み継がれていく。この当然の帰趨を開陳する本書の姿勢は納得のそれ。 編者以外の執筆者として。 今田洋三は近畿大学教養部教授。 加藤文三は埼玉大学非常勤講師。 長野暹は佐賀大学経済学部教授。 難波信雄は東北学院大学文学部教授。
Posted by 



