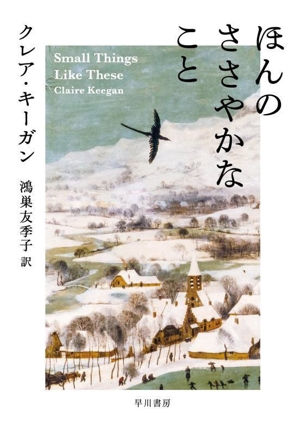ほんのささやかなこと の商品レビュー
Posted by
どの社会も抱えているような暗部とそれに向き合う人間のあり方を、言葉少なでシンプルなストーリーに凝縮させて提示している。作品としての完成度がすごい。ただ訳文に日本語としてゴツゴツしている部分が散見されやや違和感があった。(有名な訳者のものなので、原文のテイストに合わせた意図的なもの...
どの社会も抱えているような暗部とそれに向き合う人間のあり方を、言葉少なでシンプルなストーリーに凝縮させて提示している。作品としての完成度がすごい。ただ訳文に日本語としてゴツゴツしている部分が散見されやや違和感があった。(有名な訳者のものなので、原文のテイストに合わせた意図的なものかもしれないが)。
Posted by
『ウェクスフォード県のニューロスの町では、煙突が煙を吐きだし、それが薄く流れてもわもわと長くたなびき、埠頭のあたりで霧消する時季になると、じきに雨が降り、バロー川はスタウトビールほど黒く濁って水嵩を増した。町の人びとの大半はため息をつきながらこの悪天に耐えた』―『第一章』 ふわ...
『ウェクスフォード県のニューロスの町では、煙突が煙を吐きだし、それが薄く流れてもわもわと長くたなびき、埠頭のあたりで霧消する時季になると、じきに雨が降り、バロー川はスタウトビールほど黒く濁って水嵩を増した。町の人びとの大半はため息をつきながらこの悪天に耐えた』―『第一章』 ふわふわと思考は漂ってゆく。初めての長期の英国出張。滞在先近くのコンビニで買うギネスのロング缶。パブで飲む泡の細かい常温の黒ビール。冷たい雨。鼻の長い二階建てバス。『汽車に乗って、あいるらんどのような田舎へ行こう』という詩の断片。牧歌的と言ってもよい雰囲気でこの一冊は始まる。 そんな風に連想に誘われる文章は、一読すると熱量の低い淡々とした言葉が並ぶだけのようにも見える。読むものの感情を意図的に揺さぶるようなところはない。そんな筆致で、オー・ヘンリーの「賢者の贈り物」のような物語が紡がれていくのだろうかと思わせる文章。しかし、クレア・キーガンの描こうとしているものはそんな生半可なものではないことが徐々に明らかとなる。 本当は複数の本を同時並行で読むのは好きではないのだけれど、ポール・オースターの最後の一冊が余りに大部なものだから、そして随分順番待ちをした本が届いてしまったから、オースターを一旦脇に置いて読み始めた。行間もポイントも大きい薄手の一冊を読み切るのに時間は掛からない。小さなポイントで二段組みかつ800頁弱のオースターとの対比。しかし、読みかけの本のことを忘れてしまうくらいの衝撃が詰まっている。 それは、どんな社会にもあり、大っぴらに明かされていないだけの闇。日本の事例で例えてみれば、ハンセン病患者の隔離、優生保護法、あるいは女工哀史。幾つかの物語の流れの中、その不穏なものの存在は噂程度の話として先ず語られ、ある男の日常の営みの中じわじわと核心に近づいていく。紆余曲折がある訳では無いが、日常の中にある善と悪は単純に割り切れない程人々の生活に根を張り合って縺れている。そしてその後に続く修羅の道のことを思えば、決して予定調和でも大団円でもないが、ぐっと歯を喰いしばりながら最後の一文を読み終わる。胸の中にふつふつと沸き上がる感情の正体を自分でも図りかねなから。
Posted by
世界の中に、このようなものの感じ方をする人間がいて、それを小説として世に出してくれて、極東の国で翻訳され、噛み締めることができる、という奇跡。 さらに映画化もされ、来年公開されるという。 昨年見た映画「コット、はじまりの夏」の原作者だと知って、膝を打った。いい映画だった。親から...
世界の中に、このようなものの感じ方をする人間がいて、それを小説として世に出してくれて、極東の国で翻訳され、噛み締めることができる、という奇跡。 さらに映画化もされ、来年公開されるという。 昨年見た映画「コット、はじまりの夏」の原作者だと知って、膝を打った。いい映画だった。親からの愛を感じられない少女が過ごす一夏の叔母夫婦での思い出。机のビスケットが繋ぐ叔父との心の交流。 あの静謐な作品と確かにテイストは似ている。 予告編を見たけど、映画を見るのが今から楽しみだ。 こういう小説を読むと世界は繋がっているなと思う。アイルランドの「マグダレン洗濯所」の歴史を知ることもでき、クレア・キーガンの見つめる世界を、自分も見ることができたことに、小さな感動。
Posted by
「知ること」の大切さ。 こんな話を聞いたことがある。 関心のない国や土地については、地名は知っていても、地図で書いたり場所を指し示したりすることができない。つまり、自分の世界ではその土地がなかったことになっている。 これは見事に自分に当てはまっていて、知っているつもりでいたこ...
「知ること」の大切さ。 こんな話を聞いたことがある。 関心のない国や土地については、地名は知っていても、地図で書いたり場所を指し示したりすることができない。つまり、自分の世界ではその土地がなかったことになっている。 これは見事に自分に当てはまっていて、知っているつもりでいたこと恥ずかしく、また恐ろしくも感じた。関心がないということは、無視しているのと同じことなのだと。 この本は、訳者・鴻巣友季子さんのX投稿で知った。 1985年のアイルランド話。それは1996年まで続いていた。中世の出来事でない。 だからこそ驚いた。 この知らなかったことを知る驚きは、 韓国の映画「タクシー運転手」でも体験した。 隣の国でこんなことが起きていたなんて。 知ることには偶然といものがある。 たまたま手に取った本との出会いで知ることは、今後も大切にしていきたい。 そして、知ったらもう無視などできない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
心が震えるラスト! 今しなくて後悔する苦しみを死ぬまで味わうより、自分で正しいと思う事をして、これから降りかかる問題の方が軽い。 暗い話だろうから、読むのを敬遠してたけど、読んで良かった。 昔々の事では無くて、結構最近、1980年代の話だから驚く。 戦争も教科書に載ってた話ではなく、今現在の話になっている。 見ないフリしている問題が今現在、色々あると思う。 解決するには小さな1人の1歩からしか、変えていけない。 最初の一歩は潰されるだろうけど、きっかけを作らないと一生変わらない。 その1歩が自分か誰かか。 気になったほんのささいなことを、自分のほんのささいな行動で、世の中という大きなものを変えていけるのかもしれない。 些細なことの積み重ねが、良くも悪くもなる。 些細なことは、気づいた時、大きく問題になる前に修正すれば、大きな労力もいらない。 (個人的には、「 Clear thinking 」本の感想に繋がる) ゆっくり自分のために時間をとり、いつも普通と思ってる些細なことを見直す時間を持とう。 人には環境と教育が大切。
Posted by
著者はアイルランドの代表的な現代作家さんらしい。 舞台はアイルランドのとある都市、1985年のクリスマス。 ファーロングは父を知らぬ私生児として育ったものの、今は燃料店を切り盛りし、 妻と五人の娘に恵まれている。 ところが、クリスマスの直前、女子修道会に付属する施設で その実態...
著者はアイルランドの代表的な現代作家さんらしい。 舞台はアイルランドのとある都市、1985年のクリスマス。 ファーロングは父を知らぬ私生児として育ったものの、今は燃料店を切り盛りし、 妻と五人の娘に恵まれている。 ところが、クリスマスの直前、女子修道会に付属する施設で その実態を目の当たりにしてしまい・・・ 自らの生い立ちと重ねつつ、葛藤する・・・ アイルランドには、1996年まで各地に「マグダレン洗濯所」という 施設があった。 母子収容所を併設し、政府の財政援助を受けながら運営されていたものの 実態は女性への虐待と労働力の搾取・・・名ばかりの職業訓練所だったとか。 ファーロングは、その実態を垣間見てしまったのだ。 読んでいて、ずっとわけのわからない不安につきまとわれ、 先に進めなかった。 この先、きっと良くないことが起きる、平凡な日々が喪われる・・・と。 ムダがない文章なのに五感を刺激されるような文章。 惹かれるのに、この不安は何なんだろう・・・? ラストを読んだ瞬間、ああ、自分が年をとったからなんだと、納得する。 平凡な穏やかさを私は絶対に手放したくないんだな、と。 いつの間にか、小説の中で保身に走ろうとする自分に愕然とした。
Posted by
2024/11/23読了。舞台はアイルランド南東部の ウェクスフォード県にあるニューロスと言う町。 時代は100年前の出来事ではなく1985年の現代だから驚かされる。…背景には英国国教(プロテスタント)と、ローマカトリック教会の長きにわたる対立と確執がある。アイルランド共和国はカ...
2024/11/23読了。舞台はアイルランド南東部の ウェクスフォード県にあるニューロスと言う町。 時代は100年前の出来事ではなく1985年の現代だから驚かされる。…背景には英国国教(プロテスタント)と、ローマカトリック教会の長きにわたる対立と確執がある。アイルランド共和国はカトリックが主流。そんな宗教的ベースに政治的な要素が絡み合い一般の人々の生活(更に独特の階級性、ジェンダーギャップ、移民などへの排外主義)がモヤで包まれているアイルランドの風景とが微妙に上手く重なり合い、主人公の生い立ちや置かれている経済的な状況が彼を静かに動かして行く。読みやすい文体だけに一層緊迫感を感じさせられた政治小説とも言える。
Posted by
オーウェル賞受賞しただけあるって思った。 アウシュビッツが多く本の中で取り沙汰される中 まさか、平和なイメージのある場所で女性の奴隷制度が国とカトリックの宗教をも巻き込んで行われてるとは、思いもしなかった。目を背けたくなる事実が今から10年ほど前までも行われていたことにも驚いた。...
オーウェル賞受賞しただけあるって思った。 アウシュビッツが多く本の中で取り沙汰される中 まさか、平和なイメージのある場所で女性の奴隷制度が国とカトリックの宗教をも巻き込んで行われてるとは、思いもしなかった。目を背けたくなる事実が今から10年ほど前までも行われていたことにも驚いた。この物語が色々なものがモチーフになっているとこもみると、無くしてはならない歴史を、自分の言葉に変えて本を手に取る人に訴えてる現状がとても素晴らしいと感じた。中編小説ながらもすごい読了感だった。終わりも個人的に好きだった、2025年に映画化されるみたいなので是非劇場に足をはこびたい。
Posted by
「青い野を歩く」の著者の新刊と聞き、楽しみに購入。あとがきに〝ブッカー賞候補史上もっとも小さな本の一つ〟と書かれている通り、読み始めたら薄い上に字も大きい。ただ最後数ページはまさに圧巻。 堅実で慎ましやかながら、幸せな家族との暮らしの中で、世の中の影に気づいた時、私たちはどうす...
「青い野を歩く」の著者の新刊と聞き、楽しみに購入。あとがきに〝ブッカー賞候補史上もっとも小さな本の一つ〟と書かれている通り、読み始めたら薄い上に字も大きい。ただ最後数ページはまさに圧巻。 堅実で慎ましやかながら、幸せな家族との暮らしの中で、世の中の影に気づいた時、私たちはどうすべきだろう? この本に書かれた影、〝マグダレン洗濯所〟のような場所は、世界に、日本にもまだあるかもしれない中、主人公の周りの人々のように、自分はなっていないだろうか。
Posted by
- 1