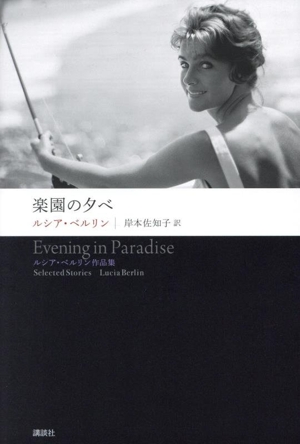楽園の夕べ の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
子どもの頃よりあちこちに住み、結婚離婚✖️3、息子4人、シングルマザーにして職業をいくつか、そして大学教師、アルコール中毒と、これでもかの人生経験。日本の私小説作家が書いたら、恨みや悲しみのお涙頂戴にも出来そうなのに、彼女の場合、全く、微塵も湿っぽくなく、ドライなのが素晴らしい。『リード通り、アルバカーキ』『桜の花咲くころ』わたしの人生は開いた本』が特に気に入りました。
Posted by
「ルシア・ベルリンの書く文章はほかの誰とも似ていない。(中略)読んだときは文字であったはずのものが、本を閉じて思い返すと、色彩や声や匂いをともなった「体験」に変わっている」 (あとがきより) 『掃除婦のための手引書』で度肝を抜かれて以降、 『すべての月、すべての年』に続く3冊目...
「ルシア・ベルリンの書く文章はほかの誰とも似ていない。(中略)読んだときは文字であったはずのものが、本を閉じて思い返すと、色彩や声や匂いをともなった「体験」に変わっている」 (あとがきより) 『掃除婦のための手引書』で度肝を抜かれて以降、 『すべての月、すべての年』に続く3冊目の本書でも、まだ、ルシア・ベルリンの文章には驚かされることばかり。参りました。(好き)
Posted by
『波瀾万丈というには余りに過酷なシチュエーションなのに、自己憐憫やウェットさは微塵もない。初期レイモンド•カーヴァーとも違って、ストーリーとしてよりカラフルだけれども、一切無駄のない言葉選びと細部に注がれる視線の鋭さは共通している。』ー掃除婦のための手引書 『いつだって彼女の視...
『波瀾万丈というには余りに過酷なシチュエーションなのに、自己憐憫やウェットさは微塵もない。初期レイモンド•カーヴァーとも違って、ストーリーとしてよりカラフルだけれども、一切無駄のない言葉選びと細部に注がれる視線の鋭さは共通している。』ー掃除婦のための手引書 『いつだって彼女の視線はクールだ。どの物語も、安易な同情や温かい眼差しが入り込む余地がないくらい研ぎ澄まされ、結末ではすっぱりと断ち切るように放り出される。 それでも愛としか呼びようのない人間臭さが、読了後に心に残る。』ーすべての月、すべての年 自分が書いた書評を再度載せるのもなんだが、陳腐であれ本書を読んでも、浮かぶ想いは同じだ。 だが、本書を読んで改めて思うのは、収められた短編たちはルシア・ベルリンの人生を下敷きにしていても、そこに留まらない普遍的な豊かさを差し出しているということだ。 抱え込んだ悲惨さとドタバタな下世話の中に、ユーモアがある。ジョークにしないと吐き出せないことがある。目を背けてやり過ごしていても、足元には、馴染み深い奈落が昏い口を開けて待ち構えていることにハッとする瞬間がある。 そして同時に、むせかえるような生きる悦びがある。 凝縮された人生の一場面に、真理とも啓示とも名付け難い何かが差し込んで、ふっと照射したのち、通りすぎてゆく。それをはっきりと捉えることはできないが、忘れられないシーンが胸に刻まれる。 幼い手で橋の欄干から投げられる硬貨。 七色に燃える精錬所の煙は友の瞳に映り込み、夏夜の端から溢れんばかりに星が流れる。 家族から離れて独り立ちした旅立ちの日に、飛行機から見たコーラルピンクに染まった砂漠の寂寥。 “ストーリーがすべて”というルシアの言葉通り、ここには心を掴んで離さない、短編小説を読む愉しみが詰まっている。
Posted by
目で文字で読んだのに、 映画をみたように思い出すのが、ルシア・ベルリンの小説だ。 どの話も匂いに満ちていて、息苦しくなるくらいなのにそれこそが生だし、人生だと思わさせてしまう。苦しいし苦いのに、どこか甘美なのだ。 「オルゴールつき化粧ボックス」の幼き日の犯罪まがいのこと。(最...
目で文字で読んだのに、 映画をみたように思い出すのが、ルシア・ベルリンの小説だ。 どの話も匂いに満ちていて、息苦しくなるくらいなのにそれこそが生だし、人生だと思わさせてしまう。苦しいし苦いのに、どこか甘美なのだ。 「オルゴールつき化粧ボックス」の幼き日の犯罪まがいのこと。(最後、家に帰ってきて「メイミーがカスタードとココアを運んできた。病人や罪人に与える食べ物だ。」そんな風にこのできごとを振り返る。まだ未就学児なのに。 「リード通り、アルバカーキ」や「日干しレンガのブリキ屋根の家」で、若い妊婦や母がたくさんの植物や花を植え育てる様の異様さ。(もちろん話の主体は夫の振る舞いであり、隣人の苛烈さではある)
Posted by
『人が表立っては言わないことが世の中にはある。愛とか、そんな深刻なことではなく、もっと体裁のわるいことだ。たとえばお葬式はときどき面白いとか、火事で家が燃えるのを見るとぞくぞくするとか。マイケルのお葬式は最高だった』―『塵は廛に』 ルシア・ベルリンの三冊目の短篇集。三冊目の翻訳...
『人が表立っては言わないことが世の中にはある。愛とか、そんな深刻なことではなく、もっと体裁のわるいことだ。たとえばお葬式はときどき面白いとか、火事で家が燃えるのを見るとぞくぞくするとか。マイケルのお葬式は最高だった』―『塵は廛に』 ルシア・ベルリンの三冊目の短篇集。三冊目の翻訳が出版されることはとても嬉しいことだけれども、これ以上翻訳される原本がないという淋しい気持ちも同時に去来する。読みたい、けれど読み終えたくない。届いた本を後回しにするべきか否か。結局手に取り、一つひとつ、いつも以上に丹念に読む。 岸本さんが言う通り、ルシア・ベルリンの文章は誰かに似ているという思いを抱かせない。いつもいつも本を読めば、ああ、これは誰々の小説を思い出すなあ、という印象に絡め取られてしまうものだけれど(極端な例では、川上弘美を読みながら村上春樹の口調を思い出したりもするのだが)、この作家の文章を読んで誰かのことを思い出したりしない。もしかすると、どこかでほんの少しだけレイモンド・カーヴァーの静謐さ(それは中毒症状の果てに辿り着く地獄と隣り合わせの境地なのか)のことがちらりと過[よぎ]る気もするけれど、カーヴァーにはルシア・ベルリンの陽気さや切実さを感じない。そしてどこか人生に対する諦めのようにも見える(けれど決して諦めている訳ではない)斜に構えた台詞。神様が意地悪なら私も神様に意地悪になってやる、といった態度。それが唯一無二の文章となって綴られている。 『あとの心配は時間だけだった。その家に人がいるのか留守なのか、すぐにはわからなかった。ドアベルの把手をこつこつ鳴らして、あとは待つ。最悪なのは、わたしたちが"久しぶりのお客さん"だという人たちだ。かならずうんと年とった人たちだった。みんなあのあと何年もしないうちに死んでしまっただろう』―『オルゴールつき化粧ボックス』 どの短篇も作家と作家の家族の話が脚色されているのだろうことは、ルシア・ベルリンの長男による序文を読まずとも三冊目の短篇集を読むものには自明だろう。そしてそのことが少し余計な感情を呼び起こす。だが、この作家の物語は常に過去形の物語。それが余計な感情に対する救いとなる。そんな風に読むことは、もしかすると邪[よこしま]すぎる読み方なのかも知れないけれど、ルシア・ベルリンを読むということは、畢竟彼女の人生を知るということなのだと覚悟するしかない。それでもそこには四人の子どもたちを守り抜いた強さがあり、作家自身のチャーミングさがあり、単に私小説を読むという地平を越えた読みがある。読みとは解釈ではないと、これ程強烈に教えてくれる作家も余りいないように思う。 『砂漠が濃いコーラルピンクに染まっていた。自分が歳をとった気がした。大人になったというのではなく、ちょうど今のわたしと同じ気分だった。自分にはまだ見てもおらず理解してもいないことがたくさんあって、でももう手遅れなのだ。ニューメキシコの空気は澄んで冷たかった。迎えは誰もいなかった』―『旅程表』 ルシア・ベルリンを読むことは彼女の目に写った風景の意味を「理解」することではない、ただその風景を並んで見ることなのだ。そしてフランスの片田舎で作家が出逢ったおばあさんのように「J'arrive!」と叫ぶのがせいぜいなのだ。
Posted by
- 1