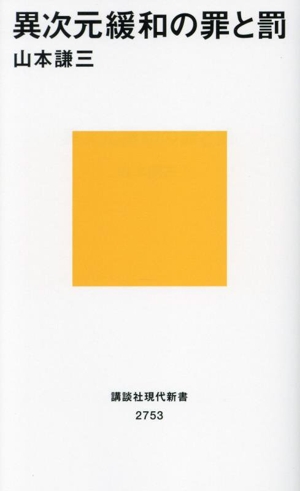異次元緩和の罪と罰 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
まずは時系列で何が行われたのかが整理できた。 で、異次元緩和って結局何だったのか。 筆者はその効果は評価していない。むしろ、これからの課題が重いとの論調。 納得できる。
Posted by
日銀の異次元緩和を批判的に解説。 1.物価と賃金の好循環は企業の生産性向上こそが重要。 2.緊急措置が講じられるといつまでも解除されないのが日本の悪しき慣習。一度立ち上げた政策を自身の手によって方向転換するのは困難。 3.今後の金融正常化のためには金融不安を起こさないよう細心の注...
日銀の異次元緩和を批判的に解説。 1.物価と賃金の好循環は企業の生産性向上こそが重要。 2.緊急措置が講じられるといつまでも解除されないのが日本の悪しき慣習。一度立ち上げた政策を自身の手によって方向転換するのは困難。 3.今後の金融正常化のためには金融不安を起こさないよう細心の注意を払いながら、数十年スパンで国債の計画的な償還を続ける必要がある。新規国債発行の抑制も重要。政府による財政支出拡大の圧力に対してどのような姿勢を見せるのか。
Posted by
私は、日銀の異次元緩和にそのスタートから関心を持ち、その推移を見てきました。経済学部を卒業した者として、「金融のできることは限られている」と思い、異次元緩和には違和感を持っていました(この辺りのことは西野智彦著『ドキュメント 異次元緩和』の感想に書いてあります)。 異次元緩和ス...
私は、日銀の異次元緩和にそのスタートから関心を持ち、その推移を見てきました。経済学部を卒業した者として、「金融のできることは限られている」と思い、異次元緩和には違和感を持っていました(この辺りのことは西野智彦著『ドキュメント 異次元緩和』の感想に書いてあります)。 異次元緩和スタート時点で、これに疑問を呈すると(リフレ派から)「お前は馬鹿か」と言われたものです。しかし、本書を読むことで、異次元緩和が後先を考えずに続けられた政策で、将来に禍根を残すものであったことがわかります。どう言い繕おうと、日銀の国債買い入れは財政ファイナンスでした。最近発表された日銀のレビューからもそうであったことが読み取れます。 櫻川昌哉慶大教授は同書の書評でこう述べています:異次元緩和は、日本人が勢いに任せて熟慮を欠いた歴史として長く語り継がれることになろう。
Posted by
異次元緩和以前の日銀と以後の日銀がどう違うかがよくわかった。 金融緩和が本来市場を退出しているはずのゾンビ企業を生きながらえさせ、それが原因となり日本の生産性の伸びが芳しくない。 過去最高益を出す企業の多くは円安による海外投資収益の上振れによるもの。 日本の実質的な国富は異次元緩...
異次元緩和以前の日銀と以後の日銀がどう違うかがよくわかった。 金融緩和が本来市場を退出しているはずのゾンビ企業を生きながらえさせ、それが原因となり日本の生産性の伸びが芳しくない。 過去最高益を出す企業の多くは円安による海外投資収益の上振れによるもの。 日本の実質的な国富は異次元緩和中も減少し続けている。 などなど、あまり頭の整理ができていなかったところがよく整理されていて学びが多かった。
Posted by
当事者ではないにしても関係者もしくは関係する組織の人に本当の意味でニュートラルの立場というのは難しいのだと思う。暴露本ではないが、書かずにはいられなかったというのがあるようにも思う。ニュートラルのフリをしつつ自分の主張を前面に出す場合と自分の主張はしたいのだけれど可能な限りニュー...
当事者ではないにしても関係者もしくは関係する組織の人に本当の意味でニュートラルの立場というのは難しいのだと思う。暴露本ではないが、書かずにはいられなかったというのがあるようにも思う。ニュートラルのフリをしつつ自分の主張を前面に出す場合と自分の主張はしたいのだけれど可能な限りニュートラル目指すというパターンがある様にも思うが、本書はその中間なのかなとも思う。 この10年の日銀のいわゆる異次元緩和はアベノミクスの成果の陰に隠れて同じく成果があったと評価されることが多いのかも知れない。成果があったと思っているのは私の勘違いかも知れない。実感が感じられないのに要素の数値では成果があったと言えることを、私は学生に血液検査など健康診断の数値では全く健康という結果だけれど気分や体調がすぐれないと感じる状態と伝えっているが、これを読むとその数値の方も本当に良かったと言えないという気もしてくる。おそらく、これまでの金融政策(財政政策を含むアベノミクス全体のことかも知れないが)の失敗を糾弾、責任追及するとかという感じよりも、新総裁のもとこれからが大変、これからどうするのかという問題提起と受け取らせてもらった。 印象に残ったのは、まずなんだかこれまで学生には机上の空論で嘘を伝えてきてしまったのかなと反省させられたこと。もう一つ私も印象操作されていたのか、日銀の目的の第一は物価の安定と思い込んでいたが、それは一部で本当はそれを含んだ通貨の信任確保だというのが発券銀行の機能も持つ日銀の本当の目的ということが妙に腑に落ちたこと。 もしかしたら、本書への賛否は分かれるのかもとも思うが、私は納得できたし、勉強不足、考え不足を痛感させられたので読んで良かったとは感じる。
Posted by
アベノミクスの3本の矢、金融政策、財政政策、成長戦略、、、 アベクロで実現させた金融政策が異次元の金融緩和。 それは実質、禁じ手といわれる財政ファイナンスを実行することだった。 2%の物価上昇を目指しながら、日本経済はデフレから立ち直ることはできず。 残る2つの矢、財政政策走りつ...
アベノミクスの3本の矢、金融政策、財政政策、成長戦略、、、 アベクロで実現させた金融政策が異次元の金融緩和。 それは実質、禁じ手といわれる財政ファイナンスを実行することだった。 2%の物価上昇を目指しながら、日本経済はデフレから立ち直ることはできず。 残る2つの矢、財政政策走りつぼみ、成長戦略は影も形もなかった。 規制緩和が起爆剤と言われていたが、一向に進まなかった。 第一次安倍政権はガチガチの官僚政治を打破する、という高い目標があり、 私も応援したものだが、官僚の攻撃に一敗地にまみれた安部さん。 ここで悪い学習をしたか、創価学会だけでなく、統一教会とも手を組み、 裏金でも何でも使って、とにかく数を増やすことに励んだ。 おかげで選挙は連戦連勝。自民党は、安倍派は絶大な権力を得た。 それを官僚体制の打破に繋げるはずが、いつしか自分のお友達を優遇する政策に。 モリカケサクラ、統一教会、裏金と、なんでもありだった。 ・・そのおおもとにあったのが異次元の金融緩和。 今や大量に抱えた国債を目の前に、海外との金利差解消のために、 金利を上げたくても上げられない。 MMTを主張する人たちは、どんどん国債を発行して、日銀が引き受ければいい、 という。さすがにそれは無理がある、と思う。 しかし同時に、ほんとに日本の財政赤字は酷いものなのかということには疑問を持つ 国のBSがどうなっているのかさっぱりわからない。 債務は分かった。しかし債権は?アメリカの債券を相当持っているのでは? その金利収入は??さっぱりわからない。 ・・・日銀に勤めた著者の新書を読んで、整理したのは以上。 第1章 異次元緩和は成功したのか? 第2章 高揚と迷走の異次元緩和 前代未聞の経済実験の11年 第3章 異次元緩和の「罪」 その1 すべては物価目標2%の絶対視から始まった 第4章 異次元緩和の「罪」 その2 超金融緩和が財政規律の弛緩を生み出した 第5章 異次元緩和の「罪」 その3 介入拡大が市場をゆがめる 第6章 異次元緩和の「罰」 その1 出口に待ち受ける「途方もない困難」 第7章 異次元緩和の「罰」 その2 なぜ立ち止まれなかったのか? 第8章 異次元緩和の「罰」 その3 国と通貨の信認の行方 第9章 中央銀行を取り戻せ 第10章 中央銀行とは何者か あとがき
Posted by
新卒で日本銀行に36年間勤めた人が書いたので、日銀の役割についてはかなり詳しい。また黒田東彦の異次元緩和が開始する前に日銀を退職しているので、異次元緩和について客観的に書ける。異次元緩和の罪というのは、とにかく日銀に国債を買いまくらせたことだ。11年間で457兆円も買増ししたの...
新卒で日本銀行に36年間勤めた人が書いたので、日銀の役割についてはかなり詳しい。また黒田東彦の異次元緩和が開始する前に日銀を退職しているので、異次元緩和について客観的に書ける。異次元緩和の罪というのは、とにかく日銀に国債を買いまくらせたことだ。11年間で457兆円も買増ししたので、この間の新規国債発行額480兆円の95%に当たるというのですから、日銀による財政ファイナンスであったことは明らかです。 問題は異次元緩和を終了させても、金融引き締めも日銀の保有国債の放出もできないことです。中央銀行の最も重要な役割は通貨の信任の確保なのですが、中央銀行が長期国債漬けなのですから、取りうる金融政策の幅は著しく制限されたままです。そして金利が上昇すれば国債が暴落し、日銀は債務超過に陥る可能性が高い。そうなれば円の信任が低下し、通貨危機みたいなことに陥ることは大いにありうるのだと思います。黒田元総裁は、2年程度で実現できるとしてあらゆる大胆な金融政策を総動員しましたが、一向に物価が上がらないので、ズルズルと10年間も日銀に国債を買いさせ続けたのです。 日銀が銀行から国債を必ず買ってくれるのですから、政府がどんなに新規国債を発行しても銀行は安心して引き受けることはできます。政治家もお金を心配することなく景気のいいことを言って、税金をばら撒けるという都合の良い構図が続いたのです。 そもそも、「物価が上がるという心理的な期待があると消費者は余計にものを買うので景気が良くなる」というのは本当のことだったのでしょうか?実際には、外食の値段が上がれば外で食べないようになるし、余計なものを買わないようにして生活防衛に走るのが普通です。顧客の創造を行うことによって生産性を上げることにより経済を成長させることが本道であり、金融政策だけで景気が良くなるはずがないのです。異次元緩和をスタートさせた当時は、リフレ派経済学者が盛んに日銀批判を繰り返していましたが、リフレ派は日銀を機能不全に陥らせたのだと思います。 この国は、どんな失敗をしてもその人たちはその失敗を認めず、認めないからいつまで経っても新しい道に切り替えることができないのです。たぶんあと数十年後にならないと異次元緩和の歴史的な総括はできないのかもしれません。
Posted by
アベノミクスが始まったときから、こんなことをして大丈夫なのかと大いに疑問であったが、今現在既にこれが失政だったことは明らかなのに、未だそれにすがっている人間が多い。 その罪は財政規律の弛緩、市場機能の低下、金融システムの弱体化などである。その内容と検証について本書には詳細に書かれ...
アベノミクスが始まったときから、こんなことをして大丈夫なのかと大いに疑問であったが、今現在既にこれが失政だったことは明らかなのに、未だそれにすがっている人間が多い。 その罪は財政規律の弛緩、市場機能の低下、金融システムの弱体化などである。その内容と検証について本書には詳細に書かれている。しかしもう過ぎてしまったことなのでどうしようもない。 で、罰その1は出口戦略への途方もない困難である。日銀の国債残高の圧縮に最低10年はかかる。その間誰が日本の国債市場に資金を供給するのか。民間金融機関は借換債の消化だけならできそう。だが新規国債の消化は財政規律の正常化の過程で時間が経つにつれて買い手不足が強まることは明らか。 その2は立ち止まれなかったこと。その効果が想定を常に下回っていたことから、誤りを認められずだらだらと続け、審議委員も任期を迎えた者は安倍内閣によって任命された腰巾着委員に代えられていった。 その3は国と通貨の信任低下。保有国債の緩やかな圧縮を図る際に、また景気の悪化やショックが起こり、政府から国債買い入れを迫られ、再び財政悪化そして圧縮とループしてしまう。また、圧縮には長期間を有することから、市場が日本円の信任にいつ疑問符を突きつけるか。 そして日本経済が取り返しのつかない状況になっても、アベノミクスを推進した人間は一ミリも責任を取ることはないのだ。大本の責任者は死んでしまったし。
Posted by
2024年81冊目。満足度★★★★☆ 当初目論見通りにならず、2024年3月に終わった日銀「異次元緩和」 本書は、当事者の日銀がまだ行なっていない異次元緩和の「総括」を日銀に36年間勤務した著者が、簡潔かつ冷静にデータを用いて行なったもの 読んで損なし
Posted by
これを読んでインパール作戦を思い出した。リフレ派の功名心を満たすことが隠れた目的で、目標の妥当性も手段の有効性も、またその副作用も真面目に検討されず、時の政権に良いように利用された。インパールで言えばまだ烈師団がコヒマを落としたくらいか。死屍累々の白骨街道が出来るのはこれから。こ...
これを読んでインパール作戦を思い出した。リフレ派の功名心を満たすことが隠れた目的で、目標の妥当性も手段の有効性も、またその副作用も真面目に検討されず、時の政権に良いように利用された。インパールで言えばまだ烈師団がコヒマを落としたくらいか。死屍累々の白骨街道が出来るのはこれから。こんな無謀な作戦に付き合わされた我々はたまったもんじゃない。もう一つのインパールとの類似点は意思決定者が誰も責任を取らないこと。これから何が起きるかによるが、河辺や牟田口のように黒田も無能な指揮官の代名詞として歴史に名を残すことになるだろう。
Posted by
- 1
- 2