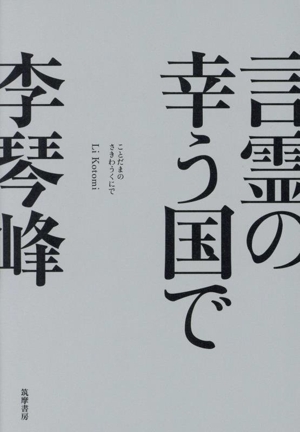言霊の幸う国で の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
批判ばかりで疲れてしまった。もう少し、物語として読める部分が欲しかった。 事前情報としてこの本の祝詞部分は無断使用・改変の訴えが出ていることを書いておく。 詳しくは下記。たまたま目にしただけです。 『神道LGBTQ+連絡会 筑摩書房発行の李琴峰氏著『言霊の幸う国で』における祝詞等の無断使用・改変について』 http://shintolgbtq.com/ 私はLGBTの情報は得ているので、この本に関しては最初から懐疑的立場だと書いておく。私の感想も『偏っている』と思ってもらっていい。ただ、全ての情報を追いかけてるわけではないので、抜けてる情報は多々ある。こう言うセンシティブな話題は「こういうことも知らないの?」という事をいう人が出てくるけど、「あなたが知ってる情報を全ての人が知っているわけではない」とだけ返しておきたい。(と、事前に書いておいたら、この本自体が『こういう事も知らないの?』という本だった。) さて、さっそく感想を……と言いたいけれど、もう一つ書いておきたい。 最後の注意書きに『作中の主人公は、著者本人ではなく、作中に登場する実名の人物も、実在の人間と完全に重なるわけではありません。ただし、作中で批判対象として実名で引用したテキストは、すべて実在のものです。』 ……小説を個人批判の道具にするな。と思ってしまった。『作中の主人公』を使って、実在人物の批判するのはやってはいけない事だと思う。twitterで未成年者がこの作品の感想で『こんな批判をしていいんだって思った。私もそうしたい』というようなことを書いているのを見かけた。個人批判はリスクが高すぎるのでやめた方がいい。自分の評判を落とすだけ。 残り感想はブログで……言葉が乱暴になってしまった部分もあるのでブクログでは控えます。
Posted by
前情報なく、タイトルに惹かれて読み始めた一冊。 著者の『彼岸花が咲く島で』は「言葉」の持つ力が大変印象的な作品だったこともあり、どういう意味なのかと思って読み始めたが、Lという女性が芥川賞を受賞する場面から始まり、実在の人物の名前も出てくるため、一瞬ノンフィクションか自伝か?と思...
前情報なく、タイトルに惹かれて読み始めた一冊。 著者の『彼岸花が咲く島で』は「言葉」の持つ力が大変印象的な作品だったこともあり、どういう意味なのかと思って読み始めたが、Lという女性が芥川賞を受賞する場面から始まり、実在の人物の名前も出てくるため、一瞬ノンフィクションか自伝か?と思いながら、その筆致の強さにぐいぐい引き込まれていく。 LGBTQに対する想像を絶する差別言説やヘイトクライムは、その酷さを知った気になっていたが、実際には本当におぞましく、信じられないとしかいえないものであった。また、差別と闘いの歴史も、深く長く辛いものであるということを、作品を通じて学ぶことになった。自分自身の理解や知識がいかに浅はかなものであったか。 差別する人、誹謗中傷をする人に対抗する人は、実名で戦うのに、加害者側はネットの中で匿名で酷い言葉を書き連ねている、と主人公が指摘する構図は、改めて今の世の中のおかしさを浮き彫りにするものであった。 タイトルは、初めは皮肉めいたものかと思って読み進めたが、命を断つことを考えながらも、小説家として言葉で記録すること、戦うことを選ぶ主人公の強さを見て、本当に言葉の力を信じている人でなければ書けない作品である。
Posted by
芥川賞作家の受賞後の日記にしてはタイトル重々しく出たな、と思いながら読んでたらタイトル以上に中身重かった。 LGBTQとかまるで不勉強「同性婚とか認めようが認めなかろうがオイラにはあまり関係ないから、それで少しでも幸せになる、苦しみから解放される人がいるなら認めてもええやん」くら...
芥川賞作家の受賞後の日記にしてはタイトル重々しく出たな、と思いながら読んでたらタイトル以上に中身重かった。 LGBTQとかまるで不勉強「同性婚とか認めようが認めなかろうがオイラにはあまり関係ないから、それで少しでも幸せになる、苦しみから解放される人がいるなら認めてもええやん」くらいの意識しかなかってんけど、モノ知らんかったなぁ、と反省。 あと、笙野頼子とか豊崎由美とかエラい言われようやな。豊崎由美については今でも本は読んでるけどSNSやラジオの話は知らず笙野頼子は最近読めてないので、書かれ方が妥当なのかどうかは一方からだけ判断しても良くないのかもやけど。
Posted by
圧倒される分厚さとその内容。 頭をガツンと殴られたような気持ちになった。 今年は自分の無知と向き合う作品に出会えているなあと思っているけど、この作品もそのひとつ。
Posted by
やられた。 相変わらず入手するきかっけは忘れてしまっていて、 タイトルから、詩集かなにかと思って読み始めた。 まあそれにしちゃ分厚い本だなあと。 そしたらいきなり芥川賞受賞。台湾人初の! ん?ドキュメンタリーか?Lこと柳千慧(りゅうちさと)。 豊崎由美も出てくるし、、 いきな...
やられた。 相変わらず入手するきかっけは忘れてしまっていて、 タイトルから、詩集かなにかと思って読み始めた。 まあそれにしちゃ分厚い本だなあと。 そしたらいきなり芥川賞受賞。台湾人初の! ん?ドキュメンタリーか?Lこと柳千慧(りゅうちさと)。 豊崎由美も出てくるし、、 いきなりSNSの反日バッシング。安倍首相を批判したと。 女性差別、外国人差別。ストーカーもいた! 今度はレズビアンバッシング。そう、彼女は30代前半のレズビアン、、、 同性愛差別。 と思いきや、 台湾から「彼女はトランスジェンダーだ」のSNS。 トランス差別。 一気に泥沼と化すSNS。 すさまじい。 これに抗うL。 後半はトランスジェンダーに対する著者の見解が滔々と述べられる。 大井に賛同する。 そもそもトランスジェンダーについては私も不勉強だった。 なぜ生まれた体にメスを入れてまで性転換をするのか、と。 それはそれを強いる法律があったから。 そうしないと彼ら彼女らは生きづらいから。 要するに弱者いじめ。マイノリティいじめだ。世の中のわずか0.5%に対して。 気づかずに差別してしまうことについては学習するしかない。 声に耳を傾けるしかない。 しかし、意識的に差別する人、自分の価値観以外は認めない人、集団についてはどうしたものか。 その権化に自民党があるとは、なんとも情けない話だ。一部の議員が裏にある組織に動かされ、、、 それに煽られ教養のない人が乗っかり、数の力になる。そうした議員を当選させる。 そういうときは比例区なんてなくせばいい、と思うが、 個人を選ぶのも党議拘束で無意味とも思う。 やはり党自体を選ぶしかない。選ばない、しかない、だ。マイナス投票権が欲しい。 話が逸れた。 自分だけは安全な場所にいると勘違いしているからこそ、マイノリティを差別できる。 東大卒の勘違い、世襲議員の勘違い。ほかにもいろいろあるだろう勘違い。 反知性主義、そのものだ。 過去はマイノリティの犠牲の上に繁栄があったのかもしれない。 成長なき現在、それが悪質化する。少ないパイをマジョリティが奪おうとする。 そこには何の根拠もない。 マイノリティを応援したい。 プロローグ 第1章 栄光 第2章 暗影 第3章 虚像 第4章 狭間 第5章 傲骨(ごうこつ) 第6章 兆候 第7章 俯瞰 第8章 因果 第9章 喪失 第10章 邂逅 第11章 時代 エピローグ 五十年後のあなたへ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
史上初の台湾人芥川賞受賞作家による、半自伝的小説。 母国語でない者が外国語で小説を書くだけでも目が飛び出るくらいすごすぎるのに、それで日本文壇の最高峰とされる芥川賞を受賞するなんて、あり得ないじゃん、と素直に驚愕している。しかし、その境遇は決して楽観視していられるものではない。その過酷な現実を如実にさらけ出してくれるのが本作。ある意味、現代という時代の嫌な側面をこれでもか、これでもか、と見せつけてくれる、衝撃的な問題作だ。 Lこと柳千慧(りゅうちさと)は『彼岸花が香る島』で芥川賞を受賞。鳴かず飛ばずの外国人作家として日本で焦燥感に駆られていた新人作家にとっては、これから栄光の日々が始まるはずだった。が、受賞スピーチの際に、時の元首相安倍晋三氏への苦言を呈したことからネトウヨに絡まれ、一気にヘイトスピーチの標的とされてしまう。 彼女は外国人であるだけでなく、レズビアンでもあった。受賞をきっかけに名が知られたことから、台湾にいた頃の元恋人に目を付けられ、執拗なストーカーに合う羽目に。それが一段落すると、今度は、トランスジェンダーだったことが台湾からバレていくという急展開に。 彼女にとって、トランスであることは最後まで隠し通したい秘密だった。しかしバラされたことで、徹底してこれに向き合わざるをえなくなっていく。 トランスの置かれた状況が、ことのほかひどい現実が、ありありと、詳細に描かれていく。特に、男性の肉体を持って生まれてしまったけれども内心の実存は女性でしかありえないトランスは、世の人々から徹底的に嫌悪され、差別される。いわく、女子トイレや女風呂に男が入ってくるぞ! そんな世の中ありえるか? などといった誤解が平然とまき散らされる。しかも差別は世のマジョリティばかりではない。あろうことか、本来ならともに戦うべき側の人々、すなわち、マイノリティであり長らく被差別側として辛酸を嘗めさせられてきたレズビアンやジェンダー活動家からも敵対視されてしまうという悪夢。つまり、男の体を持っていること自体が、彼女らにとっては我慢がならないという理屈だ。 しかし、Lたちトランスは、心の実存として、女でしかありえない。自分自身で生きていきたいだけなのに、たまたま生まれ持った肉体がそれを邪魔しているという現実。 さらに複雑さを増しているのは、肉体は男性のトランスで、かつレズビアンだという現実。それって、結局、おかまのふりをした男が単に女好きだったってだけじゃん、と容易に曲解にされてしまうのだ。 このように、本作は、前半は外国人差別から一般的LGBT差別の現実を背景としているが、後半は一気にその差別の中の差別ともいうべき、あるいは現代版差別の最先端を行く差別へと展開していく。 私自身は、性別でなぜこうも人は人を差別したがるのか、なぜそこまで性別にこだわるのか、不思議に思う。好きになった相手がたまたま同性だった。ただそれだけのことだ。なぜ同性だとそこまで嫌悪され、憎まれ、社会から排除されるのか。周囲の理解と社会の承認を得るために、なぜそこまでエネルギーを費やさなければならないのか。理解に苦しむ。 人を好きになるのに、ルールも何もあったものではない。人は異性を好きになるべきである、といった社会的通念は、単に社会が後天的に作り出したものでしかない。 人が人を好きになる。ごく自然なことだ。自然のはたらきかけに人は抗えない。たまたま相手が同性だった、その自然のはたらきに目くじら立てて憎悪の炎をたぎらすなんて、どうかしている。エネルギーの無駄遣いだ。 しかし、多くの人はそのエネルギーの無駄遣いを延々と繰り返してきている。その傾向は、とりわけ近代以降、熾烈さを増す一方だ。古代は違った。もともと、人々は同性愛に寛容だった。日本でも江戸時代は性に対してあまりにもあけっぴろげでおおらかだった。その事実は、ヨーロッパの宣教師等による報告文書でも明らかだ。そんなヨーロッパでも、古代ギリシャでは、同性愛はむしろ社会的ステータスの表れだった。 そう、とにかく、性に関するタブーや認識は、社会や時代によっていとも簡単に変えられていく代物でしかない。そんなやわな代物を、人をわざわざ傷つけるためだけの道具として採用している。それが現代版暴力の噴出という表現をとって、いま私たちの目の前に繰り広げられているのだ。 そんな社会の圧倒的暴力を前に、安易な泣き寝入りに逃げ込むことなく立ち向かう姿勢を貫いた本書。その雄姿にただただ敬服するばかりである。
Posted by
LGBT特にTへの差別を主題としたフィクションともノンフィクションとも社会批評ともいうべき作品 1.そもそも私のLGBTへの多くの蒙を啓いてくれた 2.一部に安倍・自民政権批判の部分があるが、石破氏が総裁となった日の翌日に本書を読了したことはタイミングとして幸いであった。一昨日...
LGBT特にTへの差別を主題としたフィクションともノンフィクションとも社会批評ともいうべき作品 1.そもそも私のLGBTへの多くの蒙を啓いてくれた 2.一部に安倍・自民政権批判の部分があるが、石破氏が総裁となった日の翌日に本書を読了したことはタイミングとして幸いであった。一昨日、つまり麻生の態度表明で高市確実かという状況で読み終えていたら、絶望感も深かったことであろう(もっとも今後どうなるか予断は許さないが)。 3.内容にいくつかの疑問が涌いたが、小説として深みを加えていると言えばよいだろうか いずれにせよ、ジェンダー問題に関心のある人ない人、いずれにとっても必読の書であり、大作ではあるが一気に読ませ、同時に、深く考えさせる傑作である。
Posted by
あらゆる差別に抗する、という帯の表現の通りだった。 暗澹たる気持ちになるところもあったけど、50年後に、変わっていたら良いな、変えたいなと思える読後。
Posted by
李琴峰さんはすごいです。前線で戦っている。小説の力を感じました。 ジェンダー、台日関係、ネトウヨ、安倍晋三、統一教会など、整理してくれているので、勉強にもなり、備忘にもなりました。
Posted by
SNSでの誹謗中傷や政治など安倍政権、コロナ時代の時事と主人公Lが直面している数々の問題が小説として語られている。 本当に大人になるまで台湾に住んでいたのか??と疑うぐらいに日本に精通し、言葉も日本人以上にしっかり理解している、 読むのに苦労するが対抗意識が強いのか知識が深まると...
SNSでの誹謗中傷や政治など安倍政権、コロナ時代の時事と主人公Lが直面している数々の問題が小説として語られている。 本当に大人になるまで台湾に住んでいたのか??と疑うぐらいに日本に精通し、言葉も日本人以上にしっかり理解している、 読むのに苦労するが対抗意識が強いのか知識が深まると勘違いなのだが、読み終える達成感と勘違いのためだけに読み進める。
Posted by
- 1
- 2