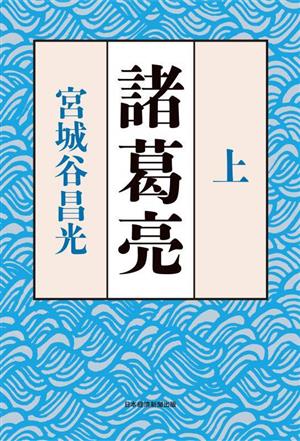諸葛亮(上) の商品レビュー
宮城谷さんらしい丁寧な筆で描かれた成長譚。吉川英治版三国志とセットで読むと、より楽しめると思います。
Posted by
三国志演義では、伏龍としての諸葛亮でしか出てこないが、そのルーツがわかってまた違った角度で味わえるので面白い
Posted by
三国志関連の小説はいくつか読んだが、諸葛亮にフォーカスを当てた話は初めて。神格化された天才軍師が幼少何をしていたのか、周りの史実と兼ね合わせて楽しく読めた。 兄の諸葛瑾と別の人に支えたのはなんでなのかという積年の悩みもついに解けた!
Posted by
簡潔な文章で流れるように読みやすかったです。 自分がイメージする諸葛亮がどのように生まれたかが知りたくて、どんどん読み進めることができました。 抜群に有名な「諸葛亮孔明」は、人それぞれにイメージ像ができあがっていると思います。でも、誰のイメージを持ってしても、この本を読みながら...
簡潔な文章で流れるように読みやすかったです。 自分がイメージする諸葛亮がどのように生まれたかが知りたくて、どんどん読み進めることができました。 抜群に有名な「諸葛亮孔明」は、人それぞれにイメージ像ができあがっていると思います。でも、誰のイメージを持ってしても、この本を読みながら描き出される脳内映像は、どんな像でも違和感なく再現されるような気がします。 筆者の読者への思いかな、と感じました。
Posted by
孔子は、学べばすなわち固くならず、と言った。本気の学問は、他人を宥せるようにさせるというより、おのれを宥すことができるようにさせるとおっしゃった。もっと学び、己に寛容になれ。 知るとは人を知ることだ、と論語にある 朽ちた木の橋でも渡り切ることができるかもしれない。築いたばかり...
孔子は、学べばすなわち固くならず、と言った。本気の学問は、他人を宥せるようにさせるというより、おのれを宥すことができるようにさせるとおっしゃった。もっと学び、己に寛容になれ。 知るとは人を知ることだ、と論語にある 朽ちた木の橋でも渡り切ることができるかもしれない。築いたばかりの石の橋でも足を乗せれば崩落するかもしれない。どこが危険で、どこが安全かはわからない。 いつ好機がおとずれるかわからない。それが人生というものであり、それまで不遇であるのが常である。もっと言えば、不遇の過ごし方によって好機が生まれる 憧れを持つことだ、それは志とひとしくなる 儒教には、おのれに及ばぬ者を友としてはならない、という教義がある 無益も益に変わる時があり益も害に変わる時があるので、全く無益というものはない 今は自分に正直に生きるのが難しい世である。生涯それを貫ける人などほとんどいないと言ってよい 劉備は利害関係を見定めて進路を決めたことはほとんどない。利を求めて動けば、害に遭う、おそらく劉備の思想の一部はそういうものであろう 大事を成すには、必ず 人をもととする 物を得ようとせず、人の心を得ようとす 悪は小さいからといって、これを為してはならず、善は小さいからといって、これを為さないことがあってはならない
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
諸葛亮孔明を描いた中国歴史小説の上巻。 上巻は劉備の益州入りまでです。 著者の「三国志」は群像劇になっているので、諸葛亮支店での物語はうれしいです。 史料に登場するのは三顧の礼からだと思いますが、それまでの来歴はあまりよく知らなかったので、フィクションとは思いますが面白かったです。 特に叔父がいい人で素直に成長させてもらえたのは、いつもの著者の主人公びいきとしても気持ちが良かったです。 ただ、三顧の礼以降は「三国志」と重なるエピソードが多くなると思うので、諸葛亮視点でどのように描くのか期待したいです。
Posted by
最近は漫画の主人公になる程、日本では 絶大の人気の諸葛亮孔明! ただ、宮城谷さん作品の三国志では 厳しく書いていた印象だった。 しかし、この作者さんは作品によって 人物像が変わる場合もあるので少し期待 したが、、、、 なんか愛が感じられない。 物語が淡々と進んでいる感じ。 ...
最近は漫画の主人公になる程、日本では 絶大の人気の諸葛亮孔明! ただ、宮城谷さん作品の三国志では 厳しく書いていた印象だった。 しかし、この作者さんは作品によって 人物像が変わる場合もあるので少し期待 したが、、、、 なんか愛が感じられない。 物語が淡々と進んでいる感じ。 下巻を読むか迷ってしまう。。。
Posted by
下巻が楽しみ。もっと感情移入された進み方かと思ったら、淡々とストーリーは、進んでいく。下巻はどうでしょう。
Posted by
中国後漢〜三国時代。世は乱れ、群雄が割拠し覇を競っていた。 これは、群雄の1人である劉備に仕えて蜀漢建国に尽力し、三国鼎立実現の立役者となった諸葛亮の生涯を描いた伝記ロマン作品である。 なお上巻で描かれるのは、父と兄に薫陶を受けた8歳頃から劉備の軍師として主君の益州...
中国後漢〜三国時代。世は乱れ、群雄が割拠し覇を競っていた。 これは、群雄の1人である劉備に仕えて蜀漢建国に尽力し、三国鼎立実現の立役者となった諸葛亮の生涯を描いた伝記ロマン作品である。 なお上巻で描かれるのは、父と兄に薫陶を受けた8歳頃から劉備の軍師として主君の益州入りを整える30歳頃までの諸葛亮である。 ◇ 亮は落日を見ていた。いつにも増して大きく美しい日がゆっくり沈みゆくさまに典麗な音楽を感じつつ佇んでいると、朱色の光の中に現れた黒い影が近づいてくるのが見えた。兄の瑾だ。 瑾は、学問をしに洛陽に行くことになりそうだと亮に告げた。張りのある声からは意欲と希望が溢れている。 亮より7歳上の瑾は今年15歳になり、志学の年齢を迎えた。父の珪も昨年から長男の留学についていろいろ考えていたようだが、兄に洛陽留学を勧めたのは叔父の玄だと亮は気づいた。瑾は現在、叔父に学問の手ほどきを受けている。 いよいよ瑾の出立の日。遠ざかる兄の姿を見送りながら亮は、自らの旅立ちの日を想像してみるのだった。 諸葛家の期待を背負い、瑾は洛陽で勉学に励んでいた。真面目で物堅い性格の瑾にとって花の都での日々は充実したものになるはずだったが、翌年この都で一大事が起こった。きっかけは霊帝の急な崩御だった。 ( 第1話「旅立ち」) 全15話。 * * * * * 宮城谷昌光さんの清冽な文章が好きで、三国志のファンでもあるため、ワクワクしながら上巻を読みました。 宮城谷さんは『三国志』同様に、この『諸葛亮』についても正史を紐解くことで筆を起こしているため、『三国志演義』主体の吉川英治『三国志』で描かれるような派手さはありません。 だから、豪傑たちの超人的な活躍も名軍師たちの神懸かり的な深謀遠慮も出てこないのです。 それだけに却って、「三顧の礼」や「水魚の交わり」といった故事成語を生み出したエピソードにはリアリティを感じましたし、孔明が農業に高い関心を寄せる描写も納得いくものでした。 最も印象的だったのは、孔明が劉備軍について、腹心の斉方に語ったことばです。 「武功を誇らない家臣団」と「功を上げた者を激賞しない主君」という劉備軍の奇妙さについて尋ねた斉方に、孔明は次のように説明します。 劉備軍は「主従関係」というよりも、「親子・兄弟の関係」が発展したものなのだと。 つまり、「御恩と奉公」のような論功行賞で結びつく関係ではなく、全員が一丸となって家長を支え家の繁栄に尽くす家族の絆で結ばれている関係。それが劉備軍であるというのが、孔明の見解なのでした。 確かに、劉備と関羽・張飛の関係は義兄弟だし、糜竺は劉備にとって「金持ちのじいちゃん」のような間柄だし、孫乾は劉備の面倒を細々と見てくれるおじさんのようだし、後に加わった趙雲や孔明も劉備の甥っ子のような身近な存在になっています。 領土を持たぬ主君が一国一城の主になるまで支え続けた旗揚げメンバーには、自分が劉備を1人前にしてやるぞという強い思いがあったと、宮城谷さんは言いたかったのだと思います。 劉備の死後、声高に功を主張する家臣が増え、自身の扱いに不平不満を募らせる魏延のような輩が出てくるのを見ると劉備の偉大さがよくわかります。 少し残念だったのは、史実として残っている関羽千里行や張飛が長坂橋を大いに騒がしたエピソードが紹介されていなかったことでした。 孔明とは関係ないので省略されたのかも知れませんが、趙雲の阿斗君及び甘夫人救出については触れられているので、何か不公平な気がしました。( つまらないグチです。ごめんなさい )
Posted by
爽やかで飄々とした諸葛亮。 突飛な事は少なく相談役的な諸葛亮? 劉備に対する人物像は言葉にしてもらってスッキリした。 蜀側に聖人君子が多過ぎてちょっとお腹いっぱいになるかも。
Posted by
- 1
- 2