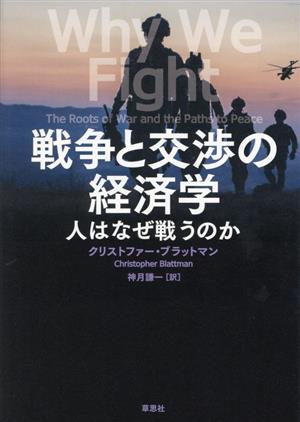戦争と交渉の経済学 の商品レビュー
戦争というのは利益が相反する両者の均衡が崩れた時に発生するという視点で、戦争を回避する方法、そして平和を維持する方法を解く本。 前半は、交渉という視点で、戦争が如何にレアケースであるかが分析される。ここは結構おもしろかった。戦争というのは両者にとってデメリットが大きいので、そこ...
戦争というのは利益が相反する両者の均衡が崩れた時に発生するという視点で、戦争を回避する方法、そして平和を維持する方法を解く本。 前半は、交渉という視点で、戦争が如何にレアケースであるかが分析される。ここは結構おもしろかった。戦争というのは両者にとってデメリットが大きいので、そこに至らないように事前に交渉が行われる。だから、戦争というのは、利害調整の失敗であり、例外ケースなのだと。 そして、戦争を引き起こすものとして、 ・抑制されない利益 ・無形のインセンティブ ・不確実性 ・コミットメント問題 ・誤認識 が取り上げられる。 後半は、前半からの反転で、平和を維持する方法が書かれるのだけど、前半部分の言い換えみたいなところがあって、若干ダルかった。 最終章は、戦争回避と平和構築への万能薬はなく、少しずつ実現していく方策を探らなければいけないという、著者の思いが語られる。この漸進的に進めるという信念を整理した「平和工学者のための十戒」は、個人的な人生観にも合っていて、良い言語化だと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
戦争が起こる理由をゲーム理論など科学の様々な側面から解き明かした本。 戦争が起きる理由は5つある。 ・抑制されていない利益 ・無形のインセンティブ ・不確実性 ・コミットメント問題 ・誤認識 そして平和をもたらす術を述べている。 特に興味深いのが交渉領域の概念である。 客観的にみて交渉可能な範囲のことを指す。 交渉領域が狭いほど戦争が起こる可能性が高まる。 逆に交渉領域が広いほど戦争が起こりにくくなる。 なぜなら交渉領域の範囲は戦争により消滅し、パイが減少するためだ。 戦争より和平を選択した場合の得られる期待が大きいのだ。 普段の生活でも戦争は避けるべきと示し、 そのための手段が提示されている本だった。
Posted by
戦争といった暴力が発生するメカニズムをミクロ経済学の枠組に当てはめて分析する。筆者によれば、世の中のほとんどの対立は暴力までには至らないが、抑制されていない利益、無形のインセンティブ、不確実性、コミットメント問題、誤認識、といった要因があると戦争が発生しやすい。それ以外の自然災害...
戦争といった暴力が発生するメカニズムをミクロ経済学の枠組に当てはめて分析する。筆者によれば、世の中のほとんどの対立は暴力までには至らないが、抑制されていない利益、無形のインセンティブ、不確実性、コミットメント問題、誤認識、といった要因があると戦争が発生しやすい。それ以外の自然災害や経済状況の悪化などは、背景事情であって必ずしも暴力に繋がるわけではないとする。敵対するグループに対して交渉余地があるのであれば暴力を避けるのが合理的であるが、上の5つの要因は交渉領域を狭めるものとなっている。 後半では、暴力に至る5つの要因に基づいてそこに至るのを回避するためのアプローチとして、相互依存、抑制と均衡、規制、介入を紹介する。 筆者の分析は論旨明快で分かりやすく、勉強になった。
Posted by
グローバル化が戦争リスクを減らすとあったが、昨今話題の経済安全保障は逆コースではないのか。独裁者が統治する自給自足可能な大国が戦争リスクが高いと考えられ、現在の世界状況はそれを証明している。
Posted by
レビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12840196241.html
Posted by
これは凄い。閉じていた目を開かされた。独裁国の暴力による恫喝や他国への侵攻。断じて許せないと思う。だからと言って戦争は悲惨過ぎる。戦略的に交渉し妥協する他ない。あくまで現実的に考え社会を科学する。一国の政策にはこういう思考が必要だ。
Posted by
- 1