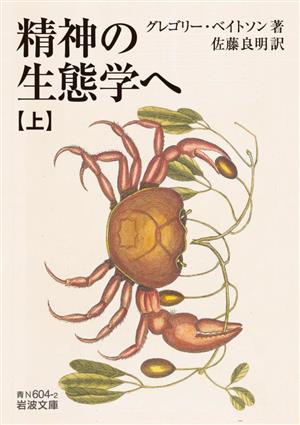精神の生態学へ(上) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本書シリーズは私の大学生活で最も影響を受けた本の1つである。 その上巻である本書には、グレゴリー・ベイトソンの主要概念である「分裂生成」、「論理階型・メタメッセージ」などが登場する。印象的な記述が至る所に散りばめられているが、その中でお気に入りの一節を記しておく。 父 「言語(language)が言葉(words)から成るとい う考え自体がナンセンスだ。...。「ただの言葉」 なんてものはないんだから。」
Posted by
メモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1783820204046491994?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
Posted by
ベイトソンは難しいという固定観念が強固にあったが、「やさしいベイトソン」を読んで、もしかして読めるかも?と思って、挑戦。 文庫本になったので、中古の高い本を買わなくても良くなったし。 上巻の冒頭は、娘との対話を通じて、ベイトソンの思想を伝えつつ、だんだんずれていく感じ、循環す...
ベイトソンは難しいという固定観念が強固にあったが、「やさしいベイトソン」を読んで、もしかして読めるかも?と思って、挑戦。 文庫本になったので、中古の高い本を買わなくても良くなったし。 上巻の冒頭は、娘との対話を通じて、ベイトソンの思想を伝えつつ、だんだんずれていく感じ、循環する感じもあり、決して、父が娘に伝える〇〇学にはならないところが良い。 そして、後半はまずは人類学者としての代表的な論考が紹介される。最初の「文化接触と分裂生成」は、ほぼ何を言っているか分からず、やっぱベイトソン苦手と思うのだが、その後の講演や論文、エッセイは思ったより読みやすい。 現時点は、疑問符がたつ論考もあるのだが、ここで読むべきことは、彼の議論の内容というより、思考プロセスの方。要るにこれはシステム思考というか、サイバネティクスではないか。 人類学的なフィールドワークを積み重ねつつ、何らかのコンセプトを見出すとそこから俯瞰的に全体を見て、目に見えないダイナミクス、システムを発見していくような感じ。 ギアツなどの解釈学的な人類学では、勝手に一般化、理論化しているという批判も多分あるだろう。そして、私もそうだと思う。 が、それでもワクワクするのは、ベイトソンの思考が見えてくるからだ。なんだか、自分と似たタイプの人かもしれないと思い始めている。 さて、中巻は、精神医療的な世界、いわゆるダブル・バインド論の登場だ。楽しみだ。
Posted by
- 1