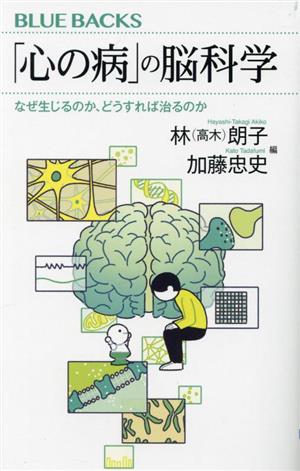「心の病」の脳科学 なぜ生じるのか、どうすれば治るのか の商品レビュー
「心の病」の脳科学 4/12 最近この手の本を読んで思うのは、この感情はただの複雑な電気化学反応かということ。観測・測定技術がないだけで今は理解できないだろうが、ブレイクスルーで一気に明らかになりそうな感じがある。 では感情が化学的に理解された時、科学知識がない人には普及せず、...
「心の病」の脳科学 4/12 最近この手の本を読んで思うのは、この感情はただの複雑な電気化学反応かということ。観測・測定技術がないだけで今は理解できないだろうが、ブレイクスルーで一気に明らかになりそうな感じがある。 では感情が化学的に理解された時、科学知識がない人には普及せず、知識がある人々の中で醸成、封印されるのではないだろうかと心配になる。 細分化が進む中、すべてを追うのは難しい・・・と今は思うが、上記技術革新後の世界では、そんな馬鹿な話はないと言われている気がする。 できればそんな世界を見てみたいし生きたい。(まぁ過去の人から見たときそれは今なだだが)神を証明できたとき、人はどうなるんだろう?生命を生産するのだろうか? 確率 一生のうち精神疾患(心の病)にかかる率 80% 統合失調症 100人に1人 双極性障害 1000人に4-7人 自閉症 1000人に1-2人 うつ病 1000人に8人 ADHD(12歳まで)100人に3-7人(男児のほうが女児より3-5倍高いとされる20人に1人) ADHD(大人)100人に2.5人(男女比1:1 40人に一人) 遺伝的要因の強いもの ・双極性障害 ゲノムの中を飛び回る転移遺伝子の影響(体細胞変異につながる)が指摘されている ・統合失調症 同上 ・自閉症 環境的要因が強いもの ・うつ病 注意:強い遺伝要因を持っていても、発症するとは限らない。変異の影響より前に、認知機能障害や、人とかかわる社会機能の低下があり、いじめ孤立などの心理的ストレスによって発症の引き金になるかのうせいもある。 脳の疾患 ・神経性疾患 細胞死 ・精神疾患 脳に顕著な委縮、神経細胞死が見られないもの。神経細胞やシナプスの働き方の変化、神経回路の配線の変化(顕微鏡レベルではかいめいできない)神経伝達物質の異常 転移遺伝子について。 用語やメカニズムは割愛。 転移頻度が上がる要件としてウイルス感染が考えられている。妊婦がウイルスに感染すると、免疫活性があがり、サイトカイン(炎症物質)が生成、胎児に移る。マウスではこの物質を胎児に投与すると、精神疾患(特に統合失調症)と関連する症状を引き起こすことが知られている。 ADHD 有病率は変化している。12歳まで3-7%。大人2.5%。子供のころに診断された人を定期観測すると、18~20歳で6割の人が診断基準を満たさず、外れることになる。が9割以上の人が成人になっても日常生活で困難を抱えた状態になる(詳細は割愛P137-8 参照)。最近の報告ではこれらと違う結果が表れている(詳細は138-140)これは診断基準がほかの疾患の症状に似ているため神経発達症のADHD以外の人も拾っている可能性が指摘されている。 なぜおこるのか、4つの障害仮説。 実行機能、報酬系、小脳機能、デフォルトモードネットワーク 子どもでは、親子相互交流療法(PCIT) 大人では 認知行動療法、投薬 双極性障害 ミトコンドリア機能障害が、カルシウム調節障害を引き起こす。カルシウム調節障害は感情関連神経回路を過剰興奮を引き起こす。物事を論理的に認識する働きよりも感情で処理する働きを強める(前頭前野の活動が低い)傾向になる。治療を続けても症状が改善されない中には双極性障害でない人もいる。(順天堂大学 気分障害センター40名より3割が該当) ニューロンフィードバックで精神精神疾患の治療ができるか。10年後には明らかになるそう。 自閉症スペクトラム。刺激が強すぎる→情報量を少なくすることで安定する。能面のロボットのほうがコミュニケーションを取りやすい。 参考書(ブクログ本棚参照) 疲労とはなにか すべてはウイルスが知っていた
Posted by
いわゆる精神病と言われる病。 「うつ病」「統合失調症」「双極性障害」「ASD」「PTSD」等など。 これらは目に見えない人の心の領域ではあるが、現存する物質である人体を依り代としているのだから物理的・生物学的な現象がどこかに生じて、このような病を発現しているはず。 というよう...
いわゆる精神病と言われる病。 「うつ病」「統合失調症」「双極性障害」「ASD」「PTSD」等など。 これらは目に見えない人の心の領域ではあるが、現存する物質である人体を依り代としているのだから物理的・生物学的な現象がどこかに生じて、このような病を発現しているはず。 というように精神病の結果系を見るというよりは、現象の原因として遺伝子や脳内の神経細胞を探ろうという試みの紹介である。 が、正直門外漢には難しすぎて途中で興味を失ってしまったので☆3つ。 ただ、よく聞くうつ病、双極性障害、統合失調症はみなよく似たものだと思っていたが、その発現機構は全く違うことに驚いた。
Posted by
ADHDの原因は以下の4つであるという仮説がある。 1.実行機能不全 2.時間感覚の障害 3.報酬系の障害 4.デフォルトネットワークの障害 4.は、新しい刺激に対して、ネットワークが上手く作用せず過剰反応してしまうという仮説。 ADHDは、感覚が鋭く傷つきやすい特性がある。...
ADHDの原因は以下の4つであるという仮説がある。 1.実行機能不全 2.時間感覚の障害 3.報酬系の障害 4.デフォルトネットワークの障害 4.は、新しい刺激に対して、ネットワークが上手く作用せず過剰反応してしまうという仮説。 ADHDは、感覚が鋭く傷つきやすい特性がある。投薬療法のメリットは、行動が慎重になること。リスクを取らない傾向になる。デメリットとして、興味が湧かなくなったり慎重になりすぎて行動ができない、などの弊害がある。投薬の良し悪しを判断して、ある期間は止めることも選択肢として入れることが重要かもしれない。
Posted by
脳科学の本、おもしろそう、と手にしたが、 難解!学術的!科学的!専門的!テクニカルターム続出。ついていけない。 やがて気づきました。これはブルーバックス。 難しいのは当然だった。 ということで、わかるところだけつまみ食い。 ASD。自閉スペクトラム症、コミュニケーション障害。...
脳科学の本、おもしろそう、と手にしたが、 難解!学術的!科学的!専門的!テクニカルターム続出。ついていけない。 やがて気づきました。これはブルーバックス。 難しいのは当然だった。 ということで、わかるところだけつまみ食い。 ASD。自閉スペクトラム症、コミュニケーション障害。 ADHD。発達障害。 そこに書かれている症状は、いま私が頭を悩ませている相手の特徴と酷似する。 苦手なこと ・興味が薄いことに注意が持続しない ・あることに関心を持ち続ける ・忍耐強く待つ、取り組むこと ・ミスのない作業、作業の完結 ・感情をコントロールする ・分析的な思考 ・順序だてて説明する ・巧みな嘘をつく ・傷つきからの立ち直り 下6つはぴったり。 こういうものを背負ったうえで、 どうやって社会人生活を送ってもらうか、だな。 遺伝子、環境、、、 脳はまだまだ奥深い。謎だらけだ。
Posted by
精神疾患や発達障害といえば、脳そのものの異状がわからないということであったが、最近の研究で、脳自体の小さな変化がこうした疾患や障害の発症に関わっているということが判明しつつあるというのである。 私自身発達障害の当事者ということもあり、自分自身どのような状態にあるのかを知りたく...
精神疾患や発達障害といえば、脳そのものの異状がわからないということであったが、最近の研究で、脳自体の小さな変化がこうした疾患や障害の発症に関わっているということが判明しつつあるというのである。 私自身発達障害の当事者ということもあり、自分自身どのような状態にあるのかを知りたくて読み始めたが、この状態について知ることができた。今後研究が更に進めば、その脳の変化に働きかけられるような治療法も確立できるのかなと、期待を持てるような1冊だった。
Posted by
ややハードな内容であったが、論文を読んだときのような満足感があり、現状で最先端の研究を知れたのではないかと思う。とくに、自閉症で見られる感覚過敏の仕組みが興味深く、また、ロボットとのコミュニケーションについてはなるほどなと思った。統合失調症の幻覚や妄想についても、シナプスの発火す...
ややハードな内容であったが、論文を読んだときのような満足感があり、現状で最先端の研究を知れたのではないかと思う。とくに、自閉症で見られる感覚過敏の仕組みが興味深く、また、ロボットとのコミュニケーションについてはなるほどなと思った。統合失調症の幻覚や妄想についても、シナプスの発火するタイミングが関係している可能性があることを知れてよかった。
Posted by
なかなか読み通すのは大変ではある。 でも、精神疾患についての研究の現在の、一角は見えてくる。 パーキンソン病やアルツハイマー、ALSなど、脳細胞が大量死する「神経変性疾患」は、脳そのものの変化から診断される。 けれども、精神疾患は、従来確認できる脳の異常がなく、症状から判断する...
なかなか読み通すのは大変ではある。 でも、精神疾患についての研究の現在の、一角は見えてくる。 パーキンソン病やアルツハイマー、ALSなど、脳細胞が大量死する「神経変性疾患」は、脳そのものの変化から診断される。 けれども、精神疾患は、従来確認できる脳の異常がなく、症状から判断するしかなかった。 そのため、ある症状が主症状なのか、他の障害から来る二次的なものなのかの判別も難しく、投薬その他の治療がうまくいかないこともあったという。 本書は、そういった精神医療の困難に対処するため、さまざまなアプローチの研究が発展したことを紹介していく。 脳の神経細胞のはたらきを解明して、神経の情報伝達回路の変調を調べる研究。 疾患の発症に繋がりやすいゲノム変異を探る研究。 環境要因としての慢性的なストレスや身体的な不調から脳内炎症のつながりを見て、疾患の原因をつきとめようとする研究。 ニューロフィードバックの新手法を用いて、PTSDの治療につなげるという研究や、ASDの子どもたちの社会性を発達させるためのロボットを用いた療育の研究なども紹介されている。 脳の報酬系を操作して感じ方を変えていくニューロフィードバックは、ちょっと恐いような気もするけれど。 過去には見えなかった変調がfMRIなどの新しい技術で見えるようになった。 その成果の一つでもある神経伝達の特性についての研究が進めば、創薬にもつながる。 治らないと言われていた精神疾患も、やがて治る時代がくるのかもしれないと思った。 「障害」であるASDやADHDも、この障害への認識は今後変わっていくのかな、と感じた。 ASDはスペクトラムだと近年よく強調されている気がする。 本書を読んで、ADHDもそれに近いものなのかな、と思った。 本書で紹介される研究にこんなものがあったからだ。 子どもの頃そう診断された人で、大人になってもそう診断しうる状態の人は6人に1人。一方、大人になってからADHDの症状が出てきた人で、子どもの時そう判断できる症状があった人はわずかだったという。 たしかに、自分について考えても、子どもの頃よりかなり集中力を欠いていることが増えてきた気がするし・・・。 患者さんの苦痛が少しでも減っていくのは間違いなく喜ばしいことだ。 ただ、新しい知見や技術を受け、社会がどうしていくのかは、また別の問題。 健康な人を基準とした社会に、病や障害を持った人を無理矢理適合させるなんてことにならないようにしたい。
Posted by
第4章 慢性ストレスによる脳内炎症がうつ病を引き起こす? 第8章 PTSDのトラウマ記憶を薬で消すことはできるか 第11章 ロボットで自閉スペクトラム症の人たちを支援する が、興味深かった。 慢性ストレスを受けることで、脳内で分泌されるホルモンが、身体に変化を及ぼしていること。...
第4章 慢性ストレスによる脳内炎症がうつ病を引き起こす? 第8章 PTSDのトラウマ記憶を薬で消すことはできるか 第11章 ロボットで自閉スペクトラム症の人たちを支援する が、興味深かった。 慢性ストレスを受けることで、脳内で分泌されるホルモンが、身体に変化を及ぼしていること。 これは、経験的にはみんな分かってることだとは思うけど、それが科学的に証明されているなんて朗報だと思う。 トラウマ記憶を薬でコントロールできてしまうこと。 そんなところまで精神疾患の研究が進んでいることは驚きだ。恐ろしいような、気になるような。「恐怖記憶の不安定化」や「恐怖反応の消去」に関する治療法も知らなかったので面白かった。 自閉スペクトラム症の人が、人間よりロボットとのほうが、目を見る頻度が高いという研究結果も傾向が顕著すぎて面白い。個人的には「人は人によって癒されていく」ということを信じていたいのだが、このことを応用することでスムーズに社会に適応していくリハビリができるのなら、それもありなのかもしれないとも思う。
Posted by
心の病、精神疾患は、身体の病気に比べて、とかくわかりにくい印象がある。 それは、精神疾患に関わる「脳」が複雑な仕組みで働いており、その全容の解明が困難であることに一因がある。 しかし、脳を知る「脳科学」の研究はさまざまな面で進んできており、精神疾患の治療も進歩してきている。そうし...
心の病、精神疾患は、身体の病気に比べて、とかくわかりにくい印象がある。 それは、精神疾患に関わる「脳」が複雑な仕組みで働いており、その全容の解明が困難であることに一因がある。 しかし、脳を知る「脳科学」の研究はさまざまな面で進んできており、精神疾患の治療も進歩してきている。そうした最先端を紹介しようという1冊。 第1部では、脳の仕組みを解説し、シナプス・ゲノム・脳回路という3つの階層から疾患がどのように生じるのかを見ていく。 第2部では、脳の変化が「心」にどう作用するのかを、ストレスや遺伝子変異、外部環境と関連して考察する。 第3部では、対症療法でない、精神疾患の治療法への道筋。PTSD、双極性障害、自閉スペクトラム症といった疾患を、薬剤やニューロフィードバック(脳血流や脳波のリアルタイムのフィードバックを通じて、特定の神経活動が自己調整できるようにトレーニングする手法)、ロボットを使用して治療することを目指す。 各章、別々の研究者が執筆しており、紹介される手法や対象疾患が多種多様であるのが特長。 全体に、意外に進んでいると感じると同時に、まだまだ未知数が多いという印象を受ける。 脳の機能が複雑であること、適切なモデルが作りにくいことがやはり脳研究が困難である所以だろう。 ニューロフィードバックは、例えば、ヘビを見て怖いと思うような恐怖反応を軽減させることにもつながるようでなかなか興味深い。一方で、この手法がうまく行った場合、悪用されて思わぬ方向に意識を捻じ曲げられるような事例が出ないのか少々気になる。 なかなか一朝一夕には進まないのだろうが、様々な方向からのアプローチを積み重ねていくことで、時に目覚ましい発展があるのがこの分野であるのかもしれない。
Posted by
一読では充分理解しきれないが、心の病気を医学的に理解できれば、心の病気を持つ人を理解するのに役立つのは間違いないと感じる。再読再再読して、理解を深めたい。
Posted by
- 1
- 2