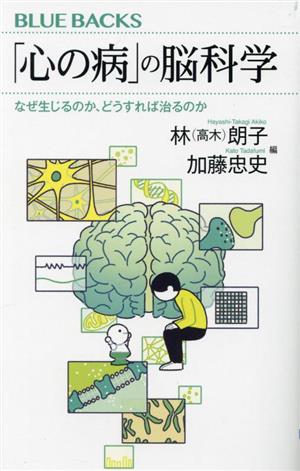「心の病」の脳科学 なぜ生じるのか、どうすれば治るのか の商品レビュー
12の先端研究が「こころの病気」もなんらかの物理的異常に由来することを可視化する 国内の12の先端研究を研究者自らが解説する形式なので「かなり高度」。医師や医学生、あるいは生物学の研究者向けの本と考えたほうがいいくらいのレベル。しかし、かなりバラバラな研究の寄せ集めでもある。入...
12の先端研究が「こころの病気」もなんらかの物理的異常に由来することを可視化する 国内の12の先端研究を研究者自らが解説する形式なので「かなり高度」。医師や医学生、あるいは生物学の研究者向けの本と考えたほうがいいくらいのレベル。しかし、かなりバラバラな研究の寄せ集めでもある。入口としてはいい。この先、診療をやりながらこの本に書かれていることが実用化されていくのを実感するときが来ると面白い。 第1部は病因論の総論3題 第1章 シナプスから見た精神疾患(研究者リンク) 第2章 ゲノムから見た精神疾患(研究者リンク) 第3章 脳回路と認知の仕組みから見た精神疾患(研究者リンク) シナプスにおける「グルタミン酸」と「ガンマアミノ酪酸(GABA)」の関係、シナプス可塑性など基本を学ぶ。ゲノム領域の研究手法ーNGS時代の研究。もう一度回路にもどって。 第2部は実際の疾患とその原因を探る研究3題 第4章 慢性ストレスによる脳内炎症がうつ病を引き起こす?(研究者リンク) 第5章 新たに見つかった「動く遺伝因子」と精神疾患の関係(研究者リンク) 第6章 自閉スペクトラム症の脳内で何が起きているのか(研究者リンク) 第7章 脳研究から見えてきたADHDの病態(研究者リンク) うつ病の化学説。動く遺伝子「レトロ・トランスポゾン」→LINE-1、これは面白い。なんとヒトDNAの半分近くが動いたあとの遺伝子の残骸。ADSモデルマウス。ADHD、他人ごとではない。 第3部は治療とからめた研究5題 第8章 PTSDのトラウマ記憶を薬で消すことはできるか(研究者リンク) 第9章 脳科学に基づく双極性障害の治療を目指す(研究者リンク) 第10章 ニューロフィードバックは精神疾患の治療に応用できるか(研究者リンク) 第11章 ロボットで自閉スペクトラム症の人たちを支援する(研究者リンク) 第12章 「神経変性疾患が治る時代」から「精神疾患が治る時代」へ (研究者リンク) メマンチンによる海馬記憶のコントロール。神経変性疾患が2010年頃から治る病気になり始めている!
Posted by
レビューが追いつかない… 新生活が始まってすぐにゴールデンウィークに入って、そのまままた新しい一週間が始まった。 仕事も、楽になったはずの通勤にもあんまり慣れなくて、なかなか読書の時間がとれない。当然、レビューを描く時間なんてもっととれない。 先月読み終わった作品のレビューを、...
レビューが追いつかない… 新生活が始まってすぐにゴールデンウィークに入って、そのまままた新しい一週間が始まった。 仕事も、楽になったはずの通勤にもあんまり慣れなくて、なかなか読書の時間がとれない。当然、レビューを描く時間なんてもっととれない。 先月読み終わった作品のレビューを、今さらながらに描いてみることにする。 これだけ医学が進歩しても、未だに解明されていない、うつ病、統合失調症、発達障害などの精神疾患の謎に迫った作品。 無事精神保健福祉士の資格を取得したわたしとしては、とても興味深い作品として手に取った。 (みなさん本当に応援してくださりありがとうございました!) 細胞学、遺伝学、神経学など、それぞれの専門家がそれぞれの立場で、最先端の研究をもとに、精神疾患の謎に迫る。 どのように発症するのか。 脳の、細胞の、神経の、どの部位が反応しているのか。 日々、実験を重ねる。 途方もないことだなと思う。毎日仮説検証していく日々というのは。 だからこそ、そこから得られる発見はとんでもないことで、山中伸弥さんが発見したiPS細胞は、こうした研究を重ねる人たちにとって、とてつもない成果だったことがわかる。 ただ、分かりやすく描かれているとはいえ、やはりすごく読むのに労力というか脳みそを使う作品で、かなりエネルギーを使った。 「シナプス」なんて言葉も、精神保健福祉士の勉強の中で触れたものの、当時教科書のどこを見ても鼻と鼻クソにしか見えない図しか載っていなくて、全然分からなくて、結局理系の知人に猿でも分かるように解説してもらったのだ。結局、脳の話に触れるには、まずはこの「シナプス」を理解しなきゃならない。わたしはそうやって事前に知人から聞いていたから、この作品の冒頭でシナプスが出てきた時になんとなく読み進めることができたけれど、その後出てくる塩基配列やDNAについて触れられている部分なんかはもう大苦戦! 各専門分野で、精神疾患について分かってきている部分も増えてきている。ただ、現在のように、体調不良を抱えた患者が病院を訪れ、自分の症状を伝える、というやり方では根本的な原因が分からず、対処療法にしかならないのだ。 その体調不良(例えば、抑うつ状態)の原因が、脳にあるかもしれないし、遺伝子にあるかもしれないし、環境にあるかもしれない。もしくはそれら全てが関与している可能性だってある。それらは、患者が自分の状態を伝えるだけでは見えてこない。さらに、それを伝えたところで医者がそれをどう捉えるかもわからない。ここで紹介されている研究が実用化され、誰でも平等に検査が受けられて、ふさわしい治療を受けられることができるようになるには、どうすればいいのだろう。そしてそれには、何年かかるのだろう。 例えば、ここで様々な分野の専門家が発表した最先端の実験結果を、それぞれの分野の専門家が共有して「なるほど!」ってなって、また新たな発見があったりするんだろうか。そうやって分野を超えて横断的に精神疾患を捉えた時、精神疾患はもはや精神疾患ではなく、脳の疾患、遺伝子の疾患、とかになっていったりするんだろうか。 わたしにはそこまでの発展的な理解はできなかった。 「なるほどー」と思ったり思わなかったりして、とにかくついていくのに必死だった。 そして今は、新しい職場で、新しい日々についていくのに必死な毎日を送っている。 Help!
Posted by
さすがのブルーバックス、素人目線では専門的なお話が多く、理解するほど読み込めませんでした。 「どうすれば治るのか」については、あまり身近にできそうなことは少なく、まだまだ研究段階なのだなという印象でした。
Posted by
神経変質疾患や、精神病を、脳の機能から分析、対策の進化や、問題に触れる。 各章毎に筆者が異なっていることもあって、幅広い上に、一個一個の掘り下げが深いこともあって、まとまりもなく、逆に浅い感じもして、えー、難しかったです。 ちょっと興味のある人が読むには向いてないかな。 入り口...
神経変質疾患や、精神病を、脳の機能から分析、対策の進化や、問題に触れる。 各章毎に筆者が異なっていることもあって、幅広い上に、一個一個の掘り下げが深いこともあって、まとまりもなく、逆に浅い感じもして、えー、難しかったです。 ちょっと興味のある人が読むには向いてないかな。 入り口ではあるが、マジに、興味がある人向けな気がする。
Posted by
専門用語満載だけど、分かりやすくて面白かった。 精神疾患を「心の病」だと思っていたが、「脳の病」である。心は脳の働きで生み出されるのだから(そもそもそんな認識がなかったのだけど)、脳の病なのだろう。 でも、この本を「初めから」読んでいくと、複雑な脳のメカニズムやら、なんやら?で、...
専門用語満載だけど、分かりやすくて面白かった。 精神疾患を「心の病」だと思っていたが、「脳の病」である。心は脳の働きで生み出されるのだから(そもそもそんな認識がなかったのだけど)、脳の病なのだろう。 でも、この本を「初めから」読んでいくと、複雑な脳のメカニズムやら、なんやら?で、色々あるのに?何故かとても素直に納得できた(不思議だ) ただ脳はあまりにも複雑で、環境等々様々な影響を受けるし、生きている人間の脳の状態を細部まで調べるのは不可能に近い。このような厳しい状況下で人間界を代表するトップクラスの頭脳の持ち主である数多の研究者たちが模索し根気よく精神疾患を「治る病」にすべく奔走されていることに敬意を払わずにいられない。
Posted by
全12章にわたって脳科学の最新話題を解説。 各章は研究者へのインタビューを元にサイエンス・ライターの立山晃さんが執筆・構成したもの。 最新研究の話題なので、素人にはやや難解だけど、概要を知るのに良かった。 精神疾患が「治る」時代がいつか到来することを願います。
Posted by
統合失調症、双極性障害、ASDやADHDといった発達障害、PTSDなど、「心の病」についての脳研究がどこまで進み、それが治療にどう生かされるかという最先端の研究を平易な形で述べられた本。平易といっても現在の研究は分子医学であり、理解が難しい。多少、臨床に生かせれそうな知見もあるが...
統合失調症、双極性障害、ASDやADHDといった発達障害、PTSDなど、「心の病」についての脳研究がどこまで進み、それが治療にどう生かされるかという最先端の研究を平易な形で述べられた本。平易といっても現在の研究は分子医学であり、理解が難しい。多少、臨床に生かせれそうな知見もあるが、精神疾患自体が単純な遺伝的要因だけではないため、研究が難しく、その本体に迫るのは困難なようだ。しかし研究者の言葉は明るく、未来は必ず開けるという姿勢には好感が持てた。
Posted by
感想 心も風邪を引く。仕組みがわかれば治療可能な病気となる。本人だけでなく社会にとっても重要。偏見をなくし支え合える世界を作る一歩。
Posted by
- 1
- 2