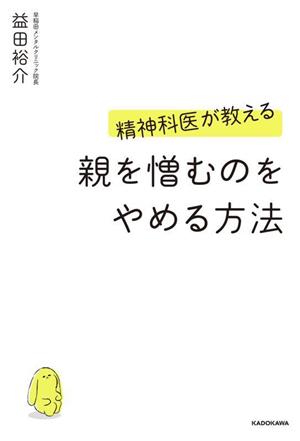精神科医が教える 親を憎むのをやめる方法 の商品レビュー
本の装丁がかわいい。 親の問題はいつだって悩ましいものだが、こんな発見があった。 •今のことではない!無力だった子供の頃の話 •「親はわかってくれて当然」は幻想 •親はあと何年生きる?もうすぐ亡くなるなら、優先順位は他のことの方が高くないか?(自分の子供のこととか) •親の発言...
本の装丁がかわいい。 親の問題はいつだって悩ましいものだが、こんな発見があった。 •今のことではない!無力だった子供の頃の話 •「親はわかってくれて当然」は幻想 •親はあと何年生きる?もうすぐ亡くなるなら、優先順位は他のことの方が高くないか?(自分の子供のこととか) •親の発言、行動には時代背景もある •親の発言、行動には性格もある(発達障害の可能性も!) 益田先生いわく、最終的に、諦観=ま、いっか と思えたらよいらしい。親は子供を愛するもの、という幻想に囚われず、ほどよい距離感で付き合えたら万々歳だなと思う。
Posted by
『あなた自身が親にとって「育てにくい子供」だった』という言葉にハッとした。過去にかけられたネガティブな言葉や態度について親を責めるだけではなく、客観視することの重要性に気付かされた。自分と親との関係を、自分と子供との関係に連鎖しないために。
Posted by
一読めには、突き放されたように感じました。それくらい耳の痛い現実を表してくれています。 精神の治療は、周りが優しく導いてくれるものではありません。信頼関係のある医師と患者の上に厳しい導きがあります。 それがわかって良かったです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
医師は事実を明らかにする。実際に起こったこと、背景要因、実は気になっていることはこちらではないか、など。主観2.0がある程度客観的で新しい決定ができることが目標。 親との絶縁=連絡を取らないという選択肢をずっと続けることはメンテナンスが結構労力がいる継続的な行為。>これはほんとにそう思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
YouTubeでも有名な早稲田メンタルクリニックの益田先生の著作。親子関係に問題があった人に向けて、ただ「私の親は毒親だったんだ」と片付けるだけでは、親子間のトラウマは乗り越えられないのだ、としたうえで、下記のように、親子について理解する手順を示す。 ・そもそも親子とは?現代の親に求められる子育てとは? ・親子関係に問題が生じる事例(どちらかに精神疾患のあったケースを想定し、解説) ・親の情報を集めて、一個人として客観的に捉える ・冷静な親理解のうえで、親との関係をどうするか、自分の将来をどうするか、考える 簡単に要約すると、近年は子育てが長期化、ハイレベル化していて、親に求められる役割が昔より増えている。その中で、どんな子育てを提供できるかは、親自身の特性や精神疾患の有無、知的レベルにより大きく異なり、格差も生まれる。親子関係に問題があったケースは、親自身に発達障害や精神疾患、貧困、知能の低さなど様々な問題があるケースが多い。その事実を客観的に理解するために、益田先生は、親の育った環境や働いている環境などの情報を集め、親の特性や価値観、生きてきた環境について冷静に分析することを勧めている。そうすることで、「自分(子供)から見た親」という一面だけでない、親の様々な側面を見ることができ、どうして自分が親子関係に苦しんだのか、客観的事実から考察することができると述べている。そうした冷静な親理解のうえで、自分は親を許すのか許さないのか、はたまた、自分自身は将来家庭を築くのか築かないのかなどについて、判断することができる。 意識はしていなかったが、これは自分が大人になるにつれ、親を少しずつ許せていった過程と同様だなと思い、実感を持って本書を読み進めることができた。同時に、私はまだまだ集まっている情報が少なく、親を一個人として捉えることはできていないのかなと思う。 特に自分が、親が私を出産したくらいの年齢になってみて感じたことだが、20代ではまだまだ精神的に未熟な人もとても多いのだろうなということだ。大人はなんでもできる万能な存在だと思っていたが、想像よりはるかに様々な脆弱性を抱えていたのだなと思うようになった。 私の中での親理解はまだまだ途上で、まだまだアダルトチルドレンなのだなと思う。「ああして欲しかった」「受け入れてほしかった」と要求を抱えていて、それに対して一個人として親がどう考えるであろうか、を想像しきれていないのだ。 また、今1番興味を持っている現象として、転移の問題がある。これは、親に求めている役割を他の人に求めてしまったり、親が演じていた役割を自分が演じてしまうような現象だ。 私は、父不在の期間が長かったからか、恋人に父親的役割を求めてしまうことがあったように思う。自分の中で起きるこうした現象についても考察して、自己理解を深めたいと思っている。 ちなみに、精神科医との人間関係の中でも転移は起こる。主治医のことをやけに嫌ったり、恋愛感情を抱いてしまったり、などだ。精神科では、主治医との会話の中で患者の病理を紐解いていくが、会話だけではどうにもならないとき、感覚的に大きな衝撃が必要になることもあって、それが、自身の転移を自覚させることらしい。 最近私も信頼できる主治医に出会うことができた。主治医には私の今までの人生のつらい話、黒歴史をできるだけ話しているし、主治医はそれに対して肯定し、前に進めるよう促してくれる。確かに、何か特別な感情を抱いてしまうのも不思議ではないのかもしれない。 しかし、そこで「どうして赤の他人である主治医にそこまで特別な、親密な感情を抱くのか?」と患者は自問自答しなければならない。人間関係には適度な距離が必要で、その距離感の中で適切な信頼関係を結び、円満にやっていけることを我々は学ばなくてはならないのだ。 私もこれからも、親や主治医との会話の中で、たくさんの気づきを得たいとともに、そこで得られた感情に真剣に向き合っていきたい。
Posted by
タイトル通り。相手は変わらないという事実を受け入れ、自分の認知(捉え方)次第でどうにでもできるという内容です。逆に自分の認知が変わらないと、状況は変わらないということでもあった。どんな病気でも依存症でも、最終的には本人の「決意」というのが響いた。
Posted by
環境、時代、精神疾患から俯瞰的な視点を持って、親を理解する。親だけでなく、人間へ理解が深まった。 寿司を美味しいもの、と捉えるのでなく,刺身と米と理解するような例えも本書にあり、めちゃくちゃな母親ではなく、そういう人なんだ、とこの本を読んで気持ちが変わってきた。 最後はどこに...
環境、時代、精神疾患から俯瞰的な視点を持って、親を理解する。親だけでなく、人間へ理解が深まった。 寿司を美味しいもの、と捉えるのでなく,刺身と米と理解するような例えも本書にあり、めちゃくちゃな母親ではなく、そういう人なんだ、とこの本を読んで気持ちが変わってきた。 最後はどこに人間の尊厳があるのか?という哲学的な問いとなり、心が動いた。
Posted by
親に対する自分の主観は一旦置いておいて、親を俯瞰で見る、というのは私の中にはない発想だった。 親がどういう生育環境で、どういう祖父母に育てられ、どういう時代を生き、職業を選択したか…このように客観的に見ることで、親への新しい理解を獲得することが、治療の第一歩だと言う。 その中で発...
親に対する自分の主観は一旦置いておいて、親を俯瞰で見る、というのは私の中にはない発想だった。 親がどういう生育環境で、どういう祖父母に育てられ、どういう時代を生き、職業を選択したか…このように客観的に見ることで、親への新しい理解を獲得することが、治療の第一歩だと言う。 その中で発達障害の可能性についての記述が多く、それに関しては思うところもあったが、全体的に今までと違うアプローチが自分の中でできそうだったので、とても良い本だった。
Posted by
益田先生の新刊。 YouTubeの時の語り口そのままに先生のフラットな姿勢が伝わってくる一冊だった。 親との関係性から発達の特性まで現代のメンタルヘルスに関わる内容が幅広い範囲で網羅されていて読みやすかった。 「家族原型」って先生の造語。概念として分かりやすかった。
Posted by
- 1