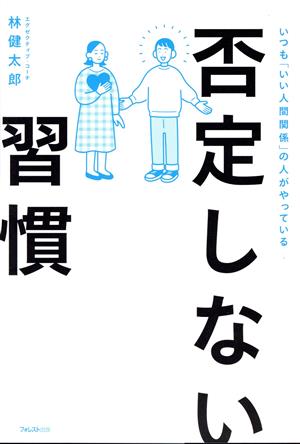否定しない習慣 「否定」をやめるだけで仕事、人間関係は9割うまくいく の商品レビュー
否定しない習慣の具体的な例が多くあり、参考になりました。取り組めそうなことから1つずつやっていきます。
Posted by
人間関係を良好にするには「否定しないこと」。無意識に否定していることもあるので注意。 否定しない3つの考え方①事実だから否定してもいい思考はしない②自分は正しいという思考はしない③過剰な期待はしない 事実を俯瞰して内観してみる(メタ認知ですね)。どうすればより良い結果を生め出せ...
人間関係を良好にするには「否定しないこと」。無意識に否定していることもあるので注意。 否定しない3つの考え方①事実だから否定してもいい思考はしない②自分は正しいという思考はしない③過剰な期待はしない 事実を俯瞰して内観してみる(メタ認知ですね)。どうすればより良い結果を生め出せたのか、振り返り会話のシナリオをつくってみる。 日本人は言葉で否定すること、されることの文化はあまりないが、非言語であったり、相手に忖度させたりすることで嫌悪感を抱かせることが多いのではないかと感じた。言葉だけでなく行動や態度にも「否定しない」習慣化の必要性があるのでしょう。
Posted by
自分の中で間違いなく今年のベスト本!! 半年前に読んでいたら今後歩む道程も変わっていたと思うが、このタイミングで出合えたことに意味があると思う。 何度も何度も読み返し、Try&errorを繰り返しながら少しずつでも実践できるよう精進します。 この本に出合えて本当に幸せで...
自分の中で間違いなく今年のベスト本!! 半年前に読んでいたら今後歩む道程も変わっていたと思うが、このタイミングで出合えたことに意味があると思う。 何度も何度も読み返し、Try&errorを繰り返しながら少しずつでも実践できるよう精進します。 この本に出合えて本当に幸せです!!
Posted by
Having read several books in this genre, I've noticed a common theme: the importance of listening attentively to others, avoiding unsol...
Having read several books in this genre, I've noticed a common theme: the importance of listening attentively to others, avoiding unsolicited advice or unnecessary interruptions, and embracing silence. While I intellectually understand these principles, I find them challenging to put into practice. But those who consistently demonstrate these qualities stand out as truly exceptional individuals, earning trust and respect in the process.
Posted by
そうは言ってもね…と心の中で否定しながら読んでしまっていました。 好きでも嫌いでもない状態から、少しでも好きになってもらえれば成功。 具体的な会話例が出てきたので、自分の仕事なんかにも使えそうな事がいくつもありました。知っているだけでは意味が無いので早速やってみたいと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
さっと読めます。 日常生活用ではなくて、会社で部下がいる人向けの内容になっています。部下からこう言われたらこう考えてこう言うとこうなる…という解説になっています。 気になった内容は ①「どうしてこんなこともできないの!」と相手に否定的な言葉を浴びせてしまうのは、「私ならできる」という上から目線。相手を否定したくなるのは、相手が自分よりも知識や経験が劣っていると思ったとき。無意識のうちに、自分の方が上だというコミュニケーションをしているからである。自分の方が「そのことに」ついて多少慣れているだけで、決して自分が相手より偉いわけでも、優れているわけでもない。 ②否定しないために「能動的に黙ること」は大事な技術。脊髄反射的に言葉を返さず、2秒以上の冷却時間をおくこと。沈黙して平和な関係性を保つ方が賢い選択である。 ③相手の言った内容を受け取ること。同意する必要はない。あいづちは「なるほど」ではなく、「そうなんだね」を使う。 私自身、以前はアドバイスのつもりで否定的なことを言うタイプでした。この本を読んでいて、その時の自分の言動を思い出して辛いものがありました。 今、私自身はは気を付けているつもりですが、私の周りには否定的なことばかりを言う、まさに、この本の悪い例の見本のような人もいます。その人たちって、きっとこの本のような本の存在すら、否定して読まないんだろうな、と思うと、残念なような気がします。(あ、否定してる?)
Posted by
人生を振り返った時に、些細な言葉で人を傷つけた事が一番強く自分の中に後悔の念として残ってるなと思ったので、人を傷つけない方法を学びたくて読んでみました。 土地柄なのか、逆に怒らせそうだと感じる例文もありましたが、参考になることも多かったです。 セルフコーチングが一番大切だろうなと...
人生を振り返った時に、些細な言葉で人を傷つけた事が一番強く自分の中に後悔の念として残ってるなと思ったので、人を傷つけない方法を学びたくて読んでみました。 土地柄なのか、逆に怒らせそうだと感じる例文もありましたが、参考になることも多かったです。 セルフコーチングが一番大切だろうなと感じたし、実践したいなと思いました。
Posted by
AudibleのテレビCMを観て気になって。コミュニケーションというよりはコーチングよりの本。この本で紹介されているマインドを、みんなが持つことができれば、人と人との摩擦はかなり減るし、心理的安全性も得られると思った。親や上司として、聴く時や伝える時の心構えや、あいづちの具体的方...
AudibleのテレビCMを観て気になって。コミュニケーションというよりはコーチングよりの本。この本で紹介されているマインドを、みんなが持つことができれば、人と人との摩擦はかなり減るし、心理的安全性も得られると思った。親や上司として、聴く時や伝える時の心構えや、あいづちの具体的方法も紹介されていて参考になった。知るだけでなく実践しなくては。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ひとことでまとめるなら、 良好な人間関係を構築・継続していくためには、相手を否定しないこと。 重要だと思ったポイントは下記の通り。 ・否定すると相手は本音を言わなくなり、離れていく。 ・自分が否定いないつもりでも、相手は否定されたと感じたら、それは否定である。パワハラやセクハラと同じで相手がどう感じるか重要。 ・自分は正しい、だから相手は間違っているという思い込みから否定が生まれやすい。 ・否定しそうになったら、「かもしれない」をつけて可能性を残す。 ・相手の話は最後まで聞き、「そうなんですね」と受け止める。それから自分の意見を発言する。 ・否定してしまったと感じたら、「否定するように聞こえたらごめん」等フォローする。 ・笑顔で相手の目を見て話す ・「さすが」等褒めることを忘れない。 ・求められてない場合のアドバイスは不要。アドバイスは否定のニュアンスがある。 まとめ 相手の話を最後まで聞き、受け止める。そのあとに相手に配慮して自分の意見を言う。バランスが大事。
Posted by
普段から否定語を多用しているので、それを無くす方法と無くすことによるメリットが知りたくて購入しました。 序文では否定をしないことで人生が変わるとあった。相手の行動を読んだり、意見を聞くことで人から好かれやすくなったり、リーダーシップが発揮できるなどビジネスにも役立つ理由が述べら...
普段から否定語を多用しているので、それを無くす方法と無くすことによるメリットが知りたくて購入しました。 序文では否定をしないことで人生が変わるとあった。相手の行動を読んだり、意見を聞くことで人から好かれやすくなったり、リーダーシップが発揮できるなどビジネスにも役立つ理由が述べられていた。 あとの構成としてはマインド形成、否定しない技術、習慣づけを紹介していた。 印象に残っているのは否定しないマインド形成のうち、意見の違い≠否定であるということ。 意見の違いを理解して目的を共有すること、共有の目的を見つけることが重要だと感じた。 他にもいろいろな手法や理由が記載されていて、仕事から日常生活に至りさまざまな場面で有用だと思われました。
Posted by