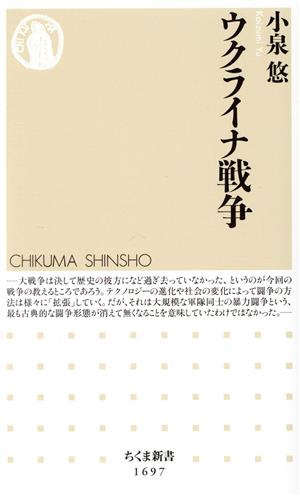ウクライナ戦争 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「大国の侵略が成功した」という実績は残してはいけない。 著者の意見に賛同します。 ・著者による総括 ①この戦争は極めて古典的な様相を呈する「古い戦争」である。 無人航空機などハイテク技術の活用、情報戦、内通者手引などの非軍事的闘争手段などはあるが、 戦争全体の趨勢に大きな影響を及ぼしたのは、侵掠に対するウクライナ国民の抗戦意思、兵力の動員能力、火力の多寡といった古典的要素だった。 戦争終結に影響を及ぼすのは暴力闘争の場になるだろう。 「新しい戦争」に備えること自体の重要性は低下しないとしても、 「古い戦争」への備えを無視して良いことにはならない。 ②核抑止は依然として大国の行動を縛っている。 アメリカ・西側諸国が武器の供与にすさ二の足を踏まざるを得ない背景にはロシアの核戦力がある。 ロシアもNATOとの直接衝突は避けざるを得ないから「エスカレーション抑止」のため、核使用には踏み切っていない。 日本はアメリカの核の傘の下にあるから、ウクライナのように直接侵掠される蓋然性は低い。 台湾はウクライナに似ている。台湾有事の際には、ポーランドと似たようなものになる可能性がある。 (兵站ハブや発信基地など) ③この戦争は「どっちもどっち」ではない。 動機や理由付けがあったかもしれないが、ロシアが一方的な暴力の行使に及んだ側であることは間違いない。 この点を明確に踏まえ、戦闘が停止されれば「解決」になるという態度は否定しなくてはならない。 日本が周辺各国で戦争した場合に、そのまま跳ね返ってくる問題である。 「大国の侵略が成功した」という事例を残さないように努力すべき。
Posted by
ロシアのウクライナ侵攻が始まった2022年の秋頃に読み始めた本ですが、途中まで読んでいて放置されていました。読み終わった部分も忘れているので、内容を振り返り返った後に図書館へリサイクルしたいと思います。 以下は気になったポイントです。 ・2022年2月から9月末までに発生した...
ロシアのウクライナ侵攻が始まった2022年の秋頃に読み始めた本ですが、途中まで読んでいて放置されていました。読み終わった部分も忘れているので、内容を振り返り返った後に図書館へリサイクルしたいと思います。 以下は気になったポイントです。 ・2022年2月から9月末までに発生した戦闘は、世界全体で1万8061回あり、このうちウクライナでの発生は、3170回と世界最多である。つまり全世界で起きている戦闘の約6分の1がウクライナに集中している、これには麻薬組織などが引き起こしたものも含まれるから、国家間紛争という括りで見た場合の比率はさらに高まる(p20) ・バイデン大統領は、ウクライナのNATO加盟には一切の言質を与えず、6000万ドルの追加軍事援助を発表したのみ、ノルド・ストリーム(パイプライン)への制裁緩和もそのままであった、ウクライナに対するロシアの振る舞いは認めないが、ロシアとの厳しい対立は望まないという姿勢である(p37) ・ウクライナ語の書き言葉は17世紀初めまで、当時のロシア語と全く同じ、話し言葉は少々違ったが、そう大きく異なった言語ではなかった、分化したのは近代になってウクライナの国民的作家が活躍するようになってから、しかし彼らとて散文はロシア語で書いていた(p68) ・ベルラーシでは憲法改正が成立(2022/2/27)し、憲法第18条から非核化と中立に関する文言が削除された、核兵器配備が少なくとも法的には可能となることを意味している(p83) ・ロシアは建前であっても徴兵勢力は投入しないと公約した以上、徴兵の事態が露見すると戦地から引き上げざるを得なかった、従って15万人というロシア軍の侵攻勢力は、全地上部隊から徴兵を除きたほぼ全力であったと考えられる。戦時動員で増強されたウクライナ軍(2020/5には70万人、開戦前の30万人、7月には100万人)に対して兵力で劣勢なことは変わりなかった(p126) ・マウリポリの陥落は2つの意味で、ロシア軍には大きな意義を持っていた、1)2014年に併合したクリミアと東部ドンバス地方を結ぶ回廊が完成した、クリミア半島につながる兵站線を確保し、南部と東部の間で兵力を融通できる、2)他の戦域に投入できる余裕ができた(p147) 2024年10月25日作成
Posted by
2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻が起きた。ロシア側は特別軍事作戦と称し、ウクライナの非軍事化、非ナチ化、ロシア系住民の虐殺の阻止という名目で、侵攻を仕掛けた。依然としても終戦の見通しがつかないが、本書はそんなウクライナ戦争を著者の分析によって今後の展開を予測する...
2022年2月24日、ロシアによるウクライナ侵攻が起きた。ロシア側は特別軍事作戦と称し、ウクライナの非軍事化、非ナチ化、ロシア系住民の虐殺の阻止という名目で、侵攻を仕掛けた。依然としても終戦の見通しがつかないが、本書はそんなウクライナ戦争を著者の分析によって今後の展開を予測する。 本書で何度か言及されるが、2022年以前からロシアのウクライナに対する動向は怪しかった。2014年クリミア半島の併合の時点で、ある意味戦争が始まっていたと著者は指摘する。(そのため本書では今回のウクライナ戦争を第2次ロシア・ウクライナ戦争と呼んでいる)2021年、著者は衛星画像から戦争準備を進めていることが明らかであったという。駐屯地に大量のテントが用意されていること、また兵舎に収まらないほどの兵士が集結していること、予備の飛行場に戦闘機や戦闘爆撃機を展開しているなど、既に戦争の予兆がみられた。そのほかにも、ウクライナ国境付近の住民がTikTokに投稿した映像が情報源となった。 しかしその一方で、予想外の事態もいくつか見られた。ゼレンスキーの指導力はもちろんのことだが、今回の戦争が短期決戦には至らず、ウクライナ側が思った以上に持ちこたえていることである。意外にもウクライナは旧ソ連諸国で2番目に軍事力を持っている。
Posted by
ずっと読みたかった本。現在進行形で起こっている惨劇であり、今更ってことなんかなく、むしろそういう気持ちへの自戒の念も込めて。さすが第一人者の手になる書で、戦争に至る背景から、予想される展開に至るまで、十分な裏付けをもって語られる。ロシアが事ここに至った原因が、いまひとつ明白でない...
ずっと読みたかった本。現在進行形で起こっている惨劇であり、今更ってことなんかなく、むしろそういう気持ちへの自戒の念も込めて。さすが第一人者の手になる書で、戦争に至る背景から、予想される展開に至るまで、十分な裏付けをもって語られる。ロシアが事ここに至った原因が、いまひとつ明白でないというのも、出口が見出しにくい大きな原因。戦争反対。
Posted by
本当ところはプーチンの頭の中にしかないのだろうけれども、ウクライナ戦争を軍事と政治の様々な状況証拠から読み解いていく。 現在はさらにイスラエルとパレスチナの紛争が起きたり、周辺環境も大きく変動しており、執筆当時よりウクライナの置かれている状況も苦しくなっており、混迷の度合いはさら...
本当ところはプーチンの頭の中にしかないのだろうけれども、ウクライナ戦争を軍事と政治の様々な状況証拠から読み解いていく。 現在はさらにイスラエルとパレスチナの紛争が起きたり、周辺環境も大きく変動しており、執筆当時よりウクライナの置かれている状況も苦しくなっており、混迷の度合いはさらに深くなっている。
Posted by
刊行のタイミングから、全容が分かる!というわけにはいかないが、軍事的な目線が特徴的であり、この戦争のきっかけ、意味するものの一端を感じられる。
Posted by
よくわかってなかったロシアウクライナ戦争の背景。 なんとなくの可能性はわかったけど、プーチンが本当に何を考えているかは不明、という感じか。
Posted by
いきなり戦争が始まった印象を持ってましたが、その一年頃前から蠢いていたんですね。2.24まで気が付かなかった無知を恥ずかしく思いました。きっとそれなりの報道があったはずなのに!あった? ロシアがウクライナ国内に協力者を作ってたって事も、なるほど。だから、あの作戦だったんですね。で...
いきなり戦争が始まった印象を持ってましたが、その一年頃前から蠢いていたんですね。2.24まで気が付かなかった無知を恥ずかしく思いました。きっとそれなりの報道があったはずなのに!あった? ロシアがウクライナ国内に協力者を作ってたって事も、なるほど。だから、あの作戦だったんですね。でも、確かにこの時代にかつてと変わらぬ塹壕戦の印象ありますし。核兵器の存在がどっちつかずの状態を作り、戦争が長引きかねないおそれ。戦争にもいろんな理論があるんですね。興味深い。また、今日の戦況でも解説が読みたいです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
東大先端研専任講師にして、軍事オタクでもある小泉悠による新書。最近新書大賞にノミネートされており、またプーチンのアメリカメディア露出が気になり読んだ。2日ほどで読めた。 1章から4章にかけて、開戦前の2021年から執筆時の2022年9月に至る時系列を辿りつつロシア・ウクライナ戦争の政治的原因・推移を考察し、第5章ではそれを踏まえた本戦争の特徴を述べている。 2021年の春からロシアは演習と称してウクライナ国境に軍を大規模展開しており、その時点で軍事的緊張が高まっていた。これにはロシア寄り(というより自国主義のため他国への介入を好まない)のトランプからバイデンへ政権が移ったことが要因として挙げられている。ウクライナのゼレンシキー(これはウクライナ語表記)も、第二次ミンスク合意の批准やNATO加盟をめぐりアメリカとの外交政策を続けていたが、はかばかしい進捗は得られなかった。 2021年9月には春の軍隊が撤退しておらず、それどころか増えていることが発覚。ここでプーチンは「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」という論文を公式発表。ウクライナとロシアの一体性を強調する右翼民族主義的な見解を大統領個人のものとして明確に示した。プーチンの動向は一時平和共存路線をとるかに逸れるものの、2022年明けには開戦は確実に。 当初のロシア側の目的は短期決戦だったらしい。首都キーウに近い北部のアントノウ空港への奇襲からも明らかなように、ゼレンシキーを退陣させ、混乱したウクライナに傀儡政権を樹立することが眼目だった。しかし、ゼレンシキーはロシアの予想を裏切り理想的な動きを見せる。アメリカをはじめとした西側からの武器供与(特にジャヴェリンはウクライナ抵抗のシンボルとなった)も手伝い、ハルキウを守り抜き北部の戦線は膠着、ロシア軍は撤退を強いられる。停戦交渉はウクライナへの歩み寄りを見せる(ただし、ブチャでの虐殺発覚により交渉は決裂)しかし、ロシアはここで東部のドンバス地方へと方針を転換。マリウポリが陥落し、ドネツィク、ルハンシクはロシアの手に落ちる。 当初の作戦に際し、プーチンと軍や情報部との亀裂が明らかに。奇妙なのは、ロシアが戦時体制に入らず動員が限られること。著者はこれを、国民への平穏な生活の保障に原因があると見ている。核兵器の使用も、前著『現代ロシアの軍事戦略』であったように、西側からの介入を牽制する材料としての威嚇にとどまった。 総じて今次の戦争は、いわゆる「ハイブリッド戦争」(戦場外部のファクターが重要な要素となる)のような新しい戦争とは程遠く、むしろ大量動員や兵器の物量によって村落を取り合う古典的な戦争であった。 さすがに現在日本でロシア知識人を代表するような存在なだけあって巧みな論理展開である。現在進行形の現象である今次の戦争が簡潔にまとめられており非常に勉強になった。今後も小泉氏の著書は必読となるであろう。
Posted by
とても読みやすい。専門的な内容のはずなのに、門外漢の自分でもスラスラと読める。筆者の文書力の高さのおかげですね。 テレビ番組などではあまり報道されてないことにも触れられているなど詳細に書かれている一方で、内容が時系列に整理されていて分かりやすい。また、第5章「この戦争をどう理解...
とても読みやすい。専門的な内容のはずなのに、門外漢の自分でもスラスラと読める。筆者の文書力の高さのおかげですね。 テレビ番組などではあまり報道されてないことにも触れられているなど詳細に書かれている一方で、内容が時系列に整理されていて分かりやすい。また、第5章「この戦争をどう理解するか」は軍事理論の話ですが、平易に書かれていて読みやすい。 第二次ウクライナ戦争はまだ続いてますが、戦争終了後にまた執筆されるのであれば、是非またその本も読んでみたい。そう感じるぐらい、とても読みやすかった。
Posted by