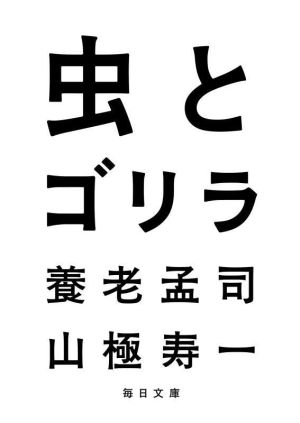虫とゴリラ の商品レビュー
生き物としてのヒトについて、現代社会の歪みについて、「虫とゴリラ」の目線で語る対談本。 野生の生き物とその生息環境を観察して、理解したりできなかったりすることは、ヒトという生き物を客観視するために効果的なトレーニングだと思う。 現代社会は、ヒトの脳で維持管理できない物を徹底的に...
生き物としてのヒトについて、現代社会の歪みについて、「虫とゴリラ」の目線で語る対談本。 野生の生き物とその生息環境を観察して、理解したりできなかったりすることは、ヒトという生き物を客観視するために効果的なトレーニングだと思う。 現代社会は、ヒトの脳で維持管理できない物を徹底的に無視し、分からない・曖昧なことには蓋をする。それは虫であり、樹木であり、個人であり、脳自身でもある。 しかし、どんなに「こんな状況はおかしい」と感じても、限界まで加速した方舟を個人が止めることはできないし、大多数の人はそれを望まないだろうという儘ならなさがある。 そんなヒトの営みなんて露知らず、虫は街の片隅にも逞しく生きていて、耳を傾ければ色々なことを教えてくれる。その声を聴く人が増えたら良いと思う。ヒトはいつでも自然の一部なのだから。
Posted by
解剖学者で「虫屋」の養老孟司と、「サル学」の研究者の山極寿一の対談です。 養老は、「脳化」や「都市化」といった概念を用いて、人間がみずから理解することのできる情報だけに目を向け、その外にひろがる「自然」を顧みようとしないことを、くり返し批判してきました。一方の山極も、ジャングル...
解剖学者で「虫屋」の養老孟司と、「サル学」の研究者の山極寿一の対談です。 養老は、「脳化」や「都市化」といった概念を用いて、人間がみずから理解することのできる情報だけに目を向け、その外にひろがる「自然」を顧みようとしないことを、くり返し批判してきました。一方の山極も、ジャングルでゴリラの生態を追いつづけてきた体験をもとに、感覚を通じて自然と交流することができることの重要性を指摘しています。 山極は「あとがき」で、「もとより虫屋とサル屋だから、見てきた世界が違う。歩みがどこで交わるだろうか、と心配したけれど、けっこう一緒に歩むことができた」と、対談を振り返っています。ただ読者としては、両者の意見のちがいがもうすこし鮮明に示されたほうがおもしろかったのではないかという気がしています。
Posted by
触覚と視覚と聴覚だけは大脳にダイレクト ペンフィールドのホモんクルスによると、唇、手、指先が非常に大きい。 脳の中でこんなに大きな部分を占めるのに、あまり利用されてない。 >>人間通し、触んないとダメだな コントロールできなければ、 傍観者(当事者意識が無い)にな...
触覚と視覚と聴覚だけは大脳にダイレクト ペンフィールドのホモんクルスによると、唇、手、指先が非常に大きい。 脳の中でこんなに大きな部分を占めるのに、あまり利用されてない。 >>人間通し、触んないとダメだな コントロールできなければ、 傍観者(当事者意識が無い)になる。 人間というのは、技術が手に入ると「やっちゃう」んですよ。
Posted by
わたしはいつから虫を触れなくなったかな、と思いながら読んだ。 養老先生は虫、山際先生はゴリラを長年見つめてきた。 見つめすぎて普通の人間より、虫寄り、ゴリラ寄り視点で世界を眺めることができるようになった。 じゃあ人間はどうなんだ?ということについていろいろな切り口から語り合っ...
わたしはいつから虫を触れなくなったかな、と思いながら読んだ。 養老先生は虫、山際先生はゴリラを長年見つめてきた。 見つめすぎて普通の人間より、虫寄り、ゴリラ寄り視点で世界を眺めることができるようになった。 じゃあ人間はどうなんだ?ということについていろいろな切り口から語り合った本。 人間の脳が発達し、言葉を獲得したことで得たもの、失ったもの。 言葉は物事を抽象化し「本来異なるものを同じものとして分類」することで効率的に処理(記憶とか伝達とか)できるようになった。 言葉以前の身体性みたいなものも大事にしたほうがいいのでは。 狩猟民族は酒は造れなかった。 農耕民族=定住者のみが酒を造った。 定住=人口増=人間関係ややこしくなる→酒でストレス発散?! 狩猟民族はややこしくなったら移動すればいいが農耕民そうはいかない →「飲む打つ買うは同時に発生したのでは」説はなるほど、と思った。 コンクリートジャングル住民として、 養老先生推奨の参勤交代(都会と田舎を行き来して住む)を すぐに叶えることは、なかなか難しいけれども、 とりあえず、気軽にできることとして、公園散歩のときに 積極的に植物物に触れたり、意識的に自然の匂いを聞きに行こうと思った。
Posted by
【before】この本を読む前の私はこれらを知りませんでした。 ・全ての五感は二重構造になっている。 ・味覚と嗅覚は化学反応で、信号は5割ずつ大脳新皮質と辺縁系(古い)に届く。 ・視覚・聴覚・触覚の信号は全部、大脳新皮質に届く。 ・7万5000年前に言葉のようなものが出てきた可能...
【before】この本を読む前の私はこれらを知りませんでした。 ・全ての五感は二重構造になっている。 ・味覚と嗅覚は化学反応で、信号は5割ずつ大脳新皮質と辺縁系(古い)に届く。 ・視覚・聴覚・触覚の信号は全部、大脳新皮質に届く。 ・7万5000年前に言葉のようなものが出てきた可能性が高い。 ・ウンカの幼虫の足の付け根の関節が歯車になっている。人間が作る歯車と同じ。 ・三葉虫の目は2つのレンズ、方解石の結晶の組み合わせで出来ている。 ・聴覚の一次中枢の神経細胞を並べたら、そのままピアノになる。 ・網膜から点の信号が届くと、中枢ではその点を次の中枢とつなぐ。だから直線は頭の中だけにある。 ・神経細胞がやっていることを、意識がなぜか取り出すことができる、それが数学。 【気づき】この本を読んで、これらについて気づきを得ました。 ・1億5000万年程前、被子植物が花を咲かせ虫を媒介に実をつけるようになった。 ・哺乳類は嗅覚が発達、鼻面を地面につけて歩く。→臭いが一番確かな情報だから。 ・猿が樹上へ移動し、視覚と聴覚を優位にした。食物だけ味・嗅・触覚で感じる。 ・人間は地面から離れて物事を理解=見えないもののリアリティを信じられる。 ・感覚の変更の結果として、言葉が出てきた。 ・「生物には必ず生きている場所がある。それ抜きには、生きていることに非ず」 ・学習とは「自習と対話」 ・抽象化は脳にとって非常に省エネになる。言葉が使えると、それができる。 ・千年前の暮らしが残っている都市は京都以外ない。暮らしの調度品がそのまま使われているからこそ、千年前の暮らしがそのまま残る。 ・シェアリングハウス、リビングは壁一面が表表紙の本棚。茶室で瞑想もできる。 ・パーソナルスペースは2畳。それ以外は視・聴・嗅覚的にメンバーで共有する。 ・日本家屋は軒が低く、夕方暮れ時に襖絵や屏風絵が映えるようになっている。 ・「現実にあるものには、必ず界面がある」人工的システム、社会には界面がない。従って全部幻想にすぎないが、実態があるからこそ幻想が成立するのである。 ・変わらないもの=情報。意識が扱えるのは「時と共に変わらないもの」だけ。 ・「統計的に見ている世界」=神の世界。 ・狩猟採集民、遊牧民は墓を持っていなかった。 ・自然の後ろ盾が無く実体経済が利益を生まないので、預金に利息がつかない。 ・ディストピアの未来では政府は限りなく小さく、世界中でグローバル企業が末端の人間まで支配する。究極の格差社会、奴隷制社会になる。 ・有機農業の本は必ず農家一軒ごとの紹介になる。「有機」は一般論で語れないから。=多様性。 【TODO】今後、これらを実行していこうと思います。 ・落ち着きたいときは、ヘッドランプをつけて手作業をする。 ・集中したいとき「周りが明るいとダメ」を応用する。 ・集中して本を読みたいとき、ヘッドランプを使ってみる。 ・気軽に出入りできるコミュニティに参加して、複線系の環境を実現。 ・一人じゃ生きられないから、シェアとか共同とか、知恵を使う。 ・「幸福を作るには、手間暇はかけた方がいい」
Posted by
虫とゴリラ、から生物の話へ、そして、人間とは、となり、今の人間の生活様式となり、どういう生き方が人間らしいのか、へ展開。面白い。
Posted by
2人の対談形式で進む。専門分野に触れながら展開される文明論。2人の圧倒的な知性と専門性に触れられるのが楽しい。
Posted by
未来の社会にとって大切なこととは?道標を参考にしつつ旅をしていかないと、 最終ページに近い2人の写真がいい。
Posted by
世の中の捉え方を考えさせられる、そんな一冊。 虫の養老孟司先生とゴリラの山極寿一先生の対話形式で進んでいく。対話形式だけどもお二方の経験と知識が豊富で読み応えがあった。 この本を咀嚼して理解するにはまだまだ世の中を経験できていないけれども、科学的な考え方というか理性主義的な考...
世の中の捉え方を考えさせられる、そんな一冊。 虫の養老孟司先生とゴリラの山極寿一先生の対話形式で進んでいく。対話形式だけどもお二方の経験と知識が豊富で読み応えがあった。 この本を咀嚼して理解するにはまだまだ世の中を経験できていないけれども、科学的な考え方というか理性主義的な考え方を改めるいい機会になったと思う。 自然と触れる機会があまりなかったので、これからは少し意識してみようかなと思った。本来の感覚を取り戻すのだ。 本を読むのに抵抗が少ない人にオススメ!
Posted by
- 1