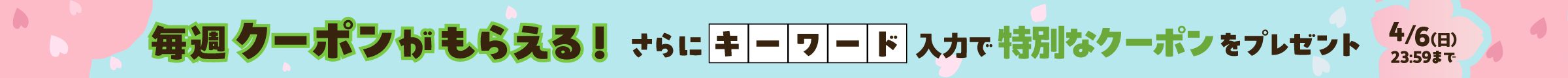草の根のファシズム の商品レビュー
初版が1987年なので、ものの見方などはとっくにわかっている事もある。その時代の流れや衝動に押されず考えていく事が大切なのだろう。 この書籍に関しては民衆がいかに容易くコントロールできるか、情報統制などがどのように行われたか、そういった事に触れずに戦争を始めた当事者を徹底して糾弾...
初版が1987年なので、ものの見方などはとっくにわかっている事もある。その時代の流れや衝動に押されず考えていく事が大切なのだろう。 この書籍に関しては民衆がいかに容易くコントロールできるか、情報統制などがどのように行われたか、そういった事に触れずに戦争を始めた当事者を徹底して糾弾する内容で名著とは言い難い。当方も戦争になった時、銃を持たされても撃つ自信がないから戦争に反対する気持ちはよくわかる。ただ腹に落ちるとは真逆の方向の書籍だった事は記しておく。
Posted by
タイトルに「草の根」とあるように、本書は、アジア太平洋戦争を草の根で支えた民衆の反応や意識を、戦争体験記や手紙、公的機関による調査等様々な資料を用いて明らかにしようとする。 本書参考文献には多くの戦争体験記が掲載されているが、著者はそれらを読み込んで、現地で従軍、商売や仕事を...
タイトルに「草の根」とあるように、本書は、アジア太平洋戦争を草の根で支えた民衆の反応や意識を、戦争体験記や手紙、公的機関による調査等様々な資料を用いて明らかにしようとする。 本書参考文献には多くの戦争体験記が掲載されているが、著者はそれらを読み込んで、現地で従軍、商売や仕事をしていた彼ら彼女らが、どのような体験をし、どのようなことを考え、あるいは戦後になって当時をどのように総括したかを、一人ひとり具体的に取り上げて叙述にまとめ、その実相に迫っている。 中国を始め、インドネシア、ビルマ、フィリピンといったアジア各地で日本軍は戦ったが、戦場における日本軍の行動、特に民衆に対する殺人、強盗、強姦、放火、略奪といった残虐な行為の数々を読むのはとてもしんどかった。兵站を軽視した軍上層部に問題があるのはももちろんだが、アジア各国への優越感や「戦争とはそういうものだ」といった意識が兵士をはじめ日本軍全体にあったのだろう(日本に限ったことではないのかもしれないが)。 また第二章では、民衆の序列として、帝国臣民である日本本土の周辺に属していた沖縄県人、アイヌ、ウィルタ、チャモロ人(マリアナ群島住民)、朝鮮人、台湾人を取り上げているが、兵として召集されたり軍事行動への協力を余儀なくされた人々が、戦争に翻弄され、あるいは敗戦後日本から切り捨てられてしまったことには、何とも言えない思いがする。 敗戦の反省から戦後を出発したのであるが、著者は、戦争体験記における記述や敗戦後の調査結果等を踏まえ、最後に次のように述べる。「…戦場や焼跡における日本民衆の原体験持つ意味は、十分に吟味されないまま、次第に見失われつつあるようにも感じられる。……戦争反対・平和意識の定着の裏側での「聖戦」感の残存、戦争協力に対する反省の中断、主体的な戦争責任の点検・検証の欠如、アジアに対する「帝国」意識の持続といった、多くの日本人に共通する意識・態度があった」(301頁)と。 現在の観点から見れば、攻撃をされた訳でもないのによその国まで出ばって行って戦争をし続けることに疑問を抱かないということは不思議に思えるが、西洋列強の植民地主義があり、アジアにおける盟主という意識を持っていた時代であれば、そういうものだったのだろうか。どうしてもその生きている時代というものに囚われてしまうのだろうな。 本書の元版が出たのが1987年、戦争を直接に経験した人たちはほとんどいなくなってしまった。果たしてその戦争経験の反省は継承されているのだろうか。
Posted by
解説=加藤陽子 https://www.iwanami.co.jp/book/b611144.html
Posted by
私が知る研究者で著者の吉見義明氏は、1990年代の従軍「慰安婦」研究、2000年代の日本軍毒ガス戦という認識であったが、1980年代の初期作品となる本書では、民衆や大衆の日記や手記、聞き取りなど膨大な資料や調査を背景として、アジア太平洋戦争を見つめ直すナラティブな作業であり、論...
私が知る研究者で著者の吉見義明氏は、1990年代の従軍「慰安婦」研究、2000年代の日本軍毒ガス戦という認識であったが、1980年代の初期作品となる本書では、民衆や大衆の日記や手記、聞き取りなど膨大な資料や調査を背景として、アジア太平洋戦争を見つめ直すナラティブな作業であり、論考は日本型「ファシズム」の変遷を検証している。 第1章「デモクラシーからファシズムへ」、第2章「草の根のファシズム」、第3章「アジアの戦争」、第4章「戦場からのデモクラシー」の四章編成で構成される。戦争へ突入し、戦争に疑問を持ちつつも最終的には戦争を支持する民衆を追った1~3章。空襲が激化し、日本が焦土化してきた中で、民衆の中からひび割れるファシズムを、論考した4章。集団的自衛権行使の名のもとに「安保3文書」で更なる軍備増強にひた走る岸田政権と日本。「富国強兵」どころか「貧国強兵」に突進する日本。今の日本の情勢だからこそ再刊された意義を深く噛みしめ、「草の根のデモクラシー(立憲主義・民主主義・平和主義・国際協調主義など)」といった市民運動を進めるためにも、広く手に取って読んで欲しい。 閑話休題 日中戦争の中で、日本軍が1942年に行った淅贛(せっかん)作戦について、2022年2月に出版された常石敬一氏の「731部隊全史」では、同作戦で細菌兵器を実践使用し、自軍である日本軍に1万人近い被害者を出したと記載されている。一方、本書の兵士の証言にはくしゃみ性の毒ガスである赤筒を使用したとの記録がある。淅贛(せっかん)作戦では、細菌兵器と化学兵器の両方が使用されたことになる。戦争の行き詰まりは経済の行き詰まりとなり、より安価な兵器となる細菌兵器や化学兵器を選択した帝国陸軍。1925年ジュネーブ議定書では細菌兵器や化学兵器の使用を国際法で縛ったが、日本やアメリカは批准は第二次世界大戦から遅れること25年ほども経過していた。また、どの程度の軍属や日本人はジュネーブ議定書を知っていたのだろうか。国際連盟を離脱した時点で、国際法は全く無視し、ハーグ陸戦条約を知っていた軍部や日本人もほとんどいなかったのだろう。だからこそ日本兵の多くが、捕虜や非戦闘員・現地住民への殺戮、略奪、強姦などの侵略行為をアジア・太平洋の地域で行ったのだろう。
Posted by
1987年の著作の文庫化。国内外を問わず戦時下の民間人の手記や当時のアンケート結果をつぶさに紹介することで、日本民衆の視点から「アジア太平洋戦争」を描き出すことを目的としている。本文約300ページ。全四章で、第一章が日米開戦前までの世相を確認し、第二、三章では太平洋戦争突入以降、...
1987年の著作の文庫化。国内外を問わず戦時下の民間人の手記や当時のアンケート結果をつぶさに紹介することで、日本民衆の視点から「アジア太平洋戦争」を描き出すことを目的としている。本文約300ページ。全四章で、第一章が日米開戦前までの世相を確認し、第二、三章では太平洋戦争突入以降、第四章は終戦直前から戦後までを扱う。 とにかく「膨大な量の戦争体験記類」から戦争体験者たちの声を丹念に拾い上げていることが本書最大の特徴だろう。日本国内だけではなく、当時の植民地や戦地に兵士として招集された民間人による記録も多数にのぼる。参照されるソースとしては、当事者による手記として刊行されていた著作がかなりを占めるほか、日記や新聞への投書、政府や米軍による調査報告書に掲載された記録なども含まれる。また、各種のアンケート結果からも、戦争の状況の変化とあわせて遷り変わる国民の意識を確認することができる。 書名となっている、「草の根のファシズム」の成立については、本書の第一章から第二章の途中までがその主たる期間にあたる。日中戦争開戦前後の時点で、政府や軍部に対しては批判的な声も多く、イタリアやドイツのような独裁を良しとする声は少なかった。しかし日本の場合、このような声は平和や民主主義、自由主義的体制には向かわず、天皇を戴くファシズム体制を生み出す力として作用することになった。本書内ではこの体制は、著者によって「天皇制ファシズム」と呼称される。この「天皇制ファシズム」が民衆の意識に及ぼした影響力・強制力については、戦後までをも含めて、著者によって再三その甚大さが指摘される。 本書を通してのまず第一の驚きとしては、戦前には民衆としても戦争そのものに反対する人々の割合は極端に少なく、論点はあくまで「戦争がどのようになされるか」にあった点が挙げられる。当時、植民地をもつ帝国としての日本の臣民であるという意識は民衆にも浸透しており、もっと明確な領土のための侵略戦争を求める声も主要な意見のひとつだったようだ。そしておそらくこの意識と連動する形で、他のアジア諸地域の住民への優越感と蔑視もきわめて一般的だったことがわかる。 このような戦前の意識との対比も含めて、全体のなかでは終章である第四章の一部でしかなく、紙数の割合としては少ないのだが、敗戦後の日本人の意識調査の結果は非常に興味深い。戦前は自明だった帝国主義から一転し、敗戦直後の日本人の多くは戦争に対して非常に強い忌避感を隠さず、平和とデモクラシー、そして経済発展による国家の繁栄を希求する。このような急激な意識の変化の反面、アジア諸国に対する蔑視や、戦争の最高責任者であった当の天皇への責任追及の声の小ささなど、戦前からあまり変わらずに持ち越されている側面も注目したい点である。 なお、もちろん戦争を経て他のアジア諸地域の人々への深い罪の意識を自覚する日本人も少なくはなく、本書でもその声が紹介されており、著者はそのような人々の特徴として、「激しい戦闘や苦戦・飢餓を体験したり、アジアの民衆と密接な交流を持った」という個人的な体験の有無を挙げている。逆に言えば、このような個人的な体験を欠いた人々においては、戦前の意識が持ち越されやすかったともいえる。 本書においてもっとも印象に残った点は、戦争前後の民衆が国家に求めるところが対極といえるほどに違うことである。民衆といえば、戦時中においては政府や軍部、天皇によって振り回され、戦後もアメリカ主導で成立した国家のレールに乗ることを強制させられる弱者というイメージをもちやすい。しかし、戦前と戦後の日本という国のあり方の変化と、民衆が求めた国家像に強い関係性がみられることは、本書を通して見れば明白に思える。当たり前のようではあるが、人々が何を求めるかが国家に多大な影響を与えるという点は、現在にも当然あてはまるところだろう。
Posted by
- 1