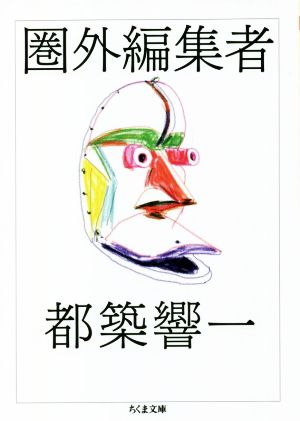圏外編集者 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
都築さんのお名前は知っていたが著書を読んだことなく、たまたま寄った書店で目に入りそのまま購入した。 読み進めていると、都築さんのような編集者は少なくなっているんだなと残念に思った。 ある事象について、人が書かないから仕方なく自分が書く、と書かれているが、強い使命感がある方なんだなと。 それに、編集者という仕事が物事に違う側面や正解は一つではないという人々の視野を広げてくれたり、価値観の多様性を投げかける大事な仕事だと再認識できた。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
古本屋でサルベージした。今ZINEを作っている最中なのだけども、そのタイミングで読めて良かった。紙の雑誌全盛期から編集者として活動してきた著者が語る編集、企画に対する今の考えはどれも興味深かった。また既存の価値観との付き合い方という広い意味で捉えれば何かの作り手でなくとも仕事論として楽しめるはず。 書籍作りの観点から八つの章立てされたインタビューの書き起こしでかなり読みやすい。著者が自身の経歴や担当作品を作るまでに至った経緯を含め丁寧に説明してくれている。どこかに所属していないからこそ歯に衣着せぬ物言いが可能で「おかしい」と思ったことを単刀直入に物申しているところが信頼できる。日本のヒップホップウォッチャーとしては『ヒップホップの詩人たち』の製作時に遭遇した日本のヒップホップのジャーナリズムに対する苦言が村の外側の視点としてオモシロかった。こんだけオモシロくて若者に局地的に人気があるカルチャーなのに内輪ノリが過ぎて外から見て何が起こっているのか分からず苦労したらしい。完全に内輪ノリでウヒヒ言っている側なので何も言えない。日本のヒップホップに限らず常に皆が興味を持っていないけれども熱がある対象を模索し既存の状況に対して怒りながら創作のエネルギーに変換してかっこいい本を生み出していくのだから有言実行とはまさにこのこと。実際、『ヒップホップの詩人たち』は数あるヒップホップ書籍の中でも資料価値は相当高い。 ネットを中心とした発信者側のハードル低下について、過去を知っている著者だからこその説得力がおおいにあった。今となっては当たり前のサービスに対するありがたみをひしひしと感じた。知の高速道路よろしく表現の民主化が進んで誰しもが表現者になれる時代となって久しいが、それがどれだけ画期的でありがたいのか改めて噛み締めさせられる。また本著を読むと何かを生み出すときの初期衝動に他人は関係ないということを思い出した。自分がやりたいからやる。シンプルだったはずのことが可視化されるアクセス数、インプレッションが目的になってしまう。そうではなく自分がオモシロいと思っていることを信じきれるかどうかが大事なのだった。道に迷ったとき読むと指針になりそうなバイブルめいた良書。
Posted by
同業界同業種の人への喝にも見える本だし、一読者として本ってこうやって出来るんだぁーと思った。でもこの著者の場合だけって事あるかも。読んでたら特殊な作り手のようなので。 書かれてる事はほんとそうだなぁと納得できる事ばかり。少数派に見える多数派を見つけるプロで弱者の味方で他のも読みた...
同業界同業種の人への喝にも見える本だし、一読者として本ってこうやって出来るんだぁーと思った。でもこの著者の場合だけって事あるかも。読んでたら特殊な作り手のようなので。 書かれてる事はほんとそうだなぁと納得できる事ばかり。少数派に見える多数派を見つけるプロで弱者の味方で他のも読みたくなりました。
Posted by
『TOKYO STYLE』を初めて見たとき、かなりのショックを受けた。こんな写真集があるんだという驚き。ちっともお洒落ではないし、住人が写っていないのに、住んでいる人の生活感や人生がダイレクトに感じられる部屋、部屋、部屋の写真。そしてオリジナル版は厚みも重みもずっしりとした重量...
『TOKYO STYLE』を初めて見たとき、かなりのショックを受けた。こんな写真集があるんだという驚き。ちっともお洒落ではないし、住人が写っていないのに、住んでいる人の生活感や人生がダイレクトに感じられる部屋、部屋、部屋の写真。そしてオリジナル版は厚みも重みもずっしりとした重量級のもの。 そこから、本書の著者、都築さんの出す本や写真集を追いかけることになった。 本書は、そんな都築さんが編集について語ったものだが、いわゆる編集のノウハウを教えるようなものではない。自分が本当に面白いと思ったことをとことんやってきた、単純に言うとそれに尽きるということ。 都築さんがこれまで書き、撮り、出版してきたものについての話は読んでいて本当に面白いし、60を超えた今でも新しいことにチャレンジしている姿に感動!
Posted by
たまたま新宿紀伊國屋で手に取りました。面白いです!お名前だけは知ってましたが、なぜか一度も読んだことがなかった。そのパンクというか反骨思想が、なぜかしっくりきて、この後、氏の著書を続けて読みました。
Posted by
・私は本を書名で選ぶ。おもしろさうだといふ書名があれば買つて読む。これだけである。何がおもしろいのか。それこそ行き当たりばつたりではあつても、書物に関するものには全部惹かれるといふことはあるから、やはり書物関連書をおもしろいとしてゐるのだと思ふ。かういふ選び方には当たり外れがある...
・私は本を書名で選ぶ。おもしろさうだといふ書名があれば買つて読む。これだけである。何がおもしろいのか。それこそ行き当たりばつたりではあつても、書物に関するものには全部惹かれるといふことはあるから、やはり書物関連書をおもしろいとしてゐるのだと思ふ。かういふ選び方には当たり外れがある。書名だけおもしろさうでもといふことはある。逆に、よく分からないけれど買つてみたらおもしろかつたといふこともある。私の場合は後者が多いやうな気がするが、これも私の何でも良いかといふ考へに起因するのかもしれない。この都築響一「圏外編集者」(ちくま文庫)もさうして選んだ1冊である。私はこの人を全く知らない。写真家としても名をなしてゐる人らしいが、それも知らない。ただ、巻頭にカラーグラビア頁があり、この人の作品、写真や編著が載つてゐる。これがおもしろさうだつた。そこで読むことにしたのである。 ・本書は8章からなり、それが問1から問8までとなる。問1「本作りって、なにからはじめればいいでしょう?」、答はその章全体である。見出しを見ると、「知らないからできること」「指があれば本はできる」「編集会議というムダ」等々で7節ある。この人の考へが分かるやうな気はするが、この人を知らないし、編著書も知らないのだから本当のことなど分かりはしない。それでも編集会議がムダだといふのは分かると思ふ。「どの出版社でも、場合によっては営業部も参加して会議で企画を決めるのが普通ではないだろうか。例えば毎週月曜の午前中、ひとり5個アイデアを出して云々」(23頁)、かういふ定例の会議はどこでも面白くないと思ふ。私がたまたまさうだつただけかもしれない。さうでなかつたとしても、それで生産性が上がるとも思へない。「つまらない雑誌を生むのは『編集会議』のせいだ」(同前)といふのは、案外正論かもしれないと思ふ。「読者を見るな、自分を見ろ」(31頁)といふ見出しもあり、そこに自らの経験で得た、「読者層は想定するな、マーケットリサーチは絶対にするな」(38頁)といふ言はば教訓があり、更に「知らないだれかのためでなく、自分のリアルを追求しろ。」(同前)とある。こんなことを言つてゐれば編集会議がおもしろくなくなるのは当然であらう。読者や市場は意識せず、自分の「リアルを追求し」て書きたいことを書く。当然、読者の当たり外れはあるが、おもしろい記事になることはまちがひない。それがたとへ本人一人のためであつても、それを書いて良かつたと思へるのは 編集者や書き手冥利に尽きるといふものであらう。これは問5「だれのために本を作っているのですか?」(161頁)とも関はる。 最初の見出しは「東京に背を向けて」(162頁)である。「東京のレコード会社の言いなりになる必要はないし、配信や販売のネッ トワークも自分たちで構築できる云々」(163頁)とあるのだが、これは「いま日本の地方が置かれている状況は、ほんとうにどうしようもない。」(164頁)からこそであらう。このやうな認識は東京にもあるのだらうが、現場の内と外では危機感が違ふ。出版関係者は東京にゐて書物を垂れ流してゐる。そこに編集会議やマーケットリサーチがあり、想定読者がゐる。現状ではそれを良しとする人の方が多さうである。そこでは食ふためにはたくさん売るしかないのである。このアンチとして出てきたのが都築氏であらうか。フ リーでずつとやつてこれたのも、この人の実力であると共に運の強さでもあらう。だからこの人は地方に移住する必要がなかつた。地方から何かを発信する必要がなかつた。幸ひであつたと言ふべきであらう。
Posted by
好奇心がクリエイティビティを生む。アウトプットされたその形はさまざまで、多数の「普通」の人々から評価を受けることもあれば、少数の「異常」の人々から評価を受けることがある。 さまざまなその形を、まっすぐ表現するのか、角度を変えて表現するのか、それは編集者のものの見え方次第で、娯楽に...
好奇心がクリエイティビティを生む。アウトプットされたその形はさまざまで、多数の「普通」の人々から評価を受けることもあれば、少数の「異常」の人々から評価を受けることがある。 さまざまなその形を、まっすぐ表現するのか、角度を変えて表現するのか、それは編集者のものの見え方次第で、娯楽になりうるし、地獄にもなりうる。 著者の考え方がぎゅぎゅっと詰まったこの本は、「モノの見方の角度の付け方」を教えてくれる。 クリエイターとして出会えてよかった本。
Posted by
<目次> 第1章 本作りって何から始めればいいでしょう? 第2章 自分だけの編集的視点を視点を養うには? 第3章 なぜ「ロードサイド」なんですか? 第4章 だれもやっていないことをするには? 第5章 だれのために本を作っているのですか? 第6章 編集者にできることって...
<目次> 第1章 本作りって何から始めればいいでしょう? 第2章 自分だけの編集的視点を視点を養うには? 第3章 なぜ「ロードサイド」なんですか? 第4章 だれもやっていないことをするには? 第5章 だれのために本を作っているのですか? 第6章 編集者にできることって何でしょう? 第7章 出版の未来はどうなると思いますか? 第8章 自分のメディアをウェブで始めた理由とは? <内容> 本当は各章は「各問」になっている。編集者都築響一の自伝のようなもの。「POPEYE」「BRUTUS」の外部スタッフ(というか臨時雇い?)から、『TOKYO STYLE』や『ROADSIDE JAPAN 珍日本紀行』、ラブホ、秘宝館やバイブのデザインなど、本人が面白いと持ったものを、自ら取材し、撮影し、出版していった過程を書いている。そして素直にその理由も述べている。やはりいつの間にか、日本は窮屈な時代になっているのだ。そしてWEB上の活動が、自分の思いを実現する術なのだろう。
Posted by
編集者講座はまじで意味なし。 そんなものに行くくらいなら、本を読んで書くべし。 わたしも完全に同意な意見であった。
Posted by
個人的に、いかに楽しく生きるかについて描かれた本だと思った。 メディアや企業が作り出した基準や流行に惑わされている方に読んでほしい。 私もマイナーな物の方が好きなので、頷きながら読んでしまった。 作者の熱が伝わってくる本だった。
Posted by
- 1
- 2