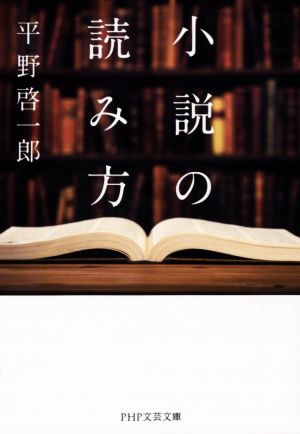小説の読み方 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
小説とはなにか 究極の述語に至る過程で著者の思惑をどれだけ映すことが出来るかを楽しむもの 主語を充填するか、前進するか プロットの舵の切り方と進路が力量を推し量れる指標となるものだと感じた。 これから小説を読む際は参考にしていきたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
4つの質問 1.メカニズム → どうしてそうなっているのか?そう書いたのか? 2.発展→作者の歴史の中で、その本はどういう立ち位置 3.機能→作者と読者にとってどういう役割を果たすのか 4.進化→文学史の中でどういう立ち位置なのか 大きい矢印(プロット)があり、それを進める小さい矢印がたくさんある。この矢印は、主語と述語の述語から方向性が分かる。 また、述語には2種類あって 1.主語充填(深み) 2.プロット(速さ) このバランスが読み応え、読みやすさに関わってくる。
Posted by
平野啓一郎さんだし、こ難しくて面倒くさい本に違いない…と思いつつ読んでみた。 予想を裏切り読みやすかった。 自分がいかに上っ面しか読んでいないことがよくわかる。同時に自分はとても物書きにはなれないと思わせる本だった。 取り上げられている本が蹴りたい背中とゴールデンスランバーし...
平野啓一郎さんだし、こ難しくて面倒くさい本に違いない…と思いつつ読んでみた。 予想を裏切り読みやすかった。 自分がいかに上っ面しか読んでいないことがよくわかる。同時に自分はとても物書きにはなれないと思わせる本だった。 取り上げられている本が蹴りたい背中とゴールデンスランバーしか読んだことなかったので、それぞれの作品を読んでからの方が良いのかと身構えたが、丁寧なあらすじと長めの引用でよくわかった。 今後に活かせるか…はさておき、楽しく読めた。
Posted by
物語を メカニズム、発達、機能、進化 の観点から考察してみる。 創造的な誤読を楽しむ。 ケータイ小説「恋空」について、文体の特徴として、形容詞、形容動詞、副詞といった修飾語が極端に少なく、まるでマンガの一コマを思わせるテンポ感、という平野さんの指摘に納得。 物語の中で、主人公...
物語を メカニズム、発達、機能、進化 の観点から考察してみる。 創造的な誤読を楽しむ。 ケータイ小説「恋空」について、文体の特徴として、形容詞、形容動詞、副詞といった修飾語が極端に少なく、まるでマンガの一コマを思わせるテンポ感、という平野さんの指摘に納得。 物語の中で、主人公がA君について語るとき、A君はそういう設定の人なんだろう、と思い込むことがあるけれど、それは主人公から見た視点のA君であり、そこに主人公という主語を補填する述語も含まれている、ということは新たな気づきであった。 言われてみれば、それは当たり前なんだけれど、創作物を読んでいる、という前提がその感性を鈍らせていたように思う。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
後半の具体ケースは読んでいないが、小説とは正式でない物語であること、観点のフレームとして、①メカニズム、②発達、③機能、④進化はわかりやすい。プロットの大きな矢印と小さい矢印のバランスはまさにアートだなと思った
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
⚫︎受け取ったメッセージ 小説を読む上でのアプローチの仕方がわかる本 実際の小説を用いての実践編が充実している 小説家による読み方指南であり、 大変興味深かった ⚫︎感想 絵画、音楽、芸能…芸術はただ漠然と受け止めて楽しむのもいいだろうが、枠組みをベースに味わうことは、その作品への理解が深まり、自分にとってとても有意義なものになる。一冊の本との出会いを大切にするためにも、読み方を知っておくことは大変有用だと思う。 一冊の本を読み、「なぜ」と考えることが、その作品や作家と向き合い、自分と向き合う時間となる 以下勉強になったこと。 2.4に関しては、意識的に考えていたが、 1.3については、個人的に意図して深めて考えたことはなかったなと思い、参考になった。 ⚫︎小説を4つの質問から考える 1、メカニズム 作者の提示する一つの世界を動かしている仕組みについて理解しようとする態度で、これまでとは違った感動を味わえる 2.発達 1人の作家を追い、その作家のテーマの発展や変化の過程を追うと、気付きがある 3.進化 社会の歴史、文化の歴史の中でのその作品の位置付けを考える。 4.機能 作者が伝えたいこと、読者が受け取るもの。その小説が、作者、読者双方に向けて持っている機能について考える。本のジャンル分け(ミステリー、ホラー、SF、恋愛…)は、この「機能」を単純化して示したものである。「この小説は、読者に対してどんな意味を持っているのだろう」「自分は、この小説と出会ったことで、どう変わっただろう」「作者は、この小説でどんな考えを深めたのだろう」…そうした小説のふるまいを考えるのが機能の問題 これら4つのアプローチから批評をするとわかりやすく、どういう点に着目して議論しているかがよくわかる。 ⚫︎知りたいという欲求と主語+述語 ⚫︎究極の述語への長い旅 ⚫︎大きな矢印は小さな矢印の積み重ね ⚫︎主語になる登場人物 主題や主役が際立つように工夫する。 (絵画と似ていると思った) ⚫︎話の展開が早い小説、遅い小説 「主語充填型述語」と「プロット前進型述語」 ⚫︎述語に取り込まれる主語 主語が人物像を他の登場人物や出来事によって補填される ⚫︎期待と裏切り バランス ⚫︎事前の組み立てと即興性 ⚫︎愛し方に役立てる
Posted by
小説は好きなように読めば良いとは思いつつ、読解力に自信がない私は本書を手にとった。 やっぱり読んでよかった! 小説って、こんなに深く読めるんだと衝撃の連続だった。 特に、私の好きな伊坂幸太郎のゴールデンスランバーの解説は、深すぎ!と思わず唸った。
Posted by
小説を読んだあとの読後感を上手いこと言語化することに憧れてこの本を読んだ。本のセレクトもジャンルごとに名作を選んでいたので自分があまり読まないジャンルの小説にも興味を持つことができた。また、小説内での登場人物、そして自分自身の感情をうまく捉えることができるようになったと感じる。
Posted by
第一弾の「本の読み方」では、スローリーディングについて語られていたが、第二弾のこちらは、小説の仕組みについて語られていた。小説を書く人、書いたことのある人が読むと、新しい視点や面白い試みなどが得られると思う。 前作の方は高校生にもおすすめしたいが、こちらは高校生では少し難しいか...
第一弾の「本の読み方」では、スローリーディングについて語られていたが、第二弾のこちらは、小説の仕組みについて語られていた。小説を書く人、書いたことのある人が読むと、新しい視点や面白い試みなどが得られると思う。 前作の方は高校生にもおすすめしたいが、こちらは高校生では少し難しいかもしれない。それだけ小説が複雑で深みのあるものなのだと感じた。 ・四つの質問 1.メカニズム(小説の仕組みはどうなっているか) 2.発達(その作家の人生のいつごろの作品か) 3.進化(社会・文学の歴史的にどんな意味を持つか) 4.機能(作者意図と読者の意味づけ、小説の振る舞いはどうか) ・主語になる登場人物と、最終的な着地点としての大きな述語 といった、第一部の大きな枠組みの説明に始まり、第二部では作品を取り上げての解説となる。 難しくはあるが、読んでいてなるほど、と思わされることが多くてためになった。国語の授業などでいかせたら面白いと思う。
Posted by
登場した主語に対して、どんな述語が続くのだろうという期待感が持続することが重要 いじめられて苦しかったのさ分かる。しかし、どうして自殺や殺人という方法を選んでしまったのだろう?他にも選択肢はたくさんあったはずだ。他人に対する「決めつけ」を注意深く回避する。 小説家にはとにかく書き...
登場した主語に対して、どんな述語が続くのだろうという期待感が持続することが重要 いじめられて苦しかったのさ分かる。しかし、どうして自殺や殺人という方法を選んでしまったのだろう?他にも選択肢はたくさんあったはずだ。他人に対する「決めつけ」を注意深く回避する。 小説家にはとにかく書き続けるという無闇な態度が、どうしても必要なのではないか。
Posted by
- 1
- 2