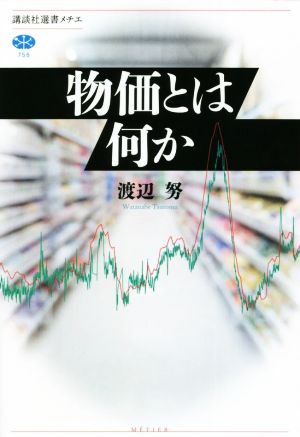物価とは何か の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
物価は、蚊ばしらである。世の中に何十万と存在する個別の商品それぞれが、一匹一匹の蚊に相当する。インフレを起こす仕組みとして、まず物価がX%の率で上がると皆が予想し、その予想を踏まえて企業や店舗が値札を書き換える、その結果実際にその率Xで物価が上がる、というメカニズムが考えられる。国民に働きかける中央銀行の行為の98%はトークである。人々の予測に働きかけるわけである。貨幣量を増やすと一時的に失業率は減少するが、しばらくすると貨幣量の増加をインフレ予想に織り込むことが完了し、失業率の押し下げ効果がなくなり、失業率は元の水準にもどる。 日本は物価が上がらない状態がかれこれ30年続いている。人々のインフレ予想が世の中を動かすことから、インフレ予想ができない層が増えているのは日本病の原因の一つだ。同じように企業もインフレ予想ができなくなっている。デフレが社会に定着すると、少しの値上げでも顧客が逃げてしまうのではと企業は恐れ、原価が上昇しても企業は価格に転嫁できないという状況が生まれる。それは企業の新商品開発への意欲を奪い、行き着く先はコストカットだ。物価下落自身はさほど大きな問題ではなく、企業が価格支配力を喪失し、それが経済の活力をそぐことこそが重大な問題だ。
Posted by
物価という身近でありながら学問となると一般には難しくなりそうなテーマをわかりやすくまとめた本。作者は実務を経験した学者、かつ起業もされているとあってこういう独特の筆致になるのかなと感じた。 最初は難解で正直つまづきそうになった。ただ、「物価とは蚊柱」という表現の意味がわかると目...
物価という身近でありながら学問となると一般には難しくなりそうなテーマをわかりやすくまとめた本。作者は実務を経験した学者、かつ起業もされているとあってこういう独特の筆致になるのかなと感じた。 最初は難解で正直つまづきそうになった。ただ、「物価とは蚊柱」という表現の意味がわかると目の前の風景が変わってくる。社会人になり教わった鳥の目(マクロの視点)、虫の目(ミクロの視点)、そして魚の目(潮流をとらえる視点)のフレームワークを使い、ここではそういうことを述べているのか、と理解するとスムーズに読めた。 インフレと雇用の関係を示したフィリップス曲線は参考になった。オルタナティブデータの活用など最前線も理解できた。 そのほかわからない事象にはその旨正直に述べる学者としての真摯な姿勢はとても参考になる。最近のSNSなどで見られる物事をシロクロはっきりさせて、時に誇張しても構わないという風潮に辟易としているので、難解なこの本を読みながら希望は見出せた。経済学は苦手だった大学時代にこそこういう本を読みたかったなあ…(苦笑)。
Posted by
久し振りの骨太本で、かなり時間がかかってしまった。読む人にはすきま時間ではなく、このために時間を作って読み進めていくことをすすめたい。 経済にうとい僕でも物価の何某かを導入として理解でき、日本経済のジレンマを知ることができる一冊だった。
Posted by
図書館で借りた。 経済系から1冊。ざっと1度流し読んだところ、「分かりにくい」というのが私の第一印象だ。タイトルの解である物価の定義も出てこず、のらりくらりとかわしていくような文章。またフィリップス曲線を紹介した直後に、70年代アメリカのスパゲッティ曲線を紹介するという流れは「著...
図書館で借りた。 経済系から1冊。ざっと1度流し読んだところ、「分かりにくい」というのが私の第一印象だ。タイトルの解である物価の定義も出てこず、のらりくらりとかわしていくような文章。またフィリップス曲線を紹介した直後に、70年代アメリカのスパゲッティ曲線を紹介するという流れは「著者はフィリップス曲線などの経済理論を否定したいのかな?」と感じてしまった。さらには、時折出る「専門家も分かっていないのです」なんて言葉は、前提や信頼をすべて崩しちゃってるのでは?なんてガッカリした。 それでも…巷での評判の高さを見て、私は再度読み返すことにした。 今度は深めに読んだ。著者の言いたいことは幾分分かった気がした。経済理論を否定したいわけではないのだろうし、逆説的に「壊せるならば、作れるはずだ」というのも理解できた。本全体の流れ・構成が評判を呼んでいるというのもなんとなく分かった。 …ただやはり、私は合わなかったかな~。
Posted by
2023/04/24 読み終わった ゆる言語学ラジオで紹介されていたので。 タイトルからがっぷり四つの迫力ある本だけど、中身はもっと骨太だった。高校程度の経済知識しか持っていなかった自分には目からウロコだった。 中でも一番面白かったのは、中央銀行総裁は嘘つきが一番いいというく...
2023/04/24 読み終わった ゆる言語学ラジオで紹介されていたので。 タイトルからがっぷり四つの迫力ある本だけど、中身はもっと骨太だった。高校程度の経済知識しか持っていなかった自分には目からウロコだった。 中でも一番面白かったのは、中央銀行総裁は嘘つきが一番いいというくだり。 情報公開なんてしたらしただけいいだろうと思っていたが、昔の中央銀行はそうではなかったということや、現在中央銀行が情報公開を積極的に行っている理由が単に公平性の観点ではないということ、この辺りが心に残った。 きちんと読み込まないと理解が追いつかない部分もあった。何度も読んで理解したい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
価格の硬直性についての理論的説明が繰り広げられた。メニューコストなのか、情報の制約なのか、、そしてしまいに出てくる日本の価格を上げられない消費者の厳しい目線というカルチャー的なもの。他の会社の価格に共鳴的に営業を及ぼすような価格支配力も失われ、、日本人は必死にコスト削減に命を燃やす、、その時間、付加価値付与に当てればいいのに!!すごく残念な気持ちになったけど、読み応え抜群です。 日本は新しい商品のうみかえで価格を上げている。そうでもしないと消費者の目が厳しい日本!ひいては儲けは賃金にもつながるのに、、。 フィリップス曲線についても教科書を超えた考察で、また勉強を重ねたら振り返って読みたい。
Posted by
元日銀マンの大学教授が物価とは何なのか詳しく教えてくれる。 「ゆる言語学ラジオ」で薦められていた。物価指数にも色々あるとか知らないことだらけ。前半は分かりやすかったんだけど、後半は難しくなった。
Posted by
良本、インフレやデフレといった概念をさらに細かく分解して説明していたりする。 難しい数式はなく、一般人にわかりやすい説明。
Posted by
大学で経済学を学んでいた頃は、理論はそうかもしれないが実態はね、と違和感を感じていた。 その後、モデルの改善は続いて、かなりわかってきた部分があるようで、納得のいく部分が増えたかなと感じる。 日本人の値上げ値下げに対する態度が非常に値上げに対して非常に厳しいと知り、ダウンサイジン...
大学で経済学を学んでいた頃は、理論はそうかもしれないが実態はね、と違和感を感じていた。 その後、モデルの改善は続いて、かなりわかってきた部分があるようで、納得のいく部分が増えたかなと感じる。 日本人の値上げ値下げに対する態度が非常に値上げに対して非常に厳しいと知り、ダウンサイジングは個人的には気に入らないが、企業の戦略としては巧妙だったんだと納得。 黒田バズーカも単なるバカ騒ぎではなく、経済理論に即した対応だったことを理解できた。 このところ賃上げが進んでいるが、これが継続するのか、大きな経済的なショックが起きないことを願う。
Posted by
経済に疎すぎる、残念な大人です。インフレと失業率に関係があることすら知りませんでした。 かなりわかりやすく書いてある本だと思いますが、金利についての知識がない上に数字の話が苦手なため、前半の理論部分は正直辛かったです。 しかし後半は、ステルス値上げなど消費者として聞いたことのある...
経済に疎すぎる、残念な大人です。インフレと失業率に関係があることすら知りませんでした。 かなりわかりやすく書いてある本だと思いますが、金利についての知識がない上に数字の話が苦手なため、前半の理論部分は正直辛かったです。 しかし後半は、ステルス値上げなど消費者として聞いたことのあるワードや、身近な物価の話で、なるほどと思うことも多かったです。 講談社現代新書の同著書の本を、読んでみようと思います。
Posted by