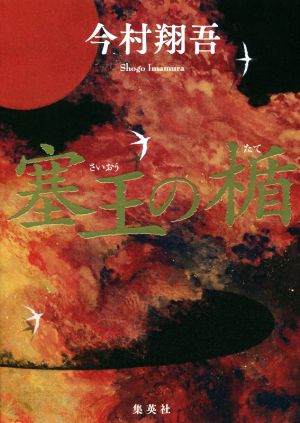塞王の楯 の商品レビュー
著者らしい、優しさと爽やかさと…。
2023年9月読了。 避けていた訳では無いのだが、しばらく積ん読状態だったので、手を延ばしました。 著者特有の爽やかで、思い遣りの有る優しい気風が、読んでいて本当に読書の醍醐味を教えてくれる、本当に直木賞に相応しい傑作だと思います。 徳川幕府に成ってからの綺麗な...
2023年9月読了。 避けていた訳では無いのだが、しばらく積ん読状態だったので、手を延ばしました。 著者特有の爽やかで、思い遣りの有る優しい気風が、読んでいて本当に読書の醍醐味を教えてくれる、本当に直木賞に相応しい傑作だと思います。 徳川幕府に成ってからの綺麗な並びの石垣よりも、豊臣時代のいわゆる「野積み」の石垣の方が、強度も強く、難易度も高かったのは知りませんでした。 てっきり「「綺麗な積み方」の方が強いんだと思い込んでいたのですが、世の中が平和に成り、「強さよりも見た目の良さ」にシフトしていったから、後世の石垣は綺麗なのだと思うと、目からウロコでした。 一方「矛方」である国友衆ですが、「そんなに素晴らしい精度の」鉄砲や大砲が作れていたのか、ちょっと疑問でしたが、このお話にはこれで丁度良いのかも知れませんね。 こんなに精緻な大砲が作れたんだったら、「大坂の陣」の時、どうして家康は南蛮の大砲(仏狼機)を使ったのかなぁ~?って、ちょっと意地悪なことも考えちゃいましたww。 なんて御託はここまでにして、読後感の爽やかさと、「人の生死については、どんな時代も関係無い」と云う、著者の信念も伝わって、大変面白く読み終えました。素晴らしい作品です。
左衛門佐
検品作業に疑問
作品自体は間違いなく秀作。ただ、髪の毛が4本挟まっていたのがとても不愉快でした。検品作業に疑問が残ります。
ちゃんもちゃんも
ああ、終わってしまった。 戦国の終わりにあって、最強の盾と矛が激突する。 終盤のまさに雷の如く鳴り響く矛と、聳え立ち何度でも再生する盾に感動する。 技能集団であるがゆえに、西軍東軍どちらの陣営に与するも自由!ってところがまたよし。 甲賀衆も滋賀なんて、ほんと滋賀県民の器用さがよく...
ああ、終わってしまった。 戦国の終わりにあって、最強の盾と矛が激突する。 終盤のまさに雷の如く鳴り響く矛と、聳え立ち何度でも再生する盾に感動する。 技能集団であるがゆえに、西軍東軍どちらの陣営に与するも自由!ってところがまたよし。 甲賀衆も滋賀なんて、ほんと滋賀県民の器用さがよくわかる。大津城に行ってみたくなった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
感動です。グッと心が熱くなりました。 同じ「集団」の中にも「組」があり、「組」の中にも「山方」「荷方」「積方」ある。職人たちは、受け持った仕事をひたすらやり遂げる。つまり、山方の一職人が積方をすることはまずない。だが、主人公である匡介は組の頭としてすべてを経験しなければならない。玲次も超一流の荷方でありながら、石を積ませてもこなせてしまう。その先を知っているからこそ仕事が「できる」 配慮ができる。ここの描写が私自身の仕事に繋がる(そうありたいとおもえる)もので心が動きました。 歴史小説を読み始めたのが最近で、数冊程度ですがおもしろい、歴史小説もっとよみたいという思いに拍車がかかった。 戦いの描写がうまくまるで見ている、そこにいるかのように思えた。描かれている2つの戦での「懸」はとても緊張感が伝わってきてドキドキします。 とてもおもしろい作品であったし、石垣や城、城跡にも興味が沸き(単純)、現在大津城はないが、長等山からの展望を楽しんでみたい。 歴史小説を読む以上は仕方がないが、距離の単位が難しい(泣 本当にいい作品でした。
Posted by
自分にとって初の今村翔吾さんの作品。 最近神保町に新しいスタイルの書店をオープンされたニュースを見て、執筆活動以外にも別に本に関する事業にも積極的に展開されている事を知った。 まだ30代と若いのにそういった販売、流通の活動にも視先が届くとは素晴らしい感性の持ち主であろう。その行動...
自分にとって初の今村翔吾さんの作品。 最近神保町に新しいスタイルの書店をオープンされたニュースを見て、執筆活動以外にも別に本に関する事業にも積極的に展開されている事を知った。 まだ30代と若いのにそういった販売、流通の活動にも視先が届くとは素晴らしい感性の持ち主であろう。その行動力に凄く好感を持っている。 今村さんの作品は色々と読んでみたいと思わされる作品が多く、まずはこちらの直木賞受賞作品から読んでみた。 舞台は戦国時代末期の近江国(滋賀県)、大津城。天下分け目の関ヶ原の戦いの一部になるのであろうか。 物語は石工職人と鉄砲職人とのプライドの攻防戦。凄い臨場感と緊張感で終盤の物語は圧巻。 以前フジテレビで「ほこ×たて」という番組があったが、ズバリこの作品のことではないか。非常に面白かった。 この作品が直木賞作品だと思わされるのが、混沌とした時代だからこそ石工も鍛冶屋も両者が平和の世を目指し腕を磨いているところ。 太平の世を自分達の腕と技術で平定するという理念、ここがプライドのぶつかり合いになり凄く面白い。 簡単にライバルという言葉では足らない、己らの意地と命と精神と使命の攻防戦がお見事だった。 この作品を読んで、現代社会にも通ずる話だと感じた。 その卓越した伝統技術を弟子にしっかりと受け継がせ、独り立ちさせている塞王。素晴らしいリーダーだ。 自分も飲食店の店主、部下は何人もいるのに教えきれているのか?導いているのだろうか? なんとも言えないとしか言いようがない。 そしてプライドの部分。ここまでのプライド持って仕事に取り組んでいないなと反省。今からまた気持ちだけでも前進していこうと決意を固めさせてもらった。 最高だった。 今後、何作か続けて今村さんの作品を読んでみたい。
Posted by
最高。城の石垣の話、大名の話、そしてストーリー、その全てが。この作品のお陰でまた歴史小説が大好きになりました。
Posted by
盾と矛。命を賭けて戦う男達の奮闘ぶりに胸が熱くなった。城が堕ちるとどうなるのか、城主はもちろん家臣も家来も町人も女、子供も悲惨な末路を辿る事になる。 戦は武将だけが行っているのではない。要塞として城の石垣をいかに強固に作り上げるか、 また、それを打ち破る為の武器をどれだけ開発する...
盾と矛。命を賭けて戦う男達の奮闘ぶりに胸が熱くなった。城が堕ちるとどうなるのか、城主はもちろん家臣も家来も町人も女、子供も悲惨な末路を辿る事になる。 戦は武将だけが行っているのではない。要塞として城の石垣をいかに強固に作り上げるか、 また、それを打ち破る為の武器をどれだけ開発するか、石垣作りの職人集団、穴太衆(あのうしゅう)飛田屋にスポットを当てた物語。 時代物が苦手な私にも本作は読み易く、戦国時代に興味が湧いた。今後は各地のお城を見る目が変わるだろう。数多くの職人の血と汗の染みついた石垣を戦いぶりに思いを馳せながら眺める事としよう。
Posted by
歴史小説は武士が主役であることが多いが、これは戦国時代を陰で支えたとも言える石垣積み職人の物語。直接刀で戦わなくとも、おのれの信念のために石垣に命を懸けた男の生き様に引き込まれた。 師匠や同僚、ライバル、そして大名など登場する人物がそれぞれ個性的でありながらも人間味があり、素晴ら...
歴史小説は武士が主役であることが多いが、これは戦国時代を陰で支えたとも言える石垣積み職人の物語。直接刀で戦わなくとも、おのれの信念のために石垣に命を懸けた男の生き様に引き込まれた。 師匠や同僚、ライバル、そして大名など登場する人物がそれぞれ個性的でありながらも人間味があり、素晴らしく魅力的に描かれている。 戦国時代と一括りに言っても、それぞれの身分や立場で正義があり、果たすべき役割や仕事があり、プロフェッショナルとしての自覚・誇りがあり。皆が平和で楽しく暮らせる世の中にするために、争いが生じ、戦わねばならないという、まさに矛盾。 物語としても文句なく面白いだけでなく、現代社会にも通ずる様々な考え方のヒントも与えてくれるような素晴らしい作品。必読の一冊。
Posted by
物語は圧倒的な力によって蹂躙される民の様子から始まり、戦国の世へと引き込まれてゆく。 特化した分野において人並み外れた才能を持つ二人が、奇しくも真逆のアプローチを以て泰平の世を目指す。互いの信念は導かれるように天下分け目の戦でぶつかり合い試されることになる。手に汗握る攻防の行方は...
物語は圧倒的な力によって蹂躙される民の様子から始まり、戦国の世へと引き込まれてゆく。 特化した分野において人並み外れた才能を持つ二人が、奇しくも真逆のアプローチを以て泰平の世を目指す。互いの信念は導かれるように天下分け目の戦でぶつかり合い試されることになる。手に汗握る攻防の行方は、そして二人の思いは。 結末まで飽きることなく楽しく読める作品。歴史小説にハマっていた頃を思い出した。
Posted by
お城の石垣職人である穴太衆と鉄砲職人の国友衆の戦い。 どちらも目指すわ泰平の世。 皆が鉄砲を持つ事で平和を目指す国友衆は今のアメリカとも重なって見えた。 この小説で、お城に対する見方も変わった気がする。 大河ドラマ以上の深い大河ドラマのようで楽しすぎた。 また、この著者の本を読ん...
お城の石垣職人である穴太衆と鉄砲職人の国友衆の戦い。 どちらも目指すわ泰平の世。 皆が鉄砲を持つ事で平和を目指す国友衆は今のアメリカとも重なって見えた。 この小説で、お城に対する見方も変わった気がする。 大河ドラマ以上の深い大河ドラマのようで楽しすぎた。 また、この著者の本を読んでみたいと思います。
Posted by