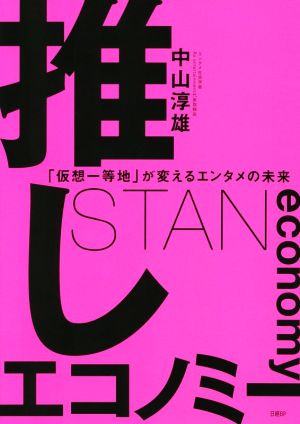推しエコノミー の商品レビュー
エンタメ業界で本格的に働き始めて一年。 職場で課題図書的に受け取った一冊。 エンタメ業界の起きている変革と来たる未来を説いてくれる、業界教育本です。 正直業界での日が浅いため、コロナ前後の変化があまり身にしみていないのですが、エンタメの歴史として非常に勉強になりました。 イチ消費...
エンタメ業界で本格的に働き始めて一年。 職場で課題図書的に受け取った一冊。 エンタメ業界の起きている変革と来たる未来を説いてくれる、業界教育本です。 正直業界での日が浅いため、コロナ前後の変化があまり身にしみていないのですが、エンタメの歴史として非常に勉強になりました。 イチ消費者として接していたコンテンツをビジネス側から見ると全く違う景色が広がっていて大変興味深く読みました。 日本のエンタメが巨大ハリウッドや中国相手にどうやって生き抜くのか、その術も警鐘と共に記されていて、仕事をする上で頭に刷り込んでおきたいと思います。厳しいが未来は決して暗くないと思わせてくれました。
Posted by
2021年刊行、コロナ禍を含めた現在のエンタメがどうなっているか?を様々なデータを元に解説。具体的な数字とともに作品ごとの経済圏が知れたり、フォートナイトなどバトルロワイヤル系ゲームの流行など、自分があまり詳しくない分野の話も知れて興味深かった。 一方、「推し」文化の考察や、タム...
2021年刊行、コロナ禍を含めた現在のエンタメがどうなっているか?を様々なデータを元に解説。具体的な数字とともに作品ごとの経済圏が知れたり、フォートナイトなどバトルロワイヤル系ゲームの流行など、自分があまり詳しくない分野の話も知れて興味深かった。 一方、「推し」文化の考察や、タムパ重視で動くユーザーや必死になってコンテンツを追う層の話などは自身の実感とは離れているなと感じたが、出資する側から数字としてのユーザーを掴もうとするとそういった解釈になるのだろうか。 また、「米中エンタメ覇権競争と日本唯一の挑戦者ソニー」の項も面白く読んだ。ソニーとパナソニック、そんな風に命運が分かれていたとは。ソニーについては金融事業が好調なことしか知らなかったため、2020年前後でゲーム・映画・音楽の事業も伸びたとは知らず、このまま頑張ってほしいと思った。 しかしながら日本が米中のように大きな資本を投下してひたすら拡張路線を突き進むのは難しいだろうというのには筆者に同意するところ。資源のない日本においてキャラクターIPが優良な資産であることは間違いないので、大切に育てていくことが大事だと思った。
Posted by
アニメやキャラクター、ゲームなどを含むエンタメ産業について、これまでの歴史を辿りながら、ユーザーにとってのニーズの変化、業界の変遷から、今後の課題について包括的に語られている本。トピックに合わせたのかピンク色のカバーが安っぽいイメージを抱かせているが、中身はこれでもかという分析が...
アニメやキャラクター、ゲームなどを含むエンタメ産業について、これまでの歴史を辿りながら、ユーザーにとってのニーズの変化、業界の変遷から、今後の課題について包括的に語られている本。トピックに合わせたのかピンク色のカバーが安っぽいイメージを抱かせているが、中身はこれでもかという分析が社会学や経営学、心理学など様々な視点から書かれている硬派な内容となっている。 現代のエンタメ市場は、ユーザーの行動はこれまでの「萌え」から本書のタイトルにもある「推し」に変化しているという。萌は内的な体験であるのに対して、推しは自己表現を伴う外的体験である。宝塚やジャニーズのファンに見られた「推し」という行動は、今やアニメやゲームの世界にも広がっている。 現代においては差別化の道具は陳腐化しているという。学歴や会社の肩書などという差別化はおしゃれではなく、ビジュアルの差別化は美女やイケメンだけに許された特権である。金持ち自慢やリア自慢は非難の対象となる。そのような社会の中で、2次元作品を介した自分の趣味嗜好の顕示は、自分自身の能力を問われない安全な自己表現となっているのである。 そして、エンタメ産業においてはアメリカの存在が市場としても供給側としても圧倒的な存在であり続けている中、そこに割って入ってきているのが中国である。巨大な市場を背景とした資本の大量投入による力技は、到底日本のエンタメ産業には及ばない。 但し、著者は米国や中国のやり方がベストであるという立場ではない。生物に例えると、米中は身体の大きい恒温動物であり生命維持の為に大量のエネルギーの取得を必要とする。一方、日本は小型の変温動物であり、活動量は少ないがエネルギーも少なくても済むと例えている。生き延びるための戦略は生物でも様々であり、必ずしも米中を真似る必要はないという。 世界第二位の経済大国などという過去の栄光やプライドにしがみつきがちな日本であるが、フランス、スイス、イタリアなどの国などは得意な分野に特化した生き方をしている事を指摘しており、日本もそこから学べることは多いと思われる。ビジネススクールの戦略論の世界でも規模の経済を背景とした競争戦略は既に過去のものとなっている。 - メモ - サイバーエージェント傘下のサイゲームスが運営する「ウマ娘」は2021年2月にリリースされ、初月の売上が驚愕の130億円を達成したという。 アプリゲームの市場規模は1.2兆円となり、売上TOP3はパズドラ(Gung Ho)、モンスト(Mixi)、Fate Grand Order(FGO、アニプレックス)が長く占めてきたという。そこに突如割って入ったのがウマ娘であり、唯一世界のゲームアプリでTOP10に入っている。
Posted by
タイトルから推し活ブームなどの潮流を解説する本かと思ったが、エンタメビジネスの動向を紹介する本。 タイトルと内容が合ってないような気がするが、エンタメビジネスについて理解するにはとても良い内容だったように思いました。
Posted by
現代、現在のエンタメと社会現象を整理した論文書! 論文と言ってしまうと堅苦しく感じるかもしれませんが、取り上げているコンテンツが身近なものばかりで難しい説明もなく明快痛快で読みやすい。 普段触れているゲーム、マンガ、アニメ、ドラマなどのエンタメビジネスの持続可能な究極はIPビジネ...
現代、現在のエンタメと社会現象を整理した論文書! 論文と言ってしまうと堅苦しく感じるかもしれませんが、取り上げているコンテンツが身近なものばかりで難しい説明もなく明快痛快で読みやすい。 普段触れているゲーム、マンガ、アニメ、ドラマなどのエンタメビジネスの持続可能な究極はIPビジネスだとよくわかります。そのゼロ→イチをどう生み出すか? この本には書かれてないのと、飛躍しすぎてる発言ですがキリストやブッダはまさにIPの元祖かもしれません。(それ以上の発言控えます) 人は偶像に惹かれる生き物なんだなーということを読書しながら考えていました。 まあとにかくエンタメとビジネスに関する紐解きに頷きっぱなしになるのと、日本人であることが誇らしく思えてきます。 エンタメ経済圏にまつわる中山淳雄さんの考察オススメです!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
この本のここがオススメ 「自分の人生の中には感動するような物語になかなか出会えない。そんな自分の代わりに、「推し」は頑張って何かを実現してくれて、感動を与えてくれる。そこで人々は理想の人生を「生きなおし」をするような作用を与えるものになっている」
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
所々難しいところもありつつ、最も印象的なのは 「萌え」→「推し」に世の中が変わっているということ 昔は 恋愛→結婚→性愛→出産の流れがあった中で、 現代は約束された流れが破綻し 恋愛/性愛/結婚/出産と分断されている。 自分のためにお金を使うようになり、 恋愛、性愛、結婚、出産に内包されるしがらみや自分の自我から、代わりに頑張っている「推し」を応援することで、理想の人生を「生き直し」しているという論理展開が印象的だった。
Posted by
何かを、推す心理的な物を期待して読んだか、エンタメの歴史や全体感が書いてありめちゃくちゃ勉強になった。
Posted by
タイトルに惹かれて手にしたが、エンタメ業界の構造変化から日本の目指すべき方向性への示唆などに富み、非常に面白かった。解説のみならず、文化圏や社会観と紐付けてエンタメを掘り下げていく内容であり、一冊を通おして楽しめた。 日本のアニメコンテンツは、放送・配信を収益化ポイントとして...
タイトルに惹かれて手にしたが、エンタメ業界の構造変化から日本の目指すべき方向性への示唆などに富み、非常に面白かった。解説のみならず、文化圏や社会観と紐付けてエンタメを掘り下げていく内容であり、一冊を通おして楽しめた。 日本のアニメコンテンツは、放送・配信を収益化ポイントとしてではなくユーザ認知のための手段として捉え、放送局や流通にこだわらない「脱テレビ化」の傾向にあり、版権ビジネスによるキャラクター経済圏として確立させることが成功の鍵となっている。また、ユーザー側のコンテンツへの関わり方としては、内的な感情による「萌え」から、「推し」という外的体験による表現へ変化し、ユーザーにとって趣味趣向は「消費財」ではなく「表現財」としていかに自分を「関与させていくか」という対象になった。インターネットにより地理的な距離がゼロになった現代において、キャラクターの死とは人々の間で共有されなくなることであり、キャラクターは思考(言語・文化・概念)の距離を埋める「交換財」としての機能を果たす。
Posted by
タイトルから勝手に「推し活」についての本かと思い手に取ったが、まじめにアニメや漫画を中心に映画や音楽ビジネスなども含めた「エンタメビジネス」について書かれていた。著者はそこを伝えたかったわけではないと思うが、現代において「売上を立てる」ためにどんな工夫が行われているか、ぼんやりと...
タイトルから勝手に「推し活」についての本かと思い手に取ったが、まじめにアニメや漫画を中心に映画や音楽ビジネスなども含めた「エンタメビジネス」について書かれていた。著者はそこを伝えたかったわけではないと思うが、現代において「売上を立てる」ためにどんな工夫が行われているか、ぼんやりとしていたものがハッキリして、自分の仕事にも役立ちそうだ。
Posted by