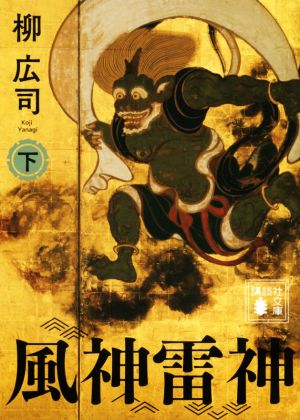風神雷神(下) の商品レビュー
俵屋宗達を造った二つの才能、本阿弥光悦と烏丸光広。 異能の絵師を理解し支える才能が時を同じくしてあったのは時代の偶然か運命の必然か・・・。ドラマだなぁ。
Posted by
下巻(雷の章)を読了。家業の扇屋を継いだ宗達は扇絵職人として京都で大人気を博すが、公家の烏丸光広に見出されて絵師の道へも踏み出す。光広の仲介で貴族や寺社の屏風絵などを次々と手掛けていったのだ。烏丸光広と本阿弥光悦。宗達はこの2人に導かれるように絵師の世界で遥かな高みに登っていく。...
下巻(雷の章)を読了。家業の扇屋を継いだ宗達は扇絵職人として京都で大人気を博すが、公家の烏丸光広に見出されて絵師の道へも踏み出す。光広の仲介で貴族や寺社の屏風絵などを次々と手掛けていったのだ。烏丸光広と本阿弥光悦。宗達はこの2人に導かれるように絵師の世界で遥かな高みに登っていく。そして死の間際に畢竟の名作・風神雷神図を残す。文章だけではイメージが伝わりにくいのでネット検索で宗達の絵画を確認しながら読み進めた。読書っぽくはないけどタマにはお勉強的読書もいいかなと思った
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
俵屋宗達の生涯が、出雲阿国、本阿弥光悦、烏丸光弘に絡んでくる。時代は秀吉から家光まで。トップが変わっても庶民が生きていくのはたいして変わりないのだと感じた。武士の歴史物と全然違う視点が楽しい。宗達の作品を改めて見てみたい。
Posted by
安土桃山時代に活躍した俵屋宗達にまつわる話。記録がほとんど残っていない為、大胆な仮説のもと、物語が進んでいく。物語の主題としては、どのようにしてあの独創性のある作品を残すことができたのか。こんな展開あるわけないと思いつつ、そうだったらおもしろいとこの説を裏付ける資料が出てこないか...
安土桃山時代に活躍した俵屋宗達にまつわる話。記録がほとんど残っていない為、大胆な仮説のもと、物語が進んでいく。物語の主題としては、どのようにしてあの独創性のある作品を残すことができたのか。こんな展開あるわけないと思いつつ、そうだったらおもしろいとこの説を裏付ける資料が出てこないかとも期待してしまう。
Posted by
情熱があれば、成し遂げれる。 若くても一生懸命自分の進んでいく姿に心を打たれる思いだった。 少しページ数が多いが、それはマハさんの宗達達への思いの強さが表れているのだろう。 全てが史実ではないが、それでも400年以上前に、15歳前後の子供達がローマまで実際に行ったことがどれだけ...
情熱があれば、成し遂げれる。 若くても一生懸命自分の進んでいく姿に心を打たれる思いだった。 少しページ数が多いが、それはマハさんの宗達達への思いの強さが表れているのだろう。 全てが史実ではないが、それでも400年以上前に、15歳前後の子供達がローマまで実際に行ったことがどれだけ苦難に満ちたものであったか、また、キリスト教弾圧という悲劇的な運命に遭ってしまう悲しさに感銘した。
Posted by
歴史ものですが、とても読みやすかったし、面白かったです。下巻は伊年ではなく、大人になった宗達の話。 宗達は確かに才能あふれる素晴らしい絵描きですが、それを真に理解するには「広汎な趣味と優れた感性、既成の価値観にとらわれない自由な知性をもった教養人の目を必要とした。」そんな人材であ...
歴史ものですが、とても読みやすかったし、面白かったです。下巻は伊年ではなく、大人になった宗達の話。 宗達は確かに才能あふれる素晴らしい絵描きですが、それを真に理解するには「広汎な趣味と優れた感性、既成の価値観にとらわれない自由な知性をもった教養人の目を必要とした。」そんな人材である光悦、光広という存在は大きかったし、彼らがいたからこその宗達だったのではないかと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
天正遣欧少年使節団に俵屋宗達が同行して、その上カラヴァッジョと出会っていたと、いうあまりにも奇抜で奇想天外な話。最初は「フィクションだからね」と思い読んでいたのだが、段々と「まさか、あるわけないよ、ね?」と。彼らの持つエネルギーが、引き寄せあってもおかしくないと思えてきた。 彼らはただ祈りたかっただけで、宗達はただ描きたかっただけの少年だった。ただ息をするように当たり前のことをしているだけだったのに、それがとても眩しくみえた。 それでも、ページが進めば進むほど、この後の彼らの過酷な運命を思うといたたまれなくたってくる。
Posted by
上下巻を通して、知った名前が出てくるので親しみやすい。最初は読みやすい感じがしたけど、途中から少し飽きかけた…最後のしめは綺麗で良かった。
Posted by
美術品をテーマとするお話はいくつか読んだことがありますが、その中では1番好きでした。 やはり有名な日本画をテーマにした分、親近感や多少の情勢知識が根底にあったからかもしれません。 けれど、俵屋宗達にフレームを当てているようで、ぼんやりとした人物像のまま終わるあたり、よい意味で広い...
美術品をテーマとするお話はいくつか読んだことがありますが、その中では1番好きでした。 やはり有名な日本画をテーマにした分、親近感や多少の情勢知識が根底にあったからかもしれません。 けれど、俵屋宗達にフレームを当てているようで、ぼんやりとした人物像のまま終わるあたり、よい意味で広い視野からの作品で気軽にサクサク読めました。 見た目はボリューミーに感じましたが、起伏が少ないので読みやすい良本です。
Posted by
やっぱり言葉が綺麗で、描写が細やかで物語の人達に魂を注いでくれる感じがマハさんの大好きなところ〜〜、、、 小説の中の人物が泣けば一緒に泣いた。 早くこの人たちの物語を読み進めたい!って思いが溢れたよ〜〜〜
Posted by