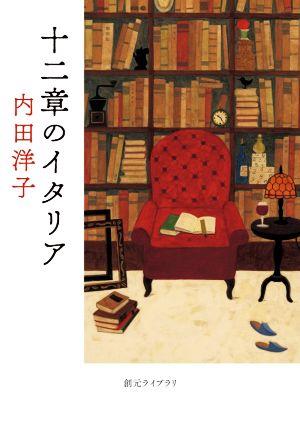十二章のイタリア の商品レビュー
文章が上手い人だなと思った! 他の本も読んでみよう。寄稿してる山口治明氏の言うように、どの章も陰翳があるから魅力的なんだろうなぁ。ユーミン的哀愁感を感じました。何故か懐かしさがある、土地の描写に日本的な何かを感じるのは何故だろう。 モンテレッジォが気になるなぁ。 そして、他の言語...
文章が上手い人だなと思った! 他の本も読んでみよう。寄稿してる山口治明氏の言うように、どの章も陰翳があるから魅力的なんだろうなぁ。ユーミン的哀愁感を感じました。何故か懐かしさがある、土地の描写に日本的な何かを感じるのは何故だろう。 モンテレッジォが気になるなぁ。 そして、他の言語を習得できる人たちに羨ましさがありますネ、私もイタリア語と英語を自分の言語に取り入れたい!そうしたらきっと、世界をもっと多面的に見ることができると思うんダ
Posted by
すべてが短編小説のような随筆集。何を読んでも満足なのですが、どうしたらこんな傑作たちがものせるのか…。
Posted by
「モンテレッジオの小さな村の旅する本屋の物語」を読んだ四年くらい前にこの本購入しておいたのだけど、この土日で読んでしまった。内田洋子氏は外大イタリア語科を卒業してイタリアに渡りジャーナリストとして日本にイタリアの出来事を送り、通信社のトップとなって、イタリアの文化、生活を橋渡しし...
「モンテレッジオの小さな村の旅する本屋の物語」を読んだ四年くらい前にこの本購入しておいたのだけど、この土日で読んでしまった。内田洋子氏は外大イタリア語科を卒業してイタリアに渡りジャーナリストとして日本にイタリアの出来事を送り、通信社のトップとなって、イタリアの文化、生活を橋渡ししてきた方です。この人の文章は静謐で爽やか、読みやすいです。 この本の中にフンベルト・エーコのことなどがとりあげてあり、読書の効用がエーコの言葉が書かれていて良かったです。是非、おすすめします。 本を読まない人は、七十歳なればひとつの人生を生きたことになる。その人の人生だ。しかし本を読む人は、五千年を生きる。本を読むということは、不滅の過去と出会うからだ。 ウンベルト・エーコ
Posted by
相変わらず内田洋子さんの本はいい。 だけど、これよりもほかの作品のほうが味わい深くておすすめ。 こちらはライトに楽しめるかな。
Posted by
内田洋子さんの本をはじめて読んだのは昨年の7月なので、ちょうど1年が経っている。このブグログでの感想を読んで面白そうだと思ったことが読み始めるきっかけだったと思う。本書「十二章のイタリア」が私にとっての11冊目の内田洋子さんの本になる。 内田さんは東京外大のイタリア語学科に入学さ...
内田洋子さんの本をはじめて読んだのは昨年の7月なので、ちょうど1年が経っている。このブグログでの感想を読んで面白そうだと思ったことが読み始めるきっかけだったと思う。本書「十二章のイタリア」が私にとっての11冊目の内田洋子さんの本になる。 内田さんは東京外大のイタリア語学科に入学される。そこから内田さんのイタリアとの付き合いが始まり、本書もそこから始まる。書名になっている通り、十二の短めのエッセイを集めたエッセイ集である。内田さんの魅力的なイタリア経験がそこでは語られているが、本書の各章に共通するモチーフは「本」である。 各章の題名は、「辞書」「電話帳」「レシピ集」「絵本」「写真週刊誌」「巡回朗読」「本屋のない村」「自動車雑誌」「貴重な一冊」「四十年前の写真集」「テゼオの船」「本から本へ」である。「テゼオの船」だけが、本と何の関係があるのかが分かりにくいが、これはイタリアの巨匠、故ウンベルト・エーコが設立した出版社の名前なのである。 このブグログに登録をされている方は基本的に本好きの方ばかりだと思う。私ももちろんそうである。内田さんの本書に促されるように、「本」に関してのエピソードを自分が思いつけるかを考えてみた。が、すぐに、いくらでも思いつくことが分かった。小さい頃に両親に買ってもらった「宝島」「十五少年漂流記」などの冒険物語。小学校高学年で夢中になって読んだ、アルセーヌ・ルパンとシャーロック・ホームズ。中学生・高校生の頃に読んだ日本の現代作家の小説の多くの舞台が東京であり、地方から東京に対する想いがつのった。大学に入って初めて読んだ英文の経済学の教科書のボリュームと、勉強することの大変さ。まだまだ沢山ある。こんなに本に対しての思い出がすぐに沢山出てくることに、逆に驚いた。 正確な生年月日は分からないが、本書を読んだりして、内田さんはおそらく私よりも一学年下にあたるのではないかと思う。学科はイタリア語ではないが、私自身も高校3年生の時に東京外大を受験するつもりで願書を出した。結局は東京外大の受験日までに合格していた大学に行き、外大は受験しなかったのであるが、もし、受験し万が一合格していたら、同じ時期に内田さんと同じキャンパスで学べたのだなと少し感慨がある。
Posted by
高校生のときにTVで黄金色の麦畑の光景を見たことをきっかけに、大学のイタリア語学科で学ぶことにした作者の、イタリアとの関わりの中にあった人生の一齣ひとこまを文章にしたエッセイ集。 そのバイタリティーで人間関係を作り、大きな企画をまとめ、通信社業務にも携わる作者。実際には喧騒の...
高校生のときにTVで黄金色の麦畑の光景を見たことをきっかけに、大学のイタリア語学科で学ぶことにした作者の、イタリアとの関わりの中にあった人生の一齣ひとこまを文章にしたエッセイ集。 そのバイタリティーで人間関係を作り、大きな企画をまとめ、通信社業務にも携わる作者。実際には喧騒の出来事や世界もあったのだろうが、作者により紹介されるイタリアの街や人物は、実に陰翳に富んで描かれている。「自動車雑誌」に出てくる、広大な地所を切り回す、一見農村女性風のフェラーリを乗り回す公爵夫人にしてから、日本人的感覚では推し量れない。 最終章「本から本へ」では、偶然訪れたヴェネツィアの古書店から、先祖が本の行商をしてきたモンテレッジォというトスカーナの町を知る。それが『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』につながる出会いとなっていく。 文庫本で250頁に満たない薄い本だが、滋味豊かな一編一編をゆっくり味わいながら読んでもらいたい。
Posted by
内田洋子(1959年~)氏は、神戸生まれ、東京外語大イタリア語学科を卒業後、40年来イタリアに在住するジャーナリスト、エッセイスト。2011年に『ジーノの家 イタリア10景』で日本エッセイスト・クラブ賞と講談社エッセイ賞をダブル受賞。現在、通信社ウーノ・アソシエイツ代表を務め、イ...
内田洋子(1959年~)氏は、神戸生まれ、東京外語大イタリア語学科を卒業後、40年来イタリアに在住するジャーナリスト、エッセイスト。2011年に『ジーノの家 イタリア10景』で日本エッセイスト・クラブ賞と講談社エッセイ賞をダブル受賞。現在、通信社ウーノ・アソシエイツ代表を務め、イタリアに関するニュースを配信するとともに、イタリアの風土、社会、人々、食をテーマに、年1~2作のペースでエッセイ集などを発表している。2019年には、日伊両国間の相互知識や情報をより深めることに貢献したジャーナリストに対して伊日財団より贈られる、「ウンベルト・アニエッリ記念ジャーナリスト賞」を受賞している。 本書は、2017年に単行本で出版され、2021年に文庫化された。 私は、『ジーノの家』にはじまり、『ミラノの太陽、シチリアの月』、『カテリーナの旅支度』、『皿の中に、イタリア』、『どうしようもないのに、好き』、『対岸のヴェネツィア』。。。と、著者の数々のエッセイ集を読んできたが、毎回、登場する著者の友人・知人たちの人間模様の複雑さ・多様さに驚き、また、それらを紡ぎ出すことのできる著者の、類稀な感受性、誠実さ、面倒見の良さ、人への興味、柔軟性、忍耐強さ、フットワークと、イタリアに対する愛情に、ただただ脱帽するのである。 本書は、1.辞書、2.電話帳、3.レシピ集、4.絵本、5.写真週刊誌、6.巡回朗読、7.本屋のない村、8.自動車雑誌、9.貴重な一冊、10.四十年前の写真集、11.テゼオの船、12.本から本へ、という12章から成っているが、いくつかの点で他のエッセイ集と趣を異にする。 ひとつは、各章のタイトル通り、広い意味での書物(と人)をテーマに編まれている点である。「テゼオの船」では、「本を読まない人は、七十歳になればひとつの人生だけを生きたことになる。その人の人生だ。しかし本を読む人は、五千年を生きる。本を読むということは、不滅の過去と出会うことだからだ。」と語ったウンベルト・エーコが描かれ、実に興味深いし(「テゼオの船」はエーコが作った出版社の名前)、「本から本へ」では、著者が後に『モンテレッジォ 小さな村の旅する本屋の物語』(2018年)に著す、トスカーナの山間の村モンテレッジォが取り上げられている。 もうひとつは、著者自身のことが描かれている点である。他のエッセイの多くでは、著者が見、聞き、感じたことがテーマとなっていたが、本書では、著者とイタリア(語)の出会いからこれまでの出来事が随所に登場する。「半生記」とまでは言わないが、ファンとしては、如何にして内田洋子は内田洋子と成り得たのかが垣間見られる、興味惹かれるものだった。 著者の数ある名エッセイ集の中でも、本(書物)好き、内田洋子ファンには、取り分け楽しめる一冊である。 (2021年2月了)
Posted by
- 1