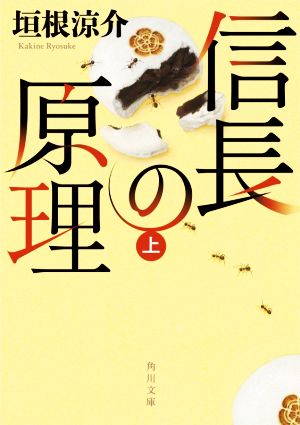信長の原理(上) の商品レビュー
一気読みできてしまう歴史小説という触れ込みを見て手に取ってみました。確かにその通りだった上巻は、織田信長の幼少期から京都にのぼるあたりまでのストーリーでした。 どこからどこまでがフィクションかわからないくらい、織田信長という人物について深く考え、その視点になってみると、きっとこの...
一気読みできてしまう歴史小説という触れ込みを見て手に取ってみました。確かにその通りだった上巻は、織田信長の幼少期から京都にのぼるあたりまでのストーリーでした。 どこからどこまでがフィクションかわからないくらい、織田信長という人物について深く考え、その視点になってみると、きっとこの通りだったのではと思えてきて、おもしろい! 歴史上の著名人もたくさん登場しますが、史実とされているそれぞれのその後を知っているだけに今後の展開が気になるところ。個人的には柴田勝家の心理描写や、帰蝶と信長のやりとりなどが読み応えありました。 現代リーダーシップやマネジメントにつながる話も多く、現役の管理職をされている方にも刺さるかもです。
Posted by
上下巻を読んでの感想 600ページもの長編だったが、最後まで読了。司馬遼太郎の物語よりもより深く、信長については、魅力的だが、非道な上司と映ったし、裏切った松永弾正や光秀もそうせざる得なかったことが、心理描写から納得させられた。信長の原理については、パレートの法則を絡めているの...
上下巻を読んでの感想 600ページもの長編だったが、最後まで読了。司馬遼太郎の物語よりもより深く、信長については、魅力的だが、非道な上司と映ったし、裏切った松永弾正や光秀もそうせざる得なかったことが、心理描写から納得させられた。信長の原理については、パレートの法則を絡めているのは面白い見方と思う。 歴史小説を読んでいると、現実の生活の多少のつらい事なども、何ほどの事でないと思えてくる。
Posted by
タイトルに惹かれて読み始めた。 二・六・二もしくは二・八のパレートの話に自然に気がついた信長がそれを家臣の統率にどう活かしたものかと逡巡するまで。 司馬遼太郎もので元亀天正の史実(に近いもの)は一通り頭に入っていたつもりだけど、本作では信長の頭の中が記述の中心なので、飽きずに読...
タイトルに惹かれて読み始めた。 二・六・二もしくは二・八のパレートの話に自然に気がついた信長がそれを家臣の統率にどう活かしたものかと逡巡するまで。 司馬遼太郎もので元亀天正の史実(に近いもの)は一通り頭に入っていたつもりだけど、本作では信長の頭の中が記述の中心なので、飽きずに読めた。 下巻が楽しみだ。
Posted by
織田家の尾張統一から姉川の戦いまでの話。 歴史小説の中ではかなり読みやすい。 信長の心情を細かく描いており、本当にこんな風に思っていたのかもと感じることができる。 歴史の流れも理解できるので良い。
Posted by
戦国時代は明智光秀入りの私にとって、織田信長ほどの暴君は他におらん!と恐ろしくなっていたが、この本を読んで、信長も推せると思った笑。いろんな人が登場して訳分からなくなったけど、全体の流れはしっかり伝わってきましたぞ! 心にハッときたフレーズを逐一書き留めているけど、この本に登場す...
戦国時代は明智光秀入りの私にとって、織田信長ほどの暴君は他におらん!と恐ろしくなっていたが、この本を読んで、信長も推せると思った笑。いろんな人が登場して訳分からなくなったけど、全体の流れはしっかり伝わってきましたぞ! 心にハッときたフレーズを逐一書き留めているけど、この本に登場する信長のサッパリとした考え方はとても素敵だったし、たわけモードの信長の心情にとても共感できて、記録が膨大な量と化してしまった。下巻も楽しみ!
Posted by
光秀の定理では「モンティ・ホールの確率」、今作では「パレートの法則」。 どちらも切り口が面白い。 史実は分かっているが武将達の立ち位置と心理描写が詳しいフィクション。 蟻を使った2:6:2の法則では信長本人の視点、苦悩や心の揺れが面白く600頁近い大作も最後まで飽きずに読めた。 ...
光秀の定理では「モンティ・ホールの確率」、今作では「パレートの法則」。 どちらも切り口が面白い。 史実は分かっているが武将達の立ち位置と心理描写が詳しいフィクション。 蟻を使った2:6:2の法則では信長本人の視点、苦悩や心の揺れが面白く600頁近い大作も最後まで飽きずに読めた。 秀吉、光秀、勝家、たくさん武将が登場する中で松永弾正が魅力的に書かれていた。 光秀の定理の細川藤孝みたいな?
Posted by
こちらのブクログの感想読んで興味を惹かれて読みました。元々、歴史好きで戦国時代も好きなので時代小説としても楽しく読めるのですが、時代小説でありながらパレートの法則(2:8の法則)を扱っているところが面白いです。しかもそれが不自然でなく溶け込んでいるという。 上下巻なのでこの話がど...
こちらのブクログの感想読んで興味を惹かれて読みました。元々、歴史好きで戦国時代も好きなので時代小説としても楽しく読めるのですが、時代小説でありながらパレートの法則(2:8の法則)を扱っているところが面白いです。しかもそれが不自然でなく溶け込んでいるという。 上下巻なのでこの話がどういう落とし所になるのかも楽しみですが、ページ数の関係上、えっ!そこで切れるの?というところで終わってしまったので早く下巻を読みたいです。
Posted by
織田信長は早くから働き蟻の定理に気が付いていた。だったら全てを働き蟻にすれば良いと考えるが上手くいかない。今川義元を討った桶狭間の戦いでは皆が決死の覚悟で働き蟻になる事で勝利出来たと考える。さらに思考を進めていく。 信長の内面を検討して実験をしていたとするのが面白い。さらには秀吉...
織田信長は早くから働き蟻の定理に気が付いていた。だったら全てを働き蟻にすれば良いと考えるが上手くいかない。今川義元を討った桶狭間の戦いでは皆が決死の覚悟で働き蟻になる事で勝利出来たと考える。さらに思考を進めていく。 信長の内面を検討して実験をしていたとするのが面白い。さらには秀吉がそれに気が付いていたと考え光秀は察する程度と差があったとしているのも、その後を考えるとよく出来ている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2:6:2の割合。どんなに優秀な兵を登用しても2割が懸命に働き、6割が流される日和見、残り2割は逃げ出す。 信長少年が幼い頃に観察した蟻の働きと全く同じ、、、。何故だ?孤独と怒りを抱えながら、家臣に疎まれ、自身の思いを理解されず苛立ちながらも独特の思想と思考が徐々に家臣からも一目置かれる存在に。 仕事の任せ方、意思決定のための情報収集など今に通ずる話題が盛り沢山。
Posted by
2:6:2のパレートの法則を信長の天才的な洞察力と組み合わせた、垣根涼介技ありの歴史小説。 天才的な視点と洞察力による発想が常人には理解されない信長と、それらを理解できずに抱く焦燥感と恐怖に苛まれる家臣達とのズレの描写は、筆者は実際にそれらを見て書いたのではないかと思ってしまうほ...
2:6:2のパレートの法則を信長の天才的な洞察力と組み合わせた、垣根涼介技ありの歴史小説。 天才的な視点と洞察力による発想が常人には理解されない信長と、それらを理解できずに抱く焦燥感と恐怖に苛まれる家臣達とのズレの描写は、筆者は実際にそれらを見て書いたのではないかと思ってしまうほどリアルに感じられた。 個人的には、有能であるが故に光秀や秀吉のような飛び抜けた才能がないことも自覚し、生き残るために勝馬に乗るしかないと腹をくくる丹羽長秀には去来するものがあった。 先に発表されている「光秀の定理」を読んでからこちらを読まれるとさらに楽しめると思います。
Posted by