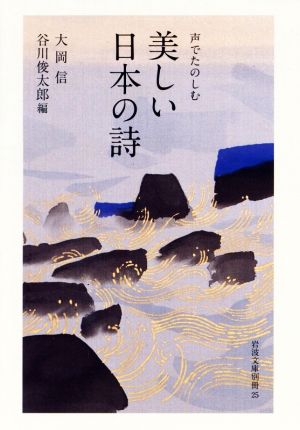声でたのしむ 美しい日本の詩 の商品レビュー
「声でたのしむ」というタイトル通り、読んでみたくなる俳句や詩、短歌、川柳など。見た目の文字でも面白いものもあり、そのギャップもまた面白いものが多い。解説もあるので読みやすくて、その解説一つ一つも面白い。
Posted by
持論だけれども、詩や歌はどれだけ引用され愛誦されたかでその価値が決まると思っている。だから、作者から訴えられない限りは、どんどん引用して広めるべきだというのが私のポリシーである。 「詩は本来、朗唱されるものです。」 ーそういう編集方針で編まれた詩歌のアンソロジー。大岡信・谷川俊...
持論だけれども、詩や歌はどれだけ引用され愛誦されたかでその価値が決まると思っている。だから、作者から訴えられない限りは、どんどん引用して広めるべきだというのが私のポリシーである。 「詩は本来、朗唱されるものです。」 ーそういう編集方針で編まれた詩歌のアンソロジー。大岡信・谷川俊太郎の偏見がかなり入っていて、気に入ったのもあるし、気に入らないのもある。しかもまる2年間半積読していた。元本は90年刊の「和歌・俳句編」「近・現代詩編」を一冊にまとめたものらしい。文庫本になったことで、いつでも携帯できることに気がついた。とりあえず、気に入った詩歌を以下にメモする。その後、気になった詩歌を見つけたら、どんどん追加していこう。コレ案外いい本である。 荻の花尾花葛花瞿麦(なでしこ)の花女郎花(おみなえし)また藤袴(ふじばかま)朝貌(あさがお)の花 ←577577形式の旋頭歌。秋の七草。山上憶良(7-8世紀)が歌った。 大和は国のまほろば たたなづく青垣山籠れる大和しうるはし ←古事記歌謡より。ヤマトタケルが絶命する時に故郷を偲んだ歌と言われているが、実際には儀式の国ぼめのうたが援用されたのだろう。 あらざらむこの世のほかの思い出にいまひとたびの逢ふこともがな 「私が死んであの世にいってしまってからの思い出のために、せめてもう一度お会いしたいのです。」 ←こう言われちゃったら、よっぽどのことがない限り、もう一度会うでしょ。和泉式部(10-11世紀)はプレイガールの元祖。 逢ひ見ての後の心にくらぶれば昔は物を思はざりけり ← 一方、権中納言敦忠(10世紀)の方は、かなりロマンチスト。前の人とはかなり対照的。 仏は常にいませども現(うつつ)ならぬぞあわれなる 人の音せぬ暁にほのかに夢に見え給ふ ←「梁塵秘抄」(12世紀後半)の最も有名な歌。後白河が撰んだ、この頃の歌謡曲。曲調は?声質は?世の辛さを感じていた人々を、この歌がどれほど癒したことか。 蛸壺やはかなき夢を夏の月 ←芭蕉、17世紀の人。辛き世のいっときの癒しの夢を、皮肉めいて笑っている。コレが近世。 大蛍ゆらりゆらりと通りけり ← 一茶、18-19世紀の人。辛き世を、それでも楽しみたいのである。 少年の日 佐藤春夫 1 野ゆき山ゆき海辺ゆき 真ひるの丘べ花を敷き つぶら瞳の君ゆゑに うれひは青し空よりも。 2 影おほき林をたどり 夢ふかき瞳を恋ひ あたたかき真昼の丘べ 花を敷き あわれ若き日。 3 君の瞳はつぶらにて 君が心は知りがたし。 君をはなれて唯ひとり 月夜の海に石を投ぐ 4 君は夜な夜な毛糸編む 銀の編み棒に編む糸は かぐろなる糸あかき糸 そのラムプ敷き誰がものぞ ←谷川俊太郎は「漢文、文語、口語を使いこなすことのできた春夫のような詩人に比べると、口語しか使えぬ現代詩人の多くは、日本語という宝の持ち腐れ」と言う。谷川と共感すること寡ない私乍ら、コレには肯く。 眼にて云ふ 宮沢賢治 だめでせう とまりませんな がぶがぶ湧いてゐるですからな ゆふべからねむらず血も出つづけなもんですから そこらは青くしんしんとして どうも間もなく死にさうです けれどもなんといゝ風でさう もう清明が近いので あんなに青ぞらからもりあがって湧くやうに きれいな風が来るですな もみぢの嫩芽(わかめ)と毛のやうな花に 秋草のやうな波をたて 焼痕(やけあと)のあるい草のむしろも青いです あなたは医学会のお帰りか何かは知りませんが 黒いブロックコートを召して こんなに本気にいろいろ手あてもしていたゞけば これで死んでもまづは文句はありません 血が出てゐるにかゝはらず こんなにのんきで苦しくないのは 魂魄なかばからだをはなれたのですかな たゞどうも血のために それを云へないがひどいです あなたの方からみたらずゐぶんさんたんたるけしきでせうが わたくしから見えるのは やっぱりきれいな青ぞらと すきとほった風ばかりです。 ←ほう、そうか これを撰んだか ほう、そうか これを撰んだか もちろん、絶筆じゃない。 2023年9月25日記入
Posted by
いつだったか、音読と黙読の経緯の話を読んでいた。 黙読という読書方法が浸透している中で、声に出して詩歌を楽しむ。音のリズムを楽しむ。 でもそうなんだよな。歌詞だって声に出しているのが当たり前なんだから、詩歌だって今の時代に声に出して楽しんでいいはず。
Posted by
大岡信×谷川俊太郎でカバー&カットが安野光雅ときたら、手に入れるの一択。 (ここに松居直が加われば、あの「にほんご」編集チーム)
Posted by
『文学は実学である』を読んで手にとりたいと思って読んだ詞華集。 一日六頁づつ読んだ。 手もとに置いておきたい本だ。
Posted by
小さい頃から読書が好きで、中高も文芸部に入り、言葉とは長年向き合ってきた。だからこそ、物事の表現の仕方や美しい言葉に興味がある。この本の題名を見た際に、まず一つに『声でたのしむ』というところから最近、声に出して読む機会が少なくなってきたと感じたこと、二つに『美しい日本の詩』という...
小さい頃から読書が好きで、中高も文芸部に入り、言葉とは長年向き合ってきた。だからこそ、物事の表現の仕方や美しい言葉に興味がある。この本の題名を見た際に、まず一つに『声でたのしむ』というところから最近、声に出して読む機会が少なくなってきたと感じたこと、二つに『美しい日本の詩』というところからどんな詩が美しいとされる作品なのか興味を持ったため、この本を選んだ。
Posted by
スペイン人詩人ロルカの詩集の読後感から、迷わず母国語の詩を求めました。 これまで使ってきたことば(音)と、なじみのある風景・におい・空気・ものの質感そして感情。詩を味わうためにはそういうものをどれだけ共有できるかが大事だということがよくわかりました。 各作品の解説は端的でありな...
スペイン人詩人ロルカの詩集の読後感から、迷わず母国語の詩を求めました。 これまで使ってきたことば(音)と、なじみのある風景・におい・空気・ものの質感そして感情。詩を味わうためにはそういうものをどれだけ共有できるかが大事だということがよくわかりました。 各作品の解説は端的でありながら、鑑賞のヒントを的確に与えてくれる上に、俳句・短歌・詩を通じて、日本語の楽しさを考えさせてくれるものでありました。
Posted by
この度、岩波文庫から出版された「美しい日本の詩」という本の中で、 少し気になることがありましたのでここに書き留めてみました。 編集者の一人である谷川俊太郎氏は、詩は声に出して読むもの、歌うものと という考えのもと、「できるだけ声に出しやすい詩、 声に出して楽しく分かりやすい詩をえ...
この度、岩波文庫から出版された「美しい日本の詩」という本の中で、 少し気になることがありましたのでここに書き留めてみました。 編集者の一人である谷川俊太郎氏は、詩は声に出して読むもの、歌うものと という考えのもと、「できるだけ声に出しやすい詩、 声に出して楽しく分かりやすい詩をえらびました。」とあります。 勿論、基本的には大賛成です。しかし…… で、原民喜の詩「日ノ暮レチカク」を取り上げ、 「カタカナとひらがなの違いは、なかなか微妙なものがありますが、 それをどこまで声で表現できるでしょうか」 とあります。 私は原民喜がカタカナを使ったのは、一文字、一文字丁寧に読んでもらえるように、 そして何より、カタカナを使うことに静かなイカリを表している理解しています。 ここに声だけに頼るのではなく、見るという一動作を加えることの意味があると理解しています。 また、草野心平の「誕生祭」という詩はどのようにして声に出して読むのでしょうか? 何行にもわたり字下げあります。 これは声でどのように表現するのでしょうか? 更に音の強弱、クレッシェンド、デクレッシェンドは? 更に更に、漢詩を鑑賞する事をどうとらえたらよいのでしょうか? 漢詩には日本語の同音異義語が頻出します。 しかしながら、菅原道真、頼山陽等々日本文学において、 漢詩は一つの文化を為しています。 漢文無くして日本文化は語れません。 また、例えば、ある詩で 「彼はどうしたのだらう ??? ……」 という下りあったとすれば、朗読者は「??? ……」をいか表現するのでしょうか? およそ詩とは表現において舞う羽のごとく全く自由なものだと思います。 そうした意味で、谷川氏の選集には、少なくと一つの落とし穴があると思います。 更に申し上げれば、耳の不自由な方、発声が思うように出来ない方、これらの方々はどうしたらよいのでしょうか?まさか、詩を読む資格無しとおっしゃるのではないでせうね。
Posted by
本屋さんで衝動買いした。買う予定のなかった本で、これほど楽しく読める本に出会うことが出来て嬉しい。ネットではやはりこういう出会いはなかなかないのではないだろうか。もちろんAmazon等ではおすすめの本が表示されるので、それはそれで良い出会いがある。でも、そもそも鏡花が欲しくて本屋...
本屋さんで衝動買いした。買う予定のなかった本で、これほど楽しく読める本に出会うことが出来て嬉しい。ネットではやはりこういう出会いはなかなかないのではないだろうか。もちろんAmazon等ではおすすめの本が表示されるので、それはそれで良い出会いがある。でも、そもそも鏡花が欲しくて本屋に行ったのに、たまたま近くにあったこの詩集を買ってしまった、これはたぶんAmazonでは予想できない出会いではないだろうか。また、電子書籍でも立ち読みに類することができるのではという意見もあるかもしれない。しかし、手に取ってみた肌触り、匂い、重さ等によって、お気に入りの本というのが決まるのであって、やはりモノとしての本が好きな人なら、本屋は永久に身近にあってくれないと困る。 話がそれてしまったが、本書には、短歌・俳句・近現代詩のそれぞれの分野から、音読することを念頭に選ばれた作品が集められている。声に出して読むのに良いもの、ということなのでもちろん黙読していてもリズムや単語の響きが心地よく感じるものばかりであった。また、音では同じでもひらがな、カタカナ、漢字表記を意図的に使い分けている作品もあり、詩人や歌人は音の響きだけではなく当然視覚的な効果を意図して作品を書いていることを感じさせられた。 さらに、本書の魅力はそうした「声」「音」をテーマにして詩や俳句を味わえるということだけではなく、選者の大岡信さん、谷川俊太郎さんが一つ一つの作品に詳しい注釈と解説を加えている点である。詩集や歌集はいくつも他に持っているけれど、収録されているすべての作品にここまで丁寧に解説が書かれていて、しかも文庫で手軽に持ち運びもできるのは初めてで、何て贅沢な本だろうと思った。 万葉集の時代から現代に至るまで選りすぐりの名作を一通り学ぶことができた。お気に入りの作品もたくさん見つけることができた。
Posted by
- 1