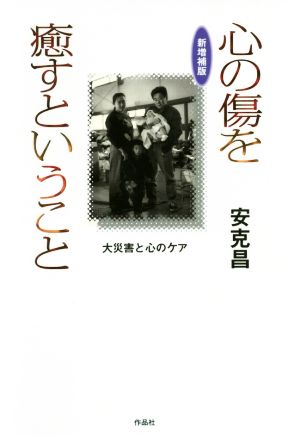心の傷を癒すということ 新増補版 の商品レビュー
被災地での様子を内面から伝える為に書かれた本ということで、被災地での混乱ぶりがリアルに伝わってくる。 被災直後は情報も無く、手探りで自分ができることに当たるしかない状況。しかし経過と共に求められる救護活動は変わっていく現実。 医療も震災直後の救急医療、そして後日起きてくる不調...
被災地での様子を内面から伝える為に書かれた本ということで、被災地での混乱ぶりがリアルに伝わってくる。 被災直後は情報も無く、手探りで自分ができることに当たるしかない状況。しかし経過と共に求められる救護活動は変わっていく現実。 医療も震災直後の救急医療、そして後日起きてくる不調に合わせた診療提供、その後長期的に必要な心のケアを読み進めるにつれて実感した。 仮設住宅一つとっても、応募に当たった時の複雑な気持ちがあり、住みづらさに耐え、通勤・通学に苦労し、世間からは解決したと思われがちであるが故に抱く反発心や切なさがある。人の心の葛藤を繊細に捉え、問題視している安医師の考えに触れることは、物事を単純に考えないよう教えてくれる。
Posted by
audible39冊目。 夫に勧められて読ました。 わたしが物心ついてから最初に記憶に残っている震災は、阪神淡路大震災です。 著者は、この震災に被災者として、そして精神科医として向き合った方です。 被災者が被災者の救助や支援にあたっていることに、今更ながら気付かされました。 ...
audible39冊目。 夫に勧められて読ました。 わたしが物心ついてから最初に記憶に残っている震災は、阪神淡路大震災です。 著者は、この震災に被災者として、そして精神科医として向き合った方です。 被災者が被災者の救助や支援にあたっていることに、今更ながら気付かされました。 地震発生直後は、命を救うために怪我をした方々の治療が最優先となりますが、次に課題となるのが、心に深い傷を負った方々の治療になります。 一人一人の患者さんに真摯に向き合い、そして、社会全体がよりよい方向に歩み出せるように考えておられ、尊敬の念を抱きました。 被災者や被災地に対する支援の在り方に大きな提言をもたらしてくださったと思います。 大切に読み継がれていくべき一冊だと感じました。
Posted by
基本、9割は安克昌の災害体験記であり、別の見方をするなら「セルロイド・クローゼット」のPTSD版である。 おそらくこの本の「患者になり得ぬ患者」とでも言うべき人々は複雑性PTSDに相当するのではないか。 言語に絶する体験をした時、人は「語り得ぬ痛み』を受け、語ることが出来ないのだ...
基本、9割は安克昌の災害体験記であり、別の見方をするなら「セルロイド・クローゼット」のPTSD版である。 おそらくこの本の「患者になり得ぬ患者」とでも言うべき人々は複雑性PTSDに相当するのではないか。 言語に絶する体験をした時、人は「語り得ぬ痛み』を受け、語ることが出来ないのだ。 それは倫理であり対面であり、然し本質的に痛みとは人それぞれの内面に生じたヌノーミスとでもいうか、触り得ない・語り得ない孤独な裂け目だ。 この様にレポート式に安克昌が見聞きしたことを書くことで、「語り得ぬ痛み」を受けた者は自らの痛みに気づく。 終章ではやはり「痛みに手当てするとはどういうことか』の本質が描かれている。 誰でも読んでいい。 例えば「痛みに触れることなく痛みの存在を知り合う」そういうことが話者と聞き手の中で共有される事により、痛みに向かい合える。 一つのレポートとして大変参考になった。
Posted by
これまで、著者について知らなかったことが悔やまれるくらい、感銘を受けました。 安先生が生きておられたら、お話を直接聞きたかった。 30年前、自分もあの時神戸にいました。親御さんを亡くした友人もいました。あのときに、このような活動をされ、考察された文章を拝読して、今の自分自身も癒さ...
これまで、著者について知らなかったことが悔やまれるくらい、感銘を受けました。 安先生が生きておられたら、お話を直接聞きたかった。 30年前、自分もあの時神戸にいました。親御さんを亡くした友人もいました。あのときに、このような活動をされ、考察された文章を拝読して、今の自分自身も癒されましたし、まだまだ続いている被災者された方のトラウマケアや、その後に起きた災害で被災された方に思いを馳せました。そして、安先生の著書の結びの言葉が、心に深く残りました。 世界は心的外傷に満ちている。"心の傷を癒すということ“は、精神医学や、心理学に任せてすむことではない。それは社会のあり方として、今を生きる私たち全員に問われていることなのである。
Posted by
阪神大震災から30年。NHKドラマアーカイブと併せてオーディブルにて拝聴 一人ひとりが尊重される社会を作るということ 誰もひとりぼっちにさせないこと 災害時はもちろんのこと、広範囲で『支援とは何か』を考えさせられた @オーディブル
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
神戸の阪神大震災から30年目に読む。NHK100分で名著の番組で取り上げられている。原著は265ページまでであるが、増補として安の死亡後に433ページまで倍近くの厚さで増補された。39歳で死亡したということもこの書を特別なものにしたということもあるのかもしれない。あと20年後の阪神大震災後の半世紀あとでもこの書は残るであろう。PTSDについて日本で改めて皆が考えるきっかけとなった本でもある。
Posted by
「苦しみを癒すことよりも、それを理解することよりも前に、苦しみがそこにある、ということに、われわれは気づかなくてはならない。だが、この問いには声がない。それは発する場をもたない。それは隣人としてその人の傍らに佇んだとき、はじめて感じられるものなのだ。臨床の場とはまさにそのような場...
「苦しみを癒すことよりも、それを理解することよりも前に、苦しみがそこにある、ということに、われわれは気づかなくてはならない。だが、この問いには声がない。それは発する場をもたない。それは隣人としてその人の傍らに佇んだとき、はじめて感じられるものなのだ。臨床の場とはまさにそのような場に他ならない。 そばに佇み、耳を傾ける人がいて、はじめてその問いは語りうるものとして開かれてくる。 これをわたしは「臨床の語り」と呼ぼう。」 常にこの言葉を忘れないようにしたい。 どうしても、あれこれ質問したくなってしまう。 理解することよりも前に、苦しみがそこにあるということに、気づき、そばに佇み、耳を傾ける人がいて、はじめてその問いは語りうるものとして開かれてくる。 耳を傾ける。これが傾聴か。安さん、もうこの時点で言っているのか。すごいなあ。
Posted by
人間って複雑。 阪神大震災も遠い過去になったけど、大きな被害はなくとも、あの当時の大変さは蘇ってくる。躁になったり鬱になったり心は目まぐるしく動くんだな。
Posted by
出版当初から知っていたが、なぜか手に取ることもなく、NHKドラマにも取り上げられたが、なぜか手に取ることもなかった。中井久夫先生が亡くなった。ケアの倫理の関連で川本隆史先生が推薦していた。どのような関連があるかと思い、手に取った。奇しくも読了はあの日の2日前であった。今も28年前...
出版当初から知っていたが、なぜか手に取ることもなく、NHKドラマにも取り上げられたが、なぜか手に取ることもなかった。中井久夫先生が亡くなった。ケアの倫理の関連で川本隆史先生が推薦していた。どのような関連があるかと思い、手に取った。奇しくも読了はあの日の2日前であった。今も28年前のことが昨日のことのように思い出す。あの頃は災害への心のケアなど日本にはなかった。その先鞭をつけた活動で、具体的であり、著者の仕事は、災害精神医学とトラウマ研究の先鞭をつけた。今も決して古びておらず、それぞれの原則が、具体的に誰でもわかるように書かれている。具体的な分だけ、涙なくは読めない部分もある。最後に兄弟の文で終わる。憎いばかりの構成の新増補版であった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2020年冬に、NHK「土曜ドラマ」枠で全4回にわたって放送され、2021年にこのドラマのをベースに映画《劇場版》が公開された『心の傷を癒すということ』の原案となった1冊です。 1996年に「サントリー学芸賞」を受賞した初版、2011年の東日本大震災を踏まえた増補版 さらに、ドラマ化に伴って、出版された「新増補版」です。 トータル約500ページでした。 「心のケア」がこの国で認められたのは、皮肉にも、1995年の阪神淡路大震災がきっかけだったことを再認識しました。 著者の安克昌先生(故人)は、震災当時、自らもそして家族も被災者でありながら、精神科医の立場として、被災者の「心のケア」に奔走します。 そして当時、当時産経新聞の記者であった河井直哉氏の依頼を受け、新聞に連載した記事をまとめたものが、『心の傷を癒すということ』(初版)です。 この初版は、第18回「サントリー学芸賞」を受賞します。 そして、時代を経て、2011年の東日本大震災をきっかけに増補版が出版され、 さらに、2020年のドラマ化をきっかけに新増補版が出版されました。 『心のケア』、改めて難しいテーマだと思いました。 皮肉ですが、1995年はバブル経済が弾けて、今で言う「失われた20年」が始まった時だと思います。 安先生を筆頭に多くの精神科のDr.の奔走、社会構造の変化で、『メンタルヘルス』というコトバも一般的に認識されてきましたが、現実はまだまだ厳しい状況が続いているのが現実だと思います。 確かに、学校でも職場でも「あいつは、精神的にもろい。」などと言われることは当時より少なくなってきたと思いますが、コロナ禍の今、メンタルの問題を抱えている人が増えている現実は否定できません。 改めて、『心のケアとは?』、『メンタルヘルスとは?』と思い直す価値のある1冊だと思います。
Posted by
- 1
- 2