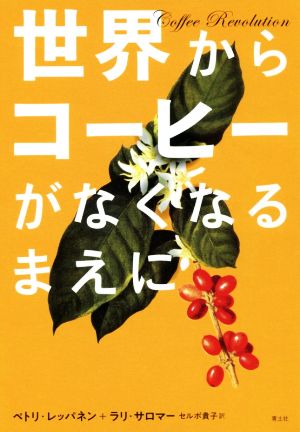世界からコーヒーがなくなるまえに の商品レビュー
フィンランド、ひとり当たりのコーヒー消費量が世界一(10㎏/年) エチオピア カルディというヤギ飼いがヤギが眠らなくなる果実を見つけた。 スペシャリティコーヒー 100点満点で84点以上の品質 買取価格2.9ユーロ/kg、最高級では4ユーロ以上 コーヒー1杯120mlに7...
フィンランド、ひとり当たりのコーヒー消費量が世界一(10㎏/年) エチオピア カルディというヤギ飼いがヤギが眠らなくなる果実を見つけた。 スペシャリティコーヒー 100点満点で84点以上の品質 買取価格2.9ユーロ/kg、最高級では4ユーロ以上 コーヒー1杯120mlに7.5g。133杯/1kg。 カフェで14ユーロ/kgの原価でも 0.1ユーロ/1杯しかしない。 Qグレーター 世界に4000人 ワインのマスターソムリエ資格に近い オーガニックな土壌と十分な水と太陽 手摘みで最適に熟した時に摘む 雑草は手で抜く、除草剤は使わない アラビカ 高地栽培、降水量も必要、年2回開花、クリーンで甘み ロブスタ 病害や害虫に強い、1年中開花、味で劣る。ベトナム産に多い 精製後、粒をそろえる、真空梱包する 焙煎後、2カ月から半年で香りは失われる 粉に挽くと酸化が始まる 生豆は石油の次に取引額の多い原材料 コーヒーで生計を立てている人は世界で1億2500万人
Posted by
フィンランド人のペトリ・レッパネン氏と、ラリ・サロマー氏によるノンフィクション作品。ブラジルのコーヒー農家、ファゼンダ・アンビエンタル・フォルタレザ農場(FAF農場)の取り組みと、コーヒー業界が抱える課題を描いている、ちなみにフィンランドは、世界でも有数のコーヒー消費国らしい。 ...
フィンランド人のペトリ・レッパネン氏と、ラリ・サロマー氏によるノンフィクション作品。ブラジルのコーヒー農家、ファゼンダ・アンビエンタル・フォルタレザ農場(FAF農場)の取り組みと、コーヒー業界が抱える課題を描いている、ちなみにフィンランドは、世界でも有数のコーヒー消費国らしい。 作品の舞台となるFAF農場は、持続可能な生産方法にこだわり、手間をかけて完熟した豆だけを手作業で摘み取っている。ブラジルといえばコーヒーの一大産地だが、意外にもコーヒーマニアの間ではブラジル産=粗悪品、というイメージが強いそうだ。そんな中、FAF農場の取り組みは各国のバイヤーから注目を集めている。 一般的にコーヒー栽培は工業化されていて、行政からは一定期間に一定の収穫量、そして買い取り業者からは価格を事前提示される場合が多いらしい。従って農場側では一定の収量、そして収入を確保するために、農薬や化学肥料を大量に投入し、未熟な豆も機械で一気に収穫してしまう。 また世界的な消費拡大に応えるため、新たに森林を伐採して耕作地を広げることが、自然破壊の原因となっており、途上国の貧しい農民の中には自分が育てている作物が、先進国の嗜好品である事を知らない人もいるそうだ。何気なくコンビニで買うコーヒーが、そんな環境から生まれているなんて、考えた事もなかった。 しかし近年ではただ美味しいだけではなく、栽培方法や農場の労働環境など、全てにおいて高品質を好む消費者も少しずつ増えてきていて、FAF農場で栽培しているような、オーガニックでトレーサビリティのしっかりした生豆が、高値で取り引きされるようになってきている。 コーヒーに限った話ではなく、多くの食糧がこのようなサステナブルな仕組みで流通するのが理想的だ。しかし、日々購入するすべての食品をトレースするのは不可能だし、約80億人まで増えてしまった人口を支えるためには、上記のような食糧生産の工業化は必要悪なのかもしれない。でも、これからは出来る範囲で出来るところから、自分もフェアな商品を選択して行きたいと思う。
Posted by
コーヒービジネスの現状を、ブラジルのコーヒー農家の一つを例に考察している一冊。 適当な品質のコーヒーを安く入手できることは大量愛飲者としては嬉しい反面、農家の状況は悲惨だろうと日々感じていました。 農業、産業、環境の多岐にわたる問題を語っていますが解決は困難であり、一消費者にでき...
コーヒービジネスの現状を、ブラジルのコーヒー農家の一つを例に考察している一冊。 適当な品質のコーヒーを安く入手できることは大量愛飲者としては嬉しい反面、農家の状況は悲惨だろうと日々感じていました。 農業、産業、環境の多岐にわたる問題を語っていますが解決は困難であり、一消費者にできることが気休め程度であることに絶望を感じました。 末永くコーヒーの味と香りと共にありたいものです。
Posted by
1.なんとなくタイトルに惹かれた 2.フィンランド人のペトリとラリが、世界一の生産量を誇るブラジルのコーヒー生産者の元へ取材し、今のコーヒー産業の実態と、これからのコーヒー産業の未来について述べています。今訪れているコーヒーのサードウェーブは、美味しさ以外の質にこだわること、つ...
1.なんとなくタイトルに惹かれた 2.フィンランド人のペトリとラリが、世界一の生産量を誇るブラジルのコーヒー生産者の元へ取材し、今のコーヒー産業の実態と、これからのコーヒー産業の未来について述べています。今訪れているコーヒーのサードウェーブは、美味しさ以外の質にこだわること、つまりは環境への配慮や生産者の価値観に目を向けることです。 量だけ確保すれば良いという時代が終わり、環境への配慮が必須となっています。止まらない環境破壊が自分達の首を絞めていることと向き合い、持続的な栽培と銘打ってこれからのコーヒー産業に必要ならやり方ということを伝えています。 3.このようなオーガニック系の栽培を推奨してる本を読むと、思うことがあります。それは、量のみを確保することで環境破壊の原因を作っていたのは、先進国の人たちにも原因があるのではないかということです。私達が飲食しているものに興味を持ち、調べたり、考えたりすることで、彼らを救えるのでは?と思える瞬間がいくつかあります。 飽食時代だからこそ食のありがたみについて真剣に考えて行かなくてはいけないと思います。
Posted by
唯一の欠点はタイトルがセンスない。洋画に原題とかけ離れた邦題をつけて、インパクトをつけるダサいマーケティングと同じやつ。原題はCofee Maters A revolution is On the way 直訳で十分本書の意図を表現できる。コーヒーがなくなると心配する話ではなく、...
唯一の欠点はタイトルがセンスない。洋画に原題とかけ離れた邦題をつけて、インパクトをつけるダサいマーケティングと同じやつ。原題はCofee Maters A revolution is On the way 直訳で十分本書の意図を表現できる。コーヒーがなくなると心配する話ではなく、コーヒーを題材としてよりより社会、「足るを知る」ことを目指すのが本質である。それを描くのにコーヒーは適材だったということだ。大量消費の嗜好品でありながら、栽培がコーヒーベルトという南国でいわゆる後進国にしゅうちゅうするため、フェアでない取引が横行し、品質は二の次にされてきた。それが最近のフェアトレード、北欧コーヒーブーブなどで是正されつつあるり、社会がよりよくなることの一つのモデルとなれるかもしれない、というお話。今ならSDGsのモデルといってもいい姿が、あるブラジルのオーガニックコーヒー農家の一家の歴史から描かれる。読み物としても、農業本としても、環境本としても楽しめる良書。
Posted by
- 1
- 2