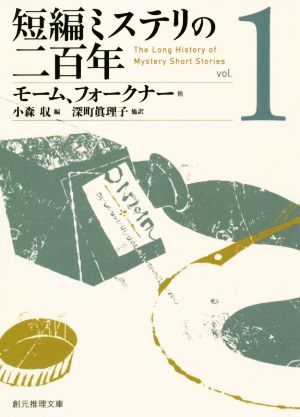短編ミステリの二百年(vol.1) の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
単純に面白くない。文学者のミステリが多い関係か、オチ、解決のない作品で、多少ミステリアスな文章という程度。昔の作品はまた一定の古臭さもありますからね。
Posted by
同じ東京創元社の乱歩編「世界推理短編集」も持っているのだが、積読本に隠れて発見できないのでこちらのシリーズから読み始める。 この巻1には20世紀初頭の作品が収められている。 錚々たる文豪のイメージのある作家の作品もあるが、やはり少々古臭さがあるのは否めない。 この本の中では、...
同じ東京創元社の乱歩編「世界推理短編集」も持っているのだが、積読本に隠れて発見できないのでこちらのシリーズから読み始める。 この巻1には20世紀初頭の作品が収められている。 錚々たる文豪のイメージのある作家の作品もあるが、やはり少々古臭さがあるのは否めない。 この本の中では、ウールリッチの「さらばニューヨーク」が、いかにもウールリッチ(アイリッシュ)らしい「暁の死戦」を思わせるタッチと展開で良かったのと、ラニアンの「ブッチの子守唄」がクライムノベルなのだが、クスリとするユーモアとオチが良くて印象に残った。 巻末に編者の詳細な解説がついており、多くの作品名をあげて丁寧に解説している。ただいかんせん自分が、解説に挙げられている作品の殆どを読んでないので、よく分からなかったのが残念だった。
Posted by
ミステリアンソロジー&たっぷりとした解説のような評論。「ミステリ」といってもかなり広義のミステリという印象です。ぴりっとしたユーモアの効いた作品が多いかな。なるほど、こういうのもミステリと言ってしまっていいのね。 お気に入りはサマセット・モーム「創作衝動」。これってミステリ? と...
ミステリアンソロジー&たっぷりとした解説のような評論。「ミステリ」といってもかなり広義のミステリという印象です。ぴりっとしたユーモアの効いた作品が多いかな。なるほど、こういうのもミステリと言ってしまっていいのね。 お気に入りはサマセット・モーム「創作衝動」。これってミステリ? と思わないでもないのですが。意外なユーモアを感じさせられるラストまでの道筋を「真相」とすれば、これはミステリでしょ。 アンブローズ・ビアス「スウィドラー氏のとんぼ返り」はさくっと短くてユーモラスな一作。デイモン・ラニアン「ブッチの子守歌」もユーモラスで好きだなあ。サキ「セルノグラツの狼」も、まさしくラストの二行でユーモアが効いています。 ウィリアム・フォークナー「エミリーへの薔薇」とジョン・コリア「ナツメグの味」は怪奇アンソロジーに収められていたこともあって再読。なんともいえない雰囲気が好きです。
Posted by
良くも悪くも編者小森氏の評価が前面に出たアンソロジー。 もともとは、東京創元社〈Webミステリーズ!〉で連載された「短編ミステリ読みかえ史」をベースにしているので、収録された各短編にプラスして、かなりのページ数の解説というか、時代を追っての短編ミステリーの発展を論じる評論が付...
良くも悪くも編者小森氏の評価が前面に出たアンソロジー。 もともとは、東京創元社〈Webミステリーズ!〉で連載された「短編ミステリ読みかえ史」をベースにしているので、収録された各短編にプラスして、かなりのページ数の解説というか、時代を追っての短編ミステリーの発展を論じる評論が付されている。 ジャンルとしてのミステリーをどう考えるかは人により様々だろうが、本書では1901年発表の「霧の中」を皮切りに作品が選ばれており、これもミステリーなのだろうかと感じるような広めのセレクトになっている。 本書で初めて知った作家としては、巻頭作『霧の中」のリチャード・ハーディング・デイヴィス、「ブッチの子守歌」のデイモン・ラニアン。 いかにもモームらしい「創作衝動」では、少数の知的読者を対象にする(したがってあまり売れていない )いわゆる純文学系の作家が、思いもしない出来事の勃発によりミステリー作品を書くことになる成り行きが描かれているのだが、両ジャンルの壁が厳然としてあった時代だからこその面白さである。 イーブリン・ウォーの「アザニア島事件」は、かなり早い段階で展開は読めるが、植民地における支配者側の生態や、何もないところに謎を見出すマニアを皮肉に描いていて、楽しく読める。 フォークナーの「エミリーの薔薇」、コリアの「ナツメグの味」は、言わずと知れた名作。読み手に真相を明らかにする手際が見事だ。 題名は知っていたのだが、今回初めて読んだウールリッチの「さらばニューヨーク」。重大な犯罪を犯してしまった夫、その事実を知りながらもあえて何も言わず逃避行を共にする妻。警察に追われているのではないかとビクつきながら逃げる二人に迫る出来事が間然となく描かれ、サスペンス満点である。
Posted by
冒頭を飾る短編「霧の中」の退屈極まる長々しさや、その後に続く作品のいずれ劣らぬ薄味さなどの数々の不満を、一篇の短編が帳消しにしてくれた。 それは、フォークナーの『エミリーへの薔薇』だ。 思いもかけぬフォークナーとの出会い、それも、かの「ヨクナパトーファ・サーガ」中の一篇だ。 力強...
冒頭を飾る短編「霧の中」の退屈極まる長々しさや、その後に続く作品のいずれ劣らぬ薄味さなどの数々の不満を、一篇の短編が帳消しにしてくれた。 それは、フォークナーの『エミリーへの薔薇』だ。 思いもかけぬフォークナーとの出会い、それも、かの「ヨクナパトーファ・サーガ」中の一篇だ。 力強い、硬質な文体で描き出される鉄灰色の髪のエミリーが、孤立無援でなんの権力も持たぬ老女が、町とコミュニティを相手に傲然と対峙し、一歩も引かない、その圧倒的な存在感。 面白い! そうか、これがフォークナーか。 小森収さん、ありがとう。 よくぞ選んでくれました。/ サートリス大佐が町長だった頃は、彼の裁量で町税を免除されていたエミリーにも、時代は移り、納税通知書が送られてくる。一向に納税しようとしないエミリーの家を町の代表団が訪れる。 【彼女がはいってくると、一行はおのずと立ちあがっていた。黒ずくめの服を着た、小柄だが肥った女性で、変色した金の握りのついた黒檀の杖をついている。首からは細い金鎖が一本、ウエストのあたりまでたれ、その先はベルトの下に消えている。体つきは小づくりで、なんとなく寸の詰まった印象。 ー中略ー 彼女は一同におかけなさいとも言わなかった。ただ部屋の戸口を一歩はいったところに立ち止まったきり、一行ちゅうのスポークスマンが口上を述べるのを、黙って聞いているだけだ。 (略) ようやく口をひらいたとき、彼女の声はかさかさして、冷ややかだった。「わたしがジェファースンの町に払わなきゃならない税金なんてありません。(以下略)」】(ウィリアム・フォークナー『エミリーへの薔薇』)/ さらに、併せて収録されている小森氏の評論「短編ミステリの二百年」の序章には、「『犯罪文学傑作選』とウィリアム・フォークナー」という項目があり、そこには冨山房の『フォークナー全集』の第十八巻には、彼の最初の短編探偵小説集である『騎士の陥穽』が、『駒さばき』の題名で収録されているとある。 さっそく図書館で予約したが、これも思わぬ収穫だった。/ 序章で、小森氏が編集方針についてふれている。 【本書は、江戸川乱歩編『世界推理短編傑作集』全五巻を引き継いで、その後の時代をふり返るのが目的です。この序章では、『世界推理短編傑作集』と同時代にあって、影の内角を形成するような一群の作品を読み返してきました。したがって、あの五巻の中に登場した作家は取り上げないという方針でやってきました。】(序章 『世界推理短編傑作集』の影の内閣)/ なるほどここまで厳格な編集方針で編んだのか。 この方針では、選ばれた短編たちにアメトークの「じゃないほう芸人のような匂いが感じられてしまうのもやむを得ないかも知れない。/ だが、この短編集の白眉は、むしろ巻末の小森氏の評論の方なのではないだろうか? その中で、氏はアガサ・クリスティの「夜鶯荘」の素晴らしさに触れた上で、 【クリスティの短編は、その大半が一九二〇年代に、おそくとも一九三〇年代前半までに書かれているようです。クリスティの三十代、デビューから十年というところです。 ー中略ー 『ポワロの事件簿』(略)『パーカー・パインの事件簿』(略)『おしどり探偵』(略)といった名探偵を主人公とした連作短編集は、どれもこの時期に書かれていますが、いずれも拙さが目立ちます。そのことは、比較的評判のよい『ミス・マープルと13の謎』(略)にもあてはまっていて、私には、この短編集が評価されるのが、よく分からない。ミス・マープルの思考法として、くり返し現われるのが、かつて似たような人を知っていたという発想ですが、この方式の推論は、強引にしか思えません。】(同上) と、書いている。/ さらに、コーネル・ウールリッチ(ウィリアム・アイリッシュ)にふれて、 【謎を組み立て、小説として構成し、それを作中人物に魅力的に解明させるという、ミステリの基本的な段取りは、決して上手ではありませんでした。とくに解決の部分は、唐突な自白に頼ったり、警察が解決後に分かったことを説明する形をとったりと、安易なことがしばしばです。】/ ウールリッチについてだけならまだしも、ミステリの女王クリスティにさえ刃を向けるというのは、自らの命を危うくしてまで権力者に対して、信ずるところを述べる(パレーシア)という、フーコーの言うパレーシア・ステース(パレーシアを行う者)の所業ではないか? この短編集、小森氏の評論を読むためだけにでも、読んでみる価値がありそうだ。
Posted by
創元推理文庫には江戸川乱歩編の「世界推理短編傑作集」というものがあるらしいのだけどそれに続くアンソロジーとして編纂されたものらしい。二百年間に出た短編ミステリの名作・傑作を全六巻に集約するという一大プロジェクトということでミステリ好きとしては見逃せない感もあって手にとってみた。一...
創元推理文庫には江戸川乱歩編の「世界推理短編傑作集」というものがあるらしいのだけどそれに続くアンソロジーとして編纂されたものらしい。二百年間に出た短編ミステリの名作・傑作を全六巻に集約するという一大プロジェクトということでミステリ好きとしては見逃せない感もあって手にとってみた。一作目ということで1800年代から1900年代はじめに出た古典が中心。作家としてはビアス、スティーヴンスン、デイヴィス、サキ、モーム、ラードナー、フォークナー、ラニアン、ウォー、ウールリッチ、コリアというところ。初期ということもあってこれがミステリ?というのもあったりするところがおもしろい。アンソロジーということで編者との相性で楽しみが大きく左右されるのだけどとりあえずは意見保留で2巻目を読んでみたいと思う。それにしても解説というか編者のあとがきというか解説が長い。個人的には編者が作品以外のところで自己主張するのはあまり好ましくないと思うので二作目以降も同じことが無いように祈っています。
Posted by
スティーヴンスン, サキ、モームなどの作家も入っている。 全体的に推理小説という感じはあんまりしないからバランス的には良いのかも。
Posted by
編者による全体の3分の一を占める解題が特徴的な短編集。編者の小森収さんは「初日通信」の人。懐かしいな。題名に「200年」とあるのはスコットランドヤードなど首都警察が整備され始めた19世紀前半から数えたもの。やがて警察もの、犯罪ものが流行し、ディケンズやバルザック、チェーホフらの作...
編者による全体の3分の一を占める解題が特徴的な短編集。編者の小森収さんは「初日通信」の人。懐かしいな。題名に「200年」とあるのはスコットランドヤードなど首都警察が整備され始めた19世紀前半から数えたもの。やがて警察もの、犯罪ものが流行し、ディケンズやバルザック、チェーホフらの作品にも警察や密偵が登場する。そして最初のミステリと言われるエドガー・アラン・ポー「盗まれた手紙」(1844年)から、ホームズを持って短編ミステリの型が出来る。 この選集に集められたのはしかし、そうした型からは外れた作品ばかり。編者いわく「世界推理短編傑作集」のシャドウ・キャビネットと読むべき作品群。 「霧の中」リチャード・ハーディング・デーヴィス(1901)。物語中の物語もまぁまぁだが、外枠のオチが最高に好き。だってそのためにこの物語は語られたのだから。 「クリームタルトを持った若者の話」R.L.スティーヴンスン(1878)。ボヘミアの王子と腹心の部下ジェラルディン大佐の自殺クラブという怪しい組織をめぐる冒険譚。 「セルノグラツの狼」サキ(1913)。これも最後の男爵夫妻による新聞の告知が俗ですごく好き。 「四角い卵」サキ(1924)。第1次大戦の銃後の田舎町の儲け話。塹壕の中の狂ったような描写から始まり、小食堂のシュールな話に転換する。編者は「キャッチ22」を引いているが、この短い話にも、戦争のナンセンスな世界が描かれている。サキにこういう話があるのは知らなかった。 「スウィドラー氏のとんぼ返り」アンブローズ・ピアス(1874)。面白い。ヨーロッパにはないアメリカ大陸ならではの話という気がする。 「創作衝動」サマセット・モーム(1926)。一番好きかも。前半のスノッブなサロンと退屈な夫人の話延々と続くが、そこから終盤の夫の駆け落ちそして最後のミステリ作家誕生の場面が鮮やか。 「アザニア事件」イーヴリン・ウォー(1932)。ウォーっぽい。短いながら登場人物がどれも気になる描写で、事件そのものも人間と社会の皮肉を描くためのスパイスとなっている。 「エミリーへの薔薇」ウィリアム・フォークナー(1930)。乾いた南部の空気を感じる作品。同性愛への言及は知らなかった。 「さらばニューヨーク」コーネル・ウールリッチ(1937)。これも意外と好きかな。映画の一場面を観るようで。 「笑顔がいっぱい」リング・ラードナー(1928)。これもアメリカの街角の匂いが漂う。当時のスピード狂のフラッパーと気のいい交通巡査のちょっとしたラブアフェアとあっけない終わりが「New Yorker」っぽいかな? 「ブッチの子守唄」デイモン・ラニアン(1930)。これも好き。コメディ映画みたいでクスクスする場面が盛り沢山。作家は「ガイズアンドドールズ」の人。あぁなるほど。 「ナツメグの味」ジョン・コリア(1941)。これも何度か読んでるけど、訳のニュアンスの違いで、与える空気が違ってくるという編者の解説に感心した。知ってても怖いよね、この話は。 こうして読んでみると、ミステリというより、人間てやつは人生のある一片を切り取って見せる短編の短編らしさがよく出ている話ばかりで、味わい深かった。
Posted by
「世界推理短編傑作集」から漏れている短編を「影の内閣」としてピックアップしていくというコンセプトらしい。確かに江戸川乱歩の選から漏れているような作品を取り上げているとは言えるが、かと言ってどれも傑作と言えるかというと微妙。もちろん、面白いものもいくつかあった。ミステリファンからみ...
「世界推理短編傑作集」から漏れている短編を「影の内閣」としてピックアップしていくというコンセプトらしい。確かに江戸川乱歩の選から漏れているような作品を取り上げているとは言えるが、かと言ってどれも傑作と言えるかというと微妙。もちろん、面白いものもいくつかあった。ミステリファンからみると評価が割れる選なのではないか。 全体の1/3を占める書評も期待していたが、あまりにも細かすぎて、読み物としては面白く感じなかった。世界の短編ミステリを読み尽くしている人には、面白く感じるのかもしれないが、私はまだそこまでの域に達していません、というのが正直なところ。 全6巻とのことなので、次が出たら、収録作を見てから読むかどうかを決めたいところ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【収録作品】「霧の中」 リチャード・ハーディング・デイヴィス 訳/猪俣美江子/「クリームタルトを持った若者の話」 R・L・スティーヴンスン 訳/直良和美/「セルノグラツの狼」 サキ 訳/藤村裕美/「四角い卵」 サキ 訳/藤村裕美/「スウィドラー氏のとんぼ返り」 アンブローズ・ビアス 訳/猪俣美江子/「創作衝動」 サマセット・モーム 訳/白須清美/「アザニア島事件」 イーヴリン・ウォー 訳/門野集/「エミリーへの薔薇」 ウィリアム・フォークナー 訳/深町眞理子/「さらばニューヨーク」 コーネル・ウールリッチ 訳/門野集/「笑顔がいっぱい」 リング・ラードナー 訳/直良和美/「ブッチの子守歌」 デイモン・ラニアン 訳/直良和美/「ナツメグの味」 ジョン・コリア 訳/藤村裕美/「短編ミステリの二百年」 小森収
Posted by
- 1
- 2