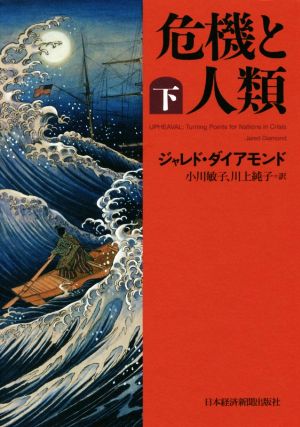危機と人類(下) の商品レビュー
オーストラリアの歴史に触れることができ、興味深かった。 加えて、日本の課題を考えるに際し、著者の前提と私のそれとの違いを認識する。
Posted by
教訓として示されたものはなかったと言うのは言い過ぎかもしれないが、期待していたほどのものはなかったように思う。 しかし、現在の日本における危機への対応についての指摘は、自分の認識とは異なっていて大事な気付きになった。
Posted by
つぎの一〇年において、これらの問題は日本にどのような結果をもたらすだろうか? 現実的にみて、日本が現在直面している問題は、一八五三年の唐突な鎖国政策の廃止や、一九四五年八月の敗戦による打撃に比べれば大したものではない。これらのトラウマから日本がみごとに回復したことを思えば、今日...
つぎの一〇年において、これらの問題は日本にどのような結果をもたらすだろうか? 現実的にみて、日本が現在直面している問題は、一八五三年の唐突な鎖国政策の廃止や、一九四五年八月の敗戦による打撃に比べれば大したものではない。これらのトラウマから日本がみごとに回復したことを思えば、今日、もう一度日本が時代に合わなくなった価値観を捨て、意味のあるものだけを維持し、新しい時代状況に合わせて新しい価値観を取り入れること、つまり基本的価値観を選択的に再評価することは可能だという希望を私は持っている。 ――本書の出版が2019年。さて10年後、本書で取り上げられた、日本、アメリカ、世界の問題はどうなっているのか。答え合わせが楽しみなような、怖いような。
Posted by
上巻に比べると、読み易さは変わらないと言えども、現在進行形という事もあり、非常に呻吟しつつ読んだ感じ。 二度目に取り上げる米、豪州、独逸が俎上に。 自国だけってアメリカへの切り口は鋭く、内容もつぶさ。方策論も多岐にわたる。 豪の現代史、特に英国コンプレックスを切り抜け、日本の侵...
上巻に比べると、読み易さは変わらないと言えども、現在進行形という事もあり、非常に呻吟しつつ読んだ感じ。 二度目に取り上げる米、豪州、独逸が俎上に。 自国だけってアメリカへの切り口は鋭く、内容もつぶさ。方策論も多岐にわたる。 豪の現代史、特に英国コンプレックスを切り抜け、日本の侵略までが知らない事ばかりだった。 第3部の現代の危機は、今さらなる一触即発問題が絡むだけに読みつつ動悸すら覚えた。 日本では今年に入って一段とSDGs問題がマスコミを絡めて姦しくなっているけれど、実際のところお祭り騒ぎというレベルにも思える。我々の大半が生きている間に先進諸国の国民一人当たりの消費率が今より低くなることは確実という刃がどれだけグサッと日本国民・・いやアメリカ国民も含め突き刺せることができるか。
Posted by
やっぱり読ませるな~というのが感想です。これまでの著書にあった人類史というより、近現代の歴史を中心に、個人の危機と国家の危機を比較し、後者については、さらに7つの国の危機対応を対比するという内容。特に、日本と米国には2つの章を割いており、関心の高さが伺えます。 7つの国は、ダイ...
やっぱり読ませるな~というのが感想です。これまでの著書にあった人類史というより、近現代の歴史を中心に、個人の危機と国家の危機を比較し、後者については、さらに7つの国の危機対応を対比するという内容。特に、日本と米国には2つの章を割いており、関心の高さが伺えます。 7つの国は、ダイヤモンド博士が住んだか関係の深い国とのことですが、読んだ中ではドイツの記述が興味深かったです。 日本については、1つの章で明治日本をうまく危機を乗り越えた事例としてあげつつも、もう1章では現代の課題を列挙。人口減少については資源保全の観点から寧ろ喜ばしいこととする一方で、移民の受け入れやドイツとの対比での中国・韓国との関わり方については、日本では議論を呼びそうと個人的には思える内容でした(ただ、「外国人からはこう見えるのか」と、これはこれで参考になりました)。
Posted by
上巻と違い、現代日本をこき下ろしている。 まあ、客観的にはそうみられているのだろうなと言う感じ。 日本は国益にそうか、ということよりも国民感情みたいなところのプライオリティが高い施策が多く、それが客観的には、ちょっと政策がクソだなと思われていると。 まあ、アメリカも大概だが、...
上巻と違い、現代日本をこき下ろしている。 まあ、客観的にはそうみられているのだろうなと言う感じ。 日本は国益にそうか、ということよりも国民感情みたいなところのプライオリティが高い施策が多く、それが客観的には、ちょっと政策がクソだなと思われていると。 まあ、アメリカも大概だが、日本ももっと国益を考えて考える部分が出てきても良いのではと思う。 ただし、結局ロビー活動とか対外的な発信力が異常に弱いため、国益にそう活動をしたとしても、それをアメリカに評価してもらうしかないと言う情けない状態。 国益にそう活動をすると言うことも必要だが、同時に英語での発信力をあげるということも、国益を考えた時に重要なファクターになるんじゃないかと思う。 (日本で声を上げている人も多いが、基本的に日本語で国内に向けてしか発信しておらず、全く世界的なコンセンサスに至らない、という日本語のが障害になっている構造)
Posted by
危機をどうキャッチして伝えるか?戦時や破綻以外に。その視点が足りない気がする。あるべき姿、国や企業をこうしたい、することがワクワクする未来が来る。その想いが無いから危機を感じないのかな、と。日本の記述は示唆に富んでる。
Posted by
何事においても、何かを変化させるときには最低限自分が行動することが必要だと言う事を皆が理解していれば、人のせいばかりにする事も随分少なくなるだろうに。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
各国に起こった危機を分析している本書は、各章それぞれとても面白いだけでなく、12の要因を分析し、他の国と比較することで、よりその国についての理解が深まる。 第8章で現代の日本を分析しているが、人口現象そのものは憂慮するような問題ではないこと、少子高齢化の対応策として移民の受け入れを提案していたのは新鮮だった。 この様にして歴史から危機とその対応策を学び、将来に生かすことで闇雲な対処をしなくていい。歴史を学ぶことは将来の自国の利益につながるのだと思った。 危機を学び、先人の知恵を得ることで、我々の社会をより良いものに変えていく。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
読み終わってから知ったけど、「銃・病原菌・鉄」の著者なんだ!! この本はいくつかの国の危機(日本も開国と敗戦の時で取り上げられている)について、12の視点で分析したもの。 歴史、心理、政治、経済、気候などなどを複合的に学べる一冊。 そして、国や組織、個人が危機に陥った時に頭を落ち着かせて、状況を把握し、危機の原因を分析し、対応法を考えられるようになる助けにもなるかもしれない。 そして、日本への厳しい指摘はできるだけ多くの日本人に読んでほしいし、受け止めなきゃと思う。 因みに、分析軸は下記。 1.危機に陥っていることを認める 2.責任を受け入れる。被害者意識や自己憐憫、他者を責めることを避ける 3.囲いをつくる/選択的変化 4.他国からの支援 5.他国を手本として利用する 6.ナショナル・アイデンティティ 7.公正な自己評価 8.過去の国家的危機の経験 9.国家的失敗に対する忍耐 10.状況に応じた国としての柔軟性 11.国家の基本的価値 12.地政学的制約がないこと
Posted by