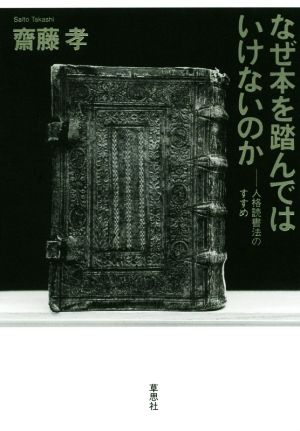なぜ本を踏んではいけないのか の商品レビュー
楽しく読んだ。 読書家の齋藤先生に 本は凄い! 本を読もう! って耳もとで叫ばれ続けているかのよう。 しばらく 健康本や児童書を中心に読書をしてきたけれど、 少しはタフな本にチャレンジしたくなった。 *著者に私淑する *心に賢者の森を持つ
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
表題の意味→ 本には 著者の生命と尊厳が込められており 人格があり 踏んではいけない 本を読むことで著者の人格・精神を継承であり自身をつくる最良の方法である→人格読書法 それを受けて本の歴史から存在意義 本の味わい方 人格読書法得られる境地 読書案内と繋がっていく 本が人格を表すと言うのは別の本でも触れられておりさらに腑に落ちた 本が何故できたか 他の消費財との違いなど気付きが多くあった
Posted by
齋藤先生の別の本を読んで、このタイトルが気になり手に取った。「本はなぜ踏んではいけないのか。本には人格があるからである」という結論が序論ですでになされている。後半まで、結論の裏付けを論じており、最後にとりわけ踏んではいけない本110冊が紹介されている、という構成だ。 私自身は本を...
齋藤先生の別の本を読んで、このタイトルが気になり手に取った。「本はなぜ踏んではいけないのか。本には人格があるからである」という結論が序論ですでになされている。後半まで、結論の裏付けを論じており、最後にとりわけ踏んではいけない本110冊が紹介されている、という構成だ。 私自身は本を踏んではいけないと大人に教わってきた。それは知識を与えてくれる物に対して、最大限に敬意を表することであるということ。齋藤先生の論説とは若干異なるが、本に対しての敬いという気持ちは通じるものがある。 「著者に私淑する」という項がある。これは孟子に由来し直接教えを受けたわけではないが、著作などを通じて傾倒して師と仰ぐことを私淑というそうだ。私の読書はまさにこれで、私淑の繰り返しである。心の師が何人もいる事は他ならぬ幸せだ。また自分の師を探しに読書をするわけだが、引用が一人前にできないとな、と反省するばかりである。
Posted by
読書によって教養を身に着けることの効用は知識を増やすことだけにあるのではなく生きる力を獲得し、困難に直掩したときの 心の支えを得ることにある。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
本だけではなく新聞も踏んではいけないと教えられて育った世代としては納得できる内容だった。 本によって、「教養を身につけ」「人生を学び」「他人の生き方を追体験する」。それゆえに、本には人格があり、踏むことはその人格を傷つけることだ。教えを乞うた本に対して失礼である。
Posted by
その答えは、本というものにはその著者の 人格が込められているから。つまり、その 本を踏むということは、その著者の人格を 否定することになるから、です。 改めて、本というものはどういう存在で あって、我々はそれとどう付き合って、 どう中身を味わうべきなのか。 「本」に対するあら...
その答えは、本というものにはその著者の 人格が込められているから。つまり、その 本を踏むということは、その著者の人格を 否定することになるから、です。 改めて、本というものはどういう存在で あって、我々はそれとどう付き合って、 どう中身を味わうべきなのか。 「本」に対するあらゆる考察と、愛を語り ます。 電子書籍化が進む今だからこそ、読むべき 一冊です。 本には当然「重さ」があります。それは 本という「モノ」としての重さと同時に 書き手の「人格」の重さも感じているので す。 電子データには残念ながらそれがないの です。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
山田詠美しいわく、ろくに本を読まずに小説家になろうとする人たちが多いことを嘆き、せめて世界の名作くらい読んでください、と。 ドストエフスキーやニーチェ、鴎外や漱石、論語や聖書、仏典、資本論やリヴァイアサン、その程度も読まない人が多いのだとしたら悲しいことだ。全て読めとは言わないが、なぜ読まずにいられるのかが私にはわからない。 西洋のシェイクスピアのように、論語の1つや2つ、引用できるくらいではないと教養人とは言えないとおもう。
Posted by
本は、ただ印刷したものではなく、書き手の人格がある。だから踏んではいけないという話。 しかし最近は電子書籍が増えて、データになってしまっていることを憂いている。 確かに昔から本を踏んではいけないということを聞いたが、書き手の人格、踏み絵、焚書坑儒などの例を考えると、本には命がけ...
本は、ただ印刷したものではなく、書き手の人格がある。だから踏んではいけないという話。 しかし最近は電子書籍が増えて、データになってしまっていることを憂いている。 確かに昔から本を踏んではいけないということを聞いたが、書き手の人格、踏み絵、焚書坑儒などの例を考えると、本には命がけの一面があることが分かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
フォローさせていただいている方のレビューを拝見して手に取った本です。 齋藤考さんの著作を通読したのは初めて。 本をうっかり踏むことが多いので、耳の痛い話でした。(床に置くからである 汗) 世界最初の本の原形『ギルガメッシュ叙事詩』から直木賞受賞作、真藤順丈さんの『宝島』までも紹介されています。 ひとが命を削って、生涯を賭けて、思想や出来事を後世に残したいと願う、その思いの結晶が【本】というのがよくわかりました。 それを踏むことなどできない、、、と書かれる齋藤さんの言葉は重い。今まで書かれてきた全ての【本】の作者たちの思いも背負ってるからなのかなと私は思いました。 あと、この本の中に‘三色ボールペンで本に線を引く’‘音読のススメ’‘古典を読むべし’など、著作を読んだことの無い私でも知っている‘齋藤メソッド’が書かれていて何十年も昔からブレてないのだな、と感嘆しました。
Posted by
齋藤さんの本はタイトルがいつも人を引きつける。本についての本もかなり書いていると思うし、ぼくも何冊かは買って読んでいる。この本はやはりそのタイトルに引きつけられた。週刊誌や新聞なら文字があってもまあ踏むことはできる。しかし、本はそうはできない。ぼくもそうである。それは本は人格であ...
齋藤さんの本はタイトルがいつも人を引きつける。本についての本もかなり書いていると思うし、ぼくも何冊かは買って読んでいる。この本はやはりそのタイトルに引きつけられた。週刊誌や新聞なら文字があってもまあ踏むことはできる。しかし、本はそうはできない。ぼくもそうである。それは本は人格であるからだと齋藤さんはいう。本書では齋藤さんが出会った、魂を揺さぶられる本の魅力と本に対面するときの姿勢を存分に紹介している。
Posted by
- 1
- 2