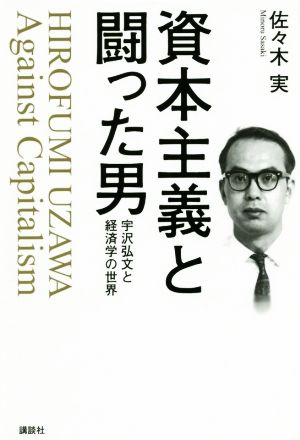資本主義と闘った男 の商品レビュー
社会科学を学ぶ大学生は必ず読んで欲しい一冊。特に経済学部と社会学部、環境やサステナビリティを学ぶの人は必読。 アメリカ経済学全盛期にその最先端を走った日本人。今現在、後にも先にも日本の経済学者として世界と渡り合えたのはこの人だけ。 宇沢弘文さんの教え子のスティグリッツといえば...
社会科学を学ぶ大学生は必ず読んで欲しい一冊。特に経済学部と社会学部、環境やサステナビリティを学ぶの人は必読。 アメリカ経済学全盛期にその最先端を走った日本人。今現在、後にも先にも日本の経済学者として世界と渡り合えたのはこの人だけ。 宇沢弘文さんの教え子のスティグリッツといえば、日本の大学のミクロ、マクロの教科書にも使われているノーベル経済学者。そのスティグリッツや、同じくノーベル経済学者のアマルティア・センが今挑んでいるGDPに代わる幸福度の研究テーマ。 その先行研究ともいえる環境や社会の価値を経済学で扱えるようにする社会的共通資本を打ち出した人。机上の論理でなく、現実に経済学を適応させようとして、まさに資本主義と戦い続けた人。 1970年以降の新自由主義によって、人は物質的に裕福になったが、それでも幸せになれない人がたくさんいる。貧富の差は開いている。 気候変動、リーマンショック、東日本大震災、コロナショックなど、20世紀のしわ寄せが表面化する中、よーやく経済学も宇沢弘文さんの見ていた世界に足を踏み出しつつあるか? まさに、近代日本史の教科書にして欲しいくらいな中身。 経済学の教科書、研究論文の全体から腑に落ちず、博士課程の学生を見て、企業にて続きをやろうと思った自分。後悔はないが、もっとこの方の著作には触れておきたかった。 恥ずかしながら、未来世代というステークホルダーを明確に出してきたのも宇沢さんというのを知らなかった。 後を継ぐものが出なかったことが宇沢弘文さんの凄さと悲しさを表しているように思う。 天才とは、生きているうちに世間に凄さがわからない人と私は思っている。そういう意味でこの人は本当に天才であり、努力家であり、誠実な方だったんだと思った。 今からでもこの方の著作をもっと読みたいと思う。そして、こういう本を書いてくれる、出版してくれることが、ジャーナリズムだと思う。素晴らしい一冊。 でも、大きな意味で言うとスティグリッツさんが、宇沢弘文さんの遺志を継いでいるのかもしれない。21世期に経済学が無用のものとなるか、SDGsを果たす有効な学問となるか。 子孫に幅広い選択肢と豊かな地球を残せるかは私たちにかかってる。 日本人が誇るべき人、宇沢弘文。ノーベル経済学賞に最も近かった日本人、宇沢弘文。
Posted by
なにかいいことを言っている髭のおじさんとしか知らなかった人が、こんなにすごい学者しかも勇気ある行動的な学者だったとは!えらく厚いし経済の難しい話になったら挫折するかもと思って読み始めたら、期待の3倍くらいおもしろかった。著者がどれだけ取材してどれだけ文献にあたって、どれだけ構成や...
なにかいいことを言っている髭のおじさんとしか知らなかった人が、こんなにすごい学者しかも勇気ある行動的な学者だったとは!えらく厚いし経済の難しい話になったら挫折するかもと思って読み始めたら、期待の3倍くらいおもしろかった。著者がどれだけ取材してどれだけ文献にあたって、どれだけ構成や流れを考えて書いたかなぁと思うほど、とても読みやすくまとまっていて、人物像がよくわかる。天才的に頭がよくて、だれもが「ノーベル賞を取るべきだった」というほどの優れた経済学者でありながら、情熱的で常に弱い立場の者に寄り添う宇沢さん。私がこれまで少しでも関心を持ったベトナム戦争、水俣、三里塚、沖縄、地球温暖化、TPPの問題など、全部宇沢さんが深く関心を寄せて自ら関わったりもしたことだったんだ。一度直に話を聞きたかった。
Posted by
岩井克人氏「欲望の貨幣論を語る」と読み合わせると理解が深まる リーマンから12年、ひたすら金融緩和による景気の拡大を続けてきた世界経済はコロナショックを乗り越えられるかという課題に直面している 根本的には「資本主義経済体制」と「有限の地球」が共存できるのか?というレベルの段階に来...
岩井克人氏「欲望の貨幣論を語る」と読み合わせると理解が深まる リーマンから12年、ひたすら金融緩和による景気の拡大を続けてきた世界経済はコロナショックを乗り越えられるかという課題に直面している 根本的には「資本主義経済体制」と「有限の地球」が共存できるのか?というレベルの段階に来ている 経済体制の選択=経済理論の選択である 経済学は科学なのか、政治経済学なのか 現代の経済学を二分して解説 画期的であり判りやすい 革命的過激さ ①不均衡経済動学・・・資本主義経済の本質 ケインズ・宇沢弘文など ②均衡経済学 ・・・主流派経済学シカゴ学派など 資本主義経済の本質は不均衡動学だが、周期的に経済危機を起こし、財政・金融の支援を必要とするので、そのままでは受け入れにくい 体制の経済学としては「平時の均衡」を前面に出して理論体系を組むのが方便だが、これは反正義の在り方。本家の米国以外では衰退しつつある。 宇沢弘文氏、岩井克人氏とも「正当経済学の不正義」に耐えられず趣旨替えを表明し、経済学会を追われてしまった。「破門」である。
Posted by
アダム・スミスの「国富論」に始まる経済学の大きな歴史の中で、資本主義市場経済が、自由主義、ケインズ主義、新自由主義の経済学と変遷し、それにのっとった経済政策が取られてきた歴史を俯瞰する。社会的共通資本をあらためて勉強したい。
Posted by
経済学には詳しくないので、分からないところが多かったが、宇沢弘文という人物や宇沢弘文を通した経済学の流れが丁寧に書かれた大作でした。 分厚い本なので躊躇しましたが、興味深いエピソードも多く、波乱万丈の生涯ということもあり、興味深く読めました。 経済学といっても、どの時間軸で見るか...
経済学には詳しくないので、分からないところが多かったが、宇沢弘文という人物や宇沢弘文を通した経済学の流れが丁寧に書かれた大作でした。 分厚い本なので躊躇しましたが、興味深いエピソードも多く、波乱万丈の生涯ということもあり、興味深く読めました。 経済学といっても、どの時間軸で見るか?どの立場で見るか?どんな目的で使うか?などでかなり変わってくると感じました。 宇沢弘文氏は、長期的な視点で、俯瞰した位置から、平等や正義、弱者のために使おうとしていた。 しかし、世界は、時代は、そうではなかった。
Posted by
数理経済学という学問分野において、間違いなく日本を代表する存在として、多数の論文により学問の進展に多大なる影響を与えつつ、突然の沈黙により学会から距離を置き、半ば”仙人”のような風貌で晩年を送った経済学者、宇沢弘文。本書は彼の半生と数理経済学という学問の発展とその限界を炙り出す超...
数理経済学という学問分野において、間違いなく日本を代表する存在として、多数の論文により学問の進展に多大なる影響を与えつつ、突然の沈黙により学会から距離を置き、半ば”仙人”のような風貌で晩年を送った経済学者、宇沢弘文。本書は彼の半生と数理経済学という学問の発展とその限界を炙り出す超一級の評伝である。 経済的合理性に基づいて一切の行動を取るという仮定の存在たるホモ・エコノミクスの存在を前提とし、近代の経済学では人間行動を数学を用いたモデルにより表現することで学問としての精緻さを明晰にすることに成功した。一方、そうしたホモ・エコノミクスという存在の仮想性に目を付け、新たな理論を立ち上げたのが20世紀後半から21世紀に勢力を伸ばす行動経済学の学派である。非合理とわかっていながらも、錯覚や一時の快楽に身を任せて行動を取る人間の実質的な愚かしさを、行動経済学では心理実験等のアプローチに基づき理論化しようとしている。 そうした学問の流れにおいて、宇沢弘文が生涯の後半で成し遂げようとしたのは、資本主義という思想の中で零れ落ちてしまう人間存在を、いかに経済学という理論の中に位置づけるかという苦闘であったと言える。 理論と実践という旧来からの二項対立において、21世紀は理論の持つ力が徐々に喪失されつつあるという印象を持つのは私だけだろうか。本書は、その生涯において理論の持つ力を信じた一人の人間の思想が痛いくらいに伝わってくる。それは経済学という理論に興味があるかどうかは別として、我々がどう考え、どう生きるべきかという根源的な問いを突き詰めるきっかけを与えてくれるものである。
Posted by
ぼくは宇沢弘文という経済学者のことは、名前しかしらなかったが、少し気になる存在だった。本書はその宇沢さんの評伝だが、この筆者の佐々木さんという人がただものではない。宇沢さんの英語、日本語論文を読みこなすだけでなく、世界の経済学者の論文を読み、その特徴、経済学会での位置を丁寧に解説...
ぼくは宇沢弘文という経済学者のことは、名前しかしらなかったが、少し気になる存在だった。本書はその宇沢さんの評伝だが、この筆者の佐々木さんという人がただものではない。宇沢さんの英語、日本語論文を読みこなすだけでなく、世界の経済学者の論文を読み、その特徴、経済学会での位置を丁寧に解説しているのである。もっとも、本書の経済学に関する部分は決して読みやすくはないが、全体は宇沢さんとそのまわりの人たちの物語、エピソードであるから、面白いことは面白い。宇沢さんは若くしてアメリカの経済学界の中に身を投入し、そこでかれ自身の理論をみがいていった。それは世界の経済が高度成長する時代であった。さらにかれはイギリス経済学との橋渡しもする。しかし、やがてかれはそこに見切りをつけ、日本へもどってくるのである。そのかれが日本で出会ったのは、経済の発展の中で生まれていた公害や南北間の格差であった。もともとかれは開発経済にも関心があったから、かれの関心はそうした貧困国や環境を含む環境経済学へと向かっていった。その契機になったのが、自動車の社会費用という問題だった。それにしても、かれと理論を切磋琢磨した経済学者たちの多くがノーベル賞をもらっているのに、どうしてかれはもらえなかったのだろう。そこには、黄色人種に対する偏見のようなものを感じるのだが。
Posted by
2019年6月2日図書館から借り出し。 600頁を超える大著であるが二日間で読み終えた。心地よい疲労感と、良書を読み終えた満足感がまだ残っている。 単なる宇沢弘文の伝記ではない。経済学説史を解説しながら、その中での宇沢の位置づけをわかりやすく説明するという困難な仕事を、たった...
2019年6月2日図書館から借り出し。 600頁を超える大著であるが二日間で読み終えた。心地よい疲労感と、良書を読み終えた満足感がまだ残っている。 単なる宇沢弘文の伝記ではない。経済学説史を解説しながら、その中での宇沢の位置づけをわかりやすく説明するという困難な仕事を、たった一人のフリーのジャーナリストが仕上げたことに驚嘆してしまう。しかも明晰な日本語が読みやすい。学部レベルなら学説史副読本にも使えるかもしれない。 加えて、経済学者として、また一人の人間として真摯に世の中に向き合った姿を、時ととしては書き手が「精神的に依存してしまって」(あとがき)いるところも感じなくはないが、見事に描き切っているように思える。不器用なまでに真面目な人だったのだろう。 それでも、晩年、老いのためか感情をコントロールできなくなっているところまで書かれている。 最後のところで、宇沢夫人に「帰国してから宇沢先生は変わりましたか」という筆者の問いに「独りぼっちでした」という簡潔な答えが返っていたというところでは、なんとも言えない気持ちになった。 文系では経済学部の人気が高まっているとか。若き経済学徒には是非とも読んでいただきたい本。
Posted by
- 1
- 2