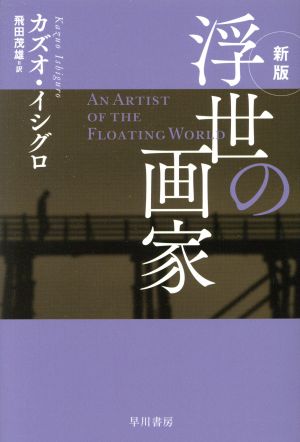浮世の画家 新版 の商品レビュー
カズオ・イシグロの第二作。戦後日本を舞台としていること、一人称の回想の語りによる作品であることは前作『遠い山なみの光』と同様。登場人物同士の視点や価値観のズレが読者に異和を感じさせながら展開していくことも共通しているが、大きく異なるのは『遠い山なみの光』におけるズレは未来に対する...
カズオ・イシグロの第二作。戦後日本を舞台としていること、一人称の回想の語りによる作品であることは前作『遠い山なみの光』と同様。登場人物同士の視点や価値観のズレが読者に異和を感じさせながら展開していくことも共通しているが、大きく異なるのは『遠い山なみの光』におけるズレは未来に対する視点の違いにあったのに対して本作におけるズレは過去に対する認識のズレが描かれているところ。一人称の語りという構成上、語り手である小野の認識上の問題と事実との差分をどう捉えるか、そして語られることの背景で語られないことをどう推測するか、聞き手であり読み手である私たちの解釈の余地が素晴らしく表現された作品だなと感じる。
Posted by
時代の流れの中で、持て囃されたり、批判されたりするものは一変する。戦前戦後は特に激変する中、迎合したり、反省して死すら選ぶ人も描かれている中、自分の信念を貫いたと信じ切ることの悲哀が、回りくどい会話や微妙な人との邂逅によってぼんやりと浮かび上がってくる。変化し続けることが重要、と...
時代の流れの中で、持て囃されたり、批判されたりするものは一変する。戦前戦後は特に激変する中、迎合したり、反省して死すら選ぶ人も描かれている中、自分の信念を貫いたと信じ切ることの悲哀が、回りくどい会話や微妙な人との邂逅によってぼんやりと浮かび上がってくる。変化し続けることが重要、という無意識に根ざされた価値観を揺さぶられる体験となった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ページが進むにつれ、小野に対して、「お前…」と思いながら読んでしまった。もちろん日常で人にお前なんて言うことはないのだけれど。 戦時中に体制翼賛の戦争画を描いて評価されていた画家の晩年。 自分のしたことを後悔はしていないが、世間の目のせいで忸怩たる思いを抱えて、無自覚ではあるかもしれないが気持ちも少し揺らいでいるといった感じ。 弟子にしたことを後悔してなさそうなあたりは恐ろしい。
Posted by
以前からちょっと気になる作家だった。ちょうど図書館前の「自由にお持ち帰りください」コーナーで見つけ、手に取った1冊。長崎県出身、イギリスの作家で、2017年にはノーベル文学賞を受賞した。 この作品は、老画家の回顧録のようなもの。戦時中に、戦意高揚のため、日本精神を鼓舞し名をな...
以前からちょっと気になる作家だった。ちょうど図書館前の「自由にお持ち帰りください」コーナーで見つけ、手に取った1冊。長崎県出身、イギリスの作家で、2017年にはノーベル文学賞を受賞した。 この作品は、老画家の回顧録のようなもの。戦時中に、戦意高揚のため、日本精神を鼓舞し名をなした主人公小野は、終戦を迎えた途端、周囲から冷たい目を向けられるようになる。戦中戦後と価値観が180度変わる大きな混乱期を人々は生きぬいてきた。「自殺」した仲間もいる。父親としての責任から、二女の結婚を何とか成就することをきっかけに、貫いてきた自らの信念と新しい価値観の間で葛藤する。舞台が、戦後間もない時代であるが、孫「一郎」に対する接し方などにも、海外ならではの個人主義的な価値観を感じる。大きなお屋敷の中で、ロッキングチェアに揺られながら昔語りを聞くような、静かな作品である。
Posted by
戦後を舞台に、戦前、戦中に画家として活躍した小野が自身の過去を語る回顧録形式の小説。 日本を破滅へと導いた軍国主義を是とし、その信念をもって数々の絵画を発表。 当時大いに受け入れられ賞賛された価値観は、敗戦後には唾棄すべきものとして扱われる。 新しい価値観を理解し、それを認め、...
戦後を舞台に、戦前、戦中に画家として活躍した小野が自身の過去を語る回顧録形式の小説。 日本を破滅へと導いた軍国主義を是とし、その信念をもって数々の絵画を発表。 当時大いに受け入れられ賞賛された価値観は、敗戦後には唾棄すべきものとして扱われる。 新しい価値観を理解し、それを認め、受容すること。 それが戦後で生きていくためには必要なのだが、価値観を変容し、新たなアイデンティティを形成するのは並大抵のことではない。 軍国主義を積極的に支持していたことに対する罪悪感、後ろめたさを拭い去ろうとする心の葛藤。 小野自身とて、もともと軍国主義など信奉していなかったのだというエクスキューズや、今や自身と袂を分かった弟子たちもかつては自分の考えを大いに支持し礼賛していたということを思い出す。 一方で、自身のかつての言動のせいで、自分の娘の結婚などに悪影響が出てしまっていることを危惧し、当時の関係者に当時のことはあたかも「なかったこと」にしてくれるよう求めたことを思い出す。 新しい価値観は認める。しかしそれを認めるとなると、古い価値観をもっていた時代に行ったこと、それに費やした時間はすべて無駄であったということになってしまう。 過去をすべて否定するのか、否定せずに受け入れることができるのか。 この小説はその壮絶な葛藤を、カズオ・イシグロの長編2作目にしてはやお家芸となる「曖昧な記憶」をもって見事に描いている。 舞台設定と表現方法は前作『遠い山なみの光』にとても近い。 戦後十数年で長崎に生まれ、その後すぐに海外に移住したというやや特殊な環境も影響しているのか、戦後という時代に特別な思い入れがあるのだろう。 また、彼が興味の対象としている、「変化する価値観の受容」あるいは「アイデンティティの崩壊と再生」みたいなテーマにとって、敗戦国の戦前、戦後というのはおあつらえ向きということもあるのだろう。 前作では女性の戦後価値観変化の受容、そして今作では男性の戦後価値観変化の受容を扱っている。 変化を受容するというのは、人格的な危機である。 事象AとBがあり、今まではAが正解でBが不正解だったものを、これからはBが正解でAが不正解となる生活を強いられる。 正解の人生を歩んできたと思っていたのが、突然、自分の人生は不正解だと言われる。これは危機である。 そこで、今までの人生を否定せず、新しい価値観を受容する必要があるのだが、そんな緊急事態に際して心が行うのは、記憶の再整理である。 矛盾する価値観に対して、それが矛盾でなくなるように、うまい具合に記憶を再整理し、整合的な記憶として、新たな価値観を自然に受け入れていく作用機序が人間の心にはある。 本作では、前作以上にその心の作用機序をうまく物語に取り込んでいるように見える。 すごい作品だと思う。 すごい作品だと思うんだけどね、私、カズオ・イシグロが描く子供が生意気すぎて受け入れられないんですよね・・・ 物語上で必要な役割だっていうのもわかってるんだけどね。読んでるとビンタしたくなってくる。 たまにビンタ超えて竜巻旋風脚たたきこみたくなる。 私には受容する装置がないらしい。 それでも、素晴らしい作品なのは間違いない。
Posted by
あなたのやったことは間違いだ、と言われるのは腹が立ちます。間違いか間違いではないかの前に、自分以外の誰かに言われることに、まず腹が立つだろうと思います。なぜなら、間違いかどうかを決めるには「これが正解」という基準が必要ですが、その正解はどこから来るのかが人によって違うはずだからで...
あなたのやったことは間違いだ、と言われるのは腹が立ちます。間違いか間違いではないかの前に、自分以外の誰かに言われることに、まず腹が立つだろうと思います。なぜなら、間違いかどうかを決めるには「これが正解」という基準が必要ですが、その正解はどこから来るのかが人によって違うはずだからです。私が行った「何か」は、私の基準によれば正解だったのです。なのに、「あなたは間違いだ」と言われる「正解」はどこから? この本の「小野」が、娘2人から、義理の息子から、弟子から、次女の婚約相手から「間違いを犯した」と判断されたのは、小野が活躍したのが戦争中で、その後「戦後」ではなく「敗戦後」になり、「正解」が正反対になったのが原因でしょう。小野は自分の「間違い」を認めますが、でもあの時はこういう幸福感があった、またある時はこういう信念があった、と繰り返し確認しているのは、「だから自分の人生としてはこれが『正解』だ」、と思うからだと思います。ですがこのように小野が、自分はあの時「間違った」のではなくこう考えたからああいう行動をしたのだ、と振り返れるのは、その行動を取ることについて「考えた」結果だったからだろうと思われます。つまり、この本を読んで「考えた」ことは、「間違ってはいけない」のではなく、「考えずにやってはいけない」のだろうということです。そうしないと、過去の過ちを振り返ろうにも覚えていないという事態になりかねません。そして、「間違いだった」と認めた後はどうすればいいか? また「考える」ことが必要なんだと思います。
Posted by
終戦前後が語られている。ゆっくりと時間が流れる。このドラマに大きな起伏はない。主人公の画家は妻と息子を戦災で亡くしている。娘二人がいる。長女には子どもがいる。画家からすると孫にあたるその子との男同士の会話がユニークである。娘と父親の会話などにも心がひかれる。父親の気持ちを娘はまっ...
終戦前後が語られている。ゆっくりと時間が流れる。このドラマに大きな起伏はない。主人公の画家は妻と息子を戦災で亡くしている。娘二人がいる。長女には子どもがいる。画家からすると孫にあたるその子との男同士の会話がユニークである。娘と父親の会話などにも心がひかれる。父親の気持ちを娘はまったくわかっていない。娘の気持ちを父親はわかろうとしない。次女の1つめの結婚話は破談になっている。その理由が何か分からない。僕は、この小説の舞台が長崎であると思い込んでいた。結局最後までどことは明かされていない。しかし、その思い込みのため、被ばくが原因ではないかと考えていた。「黒い雨」と同じように。でも、全くそういうことではなかった。どうやら父親である画家の戦前・戦中の思想に問題があったらしい。娘の次の縁談に当たって、画家は古い友人・知人をたずね、何らかの聞き込みがあったとしても昔の自分の思想についてあまり話してほしくないということを、それぞれに頼みに行く。弟子には会いに来てほしくないとまで言われている。画家たちにも師弟関係があって一緒に生活をしたりもしていたのか。駆け出しの画家には大した稼ぎもないし、すでに大家となった師匠に面倒を見てもらっていたということか。そして、その師匠の画風から逸脱すると、そこから出て行かなければならない。場合によっては、画家の世界で生きていくことができなくなってしまう。そんなことが、どこの世界でもあるのだなあ。カズオ・イシグロの世界は好きだなあ。 (新版でないのを読んだのだが、何か内容に違いはあったのだろうか。)
Posted by
戦争前後の人間関係を回想を交えて語る一人称小説です。これまで築き上げた自分と時代や価値観の変化にどう折り合いをつけていくか苦悩する様子が本人目線で綴られています。 主人公の記憶や印象に基づいた真実が事実であるとは限らない曖昧さに翻弄されました。過去の出来事が徐々に明らかになるに...
戦争前後の人間関係を回想を交えて語る一人称小説です。これまで築き上げた自分と時代や価値観の変化にどう折り合いをつけていくか苦悩する様子が本人目線で綴られています。 主人公の記憶や印象に基づいた真実が事実であるとは限らない曖昧さに翻弄されました。過去の出来事が徐々に明らかになるにつれて、「自分が捉える自分」と「他人から見た自分」の乖離も露わになり、痛みを感じました。
Posted by
以前「記憶というものは思い出すたびに書き換えられている」と読んだ。終戦により今まで是とされてきたことが悉く覆される中、様々な記憶があやふやになり、自分のアイデンティティもあやふやになりかける主人公。 戦時中にいわゆる大人であった人は自分自身の崩壊とその再構築に苦労しただろうと想像...
以前「記憶というものは思い出すたびに書き換えられている」と読んだ。終戦により今まで是とされてきたことが悉く覆される中、様々な記憶があやふやになり、自分のアイデンティティもあやふやになりかける主人公。 戦時中にいわゆる大人であった人は自分自身の崩壊とその再構築に苦労しただろうと想像した。
Posted by
第二次大戦前から画家として活躍してきた小野が、うまくいかない娘の縁談や周囲の態度から過去を回想していく。師匠の耽美主義を離れて精神主義に傾き、戦時のプロパガンダに加担し評価され、自信を深めるが、価値観が一変した戦後の日本社会で、そのアイデンティティをどう扱ったらいいか迷い悩む。 ...
第二次大戦前から画家として活躍してきた小野が、うまくいかない娘の縁談や周囲の態度から過去を回想していく。師匠の耽美主義を離れて精神主義に傾き、戦時のプロパガンダに加担し評価され、自信を深めるが、価値観が一変した戦後の日本社会で、そのアイデンティティをどう扱ったらいいか迷い悩む。 語りの中で、小野が自分の記憶の曖昧さを何度も確かめるように表現している。話の筋そのものにはあまり関係しないが、読み手としてなぜかそこにひっかかりを感じてひきこまれる。 人が過去を振り返るときの記憶の曖昧さこそが、人間らしさであり、だからこそ生きていけるのかもと思わせる。ここに焦点を当てる語りが、著者の技の一つかもしれない。
Posted by