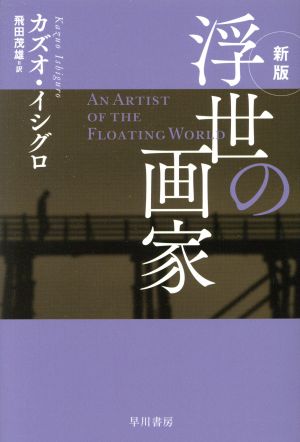浮世の画家 新版 の商品レビュー
数冊読んだイシグロ作品の中で一番好きだなあ。小津安二郎の世界に、ほんのちょっと社会派的要素を垂らしたような感じが良かった。ためらい橋とか、名前もなんかすてきだった。訳が良かったのもあるのかな。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
名作「日の名残り」と同じように、自分なりのポリシーを持って難しい時代を生きた老人の回想という形をとっている。 老人は戦時中に、愛国心を支えるような活動をしてきた画家。一時期は高い地位を得ていた(それも本人の記憶の中だけで、実際はどうだったのか、最後の方には現実と記憶の乖離も考えられるようになっているのが面白い)。 戦後、新しい価値観が広がる世の中で、自分のしてきたことに対する誇りや反省、保身、様々な感情が入り乱れる。娘や義理の息子たちにどう思われているかも気になるし、威厳は保ちたいし…。 「時代の変化」の中で、小さな一個人が翻弄される…というほど大げさな設定でもない(戦場に行くわけでもなく、戦犯に問われるわけでもない、娘の縁談の心配をするくらい)、にも関わらず、国家に翻弄された多くの人々の姿を、鮮やかに切り取っているような印象がある。
Posted by
これを30歳そこそこで書いたのか!とまずそこに驚く。たしかに日本人ぽくない言い回しや思考回路、やりとりはあちこちに見られる。特に、一郎。理路整然と喋りすぎ。けれど、主人公である小野は明治生まれの鼻もちならないじいさん。そんな作者自身からかけ離れた人間の自分語りを、その年齢でこのレ...
これを30歳そこそこで書いたのか!とまずそこに驚く。たしかに日本人ぽくない言い回しや思考回路、やりとりはあちこちに見られる。特に、一郎。理路整然と喋りすぎ。けれど、主人公である小野は明治生まれの鼻もちならないじいさん。そんな作者自身からかけ離れた人間の自分語りを、その年齢でこのレベルの作品に仕上げるのがすごいと思う。いかに彼に祖父母の記憶があるとはいえ、カケラのようなものに過ぎないはず。そこからこのサイズの図を描きおこす筆力を、若くしてすでにもってたんだなぁ。 功罪という言葉があるけれど、功績の大きさを認めると罪の大きさも同時に認めざるを得なくて、そうすれば必然的に罰を受けていない今の自分を否定しなければならなくなる。それができない人間の弱さ、が描かれていると感じた。 戦時の芸術家は難しい立場に立たされる。世の趨勢を読むか読まないか、その読みが正しいのか。小野の挫折を私たちは歴史の必然として知ってはいるけれど、それは後世の人間だから「必然」と断定できるもの。その歴史の途上に点として配置された人間が「見えた!」と思って描いた世界が、ピンホールから覗いた世界に過ぎないことを知っているのも、後世の人間だから。出来事が歴史の1ページにピン留めされた後なら、いくらでも非難できる。 ピン留めされる前の「浮」いて動く「世」界を「画家」として切り取るには、覚悟がいる。画家だけではなく、小説家や詩人達もそうだろう。ノーベル賞をもらった小説家が、後になって非難を浴びた例もある。その中で、功と罪を一身に引き受けて物を言う覚悟はあるか? それを作者は自らに問うているのかもしれないと思った。
Posted by
重たかったし、普段読む感じではなかったけれど、面白かった。画家なのがよかった。 前書きの最後の方の文章が、すごく同意した。
Posted by
過去の過ちを認めたことと、マダム川上のバーがオフィスへと変わったときのタイミングが重なるのは、本作を象徴的に表している。現実と対峙するには、浮世(マダム川上のバー)から離れなくてはならない。
Posted by
「少なくともその時は、信念に基づいて行動していた」 主人公の自尊心が強すぎる。こんな父親だったら面倒だと思ったけれど、昔の父親はこのような人が多かったのかな? 以前、NHKでドラマをやっていた。主人公は渡辺謙、上の娘が広末涼子。少ししか見ていないけれど。
Posted by
過去に誇りを持っているのか、後ろめたいのか、この相反する二つの感情の同居が、主人公の語り口調と共に過去と現在を織り交ぜつつ描かれている
Posted by
画家の人生を通して、戦前から戦後の日本における価値観の変化を描いた作品。 戦中から戦後の世情の空気の移ろいを察知した画家の、過去の自分の作品が世間に与えた影響と責任を認めつつも、時代を生きたという誇りは忘れない強さを感じる。 同じような境遇で責任を感じて自ら命を絶った作曲家との対...
画家の人生を通して、戦前から戦後の日本における価値観の変化を描いた作品。 戦中から戦後の世情の空気の移ろいを察知した画家の、過去の自分の作品が世間に与えた影響と責任を認めつつも、時代を生きたという誇りは忘れない強さを感じる。 同じような境遇で責任を感じて自ら命を絶った作曲家との対比なども印象的ではあるが、この話から思い出されるのは藤田嗣治。 彼が戦後、この作家と同じような境遇に陥り、世間から大きなバッシングを浴び逃げるようにパリに移住したことは、時代と世論の変化の残酷さをつくづく感じさせる。 そして最近のSNSを通しての、諸々の炎上騒動についても同様に考えさせる。
Posted by
時代の変化に取り残された一人の老人。それでも威厳を保とうとするが、その切ないこと。その哀愁は、我が身にも無関係ではいられない切実さもある。 『日の名残り』では大英帝国没落後も英国紳士を貫こうとする執事でそれを描き、この『浮世の画家』では敗戦後も家父長的父親を演じようとする画家で...
時代の変化に取り残された一人の老人。それでも威厳を保とうとするが、その切ないこと。その哀愁は、我が身にも無関係ではいられない切実さもある。 『日の名残り』では大英帝国没落後も英国紳士を貫こうとする執事でそれを描き、この『浮世の画家』では敗戦後も家父長的父親を演じようとする画家で描く。 ただ、『日の名残り』の方がより必死さと切なさが描出できている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
こういう感想文を投稿するのは初めてなのでご容赦ください。以下の感想は読み終わったばかりの勢いで書いています。 最初から最後まで、画家・小野の視点で描かれている。『価値観の変動』と『生き方』に焦点を当てた作品だと感じた。私がこの本から受け取ったメッセージを以下に示す。 《価値観は時代とともに移ろい行くものだから、誰しも後になって自らの過ちに気がつくかもしれない。しかし、『自分の信念に従って、全力で生きた』ならば、それの信念が間違いであったとしても後悔はしないであろう。》 また、この作品では、とかく何かを明言するのを避ける傾向にある。しかし、多数の場面を組み合わせて、人の心の動きを鮮やかに描いていた。 以下に大まかな作品の流れを示す(完全なるネタバレです)。 戦時中、小野は〈地平ヲ望メ〉という版画作品で広く影響を及ぼした。この作品に描かれた精神は「お国の為に戦う」(だと考える)。作品は、当時の小野の信念に基づき描かれ、地域で大いに賞賛されたらしい。 しかし、終戦後にこの絵のテーマとなった精神は批判される。さらに、若者も当時の『権力者』への憎しみを曝け出す。それは、若者が『権力者』に、仲間の命を奪われたと考えるからである。 小野は、回想中に自らの過ちと、人々に与えた損害に正面から向き合い認める。価値観は移ろいゆくものであるからである。当時は良しとされていたものが、現代では悪になってしまうのである。 しかし、当時の小野が『自らの信念に従って、全力で行動した』という事実は変わらない。そして、彼は自らの過ちは認めても、当時の『生き方』には業績以上の満足感を得ていたのである。 一方、若者の言う『権力者』とは、将校・政治家・実業家達であったと判明する。そこで小野は自らが感じた責任の大きさは、自分の職業に見合っていなかったと悟る。けれども、確実に社会に影響を及ぼした者としての責任を感じ、また、自らの信念を貫いた事に誇りを持ちながら生きるのである。
Posted by