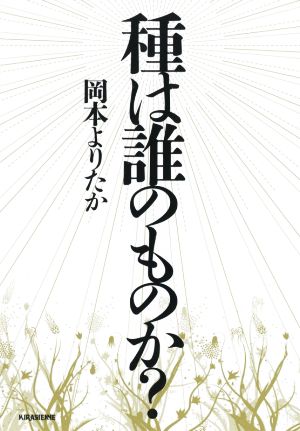種は誰のものか? の商品レビュー
『タネが危ない』は「F1」に、この本は「自家採種」に焦点を絞っていて、それぞれに問題の重要さをわかりやすく解説していると思う。 バイオメジャーが食を支配するってのは陰謀論とも言い切れない現実味がある。
Posted by
均一な規格で一定の収穫料が確保できなければ、一般流通できない農業の現状。効率化のために種は手を加えられている。生物では倫理的にNGとも思われるような遺伝子操作が種には行われる。 ・ 真冬に食べられる茄子やトマト、イボイボのないきゅうり……さまざまなニーズと膨大な食糧需要を支えるた...
均一な規格で一定の収穫料が確保できなければ、一般流通できない農業の現状。効率化のために種は手を加えられている。生物では倫理的にNGとも思われるような遺伝子操作が種には行われる。 ・ 真冬に食べられる茄子やトマト、イボイボのないきゅうり……さまざまなニーズと膨大な食糧需要を支えるために人工的に生み出された、不自然な種からできた野菜をわたしたちは食べている。テクノロジーによって操作された種は、知的財産権の保護対象になることも。 ・ 育てた野菜から種を採取することが犯罪になる国も多数あるそう。不正コピーみたいな感じなのかな… 規制によって食料支配を作り出し、地域や国家間で意図的な格差を産むことだって可能になる。 ・ 昔ながらの野菜は味が濃くて食べ応えもあってびっくりする。在来種を保護する活動を目にすることも増えた。 ・ 安全な食べ物とは果たして何なのか?なにを最低基準にするのか?考えることが多い。
Posted by
この本を読んだ後、岡本よりたかさんのSNSにアクセスし、フォローさせていただきました。この方の人柄がすごく好きになりました。尊敬しています。
Posted by
・なんで読んだか? 師匠に借りた。農家だから知っておかないと。 ・つぎはどうする? 他にもあるからそれを読む。だいぶ理解が深まってきた。前の本(タネはどうなる?)よりも客観的にわかりやすい。 ・めも 植物には栄養成長と生殖成長の2種類がある。コメは背丈が伸び分けつをするのが栄...
・なんで読んだか? 師匠に借りた。農家だから知っておかないと。 ・つぎはどうする? 他にもあるからそれを読む。だいぶ理解が深まってきた。前の本(タネはどうなる?)よりも客観的にわかりやすい。 ・めも 植物には栄養成長と生殖成長の2種類がある。コメは背丈が伸び分けつをするのが栄養成長、種をつけていくのが生殖成長。ナス科などは栄養成長と生殖成長が同時に行われる。 種を守るために硬いモミに囲まれている。小麦には硬いモミはないが禾というツンツンしたひげがあり、これで鳥に食べられないようになっている。古代小麦には硬いモミがある。 アメリカで大量のハチが消える(CCD)は雄性不稔が原因ではないか。農薬ネオニコチノイドが原因であれば、大量の死骸が出るはず。 F1のタマネギ、ネギ、じゃがいも(男爵いも、メークイーン、キタアカリ)はすべて雄性不稔。 市場の原則は、「定時・定量・定質」で、決められたときに、決められた質で、決められた量を納めないといけない。 営業をしないと決めた。人は変わらない。最初は種の大切さを伝えてこの人にわかってもらおうとしたけど、自然な流れで、種が大事だって知った人が来たら、その人にきちんと対応する、に変えた。 農業と農を分けている。種屋、農薬会社、運送会社、市場、スーパーマーケット、eコマース、レストラン、これらは農業。つくる前から21センチとか24センチとかって決まっているきゅうりもある。それは開発した企業が権利を求めるのも納得する。農は別物で古来種はこっち。自然と神様と野菜の関わり合いで、踊りがあって、祭りがある。五穀豊穣を祈り、収穫祭をする。古来種には複雑な味がある。価格が高いこともあるけど、味がしっかりあるので調味料は必要ない。 食糧管理法:1942年、農家が栽培したコメはすべて政府が買い上げ、価格を安定させてから市場に送り出していた。平成7年に廃止し、農家の自主流通米が合法になり、無農薬や有機栽培のコメが市場に出回るようになった。 主要農作物種子法:1952年、行政法であり、各都道府県にコメ、麦、大豆の原種、原原種を維持管理し、新品種を開発する義務をもたせる。 ササニシキ、コシヒカリ、ミルキークイーン、なども県が税金をつかって農業試験場で生み出した品種。独自に新しい品種をつくるのは必要なこと。種子法が廃止されたあとは、条例をつくり、今まで同様、農業試験場で新しいコメ、麦、大豆の品種をつくればよい。 農業競争力強化法、JA全中が一般社団法人化され弱まった。JA独占から民間のさまざまなプレイヤーが参加できるようにした。 種苗法の改正。もともとは知的財産に関する法律で、明らかに異なる種類を開発した場合に農水省に登録され、その種の独占販売を認める法律。例外は、農家が自家採種したもので、これはOKだった。ただし、別個に契約をすれば自家採種も禁止できる。F1のコメは各企業と個別契約を結ばされ、この中に禁止する旨記載がある。 気になる文章は「農林水産省令で定める栄養繁殖する植物に属する品種の育苗を用いる場合は適用しない」とある。繁殖には、種子繁殖(種をまくもの)と栄養繁殖(茎、根、葉、枝で増殖するもので、根で増やすじジャガイモ、蔓のサツマイモやイチゴなど)。しかも、通常は種子繁殖だけど栄養繁殖でも育つもの、トマトなども含まれる。これを国会も通さず、農家の意見も聞かず農水省だけで増やせるのが怖い。実際、357まで増えている。これはUPOV条約という知的財産権に関する法律を元に、日本でもさらに推進しようとしている。 この対策は固定種をつなぐ民間のシードバンクをつくっていくこと。 種の保管方法。種はいったん乾くと休眠期間に入り、発芽抑制物質を生成する。変なタイミングで発芽すると枯れてしまうから。濡れると発芽が始まる。湿度が高いところもNGで、封筒もNG。瓶に入れておく。寒い冬と勘違いする冷蔵庫もOK。開け締めが多いとよくないので、種用の小さい冷蔵庫があるとベター。翌年に使い切る場合は常温で季節を感じさせるのもOKだが、理想は数年分をとっておく。
Posted by
- 1