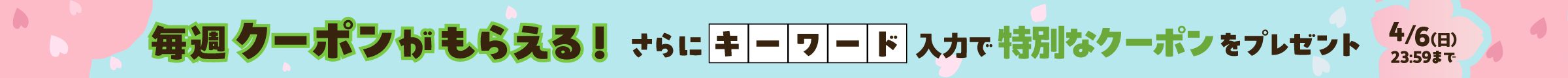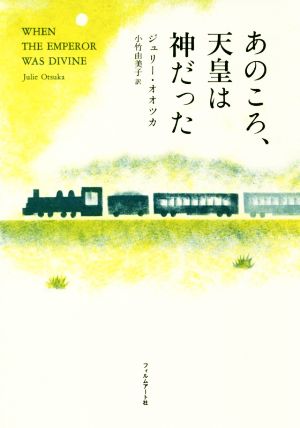あのころ、天皇は神だった の商品レビュー
戦時中、強制退去→収容所に収監された日系家族のお話。収容される前日に、母がペットを処分したり、荷物を揃えたり、子供たちを諭したり、から始まり、砂漠に近い環境の収容所に入れられる。殺されはしないが、とても生きづらい様子が綴られる。戦後父が帰ってきても、かつての精悍な様子は見られず、...
戦時中、強制退去→収容所に収監された日系家族のお話。収容される前日に、母がペットを処分したり、荷物を揃えたり、子供たちを諭したり、から始まり、砂漠に近い環境の収容所に入れられる。殺されはしないが、とても生きづらい様子が綴られる。戦後父が帰ってきても、かつての精悍な様子は見られず、心が折られたまま低空飛行の毎日を送る。その一連の描写がとてもリアルで、淡々としていて、とてもズンと胸にくるものがあった。日系というだけで抑留されていた時代。日本にも似たような境遇の朝鮮人などがいるが、苦労を目の前に、過去を振り返り、これからも語り継いでいかなければならないと感じた。 p.75 「あそこでいっしょに話してたのは誰?」 「誰でもない」と女の子は答えた。「男の人。お金持ち」女の子はちょっと言葉を切った。 「テッドっていうの」女の子は低い声で言った。「すべてうまくいきますよってお母さんに言いなさいって」 「あの人にそんなことわかるわけないじゃない」
Posted by
「スイマーズ」のジュリー・オオツカの前作。 「スイマーズ」で認知症になるアリス、モデルは作者の母親。 その少女時代を描く。 パールハーバー以後の日系人の苦難。 父親は逮捕連行され、残された妻と子(姉弟)は砂漠の収容所へ。 母親の語り、次は娘、そして息子・・・ 最後は父親。...
「スイマーズ」のジュリー・オオツカの前作。 「スイマーズ」で認知症になるアリス、モデルは作者の母親。 その少女時代を描く。 パールハーバー以後の日系人の苦難。 父親は逮捕連行され、残された妻と子(姉弟)は砂漠の収容所へ。 母親の語り、次は娘、そして息子・・・ 最後は父親。 戦後、帰還後は別人のようになってしまった父。 ・・・え、そこまでしたの!?FBI! 日本軍やナチスと変わらないじゃん。 ・・・この衝撃。 ああ、わたし、甘いな。 何の幻想をアメリカ軍に抱いていたのだろう・・・ 戦争は戦争だね。 どこの国もすることは同じ。 人を狂気に走らせる、
Posted by
登場人物に名前がないし、心理描写もない。 事実だけが淡々と端正に鮮やかに綴られていて、かえって怖さや苛烈さ、理不尽さが際立つ。 モデルは著者の祖母の一家だが、最後の「告白」の章ではその主語があらゆる日本人収容者になってる。 主人公家族に名前がないことと相まって、強制的に収容された...
登場人物に名前がないし、心理描写もない。 事実だけが淡々と端正に鮮やかに綴られていて、かえって怖さや苛烈さ、理不尽さが際立つ。 モデルは著者の祖母の一家だが、最後の「告白」の章ではその主語があらゆる日本人収容者になってる。 主人公家族に名前がないことと相まって、強制的に収容された人々、帰ってからも差別され排除された人々の話になっている。 どこも、いつでも、こんな風になってほしくない
Posted by
『屋根裏の仏さま』を読んで素晴らしかったので、こちらも読みたいと思っていたが、ずいぶん間があいてしまった。 こちらの方が先に出版されている。 この作家の特徴は語り口にある。『屋根裏の仏さま』は「私たち」が語り、こちらは母親、少女、少年の視点で語られるが、どの人物にも名前はない。...
『屋根裏の仏さま』を読んで素晴らしかったので、こちらも読みたいと思っていたが、ずいぶん間があいてしまった。 こちらの方が先に出版されている。 この作家の特徴は語り口にある。『屋根裏の仏さま』は「私たち」が語り、こちらは母親、少女、少年の視点で語られるが、どの人物にも名前はない。 ラストはそのまま『屋根裏の仏さま』につながっていく感じだった。 パウゼヴァングの『そこに僕らは居合わせた』にユダヤ人一家が連行された後、近所の人たちが家財道具や食品を持っていくという小説(「スープはまだ温かかった」)があったが、それと全く同じことが、日系人が収容された後にも起こっていたことが描かれる。あの人たち、いつ帰ってくるかわからない。もしかしたら帰ってこないかも。だったら私たちが有効に利用した方がいい。と考える普通の人たちのあさましさ。(これは困窮していたら、飢えていたら、私もやりそうなことだ。) 縄跳びをするとき縄を回すのはさせてもらえるけど、跳ばせてはもらえない女の子。「誰かに訊かれたら、中国人だって言うのよ」と子どもに約束させる母。子どもたちへの手紙に「覚えておきなさい、折れてしまうよりは曲がるほうがいいということを」と書く父。どのエピソードも辛くみじめで悔しい。 はじめに収容所に行く前に母がした準備が、また辛い。 しかし筆致は淡々としている。だから余計にそれが「当たり前」だったことが伝わる。 これらのことを私たちは知っておく義務があると思う。二度とこういう扱いをされないのはもちろんだが、こういう扱いをしてしまわないように。
Posted by
日系アメリカ人著者の処女作。 原題は"When the Emperor was Divine"。「天皇が神聖であった」頃、つまりは第二次世界大戦の頃、敵性外国人と見なされ、強制収容所に送られた人々の物語である。 主人公一家の名前は明らかでない。 母親と姉弟は...
日系アメリカ人著者の処女作。 原題は"When the Emperor was Divine"。「天皇が神聖であった」頃、つまりは第二次世界大戦の頃、敵性外国人と見なされ、強制収容所に送られた人々の物語である。 主人公一家の名前は明らかでない。 母親と姉弟は、「女」「女の子」「男の子」と呼ばれる。 一家は海の近く、カリフォルニア州に住んでいる。比較的裕福で、近所の人々とも親しく付き合っていた。 だが、その暮らしは戦争がはじまると暗転する。 父親は真珠湾攻撃の後、スパイと見なされ、どこかへ連れ去られていった。 空気は徐々に不穏になり、ついに一家にも強制退去命令が出る。 家を出て、ユタ州の砂漠の収容所へと向かうのだ。 物語は、退去の直前から、戦後、一家が家に戻るまでを綴る。 語りは三人称だが、視点は移り変わる。 退去前は「母」、列車の移動は「姉」、収容所生活、そして家に戻ってからは「弟」。 それぞれの見たこと、考えたことが綴られていく。 そこから浮彫になっていくのは、大きなものに蹂躙される人々の姿だ。 退去の準備をする母は一張羅を着て最後の買い物に出かける。粘着テープや紐はともかく、シャベルや金槌まで吟味する(実はこれには理由があるのだが)。ペットは連れていけないのでそれぞれの身の振り方を考える。 女の子はそろそろ反抗期。異性への興味も出てきている頃。豊かな暮らしが懐かしい。戦争が始まって、いろんなことが変わってしまった。 男の子は8歳。最後に見た父は、バスローブと室内履きのまま、帽子もかぶらず連行されていった。面影も忘れそうだ。収容所暮らしの中で、学校の友達はどうしているかと思うが、手紙をくれるのは1人だけだった。戻ってきても、かつての友達は皆よそよそしい。自分が収容所にいたことなどなかったかのようだ。自分など存在しなかったかのようだ。 一家の裏庭でかつて咲き誇っていた赤いバラ。そのバラはどこに行ってしまったのだろうか。 ある特定の一家を描いているようでいて、これは同じ経験をした多くの家族の物語である。主人公たちの匿名性がそれを際立たせる。 長らく不在だった父が、最後に戻ってくる。 最終章は「父」の語りである。 わずか6ページの「告白」と題された章は、悲鳴である。大きなものに手ひどく痛めつけられた人の、いや人々の。 彼らが受けた理不尽な仕打ち、抗えぬことの苦しみ、絶望。 それらがこの短い章に集約される。 彼らのいったいどれほどが本当に天皇を神だと思っていたのだろうか。 これは、「天皇は神だ」と彼らが思っていると、別の誰かが思っていたころの物語である。
Posted by
真珠湾攻撃の後、アメリカに住む日系人は砂漠の中の強制収容所へ送られ、終戦まで不自由な暮らしを強いられた。 父は当局に連行され、母子で収容所へ移動する。母、娘、息子の目線で、静かなタッチで語られるその暮らしはあまりにも過酷。生きる力を日々失われていく様子がうかがえる。 戦前は一軒家...
真珠湾攻撃の後、アメリカに住む日系人は砂漠の中の強制収容所へ送られ、終戦まで不自由な暮らしを強いられた。 父は当局に連行され、母子で収容所へ移動する。母、娘、息子の目線で、静かなタッチで語られるその暮らしはあまりにも過酷。生きる力を日々失われていく様子がうかがえる。 戦前は一軒家で裕福な暮らしをしていた日系人家族の人生を一変させた母国の攻撃。アメリカ人として暮らしていた彼らなのに、何の罪もないのに、日本人というだけで虐げられ、戦後、収容所から我が家へ戻ってきた後も差別に苦しむ。 戦争の被害は原爆や空襲だけではない。国籍による差別。それは今の時代にも続いている。心の受けた被害(傷)はどうすれば回復するの?答えを出すのは難しいだろう。。。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「あのころ、天皇は神だった」、不穏なタイトルに似つかわしからぬ淡い黄色い表紙。のどかな田園風景を一台の汽車が煙を吐いて走っている。この汽車に乗って、みんなはどこへ行くのだろう。 ユタ州の砂漠にある、日系人収容所である。 思春期にさしかかるころの少女、幼い弟、若い母親。戦前は豊かな暮らしむきだったことがうかがえる。隣近所と仲良く行き来があったことも。三人が頼りにしていた賢く強い父親は、ある日とつぜんとらわれて連行されてしまう。おしゃれな父親が、就寝中に部屋着に室内履きで連れて行かれたことに心を痛める子どもと、寝床に入る前に喉が渇いたなと呟いた夫に水を渡してやらなかったことを気に病む妻。 静かな筆致の文章はあたかも昔話を読むかのようだ。通告を受けて、あらゆる感情を押し殺し所持品を淡々と選ぶ母親。混んだ車内、乏しい飲食物、車酔いの吐き気。海が見える町から移り住んだ、なにもない砂漠に建てられた殺風景な収容所での日常(母親がかつて雇っていた家政婦のウエノさんに出くわすところは、そのなかでも私にとっては心動く一場面だった)。 そして、戦争は終わり(天皇は神ではなくなり)、三人はもとの家に戻る。父親も帰る。彼らは「幸運」だったろう、家は誰かに占拠されているわけでもなく壊されてもおらず、そこにあったのだから。内部は荒らし放題に荒らされ、母が丹精して育てたバラの木はなくなってはいたけれど。 そして最後の父の「独り語り」は圧巻だ。 写真一枚で夫を決めて、太平洋を渡り日本から米国に移民した「写真花嫁」を描いた、詩のような『屋根裏の仏さま』は忘れがたい一冊。この本より前に出された、作者の長編デビュー作という『あのころ、天皇は神だった』が復刊されたのは幸せである。
Posted by
- 1