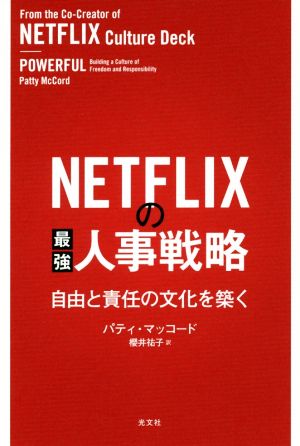NETFLIXの最強人事戦略 の商品レビュー
得られるものは大きく2つある。 一つは急成長するITプラットフォーム企業のカルチャーの作り方から運用の方法。もう一つは、ITに限らず現代に求められている人材。 ハイパフォーマーを集め、ハイパフォーマーに満足のいく環境はハイパフォーマーを集め続け、密度を高めること。その中でスキル的...
得られるものは大きく2つある。 一つは急成長するITプラットフォーム企業のカルチャーの作り方から運用の方法。もう一つは、ITに限らず現代に求められている人材。 ハイパフォーマーを集め、ハイパフォーマーに満足のいく環境はハイパフォーマーを集め続け、密度を高めること。その中でスキル的なパフォーマンス以外に最大に重要なのは、意見を言い続けること。 ハイパフォーマーという用語が何度か出てくる。ハイパフォーマーを採用し続けることが経営の主要課題ともなっている。ではハイパフォーマーとは何で、ハイパフォーマーがパフォーマンスを最大にできる環境とは何かを問い続ける。 Netflixのように、市場が変わり、必要なスキルが変わることもある。そうなった時に推薦をしてまで他社に転職させることもあるという。しかし結果は他のハイパフォーマーへの影響を受けさせないようにできることだ。
Posted by
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本とアメリカは全然違うと思った(アメリカで成果を出している一例としてはとても興味深かった) ・能力の高い人を採用しなさい ・いらなくなったら解雇しなさい ・福利厚生はいらない、なぜなら最高の仲間こそが福利厚生だから
Posted by
なぜNetflixがここまで成長できたのかわかる。 圧倒的な人材には報酬を出すし、正社員なのに業務委託のような関係で割り切る人事戦略はとても興味深い。
Posted by
先にリード氏&エリン氏の『NO RULES』を読了。NETFLIX社の独創的な人事制度を体系立てて理解するという意味では先の本に軍配があがるが、その導入に際するリアルの現場感という観点ではなかなか面白い。能力密度を濃くして透明度を上げて規制を撤廃して(但し退場は一発で)、はたして...
先にリード氏&エリン氏の『NO RULES』を読了。NETFLIX社の独創的な人事制度を体系立てて理解するという意味では先の本に軍配があがるが、その導入に際するリアルの現場感という観点ではなかなか面白い。能力密度を濃くして透明度を上げて規制を撤廃して(但し退場は一発で)、はたしてどうなったか、どういう問題が起こったか、結局どういう形の落とし所になったか。『NO RULES』を読んで興味を持たれた方は読んでみてもよいかもしれない。
Posted by
事業戦略の変化に応じて業界最高水準の報酬を掲げて積極的に人を入れ替えていく人事戦略が賛否ありそうな内容ではありましたが(そんなの日本では、うちの会社ではマネできない!等)、背景にある自由と責任の文化が重要というテーマ自体には共感できる内容でした。 とはいえ、NETFLIXが実践す...
事業戦略の変化に応じて業界最高水準の報酬を掲げて積極的に人を入れ替えていく人事戦略が賛否ありそうな内容ではありましたが(そんなの日本では、うちの会社ではマネできない!等)、背景にある自由と責任の文化が重要というテーマ自体には共感できる内容でした。 とはいえ、NETFLIXが実践する方法をそのまま真似できないとなった時に、どうやってそのような文化を醸成していくのかは結構な難問な気がします。何事にも言えることですが、ビジョンを明確にした上でのトライ&エラーが必要と思いました。
Posted by
マネジメントや育成のキャパシティを広げる必要を感じてまして。 Netflixがこれだけ風通しよく、健全なフィードバックを行える社風は、帰属する国の問題なのか、フロンティアならではなのか。 ブレない経営意識で、最も成功している会社の「らしさ」が書かれてありました。 【本文より...
マネジメントや育成のキャパシティを広げる必要を感じてまして。 Netflixがこれだけ風通しよく、健全なフィードバックを行える社風は、帰属する国の問題なのか、フロンティアならではなのか。 ブレない経営意識で、最も成功している会社の「らしさ」が書かれてありました。 【本文より】 ・自由な知性の応酬ほど楽しいものはないと思うようになった。 ・経営陣がなぜこの決定を下したのか、全員が目標の達成に最大の貢献をするにはどうしたらよいか、どんな障害が見込まれるか ・徹底的に正直であることは、わたしにとって息をするように自然なことだが、ほかの会社では必ずしもよく思われなかった。 ・リーダーは批判的なフィードバックの伝え方を練習し、具体的で、建設的で、善意が伝わるような方法で話そう。 ・斬新なのは、それぞれに相手の立場で議論させたことだ。議論するために、双方が相手の考えをしっかり理解する必要があった。 ・交渉術のセミナーで一日を過ごすのと、全社ミーティングで-何のとがめも受けずに-厄介だが理にかなった質問を上級幹部にぶつけ、解決すべき問題についてマネージャーと真剣に議論をして過ごすのと、どちらがいいか従業員に選ばせてみよう。
Posted by
類似のストーリーが各章に配置され、やや難解な構成となっているが、一冊を通して一貫したメッセージを受け取ることができた。各章ごとの振り返りや、複数回の査読が必要だが、最終的な満足度は高い。
Posted by
「NO RULES」と大筋は同じなので「NO RULES」を読んでるなら読まなくてもいいかと思います。先に発売したのがこっちだったので私は読みました。 ■よかったフレーズ ・マネージャーは自分のチームだけでなく会社全体がとりくむべき仕事と課題をチームメンバーにオープンにはっきり...
「NO RULES」と大筋は同じなので「NO RULES」を読んでるなら読まなくてもいいかと思います。先に発売したのがこっちだったので私は読みました。 ■よかったフレーズ ・マネージャーは自分のチームだけでなく会社全体がとりくむべき仕事と課題をチームメンバーにオープンにはっきりと継続的に伝える ・多くの企業委が研修に大金をかけ、従業員に仕事から長時間離れることを強いる。こうしたお金と時間、労力の大部分が的外れのことに費やされている。 ・専門家の弱点は現状の制約に縛られすぎること。新鮮な目で問題ととらえられる人が、無知ゆえに制約をすり抜ける方法をみつけることがある。 ・会社はチームであって家族ではない ・つねに柔軟性をたもち、あたらしいスキルを学び、新しい機会を検討し、折あるごとに新しい課題に挑戦して、新鮮な気持ちで自分をのばしながら働けるようにしよう
Posted by
https://twitter.com/shu_yamaguchi/status/1037854294001631232?s=20
Posted by