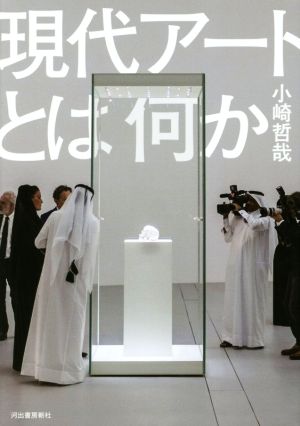現代アートとは何か の商品レビュー
2024.05.05 なかなか読み応えのある、ある意味深くて重くて辛辣な素晴らしい本であった。それでいて割とわかりやすい。勉強になった。著者には深く感謝を表明したい。
Posted by
愛知トリエンナーレをプロデュースしたディレクターによる現代アート産業俯瞰図。現代アートを形作る画廊やオークションハウス、アート・バーゼルやベネチア・ビエンナーレの舞台裏が描かれる。一般生活ではアクセスできない美術産業界を垣間見れる貴重なモノローグではあるが、舞台の内側の人間である...
愛知トリエンナーレをプロデュースしたディレクターによる現代アート産業俯瞰図。現代アートを形作る画廊やオークションハウス、アート・バーゼルやベネチア・ビエンナーレの舞台裏が描かれる。一般生活ではアクセスできない美術産業界を垣間見れる貴重なモノローグではあるが、舞台の内側の人間であるはずなのに、美術産業界に対する嫌悪感が見え隠れして、エンターテイメント教材として読めなかった。
Posted by
コンテンポラリー アートは現代美術ではなく、現代アート。 前半はアート界の様々な業界話。 知らない作家を調べながら読むのでなかなか読み進まなかったが、知識が増えた。 後半は現代アート論で、目からウロコ。 現代アートの3大要素は、インパクト、コンセプト、レイヤー。そして7つの動機。...
コンテンポラリー アートは現代美術ではなく、現代アート。 前半はアート界の様々な業界話。 知らない作家を調べながら読むのでなかなか読み進まなかったが、知識が増えた。 後半は現代アート論で、目からウロコ。 現代アートの3大要素は、インパクト、コンセプト、レイヤー。そして7つの動機。 アートの価値を決めるのは個々のアートラバーになりつつある。 日本の問題点にも言及。かなり辛口だけど事実かも。 ビジネス書のような切れ味で明快。面白かった。
Posted by
グローバル社会における現代アートの常識=本当の姿を描きつつ、なぜアートがこのような表現に至ったのか、そしてこれからのアートがどのように変貌してゆくのかを、本書は問う。
Posted by
現代アートを理解するために必要な視点を「マーケット」「ミュージアム」「クリティック」「キュレーター」「アーティスト」「オーディエンス」の6つに分け、グローバル資本主義社会における現代アートのルールを解き明かす。 『巨大化するアートビジネス』(紀伊国屋書店)が面白かったので、さ...
現代アートを理解するために必要な視点を「マーケット」「ミュージアム」「クリティック」「キュレーター」「アーティスト」「オーディエンス」の6つに分け、グローバル資本主義社会における現代アートのルールを解き明かす。 『巨大化するアートビジネス』(紀伊国屋書店)が面白かったので、さらに最近書かれた本を探して出会った。前掲書はビジネス目線の本なので省かれていた〈現代アートの評価基準〉を、本書はじっくり教えてくれる。 「理論家が力を失っている」と語られる「クリティック」の章。反対に、アーティーストにとって今日のアートはすべてがコンセプチュアルであり、アートは理論を求めているとする「アーティスト」の章。そして、デュシャンがレディメイドを発明して以来、アーティストは「選択し、命名し、新たな価値の付与」を行うという点で、鑑賞者に一歩先んじているに過ぎないと語る「オーディエンス」の章。この三章は現代アートの定義を整理してくれる。 一方で、アーティストが行なっているのは大雑把に言えば「プレゼン」であり、そのプレゼンに美術史への目配せがないとアートとして位置づけてもらえないという話なら、批評がなぜ衰弱してしまったのか疑問でもある。アーティスト自身が理論家となり、オーディエンスが能動的解釈者として関わることで、権威的な批評が成り立たなくなったのか。 本書では現代アート界で評価されるためのアティチュードを丁寧に解説してくれるので、村上隆やChim↑pomの立ち位置もやっとわかってきた。同時に、それはどうしようもなく西洋中心主義な評価軸でもある。現在、世界で1、2を争うアートコレクターだというカタールの王家も、そのコレクションの選別基準はヨーロッパにべったりだという。 この潮流を変えようとしたのが、1989年にジャン・ユベール=マルタンがキュレーションした『大地の魔術師』展と、ヤン・フートがキュレーションした『オープン・マインド』展だった。この二大キュレーターにフォーカスした章は、時代を知る人のルポルタージュとしてとても面白いし、展示を見たくなった。冷戦終了と同時に現代アートのグローバル化と脱エリート化が始まったというのも興味深い。
Posted by
現代アートを支えるシステムとしての金(マーケット)の話から始まり、その誤解や構造的矛盾を明らかにした上で、個々のアーティストや作品、歴史的な意義を再確認する。誰にでも使える独自の評価チャートを用いて現代アートの見方を提示する。 「あんな絵が100億?!」という疑問を納得できないに...
現代アートを支えるシステムとしての金(マーケット)の話から始まり、その誤解や構造的矛盾を明らかにした上で、個々のアーティストや作品、歴史的な意義を再確認する。誰にでも使える独自の評価チャートを用いて現代アートの見方を提示する。 「あんな絵が100億?!」という疑問を納得できないにせよ理解できるようになるし、現代アートのわけわからなさにも「正史」があると思うとちょっと安心する。
Posted by
読み終わるのに時間のかかった分厚い本。現代アートとその周辺についてよくわかる。大富豪のコレクターの話にはなんだかワクワクした。「ダイナスティー」とか思い出した(古い)。ただ、著者の現代アートへの興味が立体やインスタレーションに偏っているので、そこら辺はちょっと物足りないかも。絵画...
読み終わるのに時間のかかった分厚い本。現代アートとその周辺についてよくわかる。大富豪のコレクターの話にはなんだかワクワクした。「ダイナスティー」とか思い出した(古い)。ただ、著者の現代アートへの興味が立体やインスタレーションに偏っているので、そこら辺はちょっと物足りないかも。絵画が好きなので絵の話も聞きたかった。とにかく濃い本です。
Posted by
業界について辞書的に出来事を知るには良かったけれど、もうちょっとアートのことについて掘り下げられていたらなあ、と持ったりしました。でもこうやって表面だけ見るのが現代アートなんだよというのであれば、そうなのか、と納得します。
Posted by
現代アートの「動機」をチャート化した「現代アート採点法」によって、「難解」と思われがちなアート作品が目からウロコにわかりはじめるだろう。アートジャーナリズムの第一人者による、まったく新しい現代アート入門。(e-honより)
Posted by
どこか幕の内弁当的で一貫したテーマが見えてこなかったというかストーリーがよくわからなかったが、このメタ認知という輪郭がこの本の醍醐味なのかもしれない。
Posted by
- 1
- 2