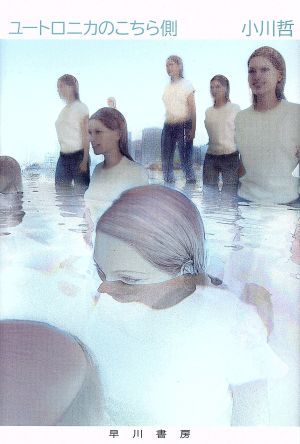ユートロニカのこちら側 の商品レビュー
著者のデビュー作。荒削り…みたいな書評を見かけたことがあるけど私は結構好きだと思った。最近彼の作品は難しい短編集が多かったが、この近未来都市のSFは、エンタメよりの楽しみ方をした。数年前の、情報銀行などか話題になっていた頃に書かれたのかなという内容。一応ディストピア小説というジャ...
著者のデビュー作。荒削り…みたいな書評を見かけたことがあるけど私は結構好きだと思った。最近彼の作品は難しい短編集が多かったが、この近未来都市のSFは、エンタメよりの楽しみ方をした。数年前の、情報銀行などか話題になっていた頃に書かれたのかなという内容。一応ディストピア小説というジャンルだと思う。 あらゆる個人データや生体データ、行動データをその会社に提供することに同意し、「あまり深く考えない質」であることで情報ランクが高いと評価された人間は、その会社が運営するカリフォルニアの実験都市の住人になれる。そこでは仕事をしなくても平均以上の生活が保障されるユートピア。トイレ以外の場所はカメラで監視されている。データ分析を元に平和を保つ都市。犯罪を「予防」するために犯罪者予備軍を特定してサナトリウムに入れる。データをかき集めてVR世界を作り上げれば、過去のどんな場面にも戻って追体験もできる。 そんな世界に対して、様々な要素を掛け合わせてどんな動きがありうるかシミュレーションするような連作短編集。例えば、その都市に外から移住した夫婦はどうなる?住み続けたら人間はどうなる?事件が起きたら警察はどうする?死んだ両親にバーチャルで会えたら?監視されていたことを知らずに育った子どもが真実に気づいたら?テロを起こそうとしたら?司法は?アルゴリズム開発者は?… 反抗してもがく少数派の人たちの姿と、違和感を持たずに溶け込む人たちの対比が良くて、自分はどっちの人間だろう…と思った。普段アルゴリズムによる情報レコメンド大歓迎の私は、後者かもしれない…
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
久しぶりに結構しっかり目のSFを読んだ。 内容としては、個人情報やプライバシーを切り売りすることで働かずして暮らせるようになるという実験都市、アガスティアリゾートにまつわる人物たちを描いた作品。 サーヴァントと呼ばれるAI?の指示通り動けば大きな間違いや苦悩にぶつかることなく過ごせるというところから人々は徐々に思考(作中でいう意識)を放棄していく様に妙にリアリティを感じる。久々に「言葉で感想を上手く言えないけどなんか面白い…」と感じる作品。 ユートピア×エレクトロニカという造語も納得できるような作品。 ただし、かなり小難しい。
Posted by
設定の面白さ、 海外と日本がうまく掛け合わさっていく ただちょっと長くて後半垂れてしまった。 それは私がSF慣れしていないからだと思うけど壮大すぎるストーリーに結末を急ぐように読み飛ばしてしまった。 でもこれが新人賞なんてすごい。 あとがきも面白かったし勉強になった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
めっちゃ現実的な設定だった。 あと数十年後にはありえる世界。 なのに、怖さがなんかあんまりわからなかった自分が怖い。 この本を読んでる時に、日本の出生率が過去最低というニュースを見た。 専門家の人たちのコメントも見た。 だけど、なんだか現実感がなくて「どうしようもない」と思った。 同じようにアガスティアみたいなことが起きても、たぶんそんなに何も思わないだろうなと思った。 人類はすでに滅亡しかかってる気がするし、滅亡しはじめてからじゃないとどうすればいいかわからない気がする。
Posted by
あらゆる個人情報(視覚や聴覚などすべて)を提供することでそこそこ豊かな生活が保証される社会、ユートロニカ。そんな社会になじめず、零れ落ちた人たち、すなわち“ユートロニカのこちら側”の人たちを描く。 過激な暴力や搾取の描写は殆どなく、ディストピア小説ではないような感じ。 社会の革...
あらゆる個人情報(視覚や聴覚などすべて)を提供することでそこそこ豊かな生活が保証される社会、ユートロニカ。そんな社会になじめず、零れ落ちた人たち、すなわち“ユートロニカのこちら側”の人たちを描く。 過激な暴力や搾取の描写は殆どなく、ディストピア小説ではないような感じ。 社会の革命的な変化は、想像力そのものを変質させてしまう。 以前は想像できていたことが、想像すら出来なくなってしまう。 不可逆的な変化の恐ろしさ。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
情報銀行に個人情報を預けることで収入と福祉や安全が得られるようになった社会を、主にそれに違和感や疑問を持つ人の視点で描いている。 登場人物が章ごとに変わる群像劇風。後半になるにつれて哲学的、思索的な内容が増えてくる。個人的には面白かったが読む人を選ぶと思う。 (少なくともメインの登場人物は)意識があること、考えることに価値を置いていて、その見方に立つとディストピア小説に見えるが、本当にそうなのか?意識があり自由である(と思っている)ことに、実際のところどれだけの価値があるのか?といったことについて考えてしまった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
アガスティアリゾートAIにより徹底された個人情報の管理下で、管理されていることを気にとめない人は自由に、神経をすり減らしてしまう人は不自由になる住民たち。リゾートに住む人はどこか人間味に欠けていて、小説の章は変わっているのに住民は複雑に思考する癖のある、似たような登場人物が集まっているのが狂気的でした。 内容が難しく読み終わるまでに時間がかかってしまいましたが、後に読み返そうと思える話でした。
Posted by
監視社会の変遷と、その社会を生きる人々の内面を描写したSF作品。今や大人気作家となった小川哲さんですが、デビュー作のみ手に取っていなかったので今更ですが読了。デビュー作とは思ないほど濃厚な物語で、非常に楽しめました。 大きな事件が起きるわけでは無いので、どこか淡々としており、S...
監視社会の変遷と、その社会を生きる人々の内面を描写したSF作品。今や大人気作家となった小川哲さんですが、デビュー作のみ手に取っていなかったので今更ですが読了。デビュー作とは思ないほど濃厚な物語で、非常に楽しめました。 大きな事件が起きるわけでは無いので、どこか淡々としており、SF作品として読むと少し盛り上がりにかける印象がありましたが、文学作品として見ると、監視社会というあり方に抵抗する個人の内面を丁寧に描いており、「自分だったらどうするか」ということも考えながら楽しめる唯一無二の作品だと感じました。4章などは、のちの「ゲームの王国」などにも通じる印象もある濃厚なストーリーで、その点でも興味深ったです。
Posted by
ユートロニカのこちら側 近未来、監視社会ディストピア。 複数の視点からの物語で構成されている。 各々の事情でアガスティアリゾートという居住特区に関わり、サーヴァントと呼ばれる個人情報を収集し情報を基にアルゴリズムされたAIと自己意識の葛藤を描く群像劇S F ストーリー。 人々は個...
ユートロニカのこちら側 近未来、監視社会ディストピア。 複数の視点からの物語で構成されている。 各々の事情でアガスティアリゾートという居住特区に関わり、サーヴァントと呼ばれる個人情報を収集し情報を基にアルゴリズムされたAIと自己意識の葛藤を描く群像劇S F ストーリー。 人々は個人情報を提供することで労働から解放され、日々の選択もサーヴァントに依存する生活で、日々の様々な選択からも解放される。 果たして自らで考えることを図らずも放棄した人々は、自由といえるのろうか。そこに意識としての自己は存在するのかを考えさせてくれる。自由とは何か。不自由があるからこその自由。自由の定義。意識と無意識。やがて到来するであろう人類の在り方についての問題提起。テクノロジーが発展していく先に人類が直面する可能性のある世界軸。人間が人間としてあるための戦いでもあるように感じた。
Posted by
最近、私の中で密かにブームになっている小川哲さんの小説です。 端的に言って大好きな作品でした。 文章の手触りも好きだし、話の展開、キャラクター造形やその背景にある哲学的な問いまで小さなことひとつひとつが個人的に刺さる。飽きることなく最後まで読み進め、読了して(終わってしまったと...
最近、私の中で密かにブームになっている小川哲さんの小説です。 端的に言って大好きな作品でした。 文章の手触りも好きだし、話の展開、キャラクター造形やその背景にある哲学的な問いまで小さなことひとつひとつが個人的に刺さる。飽きることなく最後まで読み進め、読了して(終わってしまったということに)少し残念に思ったほどでした。 ディストピアものとカテゴライズされているものの、どちらかというと「生き延びるには?」というサバイバル的要素というよりは、監視社会(=アガスティア・リゾート)について書かれた物語で、その物語の中心は「自由とは何だ?」という問いです。 さらに、そのリゾートは我々の生きている社会と地続きなのだなと思わされます。 読んでいる途中、以前読了したネット監視社会についてまざまざと思い出しました。 こちらではその内容より、より深く「見えない監視」が進んでいて、コンタクトレンズで視界を盗視したり、手首の端末から心拍や体温を検知したりと、あらゆる手を尽くして監視されています。 きっと私の付けているスマートウォッチも、単にスマートなだけではなくて、ヘルスケアの域を超えてどこかへ情報を送っているんだろうな……などと思いながら読み進めました(それでもスマートウォッチは付けたまま)。 ガチガチの監視社会であるアガスティア・リゾートについて、居住を望む人、疑いを持つ人、制度そのものの社会的価値について考える人、内側から崩そうとする人など、多様な角度からひとつの監視社会を眺めるように物語が展開されています。 ビッグテックと監視社会に関する本を読んでから目にしたので、著者はそのことに関して警鐘を鳴らしたいという意図があるのかな? と思いましたし、「それでもリゾートはなくならない」というお話の展開的に、誰かが流れに掉さしても止められるようなものではない、といううっすらとした絶望感があって、個人的にはそれが「ディストピア要素」の中核ではないかと感じました。 ユートピアの真後ろ、背中合わせにディストピアがある。でも実は、ディストピアに住んでいる側はもう殆ど思考停止していて、ユートロニカ(永遠の静寂)に陥りかけている。だから自分がいるところをユートピアと思っているだけで、実際に「目を開いている」側から見ると完全にそこはディストピア。犯罪者予備軍だと(アルゴリズムのわからない)機械に判断されたら隔離され、矯正される都市。 ……ちょっとゾクゾクする設定だと思いませんか。 しかも、この世界は「今あなた方が生きている世界と地続きですよ」と著者は言っている気がします(あくまで推測ですが)。 何なら、ディストピアSFを通り超えて、ホラー小説の域じゃないかとすら思えます。 欲を言えば、ユートロニカに人々が陥って、社会が機能不全になっていく静かな死(のようなもの)を描写として読んでみたかったな。 コールドスリープとまではいかないものの、同じような反応しか返さない母親を見て息子は何を思うのか。そういう展開を見てみたかったですね。 現代の日本に住んでいる一読者として思ったことのひとつは、アガスティア・リゾートに住める人は(金銭的な面でも精神的な面でも、いろんな意味で)「おめでたい人」「恵まれた人」なんだろうな、ということと、精神病を疑われたら隔離される辺り、日本人の場合は居住区より療養施設の方が大きくなりそうだなー、ということ。 そのまま一生を療養施設に軟禁になったまま終えてしまうであろう老人の手記とか、そういう形の続編を読んでみたい気もしますね。 冤罪をなくすために予備犯罪者を裁く、という理論が出てくるところなんかはリアルすぎるし、明らかな悪手なのに賛同者が多勢になって押し切りそうなところ、とても日本っぽい(舞台はアメリカだが)なと感じました。 「正義だと思っているから暴力に訴える」というのは今のネット社会そのものだし、ただのSFとは思えないリアルさに心を鷲掴みにされた気分です。 派手なSF演出はないですが、今となっては派手過ぎるSF要素は「しらける」こともあるよな、と思ったり。サーヴァントを始めとするゴリゴリのIT近未来要素を出しつつも、そこに焦点を当てず、「考え方」「人間(そのもの)」にスポットライトを当てたところが、個人的には良かった点でした。 借りて読んだ本ですが、半分も読まないうちに「買って読もう!」と思えた本でした。 半年後とかにもう一度読み返したいですね。 本来の本の在り方ってこうだよな、と思い出させてくれた一冊でもありました。 オススメします。
Posted by