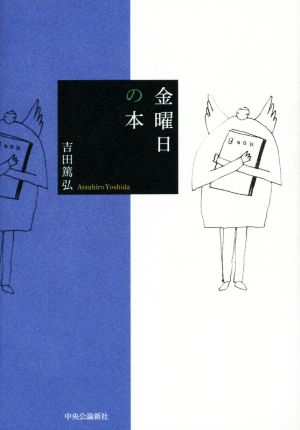金曜日の本 の商品レビュー
吉田篤弘さんの12歳までの自叙伝的エッセイ。 エピソードがトツトツと語られていく。ホントに間の繋ぎがなく、ポツリポツリと進んでいく… 吉田さんの本は、すごくリラックスして読める。精神安定剤のような…心の奥がじんわり温かくなる…そんな文章…風景、心情、人物がすぐに現れて… まず...
吉田篤弘さんの12歳までの自叙伝的エッセイ。 エピソードがトツトツと語られていく。ホントに間の繋ぎがなく、ポツリポツリと進んでいく… 吉田さんの本は、すごくリラックスして読める。精神安定剤のような…心の奥がじんわり温かくなる…そんな文章…風景、心情、人物がすぐに現れて… まず、「金曜日の本」ってタイトルがイイ。 相変わらずの挿し絵もイイ。 たった125ページなのに、そして、もちろん生きた全ての出来事を書いてるわけではないのに、吉田さんの少年時代がありありと浮かび上がってくる。 本好きで、壁新聞をやってみたり、日記を書いていたり、詩を書いていたり… 小説家になる人は、須く、多読、アウトプットもたっくさんやってるよなぁ 親戚のおじさんおばさんたち、友達たち。吉田さんが出会ってきた人たちが、小説作品に出てきたキャラクターの原点なんだなぁと感じた。 「神様のいる街」(高校生から大学生くらいの自叙伝)と同様に吉田篤弘小説ファンには、たまらない一冊だ。 読む順番が逆になってしまったけれど、それはそれで、遡っていく感じも楽しめたかな。 人生には小説的要素が多分にあるんだなぁと感じた。おそらく誰の人生にも…
Posted by
吉田篤弘さんの子ども時代の思い出が語られます。実体験ということですが、読むにつれて、あの物語、その小説に登場した、心がほっこりする場面が出没して、ハッとします。吉田さんの、古き東京への懐かしさが、物語の世界とつながっているのですね。都会ではなく、田園地帯で生まれ育った私ですが、私...
吉田篤弘さんの子ども時代の思い出が語られます。実体験ということですが、読むにつれて、あの物語、その小説に登場した、心がほっこりする場面が出没して、ハッとします。吉田さんの、古き東京への懐かしさが、物語の世界とつながっているのですね。都会ではなく、田園地帯で生まれ育った私ですが、私の懐かしさとも確かに通じていると感じました。
Posted by
914.6 「仕事が終わった。今日は金曜日。明日あさっては休みで、特にこれといった用事もない。つまり今夜から日曜の夜まで、子どものころの「放課後」気分で心おきなく本が読める! ――小さなアパートで父と母と3人で暮らした幼少期の思い出を軸に、いつも傍らにあった本をめぐる断章と、読書...
914.6 「仕事が終わった。今日は金曜日。明日あさっては休みで、特にこれといった用事もない。つまり今夜から日曜の夜まで、子どものころの「放課後」気分で心おきなく本が読める! ――小さなアパートで父と母と3人で暮らした幼少期の思い出を軸に、いつも傍らにあった本をめぐる断章と、読書のススメを綴った柔らかい手触りの書き下ろしエッセイ集。」 子どもの頃の僕は、「無口で」「いつも本を読んでいた」と周りの大人は口を揃える―小説家にして装幀家の、忘れがたい本をめぐる断章と、彼方から甦る少年時代。何度でも、どのページからでも読み返したくなる澄んだスープのような16の随想。文庫化にあたり、新規書き下ろしエッセイ「九人のおじさん」を特別収録。 目次 路地裏の猿 架空バス 夕方の手品師 舞台袖 ポータブル・レコード・プレイヤー 蛇口とヘビイチゴ ブレーキのない自転車 赤鉛筆 ピザを水平に持って帰ること 枕の下のラジオ〔ほか〕
Posted by
『神様のいる街』のあとがきで知ってから、読みたかった本。私の好みの本。 そして、このあとがき(のようなつづきの話)に『おるもすと』が出てきて、あれ、これ持ってるなと思い、本棚から取り出して、なるほどぉと思った。 本と音楽。うんうんと共感することがいろいろあった。 経験というか体...
『神様のいる街』のあとがきで知ってから、読みたかった本。私の好みの本。 そして、このあとがき(のようなつづきの話)に『おるもすと』が出てきて、あれ、これ持ってるなと思い、本棚から取り出して、なるほどぉと思った。 本と音楽。うんうんと共感することがいろいろあった。 経験というか体験というか、生きてきて触れてきたものが吉田さんを通して、ものがたりがうまれるんだろうなぁ、と思った。
Posted by
著者の子ども時代の頃が、ゆるゆると綴られている。 同年代なので、地域は違えど状況に懐かしさを覚える。 図書室に通い本好きであったことも共感できた。 本には「読む時間」の前に「選ぶ時間」がある。 もしかすると、読んでいるときと同じくらい選ぶ時間を愉しんできたかもしれない。 このこ...
著者の子ども時代の頃が、ゆるゆると綴られている。 同年代なので、地域は違えど状況に懐かしさを覚える。 図書室に通い本好きであったことも共感できた。 本には「読む時間」の前に「選ぶ時間」がある。 もしかすると、読んでいるときと同じくらい選ぶ時間を愉しんできたかもしれない。 このことばにも頷けた。 私の中での記憶も小学生低学年か中学年頃だろうか…叔父さんがプレゼントしてくれたタイトルは、「あゝ無情」だったと思うが、この一冊の本が読書好きになるきっかけだったと思う。 本によって感動を覚え、図書室に足を運ぶようになった。 そして、いろいろな本を探し、選ぶということも愉しみにしてたのだと思う。
Posted by
本を読む行為ができることが、すごく幸せだと思える。 小学生の他愛のない日常が、時系列ではなく、どんな理由でそうなったかは想像もつかない順番で並んでいる。 もし、今の自分が
Posted by
作者の幼少期の思い出がぷつりぷつりと綴られたエッセイ。私は作者とは年代が違うため、昔の日記を覗き見したような感覚で読んだ。作者の他の本で出てきたキーワードや物事がこの本に少し出てきて、他の本を読んでいる時にいつも一番近い別世界のように感じていたのは、なるほどそういうことかと何だか...
作者の幼少期の思い出がぷつりぷつりと綴られたエッセイ。私は作者とは年代が違うため、昔の日記を覗き見したような感覚で読んだ。作者の他の本で出てきたキーワードや物事がこの本に少し出てきて、他の本を読んでいる時にいつも一番近い別世界のように感じていたのは、なるほどそういうことかと何だか腑に落ちた。
Posted by
本は、読む以前に、 出逢うこと、選ぶことがある。 大人は、本を読みなさいと言うわりには、 出逢い方、選び方は教えてくれなかったな、と思う。 借りる本と買う本の違いなどもなるほどと思う。 本を買うことは、 その本を読むという未来を買うということ。 本当にそうだな、と思う。
Posted by
少年時代の思い出を綴ったエッセイ+短篇小説。吉田篤弘の生み出す物語は、作家と作品が切り離せないと、エッセイを読むたびに思う。家族や親戚、友人に同級生、諸々のエピソードが、これまでに読んだ小説の登場人物やシーンに繋がってゆき、また読み返したくなる。著者が愛読した本に「読めばかならず...
少年時代の思い出を綴ったエッセイ+短篇小説。吉田篤弘の生み出す物語は、作家と作品が切り離せないと、エッセイを読むたびに思う。家族や親戚、友人に同級生、諸々のエピソードが、これまでに読んだ小説の登場人物やシーンに繋がってゆき、また読み返したくなる。著者が愛読した本に「読めばかならず気分がよくなる」と感じた気持ちは、いつも私が著者の作品に感じていること。金曜日の夜に読めば和やかな週末を送れそう。
Posted by
『本とつきあうときはひとりでいることが重要なのだと子供ながらに気づいていた。土曜日の学校帰りだ。あのころは土曜日が金曜日だった』―『路地裏の猿』 ああそう言えば土曜日の午後は何を置いても草野球だったなあ。そして野球が終わった後も暗くなるまで遊び続けた。 クラフト・エヴィング商...
『本とつきあうときはひとりでいることが重要なのだと子供ながらに気づいていた。土曜日の学校帰りだ。あのころは土曜日が金曜日だった』―『路地裏の猿』 ああそう言えば土曜日の午後は何を置いても草野球だったなあ。そして野球が終わった後も暗くなるまで遊び続けた。 クラフト・エヴィング商會の吉田篤弘の昔語りは、いつもうっかり信じてしまうような語り口(「あとがきのような話のつづき」には本当にあったことだと綴られているけれど、要注意)。しかもうっかり信じてしまうだけではなくて、何故だか忘れていたような昔のことをいつの間にか思い出したりするのだ。 『メンマ工場と菓子工場のあいだに、ドイツから転校してきたB君の家があった。B君は少し太っていて、まつ毛が長く、横長の変わった形をした焦茶色のランドセルを背負っていた』―『架空バス』 例えば、横長の焦茶色のランドセルという言葉から、坂田くんのことを思い出すと同時に草野球のことも思い出す。野球が上手だったから、ではなくて、坂田くんの動作がとてもぎこちなかったからだ。大袈裟な動きでピッチャーの球を受け止める坂田くんは、よく足の速い子に「ミットはストライクゾーンに持って来ないとダメだ!」と注意されていたっけ。 坂田くんがドイツの小学校から転校してきたことは、家に遊びに行ったときに見せてもらった横長の焦茶色のランドセルを見せてもらうまで知らなかった。ぼくらと一緒に遊ぶようになるまで野球をしたことが無かったんだなということは大人になって後からわかったこと。 和泉くんの家には大きな秋田犬がいて、初めの頃は広い庭に放されていたけれど、その内に頑丈な檻の中に入るようになった。一緒に遊んでいても怖い思いをしたことはなかったので可哀そうには思ったけれど、和泉くんの持っていた「のらくろ」が見たい気持ちの方が強くて秋田犬のことにいつまでも気を取られてはいなかった。そう言えば和泉くんの家の方に絵の上手な同じ保育園出身の子が居て、洋風の家で一緒に鉄人28号の絵を描いたりして遊んだのだけど、その子に本物の拳銃のようなモデルガンを見せて貰ったことがあった。「秘密だよ」と言われて誰にも言ったことが無かったけれど何故か急に思い出した。 薄い茶の色付き眼鏡をしていた中島くんとは何故か仲が良かった。お互いに鍵っ子だったからかも知れないけれど、中島くん以外は誰もいない彼の家に遊びに行ってはツル・コミック版のピーナッツを飽きることなく黙って読み合った。そういえば中島くんの眼鏡に色が付いていたのはどうしてかなんて、その頃は疑問にも思わなかったのに今気が付いた。 「木挽町月光夜咄」の時もそうだったように、吉田篤弘の語りは、本当にあったことと作り変えられた記憶が奇妙に地続きで混在している。あるいは事実と想像が上手く混ぜ合わされていると言ったらよいか。そう言いながら、本当にあったことと作り変えられた記憶とが一緒くたになっていないことなんてあるのかなとも考え直す。寧ろ過去の記憶なんて自分の都合の良いように脳内で再構築されているものと考えた方が安全だとの見方もある。でも何故か、そういう嘘とも本当とも区別のつかない記憶の物語を辿るのには麻薬のような魅力がある。もちろん、中毒になったりしないよう、余りそのノスタルジックな世界に逃げ込まないようにしなければならないけれども。
Posted by