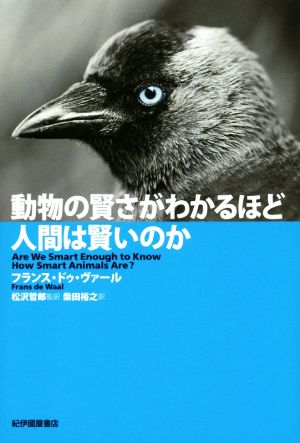動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか の商品レビュー
異なる立場の考え方に対する攻撃的な口調に終始する。淡々と語ってくれたら興味深い内容なのだが、読んでいて怒りのはけ口にされている気分になる。
Posted by
賢さには、たくさんの種類がある。 例えば、言語。 人間は言葉を喋る。犬や鳥は、今のところ人間の言葉を喋らない。だから、犬や鳥は無能なのか? 犬は人間の1億倍ほどの嗅覚をもつ。 鳥は宇宙を駆ける翼をもつ。 どちらも人間にはない能力である。 種によって、または人によって、賢さの基準は...
賢さには、たくさんの種類がある。 例えば、言語。 人間は言葉を喋る。犬や鳥は、今のところ人間の言葉を喋らない。だから、犬や鳥は無能なのか? 犬は人間の1億倍ほどの嗅覚をもつ。 鳥は宇宙を駆ける翼をもつ。 どちらも人間にはない能力である。 種によって、または人によって、賢さの基準は違うんだな、と考えさせられた本だった。
Posted by
人間は、動物と同じ生物種としての連続性の中で理解すべきとし、ユクスキュル的な動物主観的視点から、動物の認知と知能に関して紹介した著作。
Posted by
宗教上の理由で無意識に人間と動物を分けて考えてる生物学者が多くて動物独自のIQの高さをきちんと研究出来ている学者が少ないって本。 そもそもなんでチンパンジーのIQテストに人間の顔写真の識別をさせるのか、人間はチンパンジーの見分けがつかないのと同じでチンパンジーも人間の見分けはつ...
宗教上の理由で無意識に人間と動物を分けて考えてる生物学者が多くて動物独自のIQの高さをきちんと研究出来ている学者が少ないって本。 そもそもなんでチンパンジーのIQテストに人間の顔写真の識別をさせるのか、人間はチンパンジーの見分けがつかないのと同じでチンパンジーも人間の見分けはつけづらい。木登りに特化したテナガザルに何故かスプーンを渡して動作テストをしたり人間基準で考え過ぎてて動物の適性検査が出来ていない。 無意識のうちに人間は他の動物よりも優れていると考える節がある為、人を動物のカテゴリーに含めるとそれを感情論で批判する学者がいる影響で動物行動学の発展が遅れているんじゃないかみたいな内容の本でした。 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか
Posted by
非常に興味深く、面白い内容だった。かなり愚痴っぽいところがあり最初は辟易したが、それ以上に動物たちの行動が興味深く、どんどん読み進めていけた(とはいえ読むのにかなり時間はかかった) 研究者の著書としては一般人にとてもわかりやすい文体で書かれていて、専門用語のオンパレードといった取...
非常に興味深く、面白い内容だった。かなり愚痴っぽいところがあり最初は辟易したが、それ以上に動物たちの行動が興味深く、どんどん読み進めていけた(とはいえ読むのにかなり時間はかかった) 研究者の著書としては一般人にとてもわかりやすい文体で書かれていて、専門用語のオンパレードといった取っ付きにくさは皆無。ますます動物たちが好きになり、愛が深まった。 収斂進化が思ってもみなかったところで起きていること、そもそもこれは収斂進化であるという気づきがあったのが、個人的なポイント。
Posted by
辛島における猿の芋洗い行動の伝播は教科書に載るほどに有名だが、それがいかに衝撃的であったかは本書でも取り上げられている。いわゆる「サル学」の分野では日本は間違いなく先進国で、辛島の報告を行なった今西錦司、本書に解説を寄せた松沢哲郎などは本書内ではほとんどレジェンド扱いである。本...
辛島における猿の芋洗い行動の伝播は教科書に載るほどに有名だが、それがいかに衝撃的であったかは本書でも取り上げられている。いわゆる「サル学」の分野では日本は間違いなく先進国で、辛島の報告を行なった今西錦司、本書に解説を寄せた松沢哲郎などは本書内ではほとんどレジェンド扱いである。本書は、彼らに強く影響を受けた「サルと寿司職人」などの著者が、動物行動学と比較心理学を統合した新しい学問分野を紹介するもの。 B・F・スキナーらが創始した比較心理学では、動物を人間心理のモデルとして扱いながらも、「連合学習」を重視するあまりそれぞれの動物の置かれた環境を軽視する傾向があった。これに対し、動物固有の「ウンヴェルト(環世界)」と動物の行動の因果関係を重視する動物行動学に、人間中心ではない動物たちの「認知」を研究の中心に据えるドナルド・グリフィンの知見を加えた「認知動物行動学」を対峙させつつ統合したのが著者の唱える「進化認知学」。これによれば、生物の認知機能はそれぞれの生き物の必要性に適応しつつつ進化した、ということになる(「生物学的に準備された学習」)。逆に言えば、必要とされるならば異なる生物に同じ(相似)能力が別々に現れる(収斂進化)のだ。 著者は数々の有名な動物の認知に関わる実験を挙げ、人間の認知が特別だとする言説に改定を迫る。例えば、言語の使用が人間の思考過程を特別なものにした、とする定説を批判し、多くの動物はボディランゲージなどの自らの環境に準備された情報を学習して利用していることを見落とすべきでない、とする。同様に、他者の心理を推測する「心の理論」についても、ある行動の模倣の際、行為者の意図まで汲み取る「真の模倣」についてはむしろ人間よりも類人猿によく当てはまることを指摘する。また、動物実験の手法についても人間中心の環境設定をするのではなく、動物たちが通常置かれた生態的・社会的環境を考慮した設定にすることで、認知機能は人間にのみ発現した跳躍などではないことが実証されるはずだとする。 アリストテレスの「自然の階梯」を著者がまるで人間を頂点とするヒエラルキーを表現したものであるかのように批判的に扱っているのが少々気になるが、アリストテレスの意図は勿論そのようなものではなく、「神は跳躍しない」即ち生物宇宙の構成には断絶はないことを表したもので、むしろ著者の意見とベクトルが同一だ。はじめから認知に関わる帰納的な一般論を探究するのではなく、それぞれの事例研究から認知に共通する構造を炙り出していくという進化認知学の手法も、偏執的なまでにフィールドワークに拘ったアリストテレスと通じるものがあると思う。
Posted by
面白かった 驚くような事例がたくさん上がっている 行動主義者への批判がやりたいのはわかるが、それが執拗に繰り返されるのは鬱陶しい それはもういい、わかったから、て感じで この手の本でよく思うのは、観察事例と解釈とは分離して書いてくれたらいいのに、ということ もちろん、本文のな...
面白かった 驚くような事例がたくさん上がっている 行動主義者への批判がやりたいのはわかるが、それが執拗に繰り返されるのは鬱陶しい それはもういい、わかったから、て感じで この手の本でよく思うのは、観察事例と解釈とは分離して書いてくれたらいいのに、ということ もちろん、本文のなかで混乱して何が解釈で何が観察かわからない、というようなことではない そういう基本的なことでは十分、わけられてはいる。 のだけども、例えば、新しく紹介された事例を読んで、それとさっき読んだ事例を比較したい!みたいなのが起こってくるので、そんなときの検索しやすさとして。 「タコの心身問題」も面白かったけども、これも面白かったなー
Posted by
秀逸なタイトルだと思う。本書の主眼は、動物にはそれぞれの「ウンベルト」があり、それゆえ動物それぞれの特性を理解しなければ、その世界を理解することはできない、ということにあると思えるからである。そして、このタイトルは、それを探求していく進化認知学という著者が提唱する学問の方法論を見...
秀逸なタイトルだと思う。本書の主眼は、動物にはそれぞれの「ウンベルト」があり、それゆえ動物それぞれの特性を理解しなければ、その世界を理解することはできない、ということにあると思えるからである。そして、このタイトルは、それを探求していく進化認知学という著者が提唱する学問の方法論を見事に表現している。なぜ、チンパンジーが人の顔を見分けるテストを行うのか、チンパンジーの顔を見分けるテストを行うのが本来ではないのか?というわけである。本書で紹介されている動物たちの生態が興味深いのはもちろんだが、いったい、人間はどうすれば動物たちそれぞれのあまりにも異なる世界を把握できるのか、学問の進化としても大変に面白い。進化ということを考えたとき、人間だけが特別ということはないし、すべての種が必要な進化を遂げて環境に最適化している、という視点はとても重要に思える。
Posted by
進化認知学:人間とそれ以外の動物の心の動きを科学的に解明する学問を一般向けに教えてくれる本。著者は動物行動学の権威である。 いわゆる「動物」が、人間に劣らない認識力や文化さえ持っているのは、NHKの「ダーウィンが来た」とかを見ていると「当たり前じゃん?」くらい思うことなんだけど...
進化認知学:人間とそれ以外の動物の心の動きを科学的に解明する学問を一般向けに教えてくれる本。著者は動物行動学の権威である。 いわゆる「動物」が、人間に劣らない認識力や文化さえ持っているのは、NHKの「ダーウィンが来た」とかを見ていると「当たり前じゃん?」くらい思うことなんだけど、まあ、そう思うのはただのイメージにすぎない。 そこに、本当に科学的な知見を与えてくれるのがこの本で、これまでの「動物は人間より劣るもの」という理解に一石を・・・いや一鉄槌を投じるものである。 話はすごく面白い。 例えば人間は、象やチンパンジーの知能を量るために、棒を持たせたり失敗した時のペナルティを課したりする実験を行い、上手く行かないからと言って「劣」のレッテルを貼ったりする。 しかしもともとそれらは、彼らの関心や生活実態にない道具なんだから、使いこなせなくて当然なのである。つまり実験とか言いつつ、所詮は人間の尺度、上から目線に過ぎないのである・・・云々。 すごく面白いんだけど、うーん、翻訳が非常にまずい。逐語的には正確なのかどうか、全然意味が伝わって来ない悪文のオンパレード。いかにも、内容をまったく理解していない訳者と、この本を読んで学ぼうかという読者のことをまったく考えていない監訳者の共同作業といった趣である。訳者は類書をいくつも翻訳しているので、内容を理解していないというわけではなさそうだけど。(監訳者は「非常に読みやすい訳」と評価している) 翻訳のまずさがわかるほどオレは日本語ができるのか、という辺りは内緒で・・・。
Posted by
ぼくは動物は、少なくとも哺乳類は、それなりにものを考えていると思っている。当然感情も意思もあるし、個性もある。ペットの犬や猫と一緒に一緒に暮らした経験を通して、それを疑う理由はなかった。人間に比べればバカだなあ、単純だなあと思うことはあったけれど、それを言うなら連中だって人間を見...
ぼくは動物は、少なくとも哺乳類は、それなりにものを考えていると思っている。当然感情も意思もあるし、個性もある。ペットの犬や猫と一緒に一緒に暮らした経験を通して、それを疑う理由はなかった。人間に比べればバカだなあ、単純だなあと思うことはあったけれど、それを言うなら連中だって人間を見て、足遅っ、とか、ネズミも獲れないんだ、と思っているだろう。逆に言えば人間と、人間以外の動物の違いはその程度だ。程度の違いであって、質の違いではない。 だから猿が芋を洗う、カラスがクルミを道路に落として車に割らせる、と聞けば、へー(思っていたより)頭いいんだ、とは思うが、意外だとは思わない。群れで暮らす猿や狼やイルカたちは、言葉に代わる方法でコミュニケーションを取ってて不思議はないと思う。人間ができることを、動物がやってはいけない理由はないだろう。 ぼくはずっと、ほかの人もそう考えているだろうと思っていたのだが、欧米の動物学の本を読んでいると、たまにどうもそのあたりの出発点が違うんじゃないかと思うことがある。デカルトは動物には魂(?)がなく、自意識もなく、単に刺激に反応しているだけである、という説を唱えたらしいが、ひょっとしたら未だにそういう見方が基本にあるんじゃないだろうか。だからこそ科学的に動物の振る舞いを調べる方法論が発達したのかもしれないけれど。 本書はつまらなくはないのだけれど、動物にも当然知的能力があるよね、と思っているぼくのような読み手にとっては、驚きはあまりない。
Posted by
- 1
- 2