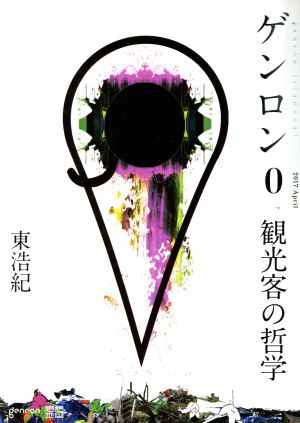ゲンロン0 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
政治に他者に関わることなく引きこもって自らの欲求を追求して暮らすことが可能な動物の時代。神も国家もアイデンティティの拠り所として機能せず、グローバルリズムを否定するためにテロリストでさえふわふわした浅薄な理由で(動画を見て)生まれる。テクノロジーとグローバル化により均質になっていく世界で、数々の哲学者の論説をひもときながら人はどうあるべきか模索する。 本来は世界市民となるはずだった現代人はリベラリズムに疲れはて、リバタリアニズムとコミュニタリアニズムに分裂している。グローバリズム(経済的利益、肉体関係)はナショナリズム(政治、恋愛関係)を取り残したまま歪な秩序として浸透したのだ。SNSやLGBT運動に見られるネットと愛さえあればどうにかなるというマルティテュードも実効性が薄い。 シンギュラリティは空想社会主義にすぎず、仮想現実世界では匿名性がフェイクニュースやヘイトなど悪い意味で現実を侵食していく。 筆者は観光客=二次創作だと主張する。観光とはまさに産業社会によりうみ出された産物、大衆消費行動だ。しかし観光は単なる娯楽であると同時に誤配を生み、偶然性によって人の視野を広げ社会を繋げ直す。そして観光客は訪れる場所を観光地に変える。観光客は無力ではない。 国という概念が機能しなくなったテロリズムの問題は文学の範疇にあると筆者はとく。ドフトエフスキーの地下室人の手記、カラマーゾフの兄弟、悪霊について取り上げている。強制されると反発するためだけに反発するのが人の性。人はライプニッツ的理想の世界に殉じようとするが、現実の不条理に耐えられなくて絶望してテロリストとなり、さらにどちらの態度からも離れた無関心なニヒリストとなる。ニヒリストを克服するには、不能な父(観光客)となるしかないという。そして解決は次の世代に託し、そしてまたテロリストが生まれていく…。終わりなき円環の中に人は生きていくと筆者はしめくくる。
Posted by
確かに過去のどのゲンロンよりも読みやすい(カラマーゾフの兄弟は再読しないといけないけど)。観光客という響き、家族という言葉に対して扱う内容は深い。2017年の、いま、この環境において、いかに他者と関わることができるのか、世界とどうつながることができるのか、社会をつくることができる...
確かに過去のどのゲンロンよりも読みやすい(カラマーゾフの兄弟は再読しないといけないけど)。観光客という響き、家族という言葉に対して扱う内容は深い。2017年の、いま、この環境において、いかに他者と関わることができるのか、世界とどうつながることができるのか、社会をつくることができるのか。それが「観光客」で、そして「家族」であるというのがたどり着いたところ。誤配された家族的類似性。これから第二部の内容をどう深めていくのかが、文字通り親である東浩紀と東チルドレンの宿題。
Posted by
2017.4.1-2017.4.9 お勧め。 読後に思つたことをブログに書きました。(全4回) https://blogs.yahoo.co.jp/yoshiharajya/55759883.html
Posted by
不思議な本である。そして同時に傑作である。 本書のテーマは重い。極めて重い。今の世界が直面する困難の構造を析出し、それを突破する主体を構想する。それが本書の目的である。ところが、その重すぎるテーマを前にして本書の叙述スタイルはなんだかとっても妙だ。文章はわかりやす過ぎるほどに明...
不思議な本である。そして同時に傑作である。 本書のテーマは重い。極めて重い。今の世界が直面する困難の構造を析出し、それを突破する主体を構想する。それが本書の目的である。ところが、その重すぎるテーマを前にして本書の叙述スタイルはなんだかとっても妙だ。文章はわかりやす過ぎるほどに明快であり、哲学書・思想書にありがちな晦渋さとは無縁。随分くだけた表現もあり、場違いなほど俗っぽい物言いに思わず吹き出してしまうこともしばしばだった(とはいえ、これは東の話術=トークにおいてはおなじみのものだが)。もともと著者・東は複雑なものをシンプルに整理して提示する達人だが、本書ではその技術がいよいよ究められつつあるように感じられる。 全体の構成も面白い。本書は二部構成で、第1部ではまず今の世界のありようを描き、それに抵抗する主体として観光客=郵便的マルチチュードなる概念が提示される。この新しい主体のアイデンティティの在り処を探るのが第2部となる。詳細については実際に読んでもらえればいいのだが、東は上記のストーリーを描き出すために多様なモチーフを呼び出している。観光学や政治哲学を参照して記述する第3章あたりまではいいとして、第4章以降はネットワーク理論に情報社会論(サイバースペース論)にドストエフスキー論と怒涛の展開である。さらに第1章のあとに挿入される付論では東の過去の仕事であるオタク論および福島第一原発観光地化計画についても言及され、本書との接続が図られている。このような混淆性により、本書を読むことそれ自体が一種の知的観光となっている。まさに構成の妙と言えよう。 以上のような独特の叙述スタイルは、課せられたテーマの深刻さにもかかわらず、本書をさわやかで風通しのよいものとしている。この「まじめ」と「ふまじめ」の同居こそ、本書の不思議な印象の正体だろう。 内容については下手な要約をするより実際に読んでもらうのが一番だと思う。大変刺激的な議論である。第2・3章の近現代政治哲学の鮮やかすぎる整理は大変勉強になった。第4章で試みられる社会思想とネットワーク理論の接続は驚くべきアイデアであり、今後賛否両論を呼ぶことになるだろう。第6章は東の初期の仕事であるサイバースペース論のアップデート。第7章(最終章)のドストエフスキー論は感動的ですらある。 ついでに言うと、本書は「東浩紀による東浩紀入門」としても読むことができる。前述した「多様なテーマ」とは、つまりは東が過去に取り組んできた仕事の集積であり、それを「観光客」というパースペクティブから再構成し、そこに新しいアイデアを加えてできたのが本書ということになるだろう。これまで東浩紀の最初の一冊は『動物化するポストモダン』か『弱いつながり』あたりだったのかもしれないが、これからは間違いなく本書となるはずだ。入門したところから一気に最前線まで連れていってくれるのだから贅沢なものである。
Posted by