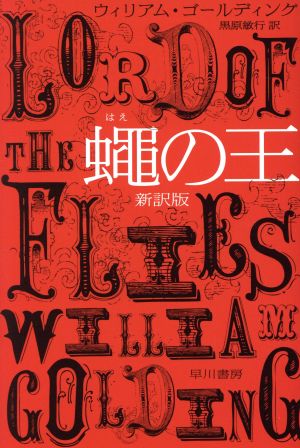蠅の王 新訳版 の商品レビュー
実に子どもらしい子どもたち。ルールを作っても守らない、自分がやりたいことへの衝動を抑えられず、作業に協力しない姿など、非常にリアル。しかし、大人ならしっかりルールを守って何ヶ月も火の番ができるか?暴力なしに協力して生き抜けるか?かなり、怪しい。人間の本質がこの物語の指摘の通りだと...
実に子どもらしい子どもたち。ルールを作っても守らない、自分がやりたいことへの衝動を抑えられず、作業に協力しない姿など、非常にリアル。しかし、大人ならしっかりルールを守って何ヶ月も火の番ができるか?暴力なしに協力して生き抜けるか?かなり、怪しい。人間の本質がこの物語の指摘の通りだとしたら、どうやって社会を作っていったらいいか、考えさせられる。少なくとも、ルールをどんどん増やすだけでは、意味がないとよく分かる。
Posted by
1950年代に書かれた人間の根源的、性質的部分を自身の体験をもとに宗教的要素を絡めながら物語として描かれた作品。 時代背景などを考えながら、なぜ「蠅の王」なのか、自分がもしこの一員だとした、などと考えながら読んでいくとこの物語の恐ろしさを体感、実感できる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
子供だけの楽園だと思っていたが・・・最後には・・・。 最近日本でもイノセンツという映画が公開されていましたが、それと同じで子供って実は残酷なんですよね。 子供だけではなく本来人間の内にはこういう残酷な1面がみんなにあって、それを理性で抑えてるだけなんですよね。 第十二章の最後の展開には今までのゆったりとした展開からのギャップが凄く食い入るように読んでしまいました。
Posted by
序盤から不穏な空気が漂っていて、ページをめくる手がとまりませんでした・・・!どうすればこうならなかったんだろう・・・と読後もああでもないこうでもないと考えを巡らせてしまう。モヤモヤするけど読めて良かった名作です!
Posted by
読んだことがないけど、これは十五少年漂流記の逆バージョンなんだね 少年たちの集団の在りかたは社会の縮図で、ラルフとジャックの力関係の流れを見て、チラッと『動物農場』を思い出したりした ラルフが途中、煙を絶やさないことが一番大切なのに誰もかれもその重要さをわかっておらず、自分も...
読んだことがないけど、これは十五少年漂流記の逆バージョンなんだね 少年たちの集団の在りかたは社会の縮図で、ラルフとジャックの力関係の流れを見て、チラッと『動物農場』を思い出したりした ラルフが途中、煙を絶やさないことが一番大切なのに誰もかれもその重要さをわかっておらず、自分もまたそれを忘れてラクなほうへ流されて生活してしまうことを吐露していたのが印象的だった。 ルールを守ること、それぞれの役割を果たすことを誰もができていない。そしてそれらをおチビたちに教育することも思いつけずにいる。だけど多分、それが普通の少年たちの姿なんだとこの本は突きつける。
Posted by
無人島に不時着した飛行機、そこで生き残った子供達による生活を描いたものであるが、新訳版ということもあり、非常に読みやすくはあったものの、西洋の文化的な下地などをあまり理解できていなくても考えさせられるのは名作たる所以なのであろう。 果たしてこの作品の主人公ラルフは何歳の設定で...
無人島に不時着した飛行機、そこで生き残った子供達による生活を描いたものであるが、新訳版ということもあり、非常に読みやすくはあったものの、西洋の文化的な下地などをあまり理解できていなくても考えさせられるのは名作たる所以なのであろう。 果たしてこの作品の主人公ラルフは何歳の設定で、一体どの程度の人数が不時着し、何日ほど島で過ごしていたのであろうか。これらをあまり絞りすぎていないからこそ想像に頼らざるを得ない。 そもそも子供たちによる自治について、この作品では失敗に陥っているのであるが、何故にそうなったのかを考察することは、必要不可欠であろう。その要因たるものとして、集団心理より人の残虐性や人より優りたいという虚栄心にも似た欲望など、子供であろうとさまざまなものを人は元来有しているからなのであろう。 それは極限まで追い詰められればこそ判断・考えを超えたものが滲み出てくるのであろう。 火を起こすことにより、救助を求め続けることが正常な判断によるもので、これを正しいものとして描かれると反対に、豚を殺してその肉を食べるというのは何処か野蛮で悪を感じさせる描かれ方をしている。 しかし現実的に狩りを実行して食糧を確保するというのは生きていくことに欠かすことが出来ないもので、人間として「食べる」ことは何よりも優先されるべきものであり、そう考えればやはりそれを悪と捉えるとすれば、原罪的に人は悪の種子を有しているものと捉えられよう。 そしてどうして互いに反発し争わなければならなかったか。そこまでまだまだこの作品を読み込めていないのが本音である。
Posted by
無邪気な子供達が大人のいない自由な無人島で生活していくと……!? という話だったのですが、私のような捻くれた性格の人が読むと「そうなるのだろうな」と少し冷めた気持ちになってしまいました。 恐らくこの作品が書かれた当時としてはトンデモナイ衝撃作だったのだろうと思いますが、ネットの...
無邪気な子供達が大人のいない自由な無人島で生活していくと……!? という話だったのですが、私のような捻くれた性格の人が読むと「そうなるのだろうな」と少し冷めた気持ちになってしまいました。 恐らくこの作品が書かれた当時としてはトンデモナイ衝撃作だったのだろうと思いますが、ネットの評価で言われるほど狂った作品ではありません。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
私はこの作品における「ほら貝」は組織や社会といったシステムのメタファーであると考えた。強いカリスマ性を持つものが作り上げた組織ではそのリーダーが強い発言権を持つ。しかし、それはリーダーであるもののカリスマによって成り立っているものであり、民主的な行動(組織全体に発言権を持たせたり平等に接し合うこと)を行うのは有効ではない。また、物語終盤でほら貝が破壊されたのはシステムの崩壊を暗喩している。カオス状態の環境でシステムを維持するのは難しく、これまでのリーダーの行動に異議や不満を抱いていたものがそのシステムを崩壊させる行為はまさしく世界の縮図であると感じた。 非常に面白く色々と考えさせられる作品だった。
Posted by
展開がテンポ良くだがじわじわと状況が変わるのが伝わり、書き方がシンプルで良い。 人間の獣性をよくかけてる
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
子どもというものは大多数が周囲の環境によって簡単に染まってしまうほどの純朴さをもち、悪か善かどちらになるかは周囲の環境ないしリーダーの存在性(カリスマ的素養)に依存する。刹那的であり、自己保身的である。責任をもつものが存在していない完全なる自由の或る地とは、楽園にも地獄へも姿を変えることができるが人間である限りは楽園となるとはないであろう。大義名分・言い訳・事情、言葉としては何でもよいが理由さえ存在すれば他者を自己利益のために侵害することができるのだから。ここでいう蠅の王とは恐怖の雰囲気そのものであり、これ自体に力はない。しかし一度蔓延してしまえば簡単には収束されず、子供ほどの純たるものしか存在しないのであればなおのことである。
Posted by