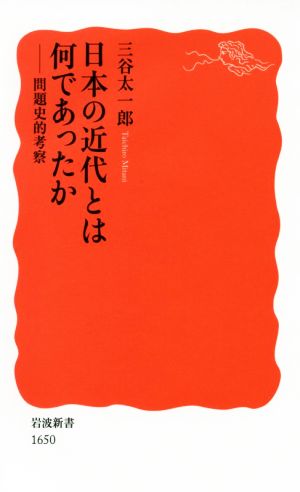日本の近代とは何であったか の商品レビュー
明治以降の日本の体制について研究した本。政治体制、資本主義、帝国主義、天皇制について詳しく述べている。知らなかったことが多く、勉強になった。ただし項目によっては、特に、植民地獲得の拡張的政策については違和感のある論述もあった。はっきりとは言えないが、なにか違うような気がしてならな...
明治以降の日本の体制について研究した本。政治体制、資本主義、帝国主義、天皇制について詳しく述べている。知らなかったことが多く、勉強になった。ただし項目によっては、特に、植民地獲得の拡張的政策については違和感のある論述もあった。はっきりとは言えないが、なにか違うような気がしてならない。学術的ではあった。 「日英の政治には、決定的な違いがありました。英国には自由主義的伝統、とくにその主要な要素である「個人の尊重」の伝統が影響力をもっていたのに対し、日本にはそれはたしかになかったのです」p18 「(マックス・ウェーバー)合議制というのは行政任務の専門家が進行して、専門家が不可欠となってくるような状況において、支配者が専門家を利用しつつ、しかも専門家の優勢がますます増大していくという傾向に対応して、自己の支配者としての立場を守ろうとする目的意識に適合した典型的な形式です。つまり、支配者は合議制によって、それに参与する専門家たちを相互に競わせ、それを通じて彼らをコントロールする」p44 「大久保利通の海運保護政策は、徹底して三菱会社に及ぼされました。大久保は内務省駅逓寮に所属していた汽船13隻を挙げて三菱に付与し、補助金年25万円を14か年にわたって給付することとしました。また廃藩置県後に政府が諸藩所有の汽船を収め、これらをもって組織させた郵便蒸気船会社が危機に瀕した時、大久保の提議によって所有船18隻を政府が購入し、これらも三菱に付与しました。こうして政府の厚い保護を受けた三菱は沿岸航路から外国海運業者を駆逐し、極東海域全域を掌握することになります」p94 「日本が欧米諸国との間で大使の交換を認められるのは日露戦争後のことです。日露戦争の勝利によって日本は国際社会においてはじめて一等国として認知され、実質的意味の国際社会のメンバーとなったのです」p150 「朝鮮ではついに一度も文官総督が出現しなかったのとは対照的に、台湾総督には九代にわたって文官が任命されます」p179 「挑戦と台湾における教育について、日本人と現地人とを分けず、同一勅令によって規定し、実質においては日本人と現地人との間に、ある範囲の共学を実施するとともに、大学教育の導入等現地人に対する教育水準の引き上げを図った」p182 「教育勅語のいう、天皇の祖先が忠孝の徳を立て、臣民が心を一にして世々その美をなしてきた。これこそわが国体の精華であって、教育の淵源もまたここに存する」p228
Posted by
日本の近代=明治維新 西洋の近代=神 http://blog.livedoor.jp/yamasitayu/archives/52172300.html
Posted by
政党政治・資本主義・植民地・天皇制を切り口に日本近代史を総論しようとする一冊。 大ベテランの先生こそ専門の研究領域の総論を書くべきだと思うので、こういう本は大事。「青春期の学問」ではできない「老年期の学問」として総論を書くというスタンスもある意味正しい。ただ「最近の研究成果を踏ま...
政党政治・資本主義・植民地・天皇制を切り口に日本近代史を総論しようとする一冊。 大ベテランの先生こそ専門の研究領域の総論を書くべきだと思うので、こういう本は大事。「青春期の学問」ではできない「老年期の学問」として総論を書くというスタンスもある意味正しい。ただ「最近の研究成果を踏まえていない」という批判をかわす方便というか、開き直りにも見えて、なんだかなぁという気持ちにもなる。。。 自分には少し難しかったので要再読だけど、資本主義の章はちょこちょこ気になった。たとえば不平等条約の下では外資に依存しない資本主義にならざるをえなかったとか、自国文明への「恥」の意識が近代化の促進要因になったと書かれている。面白い理解なんだけど、ずいぶん消極的な印象も受ける。本当にそうなんだろうか。
Posted by
日本の近代について、政党政治、資本主義、植民地、天皇制という4つの点から考察。 教科書で習うような近代の概念をさらに深掘りし考察を加える。 部分的に見れば、近代の概念を覆される。特に意識をしなければ、戦前=近代は遠いものだとどこか自分の離れたところに置いていたが、その形成過程...
日本の近代について、政党政治、資本主義、植民地、天皇制という4つの点から考察。 教科書で習うような近代の概念をさらに深掘りし考察を加える。 部分的に見れば、近代の概念を覆される。特に意識をしなければ、戦前=近代は遠いものだとどこか自分の離れたところに置いていたが、その形成過程を見ることで、当時を生きた人々がどのような考えに基づいて「近代」を作ったかが考察でき、その制度の合理性および非合理性について整理することができる。 ある程度まとめて言えば、制度とは、なんらかの一貫した意図を持って形成されるのではなく(もちろん形成する当初は一貫した意図があるのだろうが)様々な意図や環境が混じり合って出来るものだと思われる。日本の戦前の政治制度は最終的に戦争に向かい破綻したが、その政治制度は当初からその結末を迎えるように作られたのではなく、合理性を求め作られ、しかし他面的には非合理であり、破綻を迎えた。 現状の政治制度でも、ある面では合理的でも、大きく非合理な面もあるのかもしれない。
Posted by
総論・俯瞰的な近代の考察。 ・慣習から議論へ ・自立的資本主義の条件 ・国際的資本主義への転換 ・国体と政体
Posted by
序論のバジョット論はとっつきにくかったが,日本の具体論に入ってからは楽しく読めた.「議論による統治」を標榜してそれを実現してきた明治国家の政治面での動き,さらには大久保利通を元とする経済面での展開もおおよそ理解できたと思っている.議会の中での枢密院の存在をクローズアップして,植民...
序論のバジョット論はとっつきにくかったが,日本の具体論に入ってからは楽しく読めた.「議論による統治」を標榜してそれを実現してきた明治国家の政治面での動き,さらには大久保利通を元とする経済面での展開もおおよそ理解できたと思っている.議会の中での枢密院の存在をクローズアップして,植民地に対する法制度の動きは特に面白かった.台湾と朝鮮では大きく異なっていることも知らなかった.最後に出てきた「教育勅語」の成立する過程の話は天皇と憲法との絡みがあることだと知り,意外な事実だった.歴史の授業は近代史まで進まなかった記憶があるが,教えておく必要があると感じている.
Posted by
幕末から明治の時代、自分はその時代を生きたわけではないので想像することしかできないけど、きっと庶民ですら社会の激変を肌で感じたのだろうと思う。その改革には良いこともあれば悪いこともあった。端的に言えば西欧列強に倣った帝国主義が禍根を残し、現在の外交にも影を落としている。決して遠い...
幕末から明治の時代、自分はその時代を生きたわけではないので想像することしかできないけど、きっと庶民ですら社会の激変を肌で感じたのだろうと思う。その改革には良いこともあれば悪いこともあった。端的に言えば西欧列強に倣った帝国主義が禍根を残し、現在の外交にも影を落としている。決して遠い昔の話ではなく、今日の我々の生活にも脈々と受け継がれているトピックを知ることができる。
Posted by
日本の近現代史に疎いので勉強しようと買ったのだが、知りたかったものとは違ったので当てが外れた。 序章から第二章まではよくわからなかったので読み飛ばした。ただ、教育についてと良妻賢母については記憶にとどめたい。 後半は面白かった。特に教育勅語はいかに作られたのか、はとても興味...
日本の近現代史に疎いので勉強しようと買ったのだが、知りたかったものとは違ったので当てが外れた。 序章から第二章まではよくわからなかったので読み飛ばした。ただ、教育についてと良妻賢母については記憶にとどめたい。 後半は面白かった。特に教育勅語はいかに作られたのか、はとても興味深い。井上毅についてもっと知りたい。
Posted by
副題に「問題史的考察」とあるように、「政党政治」「資本主義」「植民地」「天皇制」という近代日本の根源に関わる4つの問題を歴史的に考察した書。著者は政治史学界のいわば「レジェンド」的存在の大御所だが、分析視角の鍵としてウォルター・バジョットを持ってきたり、日本の近代化の特殊性を相...
副題に「問題史的考察」とあるように、「政党政治」「資本主義」「植民地」「天皇制」という近代日本の根源に関わる4つの問題を歴史的に考察した書。著者は政治史学界のいわば「レジェンド」的存在の大御所だが、分析視角の鍵としてウォルター・バジョットを持ってきたり、日本の近代化の特殊性を相変わらず西欧(というより英米)との偏差によって規定するあたり、レジェンドであるが故の「古臭さ」は否めない。明治前期の非対外募債主義を幕末の「倒幕派」に遡及している点などおかしいところもある。とはいえ、最近はアプリオリに自明の前提として等閑視されている歴史学の根源的問題、すなわち「なぜ日本は非欧米圏で唯一植民地にならず、近代国民国家の形成に『成功』したのか?」という問いを検討する上で様々な示唆を与えてくれる点は評価するべきだろう。
Posted by
著者の問題意識と分析は頷けるところ多々あるが、将来展望の部分はりそうしゅぎてき、希望観測的すぎないか。
Posted by