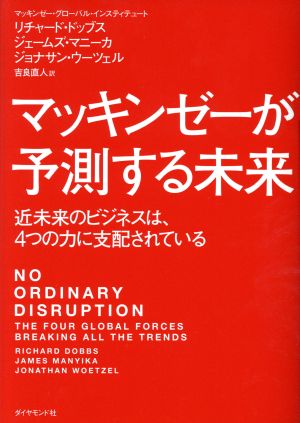マッキンゼーが予測する未来 の商品レビュー
んー、3分の2ほどまで読んで止めました、期待した内容と違い、退屈で時間がもったいないからです。次の本に移ります。❌
Posted by
本書で予測される未来での事象のうち、特に注目したのは以下でした。 I.STEM (科学、技術、工学、数学)分野を専攻する学生の比率は、2008年時点での世界平均23%に対して、シンガポールの54%を筆頭に、中国42%、台湾35%、韓国35%と続いています。ちなみに日本は21%。...
本書で予測される未来での事象のうち、特に注目したのは以下でした。 I.STEM (科学、技術、工学、数学)分野を専攻する学生の比率は、2008年時点での世界平均23%に対して、シンガポールの54%を筆頭に、中国42%、台湾35%、韓国35%と続いています。ちなみに日本は21%。今週のエコノミスト誌には、数学とコンピューター分野で最も評価された論文トップ1%の数で、トップ15大学のうち、9が中国(香港含む)及びシンガポールの大学との記事が掲載されたました。 II.2025年までにFortune500社中、230社が中国を筆頭とする新興国の企業となる、とのことです。ちなみに、先日、同誌はタイのチャロン・ポカパン(CP)グループ会長の子息により買収されると発表されました。 III.平均寿命が長くなると同時に、投資収益率が低下することにより、高齢者がより長く働かざるを得ない可能性があります。これにより、世界で労働力人口に占める高齢労働者(55歳以上)の比率が、2014年の14%から2030年の22%へ上昇することが予想されています。 上記3つを勘案すると、超文系である私が高齢期を生き延びるには、STEM分野を学びなおし、新興国企業(中国やインドの)で、体力・健康を温存して長く働くよう精進することが必要になる、ということでしょうか。
Posted by
人口変化や新興国の状況、技術による今後起こりうる世界を予測したもの。将来のビジネスのあり方を考えるのに役立った。
Posted by
細切れの読書になってしまったので、流れが途切れ途切れであるのだが、 1章の都市化のパワーなどは経済地理学を学んでいたこともあり興味深く読んだ。 これからは国家単位でなく都市単位で物事が進んで行くことが多いと思う。 日本は年間40万人の人口減少が起きており、この規模は宮崎市など地...
細切れの読書になってしまったので、流れが途切れ途切れであるのだが、 1章の都市化のパワーなどは経済地理学を学んでいたこともあり興味深く読んだ。 これからは国家単位でなく都市単位で物事が進んで行くことが多いと思う。 日本は年間40万人の人口減少が起きており、この規模は宮崎市など地方の政令指定都市が毎年1つずつ消滅しているような規模なので、 残酷に思われるかもしれないが、人口を維持する(経済発展を目指す)都市と、人口を減少させる都市との取捨選択をする必要が出てくると思う。 そうでないと国際競争には勝ち残ることができない。 この本によれば、そういった政策の決定は様子見と先延ばしにせず、小規模な実験を迅速に行なっていくことがこの変化の早い時代には必要なことなのだが、日本にそれができるか。 人口減少する都市も、人口密度が減ることで可能となることを模索していくべきだと思う。 例えば大規模農業や自動運転の実験など、これから発展が見込まれて広大な用地を必要としそうな分野の先進地域となれる可能性があるので。サメを食う小魚になれる可能性もある。 どんなに過去を懐かしんでも時計の針が戻ることはないので、変化を楽観的に捉えて前向きに生きていけるようになりたい。 たぶんこの本に書かれていることの数%しか頭に入っていないので、また機会があれば読み返してもいいかもしれない。 目次を見るだけでヒントが得られるかも。
Posted by
マッキンゼーのネタ本。どれもトレンドを押さえていて反論の余地はないものばかり。大企業だけでなく、中小企業も否応なく巻き込まれる社会環境の変化が整理されている。 日々の変化は微々たるものであっても、時間軸を広げると激変していることが多い。ましてや、20世紀初頭ならともかく、21世...
マッキンゼーのネタ本。どれもトレンドを押さえていて反論の余地はないものばかり。大企業だけでなく、中小企業も否応なく巻き込まれる社会環境の変化が整理されている。 日々の変化は微々たるものであっても、時間軸を広げると激変していることが多い。ましてや、20世紀初頭ならともかく、21世紀になると変化のスピードは速い。速すぎる。だからこそ、巨大企業でさえ追いつけない技術、ビジネスモデルの変化が多発しているのだ。
Posted by
最近感じていた世の中に対する不確実性と近しい内容であった。 これからの時代において、個人としては、これまで培った直観をリセットするとともに、スピード感をもって取り組まなければならず、企業経営においても同様である。 脅威として見なすのではなく、同時に大きな事業機会にもなるという...
最近感じていた世の中に対する不確実性と近しい内容であった。 これからの時代において、個人としては、これまで培った直観をリセットするとともに、スピード感をもって取り組まなければならず、企業経営においても同様である。 脅威として見なすのではなく、同時に大きな事業機会にもなるということ。これから世界は豊かになり、健康になり、超寿命になる。 脅威としても捉えつつ、機会としても捉えていきたいですね。 機会として捉えるときに重要だなと思うのは、風が吹けば桶屋が儲かる的な、起きたことが最終的にどうなっていくのか、どんな機会が生まれるのかを見出す能力なのだと思う。 今回のケースで言えば、自動運転車⇒事故減る⇒提供する臓器提供が減る⇒人工臓器の需要高まるといったような。 落合陽一氏の本でもあった自動運転タクシーの料金が安価になるみたいなリアルな妄想も一緒かと。 以下、メモ 大企業としては、①インキュベーション機能を有して新たな技術やビジネスモデル等をつねにウォッチ ②これから生まれてくる数十億にもなる中間層は、無名都市に集まって、都市化は加速するので、その都市への展開が求められる ③高齢化も同時に起きるので新たなマーケットが生まれる ④資源不足になるので、エネルギーや食品廃棄等にも新たな事業機会が生まれる ⑤データ活用 ⑥高度人材の不足と低スキル人材の余剰 (編集中)
Posted by
『それは、私たちの意思決定の大半が、今でも個人の直観に支えられたものだからだ。これは、当たり前の人間の性向であり、私たちの直観は自分の経験の組み合わせと、物事がどのように動き、機能するべきなのかという思考により形作られている。』 この直観をリセットするために4つのトレンドについ...
『それは、私たちの意思決定の大半が、今でも個人の直観に支えられたものだからだ。これは、当たり前の人間の性向であり、私たちの直観は自分の経験の組み合わせと、物事がどのように動き、機能するべきなのかという思考により形作られている。』 この直観をリセットするために4つのトレンドについて論じている。 1.経済の重心の移動 2.テクノロジー・インパクト 3.地球規模の老化 4.「流れ(フロー)」の高まり 非常に密度が濃くて、読み応えのある作品。 中途半端な未来予測本を何冊も読むより、この一冊を読み込む方が価値がある。良かった。
Posted by
途上国の躍進による経済の重心の移動、技術革新と普及のスピードアップによるテクノロジーインパクト、平均寿命の上昇による地球規模の高齢化、貿易に加え資本、人々、情報のグローバルな「流れ」の高まりの中で世界は驚くほど変貌を遂げつつあり、分かっていると思っていることが間違っていると説き、...
途上国の躍進による経済の重心の移動、技術革新と普及のスピードアップによるテクノロジーインパクト、平均寿命の上昇による地球規模の高齢化、貿易に加え資本、人々、情報のグローバルな「流れ」の高まりの中で世界は驚くほど変貌を遂げつつあり、分かっていると思っていることが間違っていると説き、正しい未来を見詰めよと啓蒙します。 特に途上国の都市化に関しては、かつて地理で勉強した世界とまるで別世界、日本が「途上国」から勃興した60年代から70年代、そしてバブルが崩壊するまでの時代とは全く違う世界に生きていることを分かっていたつもりでしたが、改めて認識しました。
Posted by
都市化、高齢化、消費者層の増加など、グローバルメガトレンドから現状と将来を眺める視点を追体験できる。目先の事に目が行きがちだが、忘れてはならない視点。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
予測することも重要だが、それよりも自分の思考にリミッターをかけてしまい、限界を作ってしまうことの方が問題。現状維持バイアスを捨てて、新しいことを積極的に取り入れることが大事。 これから起こることは危険も伴うかもしれないが、結果としてはそれが機会を捉えていることにつながる。 例えば高齢化でさえも、悲観的に考えずにチャンスと捉えれば、解決策は必ず見つかるはず。人類はそうやって進歩してきた。
Posted by