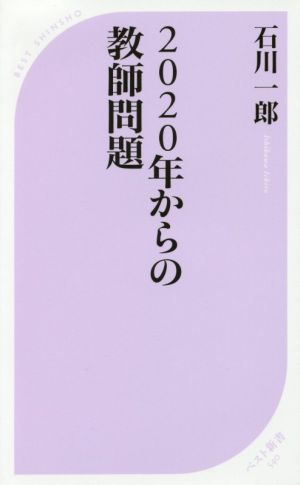2020年からの教師問題 の商品レビュー
・読書感想文の場合 →欧米の「bookreport」 ○要約 ○作者のこだわりや主張を教師の方で「問い」を立て生徒たちに議論させる 例)もし、あなたがKだったら、先生の発言に対してどのような行動を取るか(「こころ」より) ・地歴公民の場合 →江戸時代の三代改革と田沼意次の政治を...
・読書感想文の場合 →欧米の「bookreport」 ○要約 ○作者のこだわりや主張を教師の方で「問い」を立て生徒たちに議論させる 例)もし、あなたがKだったら、先生の発言に対してどのような行動を取るか(「こころ」より) ・地歴公民の場合 →江戸時代の三代改革と田沼意次の政治を比較し、あなたであればどのような経済政策を取りますか ○覚えた知識をそのままにせず、「自分であればどうするか」を考えられるような授業づくりをする。 ・ディベートの場合 →意見を対立させたまま終わるのではなく、最終的にお互いにとっての最適解を出せるようなディベートの授業をする。 ⭐︎あなたであればどうしますか?という問いをする。 ・クリティカルシンキング →自分が言おうとしていることが論理的な考察かどうか確かめること。 ○因果関係 ○比較検討 ○抽象化 →最後に問われるのは自分軸 サイクル モヤ感(悩み、考える)→クリティカルシンキングでチェック→自分軸と向き合い答えを出す。 教師が主役になってはいけない。
Posted by
1990年に始まった大学入試センター試験は2019年度(2020年1月)の実施を最後に廃止され、翌年度から「大学入学共通テスト」に切り替わる。これは単なる入試制度の変更ではなく、大学教育と高校教育・そしてその接点である入試という「三位一体」による大々的な教育改革という位置付けだ。...
1990年に始まった大学入試センター試験は2019年度(2020年1月)の実施を最後に廃止され、翌年度から「大学入学共通テスト」に切り替わる。これは単なる入試制度の変更ではなく、大学教育と高校教育・そしてその接点である入試という「三位一体」による大々的な教育改革という位置付けだ。21世紀に入って急速に進む経済のグローバル化は、AIの普及と相まって今後は予測出来ない状況、つまり大学を出ても食っていけない事態を招くという危機感を持った日本政府が、数式や年号などの暗記物に象徴される「知識の習得」から、学んだ知識を使って自分の頭で考える「知識の活用」へと大転換し、ヒト・モノ・カネ・さらには情報が国境を越えて交錯するグローバル社会に通用する人材の育成を目指すもの。本書は戦後初とも言える日本の教育改革において、その鍵を握る現場の高校教師がいかに改革を実行すべきなのかを、私立の中高一貫校の校長を務めた著者が期待と不安を織り交ぜて提言する。
Posted by
大学のレポートの課題図書に指定されたので、読むことになった。3年前に筆者があげた声は、無駄になってはいないだろうか。2020年現在の視点からこの本を読んでみると、教育改革に向けた準備の遅れを感じざるを得ない。結局、教育問題は教師のワークライフバランスの問題に行き着いてしまいがち。...
大学のレポートの課題図書に指定されたので、読むことになった。3年前に筆者があげた声は、無駄になってはいないだろうか。2020年現在の視点からこの本を読んでみると、教育改革に向けた準備の遅れを感じざるを得ない。結局、教育問題は教師のワークライフバランスの問題に行き着いてしまいがち。根本を変えなければ。
Posted by
2020年以降の大学入試試験が変わる事により、教師が対応しきれない懸念、課題を提示した本。今後は答えはひとつではなく、考える力を試すものになる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「もしあなたがザビエルだったらどのように布教活動をしますか」 これからの入試にはこのような「答えが一つに定まらない問題」だらけになる。 「もう受験終わってるし...」と思っている方ほど、危機感を持って読んでいただきたい。 なぜ今教育が変わるのか。 それは今までの「知識習得型教育」では、今後の予測不能な未来を生きていけないからだ。 本書では実際にどのような教育をし、どのような能力を子どもたちに身につけさせるべきなのかを、国内外の事例とともに考えさせてくれる。 その上で教師としての立場は「指導者」ではなく「プロデューサー」であると本書では述べている。 生徒に問いを与え、生徒の答えから先生もまた考え、生徒とともに高め合う関係がこれからの教師には求められる。 ただ、現代の教師は忙しい。 それも部活動や雑務などの「生徒指導」以外の部分で。 教育制度変革も大事だが、教師が生徒に向かう時間や、教師自身が学ぶ時間を取れるようにすることもまた大事であると思う。 実際自分の意見が言えない人は、日本に多い。 実際私も自信がない人間の1人だ。 私自身今回の教育改革には賛成ではあるが、今までそのような教育を受けて来なかった我々大人にとっては「考えさせる」教育は非常に難しいものである。 日々の生活から、自分の意見を考える練習を今後大人の皆様が取り組んでいく必要がある。 本書では2020年以降の教育に「教師」が対応するための方法が主体で書かれているが、私は「教師」だけでなく「大人」の皆様にぜひご一読いただきたい。 なぜなら「教師」は一時期のプロデューサーに過ぎず、一生涯のプロデューサーは「親」だからだ。 どれだけ教師が努力しようと、親である大人の皆様が今後の教育方針に「理解」と「協力」しない限り、今後の日本は一生変わらない。 教師だけでなく、一丸となって日本の教育を変えていくことが今後求められるだろう。
Posted by
教育業界の課題が列挙されていて、網羅性がたかく読みやすい。 この本を入り口にして、 活用/ラーニング/クリティカルシンキング/ディベート/指導者ではない/ワークライフバランス/プロデューサー/ジョハリの窓/マインドを変える といったテーマに関心を広げていきたくなる。
Posted by
2020年に廃止となる、大学入試センター試験。以降は「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」と呼ばれる新たな試験が実施されることとなる。この事実をなんとなくでも知っている人というのは、少なくないだろう。しかし、このセンター試験廃止の背景に、文科省による大規模な教育改革が存在するこ...
2020年に廃止となる、大学入試センター試験。以降は「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」と呼ばれる新たな試験が実施されることとなる。この事実をなんとなくでも知っている人というのは、少なくないだろう。しかし、このセンター試験廃止の背景に、文科省による大規模な教育改革が存在することを認識している人は、教育関係者でない限りほとんどいない。変わるのは入試だけではない。学校教育は、「知識の習得」を中心とした従来の学習から「知識の活用」を目指すスタイルへと大転換を迫られている。その際鍵を握るのは、教育の実践者である教師であることは間違いない。果たして、現在の教師たちに改革を実行し教育をアップデートすることは可能なのだろうか。 答えのない「問い」を生み出すことがどこまでできるか。
Posted by
現行の学習指導要領が大幅に改訂されて、教育についてかなり大きな範囲で見直しがなされている。そもそもその背景にあるのは大学入試の変化、つまりセンター試験の廃止とそれに伴う大学入試の変化である。そしてなぜ大学入試が変わるのかとなれば、社会で求められる人材の時代経過に伴う変化にある。そ...
現行の学習指導要領が大幅に改訂されて、教育についてかなり大きな範囲で見直しがなされている。そもそもその背景にあるのは大学入試の変化、つまりセンター試験の廃止とそれに伴う大学入試の変化である。そしてなぜ大学入試が変わるのかとなれば、社会で求められる人材の時代経過に伴う変化にある。そんな教育に関する大きな変化を前にして、教師がこれからどうあるべきか、現状の教育の問題点はどんなところなのかについて分かりやすく事例などを上げながら解説してくれている。 自分自身のことを振り返りながら読んでみたのだが、なるほどと心に刺さる内容がたくさんあった。授業の内容や、教え方の見直し、そもそもこの本的には、教えるということもニュアンスとしては違う気がするが、今後の参考になる部分が非常に多い。未知の大学入試やその先の未知の社会に出て行く人材を自分たちはどのように教えて行ったらいいのか、いろいろと考えさせられた。
Posted by
http://www.kk-bestsellers.com/cgi-bin/detail.cgi?isbn=978-4-584-12540-3 , http://www.seibo.ed.jp/nevers-hs/
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「教育改革はやらないほうがいい」のか、「自分までは何とか変わらなくていって欲しい」のか、「未来を生きる子どものため、そして自分自身のため変えていきたい」のか、教師という仕事をやっている人が自分を振り返るための本としてオススメです。 変化を拒否する教員たち、教育改革を止める職員室の勢力は一掃されるべきだ、と喝破している本にはなかなか出会えない。
Posted by