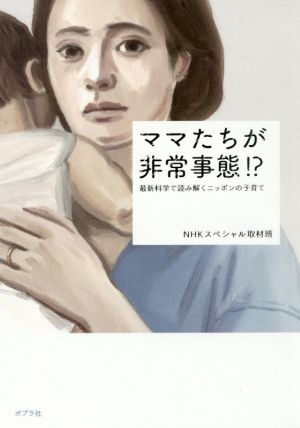ママたちが非常事態!? の商品レビュー
共同養育、イヤイヤ期、イクメンパパとオキシトシン等、雑多なトピックが比較的良く整理されていり思った。 特に母性が経験で育まれるもの、というのは新しい知見だった。
Posted by
数時間で読み終わった。育児で疲れてても読みやすい。 要点は番組HPでも読める。 夜泣きについて。胎児の頃は昼夜問わず寝てるので、産後数ヶ月はそのリズムを引きずってる。また、睡眠中の脳の信号を身体に送信するのをブロックする機能が未発達なので、脳波は寝てても動いたら泣いたりする。そ...
数時間で読み終わった。育児で疲れてても読みやすい。 要点は番組HPでも読める。 夜泣きについて。胎児の頃は昼夜問わず寝てるので、産後数ヶ月はそのリズムを引きずってる。また、睡眠中の脳の信号を身体に送信するのをブロックする機能が未発達なので、脳波は寝てても動いたら泣いたりする。そこで抱っこしてあやすとほんとに起きてしまうのでよくない。研究者曰く、10秒ほど様子を見るのがおすすめとのこと。 人見知りについて。はじめは母親しか認識してなかったのが、成長につれて他人を認識するようになると怖がるようになる。成長段階の途中ということ。野生の動物と同様に目を直視すると威嚇になるので、目を合わせずに体を近づけるのが良いらしい。 イヤイヤ期について。脳の発達段階の途中ということ。欲求などを司る部分が発達したあと、衝動を抑える実行機能がまだ未熟な段階。回避する方法はなく、発達段階だと思えば楽になるという感じ。 実行機能を鍛える方法が紹介されてる。カードを使ってルールに基づいて我慢させる方法。口で言うと恐怖で抑え込むことになるので、カードは良さそう。 父親の脳の変化について。母親は妊娠中や出産時に脳が大きく変化し、赤ちゃんの泣き声にびんかんになったりする。父親も、育児をすると母親ほどじゃないけど同様に変化をすることが実験で確かめられている。とはいえ、同じ役割を期待するのじゃなく、ある意味で、一歩離れて冷静な役割がいるほうが家族全体としては良いんじゃないか、という感じ。
Posted by
子育てにまつわる様々な悩みを科学の立場から解明する。発想が理系だなあ(しかも、さすがにダーウィンが来たの担当だと思わされる見事な動物との比較)と感心するとともに、現代の母親が理詰めで子育てに立ち向かわないとやっていけない辛さを表すようでもあり、なんとも微妙ではあるが、色々な悩みが...
子育てにまつわる様々な悩みを科学の立場から解明する。発想が理系だなあ(しかも、さすがにダーウィンが来たの担当だと思わされる見事な動物との比較)と感心するとともに、現代の母親が理詰めで子育てに立ち向かわないとやっていけない辛さを表すようでもあり、なんとも微妙ではあるが、色々な悩みが科学的に証明される様は面白い。 人見知りやイヤイヤ期の謎が脳科学から明かされる。抑制能力(我慢できる力)が将来の犯罪防止に役立つかもというアプローチは面白くもあり、グリッド云々同様、アメリカ的なアプローチだなあと。それだけ貧困格差と犯罪率が高いということなんだろうなあ。 個人的には、「妻のトリセツ」の筆者も述べていた、女性に特有だと言う「女性同士の経験の共有」(=井戸端会議)が非常に苦手で、産後女性の「ママ友を求める気持ち」はそこまで共感できるものではなかったので、自分はチンパンジーから分岐できていないのではないかと危惧を覚えた。が、たしかに自分でコントロールできない子供の時間軸に振り回されることからくる焦燥感や社会からの孤立感、疎外されている感、強い感情の発生を思い出すときに、その裏に複雑なホルモンと脳の働きがあったのかと思うと、なんとも感慨深い。 最終的には、種によって固定されているはずの子育て方法が、現代の人間だけは柔軟なのだから頑張ろうという前向きな結論。動物との比較ではまさにそうで面白いのだが、これを最近読んでいるフェミニスト的な著者たちの視点を借りて読むならば、だからこそ現代女性の苦悩が増長されている気もする。 大半が農業や狩猟という第一次産業で生計を立てていたならばいいのだろうが(しかも男子に狩猟等を教えるという点で、教育=父親という流れがあった)、現代は男女どちらでもできる仕事がメイン。子育ても小中高大と男女の差もない→実質全て母親の負担。共働きが過半数の状態の中、「科学的に男性脳に母脳を求めることはできないので、男性が女性と同等に子育てできないのは男性が悪いわけではないですが、共働きでいっしょに子育てしていきましょう」というのでは、結局常に母親がストレスを溜めながら、「これは科学だ」と自分にマントラを唱えながら耐える状態が続くのではないかと思ってしまう。いっそここまで科学科学というのなら、育児をする男性には男性脳を母脳に変えるホルモン治療とか脳手術とか「科学的な」方法はないものかと思ってしまう。いずれにせよ、育児問題を脳科学的アプローチとフェミニズム的アプローチ両方から考える機会になって面白かったです。
Posted by
【いちぶん】 実は動物の中で、大切なわが子を他人の手にゆだねることができるのは人間だけだといわれています。 (p.84) 共同養育を求める母の体の本能と、現代の孤独な育児環境、そのギャップに母たちは苦しむ。それこそが“現代ニッポンの母の7割が育児に感じる孤独 ”の正体だと考えら...
【いちぶん】 実は動物の中で、大切なわが子を他人の手にゆだねることができるのは人間だけだといわれています。 (p.84) 共同養育を求める母の体の本能と、現代の孤独な育児環境、そのギャップに母たちは苦しむ。それこそが“現代ニッポンの母の7割が育児に感じる孤独 ”の正体だと考えられるのです。 (p.86)
Posted by
「どうしてこんなに育児がしんどいのだろう」 私も0才育児、かなり実感しました。 夜泣きの理由、人見知りの理由、かわいいと思えない心理、赤ちゃんやママについて科学的に説明してくれていて、いわるゆ育児本とはまた違った形で勇気付けられました。「こういう状況なんだ」と目の前赤ちゃんの行動...
「どうしてこんなに育児がしんどいのだろう」 私も0才育児、かなり実感しました。 夜泣きの理由、人見知りの理由、かわいいと思えない心理、赤ちゃんやママについて科学的に説明してくれていて、いわるゆ育児本とはまた違った形で勇気付けられました。「こういう状況なんだ」と目の前赤ちゃんの行動の科学的根拠を知れば、しんどい気持ちが少しでも救われるように思いました。
Posted by
[図書館] 読了:2020/6/20 最近は常識になってきている事柄も多いけど、これが出版された2016年はまだまだだったよなぁ…。流れを変えたNスペだったと思う。 科学で証明されてはいても、迷信や信仰は変えられない、ってのがまた母親を追い詰めるのだろうなぁ。 「子育てがつ...
[図書館] 読了:2020/6/20 最近は常識になってきている事柄も多いけど、これが出版された2016年はまだまだだったよなぁ…。流れを変えたNスペだったと思う。 科学で証明されてはいても、迷信や信仰は変えられない、ってのがまた母親を追い詰めるのだろうなぁ。 「子育てがつらいのは、決してあなたのせいではありません。」 人間の赤ちゃんは、二足歩行の代償で小さくなった骨盤が原因で、ほかの動物より1年近く早い状態で生まれてくる。人間の子供はほかの動物より育てにくい。 「母性」は本能で最初から備わっているとのではない。人工飼育下のチンパンジーは、自分の産んだ子を我が子と認識できず、恐怖のあまり頭を掴んで引っ張り出し、床に叩きつけた。ほかの個体の出産や育児を知らないことが理由と考えられる。 オキシトシンは愛情を増幅する一方、怒りや攻撃性をも何十倍にも増幅する。母親はこの増幅された振幅の間を揺れ動く。 父親は母脳(泣き声に瞬時に反応、常に赤ちゃんを気にしている)にはなれない。しかし、子供のけがなど瞬時に敏感に反応してパニックになってしまう場合もあるので、ゆったり判断できる人がいた方がいい場合もある。 妻は自分がスーパーウーマンに変わってしまったことを自覚し、夫はそうはなっていないことを理解する。夫は子どものために心も体も変えてしまった妻のことを理解し、ならば自分には何ができるのかを考える。
Posted by
第一子出産後、途方もなく不安な気持ちで押しつぶされそうな事が幾度もあった 夜中3時に授乳してる時には、一人世の中に取り残されてるような気持ちになり、朝主人も含め多くの人がパリッとした格好で外に向かう姿さえも羨ましく感じた 多くの育児書では子どもの成長を過程にフォーカスし、子ど...
第一子出産後、途方もなく不安な気持ちで押しつぶされそうな事が幾度もあった 夜中3時に授乳してる時には、一人世の中に取り残されてるような気持ちになり、朝主人も含め多くの人がパリッとした格好で外に向かう姿さえも羨ましく感じた 多くの育児書では子どもの成長を過程にフォーカスし、子どもを育てる上での必要条件で、母親であるそれを理解し我慢するものだと思っていた 本書は科学的アプローチで、子の成長について触れており、読んでいて非常に納得感があった もうまもなく産まれる第二子 生物史上最も育てにくい生命体を愛おしく迎え入れたいと改めて思えた
Posted by
育児を科学することで、産後うつやイヤイヤ期が起きる理屈が見えてくる。ただイライラするのではなくて、どう解決すればいいか。夫婦以外にも是非読んで欲しい!NHKスペシャルの名著。
Posted by
出産前に読みたかった。 ホルモンの影響だとわかってたら、もう少しだんなさんを大切にできたかも(ごめん)
Posted by
精神的なことではなく科学的な根拠で「育児のしづらさ」が語られている点は面白かったが、対処法が乏しかったのがややマイナス。(これは当事者たちで考え、試行錯誤して乗り越えなくてはならないということだろう) それでもこうした事実を「知っている」ことは大事だと思う。 印象に残ったのは...
精神的なことではなく科学的な根拠で「育児のしづらさ」が語られている点は面白かったが、対処法が乏しかったのがややマイナス。(これは当事者たちで考え、試行錯誤して乗り越えなくてはならないということだろう) それでもこうした事実を「知っている」ことは大事だと思う。 印象に残ったのは以下の点。 ・子育ての原型は「共同養育」。今の「孤育て」はその対極をいくもので、母親が孤独感を深めがち。 ・母性は産んだときからあるのではなく、経験によって育まれるもの。 ・夜間赤ちゃんが起きても睡眠中の可能性もある。10秒間様子を見守ってみる。 ・抑制機能を鍛えるトレーニング。自分で理解させ行動させる。 ・父より母の方がこどもに対する反応が早いのは当たり前。持ちうる能力、役割は違っていい。
Posted by