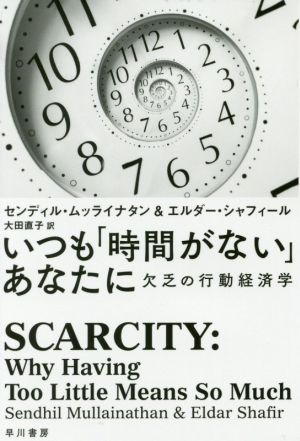いつも「時間がない」あなたに の商品レビュー
欠乏が起こす問題はそのことに集中しすぎること。 他のことに集中出来ずミスする 貧乏な人は視野が狭いなど。 話が冗長すぎる点が難点
Posted by
時間管理の本かと思いきや、行動経済学の本。欠乏状態をいかにして回避、もしくは自分でわかった上で利用するか?
Posted by
余裕あるときなら十分予測出来たこと|してたことなのに、忙しくて先のことを考えられずにほっといて、いざそれが起こると驚きと衝撃を受けたり... たとえばプロジェクトでも、ボヤに気づいてはいてもトンネリングの外にいってしまって炎上してから気づくなんてことは達成や時間への欠乏が生んで...
余裕あるときなら十分予測出来たこと|してたことなのに、忙しくて先のことを考えられずにほっといて、いざそれが起こると驚きと衝撃を受けたり... たとえばプロジェクトでも、ボヤに気づいてはいてもトンネリングの外にいってしまって炎上してから気づくなんてことは達成や時間への欠乏が生んでることなのかな。往往にして詰め込みが正義(であらねばならない)という考えに陥りがちだけどスラックを持つことは怠けではなく、リスクヘッジだということにとらえ直さないとね。
Posted by
序章 第1部 欠乏のマインドセット 第1章 集中とトンネリング。第2章 処理能力への負荷。 第2部 欠乏が欠乏を生む 第3章 荷造りとスラック。第4章 専門知識。第5章 借金と近視眼。第6章 欠乏の罠。第7章 貧困。 第3部 欠乏に合わせた設計 第8章 貧困者の生活改善。第9章 ...
序章 第1部 欠乏のマインドセット 第1章 集中とトンネリング。第2章 処理能力への負荷。 第2部 欠乏が欠乏を生む 第3章 荷造りとスラック。第4章 専門知識。第5章 借金と近視眼。第6章 欠乏の罠。第7章 貧困。 第3部 欠乏に合わせた設計 第8章 貧困者の生活改善。第9章 組織における欠乏への対処。第10章 日常生活の欠乏。 結論
Posted by
タイトルだと、時間管理について書かれていると思ってたけど、内容は各種の貧困についての学術書。 丁度貧困層への支援について考えていた時に出会ったので、参考になった。 読んだ結果、貧困層への支援の難度の高さが思った以上に大変だと思った。
Posted by
欠乏とそれがもたらす問題に着目することで、問題の本質が見えてくる。 欠乏がダイレクトに処理能力の不足に結びつき問題が発生しているという認識、ものすごく適用範囲の広い発想だと思う。 特に貧困関係の議論は非常にためになった。 論じる順番、説明の仕方にも工夫が凝らされている。 所与...
欠乏とそれがもたらす問題に着目することで、問題の本質が見えてくる。 欠乏がダイレクトに処理能力の不足に結びつき問題が発生しているという認識、ものすごく適用範囲の広い発想だと思う。 特に貧困関係の議論は非常にためになった。 論じる順番、説明の仕方にも工夫が凝らされている。 所与の処理能力を問題にせずに、環境がもたらす処理能力の変動を問題にしているので非常に風通しが良い。 行動のデザインを変えるきっかけに。 とりあえず自動積立て預金開始しました。
Posted by
時間をかけてゆっくり読みました。「欠乏」についてサイエンスの視点でしっかりとしたデータを元に書かれているので納得感があった。
Posted by
欠乏とは、自分が持っているものが必要と感じるものより少ないこと。時間やお金。欠乏は人間の処理能力に対して大きな負荷となり、考え方や行動が変わり、判断力が落ちる。欠乏が欠乏を産む。 お金がないのも、時間がないのも同じ、というのはなるほどでした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・心配事などがあると処理能力が下がる為、ミスが増えたり生産性が下がったりする。そもそもの不安を解消した方が良いそう。 ・締め切りがきつくて時間の不足を強く感じるグループを作ったところ、そちらの方が高い生産性を見せた。締め切りに遅れる事も少なかった。 ・自制心は意思の力にも左右される。意志力の機能は十分に理解されていないが、とくに性格、疲労、注意力の影響を受ける。 ・自制心は実行制御力に大きく依存している。人は実行制御力を用いて注意を払い、行動を起こし、直感的反応を抑え、衝動に抗う。 ・「意志力とは自分の注意と思考をコントロールする方法を覚える事だと気づけば、現実にそれを強められるようになる」 ・建設プロジェクトについてのある研究「週60時間以上の勤務スケジュールが約2ヶ月以上続いた現場では、生産性低下の影響が蓄積し、そのせいで完成美は、同じ人数が週40時間勤務で達成したであろう日より遅くなる。」 ・あるソフトウェア開発者の指摘によると、スタッフが週60時間働くようになったとき、最初の数週間はこなせる仕事がぐっと増えたという。しかし5週までに、週40時間働いていた時よりもこなす仕事量が少なくなっていた。 ・労働者が睡眠時間を減らすと、意欲が低下し、ミスが増え、ぼんやりが多くなることは、研究によって何度も示されている。 ・たいていの人は増大する職場の要求に、勤務時間を増やすことで対応するため、どうしても体にも頭にも心にも負担がかかる。そのせいで従業員のエンゲージメントレベルが下がり、注意散漫がひどくなり、離職率が上がり、医療費が急増する。 ・欠乏の世界では、長い期間はトラブルのもとだ。初めのうちの豊かさが無駄を促し、期日が近づくころにはトンネリングとほったらかしが生じている。長い期間を段階的にいくつかに区切ると、悪循環になる前に断ち切る事ができる。同じ事がお金にも言える。 ・生産性は決定的に処理能力に依存している。労働者は効率的に働かなくてはならない。経営者は賢明な投資判断を下さなくてはならない。人的資本を築く為に学生は学ばなくてはならない。これらすべてが処理能力を必要とし、今日の処理能力低下がさらに将来の生産性を低下させる可能性がある。
Posted by
久々にすごい!と思う著書だった。この本で書かれていることだが、今回図書館で借り、2週間という限られた期間があったおかげで、無事読み上げることができた。 至る所に付箋を貼っておきたい項目が多数あった。読み上げるのに処理能力を使ったおかげで、返却日の翌朝までかかり、付箋を貼る余力は...
久々にすごい!と思う著書だった。この本で書かれていることだが、今回図書館で借り、2週間という限られた期間があったおかげで、無事読み上げることができた。 至る所に付箋を貼っておきたい項目が多数あった。読み上げるのに処理能力を使ったおかげで、返却日の翌朝までかかり、付箋を貼る余力は無かった。 再度借りる、買うなどしてもう一度読み直す必要を感じる。余裕のあるときにそれができるかは??だが。 スラック(余裕)がないと、ちょっとしたつまずきや予定外の出来事が起きた時の遅れに対応できず、常に一歩遅れた借金状態に陥り、なかなか抜け出せない。借金状態は、思考能力が常にその部分に取られトンネリングを起こすことで、おろそかになる事があふれ、ジャグリングする。 1文でまとめるとこんな感じだろうか…。薬を飲み忘れる人への対策など、余計なお世話かなぁ…と思っていたことが、結果として非常に良い効果があるとわかった。悪徳な方が利用すれば、結構な金儲けになりそうだ。 人の性格ではなく、人間の特性としてある、の様に述べたことが真実であるならば、本当に意義深い。
Posted by