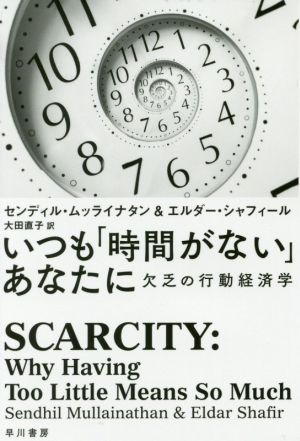いつも「時間がない」あなたに の商品レビュー
いつも時間が無い、借金を重ねてしまう、ダイエットが続かない・・ これらはバラバラに見えて、実は原因は同じではないか?という話。その原因は、「欠乏」(自分の持っているものが、必要だと思う量よりも少ないこと。心に余裕がないこと。)。欠乏が起こると、脳の処理は欠乏に対して大きく使われて...
いつも時間が無い、借金を重ねてしまう、ダイエットが続かない・・ これらはバラバラに見えて、実は原因は同じではないか?という話。その原因は、「欠乏」(自分の持っているものが、必要だと思う量よりも少ないこと。心に余裕がないこと。)。欠乏が起こると、脳の処理は欠乏に対して大きく使われてしまう。これをトンネリングという。トンネリングには、「集中ボーナス」がつくことがある(締切効果)。とはいえマイナスの方が大きいので、欠乏が起こらないようにすることが大切。 自分は、夏休みの宿題を初日に全部終わらせるタイプだし、プロジェクトは二週間は余裕がないと不安。欠乏をひたすら避けてきたと思う。他要因で切羽詰まったプロジェクトは全部失敗してきた。 ・適切な期限を設ける ・適切なバッファを設ける。 色々書いてあったものの、結局はこれだけなんじゃないか。
Posted by
今の私の生活にはあまり必要ないと感じた。 しかし、所々目線を変えたアイデアで、企業や国や人々が取り入れれそうなものがあり感心した。 私が理解力に乏しく、この本がどうしても持つべき者たちの勝利に感じてしまい、身も蓋もないなぁと お金か時間があれば大抵のこと解決できる的な。 全...
今の私の生活にはあまり必要ないと感じた。 しかし、所々目線を変えたアイデアで、企業や国や人々が取り入れれそうなものがあり感心した。 私が理解力に乏しく、この本がどうしても持つべき者たちの勝利に感じてしまい、身も蓋もないなぁと お金か時間があれば大抵のこと解決できる的な。 全然違った解釈ならすみません。 いずれにしても、たとえ持たざるものであっても、いくら処理能力に負荷がかかってても、 如何に決断、選択するかであり、 それはセンスの一言に尽きる そのセンスはやはり教育や成育環境によるものが大きいという持論があり、 今後の人生も自分が納得いく選択をし続けたいなぁと思いました。
Posted by
題名の通り、いつも何かに追われている私の生活を振り返るにはもってこいの本でした。何より、読了後は自分の公私共に行動を客観的に見ている自分がいます。
Posted by
ハーバード大の経済学教授(ノーベル経済学賞の受賞も噂されてるそうですが、今年は残念ながら…だったようで)とプリンストン大の心理学教授の共著による、「欠乏」をテーマとした1冊。 原著を直訳すると「欠乏:なぜ足りないことがそれだけ意味を持つのか」でしょうか。 人間は、欠乏しているモノ...
ハーバード大の経済学教授(ノーベル経済学賞の受賞も噂されてるそうですが、今年は残念ながら…だったようで)とプリンストン大の心理学教授の共著による、「欠乏」をテーマとした1冊。 原著を直訳すると「欠乏:なぜ足りないことがそれだけ意味を持つのか」でしょうか。 人間は、欠乏しているモノ/コトに意識を奪われてしまう。ただ、それだけではなくて、その分野に強い能力を発揮することもできる、と。 読了して感じたのは、「本当の問題」を探すことの重要さと大変さ。 貧困に悩む人々に補助金を支給しても、結局貧困から抜け出せないという事例が出てきます。それを「貧困者たちのマインドが欠如している」みたいに言い訳を連ねるのは簡単ですが、結局それじゃ世の中はいつまで経っても良くならない。 彼らを貧困に繋ぎとめているのは経済的な欠乏だけでなく、様々な悩みに気を取られる「処理能力の欠乏」もあって…という話。 ではどうすれば良いのか。著者が例に出したのが、米軍の爆撃機でパイロットが着陸後に(なぜか)車輪を引き上げる事故が多発していた事例への対処。パイロットの訓練や資質の問題ではなく、コクピットの設計が紛らわしくて事故が起きてしまっていた。 制度の設計も同じで、支給の仕方を上手く考えないといけない、という話でした。 本著の内容とは少し外れますが、個人的に感じたのは、今後の世の中において、潤沢なリソースを活用できるのは贅沢な一部のプロジェクトに限られると思うので、常に「欠乏」と付き合う必要があるということ。 そう思った時、本著のように現場に目を張り付けて事例を分析して解決策を見つけ出して、みたいなアプローチができるかしら…とちょいと暗い気持ちになりました(^^; ちょっとした工夫で乗り切れそうなものもありましたが、それも現場へ落とし込むのは大変だよなぁ。。と。 ちなみに、本著、なぜか読むのにすっごい時間がかかりました。とにかくモチベーションが湧かず、図書館の返却期限に追われて(本著にある「集中ボーナス」そのまんま…)なんとか読了した次第です。 「時間がない」とか「欠乏」とか表紙に書かれて、中身もそんな事例ばっかだからでしょうか…。行動経済学者の皆さまには、この事象の解明をぜひお願いしたいです!(笑
Posted by
だいぶ分厚いけど、事例で埋め尽くされていて冗長な印象。 結論、とにかくスラック(余白)が大事ということだ。人生にいかに余白をつくりだせるか。
Posted by
時間に追われる原因はギリギリまで余裕がない状態になるまで時間を無駄に使っていることだと理解しました。
Posted by
自分にとって必要な時間・お金が足りないと感じるとどうするか? 集中し取り組む。そのことかが視野狭窄をを起こし、処理能力を低下させ、欠乏が欠乏をよぶ。まさに。 切羽詰まってやったことは、やっつけ仕事になり、すっきりしないことが多い。自分の処理能力等をシビアに考慮し、ゆとり・余裕...
自分にとって必要な時間・お金が足りないと感じるとどうするか? 集中し取り組む。そのことかが視野狭窄をを起こし、処理能力を低下させ、欠乏が欠乏をよぶ。まさに。 切羽詰まってやったことは、やっつけ仕事になり、すっきりしないことが多い。自分の処理能力等をシビアに考慮し、ゆとり・余裕を持って行動していきたい。
Posted by
主に時間とお金に関して、なぜ欠乏が起きてしまうのかのメカニズムを大量の研究によって解明する本。 よく夏休みの宿題は夏休みが終わるギリギリになって初めて焦って手を付けるみたいなことがあるけれどなぜそれが起きるのか、みたいな。 時間がない状態に陥るとそこから脱するために処理能力を占有...
主に時間とお金に関して、なぜ欠乏が起きてしまうのかのメカニズムを大量の研究によって解明する本。 よく夏休みの宿題は夏休みが終わるギリギリになって初めて焦って手を付けるみたいなことがあるけれどなぜそれが起きるのか、みたいな。 時間がない状態に陥るとそこから脱するために処理能力を占有されることになりさらに時間を失う状況に追い込まれてしまうみたいな話が面白かった。 一番大事な、じゃあそういう状態にならないためにはどうすればいいかみたいなとこがすごくあっさりしてたのがちょっと物足りなかったかも。
Posted by
読む時間がなくて他の記事での要約を見た上での所感。 「いつも時間がないあなたに」 https://honz.jp/articles/-/43694 どうしたら集中して作業ができるか? ・・・期限ギリギリまで作業をしないこと。そうするとものすごく集中できるので通常より早く作業で...
読む時間がなくて他の記事での要約を見た上での所感。 「いつも時間がないあなたに」 https://honz.jp/articles/-/43694 どうしたら集中して作業ができるか? ・・・期限ギリギリまで作業をしないこと。そうするとものすごく集中できるので通常より早く作業できる。 しかし、その間トンネリングという、集中する代わりに周りの大事なことに目を向けることができなくなる。 このデメリットは、メリットを上回る。 だから、必ず余白、スラック、余裕を持ったスケジュールにすること。 こんな話をどこかで耳にしたことがある。 手術室が3つあって、その稼働率をいつも100%にしていたところ、緊急手術のスケジュールが入ってしまい、 リスケ、調整などで時間が取られて、稼働率が下がってしまうこと。 逆に、3つの手術室のうち常に1つを空けておくことで、緊急対応にも柔軟に対応でき、稼働率を高められたという例があった。 これはとても示唆的で、スケジュールをミチミチにつめてしまうと、想定外の事態に対応できなくなるから、 想定外の事態のための余裕を持たせておこう。
Posted by
欠乏は集中力を増し処理能力を上げる一方トンネリング(視野狭窄)を起こして処理能力を下げる。ちなみに処理能力の高低は能力そのものの高低ではなく欠乏が生み出した状況である。後者は負の連鎖を起こすためネガティブな影響が大きいが、この状況に陥るのを防ぐためにはスラック(余剰、ゆとり)を持...
欠乏は集中力を増し処理能力を上げる一方トンネリング(視野狭窄)を起こして処理能力を下げる。ちなみに処理能力の高低は能力そのものの高低ではなく欠乏が生み出した状況である。後者は負の連鎖を起こすためネガティブな影響が大きいが、この状況に陥るのを防ぐためにはスラック(余剰、ゆとり)を持つことが有効である。聞けば当たり前に聞こえるが、世界の貧困問題からタスクに追われる家庭人、ビジネスパーソンにも広く影響するこの欠乏問題は省みられていないことが多い。日本語タイトルがミスリードな所が惜しいが大変貴重な名著。
Posted by