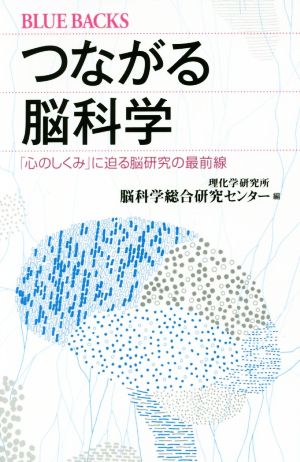つながる脳科学 の商品レビュー
アルツハイマー病は記憶をつくること(記銘)ができないのではなく、思い出すこと(想起)ができないだけだった
Posted by
脳科学の最先端の研究を複数の分野で説明している。時間と空間とのつながり、外界とのつながり、感情と記憶のつながり、ニューロンのつながり、記憶と脳のつながり、親子のつながり、理論と脳のつながり、脳の病と治療のつながり、最新技術と脳研究のつながり。脳に関するさまざまなつながりの研究の最...
脳科学の最先端の研究を複数の分野で説明している。時間と空間とのつながり、外界とのつながり、感情と記憶のつながり、ニューロンのつながり、記憶と脳のつながり、親子のつながり、理論と脳のつながり、脳の病と治療のつながり、最新技術と脳研究のつながり。脳に関するさまざまなつながりの研究の最前線がわかる。
Posted by
理化学研究所脳科学総合研究センターの最先端の執筆陣による脳に関する多面的なアプローチ。脳の謎に迫るプロセスは新たな謎の発見につながる。脳の仕組みを築き上げた生命体の不思議さは尽きない。現象分析的手法や生物学には珍しく理論構築からの検証。因果関係の縺れはほぐれていくが、進化的必然性...
理化学研究所脳科学総合研究センターの最先端の執筆陣による脳に関する多面的なアプローチ。脳の謎に迫るプロセスは新たな謎の発見につながる。脳の仕組みを築き上げた生命体の不思議さは尽きない。現象分析的手法や生物学には珍しく理論構築からの検証。因果関係の縺れはほぐれていくが、進化的必然性といった本質的な謎は深まるばかり。意識を作り出す心の神秘性、無意識で働く体との連動。これをいま考えている頭の活動、脳はすごい。
Posted by
現時点での最新の脳科学(の一部)を理化学研究所脳科学総合研究センター(所長は利根川進氏で第一章を担当)の方々が各分野について紹介している。 内容は学術的な突っ込んだ内容も記載されているので、全てを理解することはできないが、現時点で脳のことがどの程度分かってきているのかを知ることが...
現時点での最新の脳科学(の一部)を理化学研究所脳科学総合研究センター(所長は利根川進氏で第一章を担当)の方々が各分野について紹介している。 内容は学術的な突っ込んだ内容も記載されているので、全てを理解することはできないが、現時点で脳のことがどの程度分かってきているのかを知ることが出来るので、一読の価値はある。
Posted by
優しく書かれた脳科学の最先端…と云う感想を書きたいのですが、いやあそれでも難しかった(笑)理解が落ちてくるまで読み返して時間がかかってしまったけれど、とても面白かったです。ハエの嗅覚は凄いなあとか。 知りたかったのは8章と9章、そしてこの一冊の総括もこの2章に纏められている様な気...
優しく書かれた脳科学の最先端…と云う感想を書きたいのですが、いやあそれでも難しかった(笑)理解が落ちてくるまで読み返して時間がかかってしまったけれど、とても面白かったです。ハエの嗅覚は凄いなあとか。 知りたかったのは8章と9章、そしてこの一冊の総括もこの2章に纏められている様な気がします。 土と空気と水、人間も自然の産物でありながら、その中に倫理とか個性とかどうして芽生えるのだろうか。そしてそれを治療や改善する事は人として道を外れる事なのだろうかとかとか。ううむ。
Posted by
全体像がわかるわけじゃないけど、どういう研究が今行われているのか、それがどんなに気の遠くなるようなものであっても真実を追究していこうという思いが伝わってくる良書。研究というものの凄さの一面を見られた気がして意外な収穫。
Posted by
「つながる脳科学」 理化学研究所の脳科学総合研究センターの研究員による脳科学研究の紹介である。 9人の研究員により、記憶、時空間の認識、シナプスによる情報伝達、嗅覚のメカニズム、数理モデルと脳、感情と神経回路、脳研究のテクノロジー、脳と心の病気、親子関係と脳についての研究内容がそ...
「つながる脳科学」 理化学研究所の脳科学総合研究センターの研究員による脳科学研究の紹介である。 9人の研究員により、記憶、時空間の認識、シナプスによる情報伝達、嗅覚のメカニズム、数理モデルと脳、感情と神経回路、脳研究のテクノロジー、脳と心の病気、親子関係と脳についての研究内容がそれぞれ紹介されている。 そんなことまでわかるのかという反面、脳全体の研究という意味ではまだまだだという感じがする。 とはいえ驚いたのはその実験方法の一つである。 遺伝子改変マウスで特殊なタンパク質をニューロンに発現させ、そのニューロンに光を当てるだけで好きなタイミングでニューロンを興奮させたり抑制させたりする技術である。 そういえば、テレビで頭に電線がつながっているマウスを見たことがあるがあれがそうだったのかと今さらながら思い出してびっくりした。もっともとても人間には適用できないが。 マウスを使っていろいろ研究が進み、基本的な脳の機能は次第にわかってくるかも知れないが、果たしてどこまでわかるのだろうか。そして、それは人間にどこまで適用できるのだろうか。最終的には認識や思考まで解明することができるのだろうか。 結局のところ医療分野での応用を除けば、人間もただの有機物による機械と同じだと言うことがわかるだけのような気がする。
Posted by
相当難しいことを、かなり分かりやすく書いてある印象。それでも自分にはちょっと難しいところもあったけど。脳ってまだまだ未知の世界なんですね。長い時間をかけて進化してきた生物の神秘。流行りのAIとは別物なんだなぁって思いました。またいつか再読して理解を深めたい一冊です。
Posted by
ミトコンドリアDNAの変調が双極性障害に関連している可能性や、メスとの同居によりオスの子育て行動を促す部位が攻撃行動を促す部位を抑制する検証結果など、興味深い知見。社会性や愛情といった人間の営みを聖域化してそれらへの脳の関与を追求しないことは、社会性の上に生じる諸問題の解決を回避...
ミトコンドリアDNAの変調が双極性障害に関連している可能性や、メスとの同居によりオスの子育て行動を促す部位が攻撃行動を促す部位を抑制する検証結果など、興味深い知見。社会性や愛情といった人間の営みを聖域化してそれらへの脳の関与を追求しないことは、社会性の上に生じる諸問題の解決を回避することになるのでは、という見解に考えさせられる。得られた知見をどう生かすか、科学者のみの責任に帰する問題ではなく社会が引き受けるべき問いであろうことを再認識。
Posted by